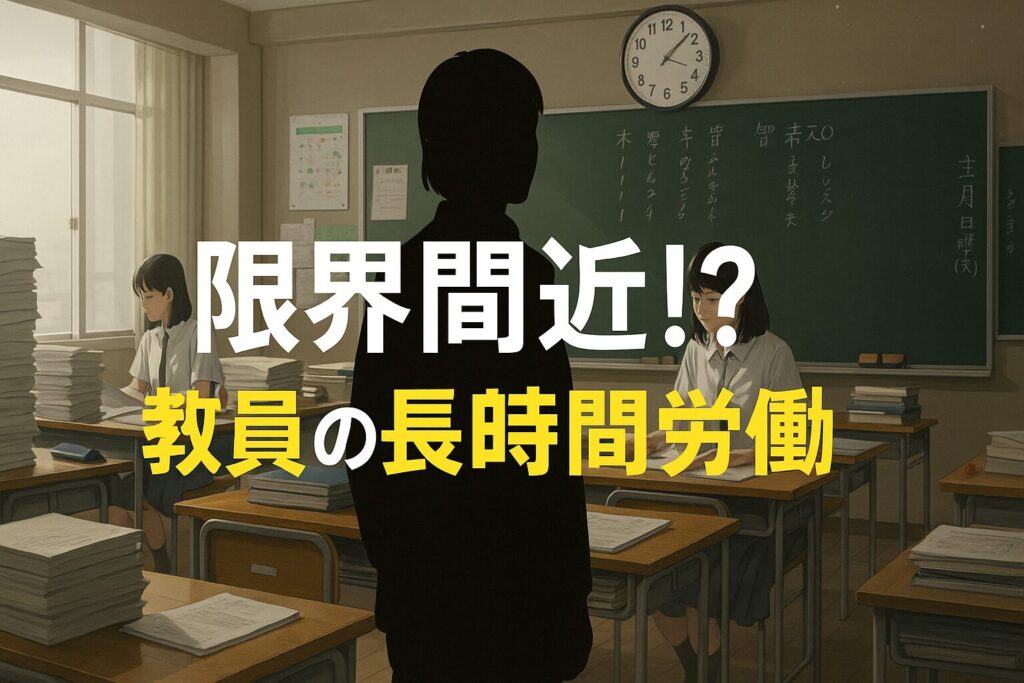
日本の教員は「世界一忙しい」 – 最新調査データが示す実態
日本の学校教員の長時間労働は国際的にも突出しており、度々「世界一忙しい」と指摘されています。実際、OECDの国際教員指導環境調査(TALIS)2018によれば、日本の中学校教師の1週間当たりの平均勤務時間は約56時間で、参加48か国中最長でした。これはOECD平均の約38時間を大きく上回り、2位のカザフスタン(約49時間)よりもかなり多い水準です。日本の小学校教師も同様に約54時間と長時間で、授業準備や生徒指導に費やす時間は各国と同程度ながら、事務作業や課外活動(部活動)対応に費やす時間が極めて多いことが特徴です。下表に国際比較の一例を示します。
表1: 国際比較(2018年)における教員の平均勤務時間
| 指標 | OECD平均(中学校) | 日本:中学校 | 日本:小学校 |
|---|---|---|---|
| 1週間の総勤務時間 | 38.3時間 | 56.0時間 | 54.4時間 |
| 事務・雑務に費やす時間 | 2.7時間 | 5.6時間 | 5.2時間 |
文部科学省が令和4年度(2022年)に実施した最新の「教員勤務実態調査」でも、日本の教員の長時間勤務の実態が裏付けられています。同調査によれば、平日1日あたりの在校時間(=学校にいる時間、研修や校外引率含む。休憩や自己研鑽時間を除く)は、多くの教員で10時間前後にも及びます。具体的には、小学校教諭で平均約10時間45分、中学校教諭で約11時間01分と、依然として1日あたり2〜3時間の残業が常態化している計算になります。以下の表は職種別の平日平均在校時間を示したものです。
表2: 職種別・平日1日あたりの平均在校時間(令和4年度調査)
| 職種 | 小学校(平日平均在校時間) | 中学校(平日平均在校時間) |
|---|---|---|
| 校長 | 10時間23分 | 10時間10分 |
| 副校長・教頭 | 11時間45分 | 11時間42分 |
| 教諭 | 10時間45分 | 11時間01分 |
| 講師(非常勤) | 10時間18分 | 10時間27分 |
| 養護教諭 | 9時間53分 | 9時間53分 |
このように管理職を含め1日10~12時間近く勤務している計算になり、教師の勤務環境がいかに長時間労働に及んでいるかが分かります。また、在校時間外に自宅へ仕事を持ち帰る「持ち帰り残業」も平均で平日・休日に20~40分程度発生しており、持ち帰り分も合わせると実質的な総労働時間は1日11時間を超えるケースが少なくありません。週当たりで見ると、「50〜60時間」が最も多い層であり、小学校では週50~55時間未満が最多、中学校では50~60時間未満の層が厚くなっています。実際、週60時間(=月240時間)を超えるペースで働く教員も珍しくなく、いわゆる「過労死ライン」(月80時間超の残業)に達する教員も相当数存在する状況です。
なお、前回調査の平成28年度(2016年)結果と比較すると、小中学校教諭の平日平均在校時間は約30分短縮しており、一見すると働き方改革の効果が表れているようにも見えます。しかし依然として「世界一長い」水準から大きく改善したとは言えず、未だ厳しい長時間労働の現状が浮き彫りになっています。むしろ近年はコロナ禍対応やGIGAスクール構想(1人1台端末配布)対応など新たな業務も増加しており、従来業務と相殺されて辛うじて30分の短縮に留まったという分析もあります。要するに、日本の教員の時間外労働は慢性的・構造的な問題であり、国際比較や最新統計から見ても極めて深刻な状況にあると言えるでしょう。
長時間労働を生む構造的課題 – 給特法、業務過多、ICTの遅れ
では、なぜここまで日本の教員は忙しいのか。その背景には複数の構造的課題が存在しています。本章では、特に重要な要因として指摘される以下の点について解説します: 1) 教職調整額と給特法の問題、2) 授業外業務の多さ、3) 部活動顧問負担、4) 教員不足の深刻化、5) 校務のICT化(DX)の遅れ です。
「定額働かせ放題」?給特法と教職調整額の問題
日本の公立学校教員の勤務環境を語る上で避けて通れないのが、いわゆる「給特法」(正式名称:「公立学校教職員給与特別措置法」)の存在です。給特法は1971年に施行された法律で、公立学校教師に対し給料月額の4%を「教職調整額」として一律支給する代わりに、時間外勤務手当・休日勤務手当を一切支給しないという特殊な労働条件を定めています。簡単に言えば「超過勤務手当なし」の代償措置として4%の上乗せ給与を与える制度ですが、裏を返せばどれだけ残業しても追加賃金が発生しないことを意味します。このため給特法は皮肉を込めて「定額働かせ放題法」とも揶揄され、無限残業を許している元凶と批判されてきました。
さらに給特法には、教員に命じて良い時間外業務を「超勤4項目」(非常時対応、生徒指導上の緊急措置、修学旅行等行事、災害等)に限定する規定もあります。本来はそれ以外の業務で残業させてはいけない建前ですが、実際には日常的な事務作業や部活動指導など数多くの業務がこの枠外で行われています。建前と現実の乖離から生じる違法状態を黙認したまま、「サービス残業」が常態化してきたのが実情です。つまり給特法は、本来教師を保護するための制度であったはずが、結果的には無償残業の温床となり長時間労働を構造化させているとの指摘があります。
近年、この問題にメスを入れるべく給特法改正の議論が活発化しています。中央教育審議会は2024年、「給特法は継続し教員に時間外手当を支給しない原則を維持する」という答申を出しましたが、一方で教職調整額については4%から引き上げを検討する方向が示されています。政府の「骨太の方針2023」でも教員処遇改善として教職調整額を「少なくとも10%以上」に引き上げる検討が明記され、財務省は働き方改革の進捗を条件に段階的に引き上げる案を提示しました。文科省も2024年度予算で13%への引き上げを要求するなど、具体的な数値が議論に上っています。しかし、一律の調整額アップだけでは残業削減に直結しないとの懸念も強く指摘されています。実際、調整額は残業の有無に関わらず全員一律支給のためインセンティブになりにくく、むしろ必要なのは業務量そのものの削減や教員定数増による負担分散だという意見もあります。今後の給特法改正論議では、こうした現場の声を踏まえつつ「定額働かせ放題」の構造をいかに是正するかが大きな焦点となるでしょう。
授業以外の業務が多すぎる現状
教員の業務過多を語る際によく聞かれるのが「教師は本来の授業以外の仕事が多すぎる」という嘆きです。実際、日本の教員は授業準備や授業そのもの以外に、膨大な校務・事務作業を抱えています。例えば成績処理、学級通信の作成、保護者への連絡、各種行事の準備・運営、学校だよりやホームページ更新、給食指導、清掃指導、校内巡視、安全点検、さらには教育委員会や文科省への統計調査回答など、その種類は多岐にわたります。驚くべきことに海外では教員が行っていない業務まで日本では教師の役割とされており、OECD調査によれば、他国では事務職員などが担当する「教材や備品の発注・管理」「施設の修繕手配」「学納金の徴収」等も日本では教師自身が担っている例が多いのです。
このように本来教師以外でもできる雑務まで背負い込んでいることが、日本の教員の業務負担(教員負担)を増大させている大きな要因です。言い換えれば、「教員=オールラウンダー職」になってしまっているのが日本の学校の特徴であり、授業に専念できる環境が整っていません。結果として、教材研究や研修など本来注力すべき教育活動の時間が圧迫され、職能開発や授業改善に費やす時間が日本の教員は国際的に見て最低水準になっているとの報告もあります。この問題に対しては、後述する「校務DX」やスクールサポートスタッフ(学校事務支援員)の活用拡大などで事務作業を省力化・外部化し、教師が子どもと向き合う時間を確保する取り組みが求められます。
部活動指導の負担と地域移行の動き
日本の部活動(クラブ活動)は、教師の長時間労働を語る上で避けて通れない項目です。多くの中学校・高校では教員が顧問となり放課後や週末に練習・試合の指導を行っていますが、これは無給の上に拘束時間も長いため、教員の負担増につながってきました。平日の放課後指導だけでなく土日の大会引率なども重なれば、週当たり数十時間が部活動対応に割かれるケースもあります。文科省の2018年調査でも、日本の中学校教員が課外活動(部活)に費やす時間は国際平均を大きく上回っていることが指摘されています。
こうした状況を改善すべく進められているのが「部活動の地域移行」です。これは学校管理下の部活動を地域のクラブやNPO・民間指導者に段階的に移管し、教師の負担を軽減しようという改革です。文科省は2020年に方針を打ち出し、2023年度から公立中学校の休日の部活動を順次地域移行する取組がスタートしました。2023〜2025年度の3年間を「改革推進期間」と位置づけ、まずは休日(土日の活動)から地域移行を進め、平日の活動も含めた全面的な移行を目指す計画です。自治体によって計画に差はありますが、例えば2026年度には神戸市で公立中学校の部活動を完全地域クラブ化(学校での部活終了)することが決定しています。文科省のガイドラインでは、遅くとも令和10年度(2028年度)までに中学校の部活動は地域移行を完了させる目標が掲げられています。
部活動地域移行には、教師の負担軽減だけでなく「子どもが専門家の指導を受けられる」「活動の選択肢が増える」といった教育的メリットも期待されています。一方で、受け皿となる地域クラブの指導者や資金の確保、保護者の費用負担増など課題も指摘されています。特に地方では代替の社会体育団体が十分存在せず、短期的には教師が地域クラブの運営を支援するケースも考えられます。それでも、長い目で見れば部活動指導を教員の「職務」から切り離す意義は非常に大きく、現に2023年度の教員勤務実態調査でも部活動指導にかかる教員の休日出勤時間は減少傾向が見られています。今後は地域や民間との連携を強化しつつ、この改革を着実に進めることで、教師の週末の休養や専門業務への専念時間を確保していくことが重要です。
教員不足の深刻化と長時間労働の悪循環
近年、「教員不足」という言葉がニュースでも頻繁に取り上げられるようになりました。これは教員志望者の減少や若手教師の早期離職などにより、各地の学校で必要な教師数を確保できない事態が生じている問題です。教員不足は教師一人ひとりの業務量をさらに押し広げるため、長時間労働の一因であると同時に結果(離職増)でもあるという悪循環を生んでいます。
文科省が初めて教員不足の実態調査を行った2021年5月時点では、公立小中学校で欠員となっていた教員は1701人に上りました。これは小中学校約1,350校(20校に1校の割合)で担任不在などの事態が発生していた計算になります。その後も状況は悪化傾向にあり、2024年度当初時点で「前年より不足が悪化した」と回答した都道府県・政令市教委は22団体にも上りました。現場教員へのアンケートでは、年度途中(夏~冬)に教員不足がさらに深刻化する実態も浮き彫りになっています。ある調査によれば、年度開始時に約37%だった「自校で教員不足を感じる」との回答率が、冬には小学校64.2%、中学校55.9%にまで上昇したとのことです。つまり年末時点では半数以上の学校で何らかの欠員が生じている計算で、配置後の体調不良や産休・育休代替要員の不在などにより、次第に欠員校が増えていく状況が示唆されています。
教員不足を招く要因としては、若手教師の離職と採用希望者の減少が大きなポイントです。特に新規採用教師が過重労働やストレスで早期に燃え尽きてしまうケースが問題視されています。東京都のデータでは、新採用教員の約4.9%が1年以内に離職しており、この割合は年々上昇しています(2022年度は4.4%)。離職者の約半数は病気(精神疾患等)を理由としており、その7割が小学校教諭でした。一般的な民間の離職率と比べれば低い数字とはいえ、終身雇用が前提だった教職において初年度で5%弱が辞めてしまう現状は看過できません。また教員採用試験の志願者数も減少が続いており、2024年度の公立学校教員採用試験では全国の志願者数が約12万7千人と前年比4.5%減となり、過去最低水準の自治体も出るなど深刻です。競争倍率も全体平均で3~4倍台まで低下し、2000年代初頭に10倍以上あった時期から大きく低下しています。背景には長時間労働や高ストレス職場を敬遠する若者の傾向があると分析されており、待遇改善と魅力向上が急務となっています。
教員不足はそれ自体が問題であると同時に、残った教員への負担増(授業数増や部活動兼務など)を招き、さらなる離職や志望者減を呼ぶ悪循環に陥ります。このスパイラルを断ち切るためには、次章で述べるような政策的な働き方改革の推進に加え、臨時的な人員補充策(定数外教員や非常勤講師の確保)、スクールサポートスタッフ等の充実による業務分担など、多角的な対策が求められています。
校務のICT化(校務DX)の遅れと期待
最後に、日本の教員の長時間労働を助長する要因としてICT化の遅れ、いわゆる「校務DX(デジタルトランスフォーメーション)」の遅滞も指摘しなければなりません。学校現場では依然として紙ベース・手作業の事務が多く、出欠管理から成績処理、保護者連絡まで煩雑な作業に時間を取られがちです。例えば出欠簿や成績表の手書き入力、膨大な配布物の印刷と仕分け、電話連絡網対応など、デジタル化すれば効率化できる業務が多々残っています。
しかし近年、文科省のGIGAスクール構想で教師・児童生徒に1人1台端末と校内ネットワーク環境が整備されたことを追い風に、校務DXも少しずつ前進しています。文科省は各学校での取組状況を自己点検する「校務DXチェックリスト」を公表し、全国調査も開始しました。2024年末に公表された結果によると、ICT活用による業務効率化で効果実感が特に高かったのは「教職員と保護者間の連絡のデジタル化」「教職員と児童生徒間の連絡のデジタル化」「校内連絡のオンライン化」でした。これは従来プリント配布や電話に頼っていたものをメールや連絡アプリ、オンライン掲示板等に置き換えることで、大幅な時間短縮に繋がったことを意味します。実際、プリント削減や押印廃止などによりデータ入力・処理の時間が短縮し、その分を授業準備に充てられたという学校も出てきています。
ただし、校務DXの推進状況には自治体間・学校間で差があります。システム導入の予算やICTに明るい人材の配置、有効なツールの選定といった課題もあり、「ICT機器は揃ったが活用しきれていない」との声も少なくありません。DXはあくまで手段であり、人が使いこなしてこそ効果を発揮します。教師自身のICTリテラシー向上や、ツール導入時の研修サポートも重要です。また、ルール整備も欠かせません。例えば時間外のメール対応ルールや、チャットツールによる逆に「24時間繋がってしまう」弊害を防ぐガイドライン策定など、ICT化と並行して働き方のルールメイキングも必要でしょう。いずれにせよ、学校現場のデジタル化は教師の負担軽減と教育の質向上の両面に資する重要施策であり、国・自治体を挙げたさらなる推進が期待されています。
長時間労働が招く深刻な影響 – メンタルヘルス悪化・離職・教育の質低下
前章まで述べた構造的な長時間労働は、すでに教員の健康や学校教育の持続性に深刻な影響を及ぼしています。本章では、その具体的な影響として 1) 教員のメンタルヘルス不調(精神疾患による休職者の増加)、2) 若手教員の離職増加、3) 教育の質への影響(人手不足による学習機会の損失) を見ていきます。
過去最多を更新する教員の精神疾患休職
長時間労働や業務過多は教員の心身を蝕み、うつ病など精神疾患による病休者を増やしています。文科省の調査によると、2023年度にメンタル不調で休職した公立学校教職員は7119人(全教職員の0.77%)にのぼり、3年連続で過去最多を更新しました。この数は前年度(2022年度)の6539人からさらに580人増加したもので、小学校で3443人、中学校で1705人、高校で966人、特別支援学校で397人など全ての校種で増加傾向にあります。特に20代〜30代の若手教師の休職が増えており、2023年度は精神疾患休職者のうち勤務年数3年未満の教員が6割超を占めました。性別では女性教員の方が多く(全体の約60%)、育児や家庭と仕事の両立ストレスなども背景にあると考えられます。
さらに2023年度から初めて、病休に至った原因要因の内訳が調査されました。それによると最も多かった要因は「児童・生徒への指導そのものに関すること」で26.5%を占め、次いで「職場の人間関係」が23.6%、「校務分掌や調査対応等の事務的業務」が13.2%と報告されています。つまり生徒指導の難しさや職場内の対人ストレス、そして大量の事務処理が教員のメンタルを追い詰めている実態が浮き彫りになっています。もちろん、こうした背景には長時間労働で心身の余裕を失っていることが大きく影響しているでしょう。
教員の精神疾患休職者が増加し続けることは、単に個人の健康問題に留まらず、学校運営全体にも深刻な影響を及ぼします。休職者が出ればその穴埋めで他の教員の負担が増し、代替教員の確保にも苦慮するという負の連鎖につながります。また生徒にとっても担任や担当教員の交代は学習面・精神面で不安を与えかねません。文科省や各教育委員会もメンタルヘルス対策を強化し、スクールカウンセラーの配置拡充や産業医によるケア、管理職研修でのメンタルヘルスマネジメント指導などに取り組んでいます。しかし根本的には長時間労働の是正こそ最大のメンタルヘルス対策であると言えるでしょう。働き方改革を進めることで「休職予備軍」とも言える疲弊した教員を減らし、心の健康を守ることが急務です。
若手教師の離職と教員志望者減少の問題
前述のとおり、過酷な労働環境は若手教員の離職にも直結しています。かつて教職は「一度就職すれば定年まで勤め上げる」ことが多い安定職でしたが、近年は新卒教師が数年以内に辞めてしまうケースが珍しくなくなりました。東京都の例では、新採用後わずか1年以内に約5%が退職しており、他県でも「3年以内離職」が増えているとの報道があります。離職理由で特に多いのが前節で触れた精神疾患(燃え尽き)ですが、それ以外にも「激務で家庭との両立が困難」「他産業へのキャリア転向」など様々な事情があるようです。
若手が定着しないと、学校としては常に新人を育て直す負担が生じる上、人手不足にも拍車がかかります。指導経験が浅い30代以下の教員層が薄くなることで、学校全体の活力や将来の管理職候補にも影響が及びます。子どもたちにとっても、本来担任や部活動で継続指導すべき若手教師が次々いなくなるのは好ましいことではありません。
さらに長時間労働のイメージは教職志望者の減少にも直結しています。前述のように教員採用試験の志願者は年々減り続け、かつて高倍率だった小学校教師ですら一部地域で応募者不足に陥っています。これは「子どもに教える仕事は魅力的だが、あの激務は無理」と感じる学生が増えているためと考えられます。実際、教育学部生へのアンケートでも教員の働き方への不安がしばしば上位に挙がります。このままでは有為な人材が教壇に立たなくなる恐れがあり、結果として教育の質低下にもつながりかねません。
以上のように、長時間労働の問題は教員個人の健康のみならず人材の確保・育成という教育システム全体の持続可能性にも関わる重大課題です。これ以上状況を悪化させないためにも、次章で述べるような各種改革を通じて労働環境を改善し、若手が希望を持って働き続けられる現場を作ることが急務と言えるでしょう。
教員の負担軽減に向けた最新の改革動向 – 給特法改正・部活動改革・校務DXほか
深刻化する教員の長時間労働問題に対し、国や自治体もようやく重い腰を上げ始めています。ここでは、2023~2025年時点で進行中の主な政策改革として 1) 給特法改正を含む働き方改革の動き、2) 部活動改革(地域移行)の進捗、3) 校務DX推進、4) その他の業務改善策 を紹介し、現状と効果、残る課題を整理します。
給特法改正と働き方改革プラン
前述した給特法・教職調整額の問題に対し、政府は教員の働き方改革の柱の一つとして法改正による処遇改善を進めようとしています。文科省は教員の長時間労働是正に向け、中央教育審議会で議論を重ねた上で2024年1月に答申をまとめました。その中で、教職調整額の引き上げと勤勉手当における勤怠評価の導入など、教員の処遇改善策が提言されています。調整額に関しては前述のように将来的に10~14%程度まで段階的に増額する案が有力で、2025年度以降の予算措置で反映される可能性があります。
しかし給特法そのものについては「時間外手当を払わない特殊ルールを継続」という結論であり、依然として抜本的な勤務制度改革には踏み込めていないとの批判もあります。実際、教員組合や有識者の中には「時間外労働を他の公務員並みに適正支給し、超過勤務を抑制すべき」として給特法の廃止・抜本改正を求める声が根強くあります。2025年4月には国会前で「給特法改定案に反対」の教師らのアクションも行われました。国としては財政上の制約もあり一度に大改革は難しいものの、勤務実態に応じた柔軟な手当支給や労働時間上限の法制化など、さらなる踏み込みがなければ現場の不満は解消されないでしょう。
一方、文科省は勤務制度以外でも様々な働き方改革策を打ち出しています。例えば「変形労働時間制」の導入もその一つです。繁忙期と閑散期で勤務時間を調整できる制度で、すでに一部自治体では夏休みにまとめて休暇を取得させる試みが始まっています。また在校時間の上限ガイドラインも設けられ、月45時間・年360時間を超える残業は原則させない目標が掲げられました。法律で強制力こそないものの、各校長に対し超過勤務が常態化しないよう管理監督責任を明確にしています。
文科省はさらに業務削減のアクション・プランとして「学校における働き方改革加速プラン」を策定し、各教育委員会に対し具体的な取組を要請しました。例えば公文書の簡素化や会議の効率化、長時間勤務教員への面談実施、ノー部活デー設定、研修のオンライン化推進など、多岐にわたる項目が盛り込まれています。これらは強制ではありませんが、国が方向性を示すことで自治体が動きやすくなりつつあります。
現場レベルでも、校長会や教育委員会を中心に学校ごとの業務改善が進められています。業務の洗い出しと見直し(スクラップ&ビルド)を行い、「なくせる業務は思い切って廃止する」「民間に委託できるものは任せる」などの改革を断行する学校も出てきました。例えばある自治体では、学校だよりの発行頻度を減らし連絡は基本デジタル配信に一本化、成績処理もタブレットで実施、宿題の丸付け支援に地域ボランティア活用、といった工夫で残業時間を減らした事例があります。また部活動外部指導員の積極登用によって顧問教師の負担を軽くした学校や、事務職員・スクールサポートスタッフを増員して教員を事務作業から解放した自治体もあります。
このように、国の制度改正から現場の創意工夫まで、多層的な働き方改革がようやく動き始めています。重要なのは、これらを単発の施策に終わらせず継続的なフォローアップと改善を行うことです。教員の働き方改革は一朝一夕には実現しませんが、逆に待ったなしの状態でもあります。給特法の今後の扱いも含め、2025年以降も政府・自治体が本腰を入れて改革を進めていくことが期待されます。
部活動改革の進捗と効果
部活動の地域移行については前節ですでに詳述しましたが、ここでは2023~2025年時点の進捗状況とその効果を補足します。2023年度から始まった公立中学校の休日部活動の地域移行は、各地でモデル事業や先行実施が進んでいます。例えば東京都や神奈川県では、休日に地域クラブが学校施設を借用して練習を行うケースが増えてきました。また部活動指導員(非常勤)の配置拡充により、教員が関与せずとも活動が回る部も出てきています。
文科省は地域移行の進捗を毎年フォローしており、2024年時点で全ての都道府県が地域連携・移行に向けた計画を策定済みとされています。具体的な完全移行のタイミングは地域差がありますが、多くの自治体が2025~2027年度をメドに休日の部活は地域化する方針です。また、中には平日も含めて早期に全面移行を決めた自治体(例:神戸市の2026年度計画)もあります。
この改革の効果として徐々に表れているのが、部活動指導に割く教員の時間が減少し始めたことです。文科省の勤務実態調査速報でも、2016年比で中学校教員の休日在校時間が平均で約1時間減ったとの分析があります。これは部活動指導の縮減等が寄与した可能性があります。また「土日の部活引率がなくなり家族と過ごす時間ができた」「顧問を外れたことで授業準備に集中できるようになった」等の教師の声も聞かれ、ワークライフバランス改善の一助となっています。
もっとも、地域移行はまだ始まったばかりで、引き続き課題も山積です。特に地方部では指導者確保が難しく、「教師なしでは成り立たない」との懸念もあります。また保護者負担や生徒の移動手段確保といった問題も解決が必要です。それでも改革の方向性としてはほぼ異論がなく、国も財政的支援を拡充しています。2023年度からは地域クラブ設立への補助金や、スポーツ庁による人材バンク(指導者データベース)整備なども進められました。今後数年間が勝負所となるため、関係各所の連携により課題を乗り越えつつ、教師の負担軽減という本来目的をしっかり達成することが期待されます。
校務DX推進の現状と課題
校務DX(業務のデジタル化)についても、既に述べたようにGIGAスクール構想を土台に進展が見られます。文科省は「次世代校務支援システム」の検討を開始しており、教務・学籍管理・成績処理・健康管理などを一元管理できるクラウドシステムの導入を各自治体に促しています。また校務DX推進アドバイザーを全国に派遣し、先進校の事例共有や技術的助言を行う取組も始まりました。
2024年にはデジタル庁が「校務DXダッシュボード」を開設し、全国の進捗状況を見える化しています。それによると、電子出欠システムやオンライン職員会議の導入率は徐々に高まっているものの、課題も浮き彫りになりました。一つは自治体ごとのバラツキです。進んでいる地域では独自の校務支援システムを既に稼働させ、教員の入力負担が大幅軽減された例もありますが、遅れている地域では未だに紙の出欠簿・通知表というところもあります。またシステムの相互連携も課題です。例えば成績システムと学籍システムが別々だと二重入力が発生するなど、せっかくICTを入れても効率化につながらないケースもあります。
このため国は、標準仕様の統一や地方間連携を模索しています。具体的には「校務DX標準モデル」の提示や、教育委員会向けの研修プログラムの充実です。また予算面でも、校務支援システム導入に対する補助や、老朽化した学校ネットワーク更新への財政措置などが2024~2025年度予算で計上されています。
校務DXは地味ながら確実に効果を上げつつある改革であり、「もっと早く進めてほしい」という現場の声も強いです。実際にDXが進んだ学校からは「書類作成時間が激減し、その分子どもと向き合う時間が増えた」「テレワークが可能になり在宅で採点・資料作りができた」等の報告があります。もちろんICTだけで全てが解決するわけではありませんが、他業界に比べデジタル化の遅れていた教育現場において、DXは最も即効性のある業務改善策の一つです。今後も国の後押しを受けつつ各学校で創意工夫を凝らし、煩雑なルーチンワークから解放される教員を増やしていくことが期待されます。
その他の業務改善策の展開
上記以外にも、教員の負担軽減につながる様々な施策が展開されています。その一つが定型業務のアウトソーシングです。例えば通知表の印刷・ホチキス留め、学校給食の配膳台清掃、教材準備など、一部地域では行政や民間企業と連携して外部スタッフに任せる取り組みがあります。東京や政令市では「学校支援員」や「外部人材バンク」を活用し、事務補助や図書整理、学習補助員などを積極的に配置しています。北海道や千葉市などでは全校にスクール・サポート・スタッフ(教員業務支援員)を配置し、各種文書作成や採点補助を担ってもらう体制を整えています。
また、学校運営の見直しも進んでいます。例えば行事の簡素化・統廃合です。毎年恒例だった運動会や学芸会を隔年開催にしたり、内容を見直して準備負担を軽減したりする学校も出てきました。「伝統だから」と続けてきた慣例行事もゼロベースで要不要を検討し、本当に子どものためになるもの以外は思い切って廃止する判断も必要です。実際にある高校では、長年続いた全校祭典をやめたところ教員の残業時間が大幅に減り、その分補習や進路指導に時間を割けるようになったという例も報告されています。
勤務環境の整備も重要です。老朽化した校舎や空調の不備は教員の疲労を倍加させます。政府は2025年度に向けて、全普通教室へのエアコン設置やトイレの洋式化などハード面の改善予算も計上しています。また職員室のレイアウト見直しや、防音個室ブースの設置などで集中作業できる環境を作る動きもあります。ちょっとしたことですが、こうした配慮が教師のストレスを和らげ生産性を上げる効果が期待されます。
最後に、意識改革も欠かせません。日本の教師は「子どものために」と自己犠牲を厭わない傾向があり、それが美徳とされてきました。しかし時代は変わり、教師自身の健康や生活を大切にすることが結果的に子どもへのより良い教育につながるという考え方が浸透しつつあります。管理職も含め「休むときは休む」「効率よく働く」「お互い様で仕事を助け合う」という職場風土を醸成することが、長時間労働の是正には不可欠です。最近では「〇時には完全退勤」を職員間で声掛けし合ったり、定時に一斉に音楽を流して仕事を切り上げる学校も出てきています。こうしたマイクロ改革の積み重ねが、大きな効果を生むこともあるのです。
先進自治体・学校の取り組み事例 – 短期・中期・長期の改善ロードマップ
改革のヒントは既に現場から生まれつつあります。ここでは、教員の働き方改革で成果を上げている先進自治体・学校の事例を紹介しつつ、今後取り組むべき短期・中期・長期の改善ロードマップを提案します。
先進事例:神奈川県・神戸市などの大胆な取り組み
神奈川県は教員の働き方改革に積極的に取り組む自治体の一つです。2025年3月には県と全市町村教育委員会が共同で「教員の働き方改革加速化宣言」を行い、具体的な目標を掲げました。その中で特筆すべきは「時間外在校等月45時間超の教員割合0%」という大胆な目標設定です。つまり月45時間を超える残業をする教員をゼロにするというもので、年度当初から業務配分を調整し、超過しそうな場合は業務削減・人員派遣等で対処する計画です。また年360時間超も0%とし、年間ベースでも過労死ライン(年720時間超)はもちろん半分の360時間すら許さないという強い決意を示しています。
神奈川県はこの実現に向け、重点改革期間を設け市町村を支援する考えです。例えば県費でスクールサポートスタッフを増員配置したり、ノー部活デーの全校実施、学校閉庁日の徹底などを進めています。すでに県内のモデル校では、残業削減と並行して教員のウェルビーイング向上(「働きやすい職場」と感じる教員80%以上)という目標も達成しつつあります。神奈川県の取組は、自治体レベルでここまで踏み込んだ目標を掲げた点で全国の注目を集めています。
神戸市も注目すべき事例です。前述のとおり2026年度に公立中学校の部活動を完全地域移行すると決定したほか、2023年度には小中学校の全教室に冷房完備と校務PC配備を完了させ、教員の作業環境改善を一気に進めました。さらに独自の業務アシスタント制度を導入し、各学校に事務処理専任の非常勤スタッフを配置しています。これにより通知表入力や各種調査集計といった業務はアシスタントが担い、教員は授業と生徒対応に専念できる時間を増やしています。神戸市教育委員会の試算では、これらの改革で教員一人当たり年間200時間以上の負担軽減が見込まれるとのことです。
他にも新潟県阿賀町では学校ごとに働き方改革チームを作り業務の見直しを徹底した結果、教員の退勤時刻が平均1時間早まったといいます。秋田県のある中学校では部活動指導員の活用で教員の休日出勤をゼロにした事例があります。東京都も2022年度から「働き方改革推進校」指定制度を設け、先進的取組を行った学校には加配教員を増やすなどインセンティブを与えています。指定校の一つでは、校長のリーダーシップで会議・研修を大胆に削減し、定時退勤日を週2回設定して実施、時間外勤務が全体で2割減少しました。
これら先進事例に共通するのは、明確な数値目標とトップダウンの改革推進です。ゴールを定め現状を見える化し、管理職が旗振り役となって組織全体で取り組むことで、短期間で効果を出しています。そして効果が出た施策は継続・拡大し、効果の薄いものは修正するというPDCAサイクルを回しています。教育現場は往々にして忙殺されPDCAが疎かになりますが、先進校・自治体はそこを意識的にマネジメントしている点が特徴です。
改善ロードマップ:短期・中期・長期の展望
最後に、以上の知見を踏まえつつ、教員の長時間労働問題解決に向けた短期・中期・長期のロードマップを描いてみます。
- 短期(今すぐ~1年程度):まずは各学校・教育委員会ができることから即実行する段階です。具体的には「業務の断捨離」と「時間管理の徹底」です。不要不急の書類や会議は直ちに削減・延期し、定時退勤日やノー部活デーを設定して教職員全員で遵守します。また非常勤講師や部活指導員の緊急増員を行い、授業準備や部活動の負担を分散します。管理職は長時間勤務の教員に個別面談を行い、業務配分を調整します。メンタル不調者の兆候があれば早期に休養・治療させるよう勤怠管理を強化します。ICTツールのすぐ使えるもの(オンライン連絡ツール等)は即導入し、紙のプリント・手書き業務は可能な限り廃止します。短期的には「まず残業月80時間超の職員をゼロにする」「休日は必ず週1日は休む」といった最低限守るラインを全校で共有し、過労死ラインを割り込むことを目指します。
- 中期(今後2~3年程度):給特法改正や定数改善など制度面の改革が具現化する段階です。2025年前後には教職調整額の引き上げや働き方改革関連法の適用拡大(労働時間上限規制の公立校教員への適用検討等)が進む見込みです。それと歩調を合わせ、各自治体は教員定数の拡充(少人数指導やチームティーチング推進による増員要求)や待遇改善(給与アップや特殊勤務手当の新設)に取り組み、人材確保を図ります。また部活動地域移行を完了させ、休日の教員完全休養を実現します。校務DXでは、全国標準の校務支援システムが整備され、出欠・成績・通知表・調査統計など主要業務がクラウドで一元化されるでしょう。これにより煩雑だった入力作業が大幅に効率化し、事務作業時間をさらに削減できます。同時に勤務文化の改革も中期の目標です。定時退勤や年次有給休暇取得が当たり前になり、互いに休暇を補い合う職場風土を醸成します。中期的な数値目標としては「時間外在校時間月45時間以内を徹底」「年休日取得率50%以上」といったラインが設定されるべきです。
- 長期(5年~10年程度先):長期的には、教員の働き方そのものが大きく様変わりしていることが理想です。例えば小学校高学年の教科担任制や教師と事務スタッフの役割分離が進み、教師は専門教科の指導に集中し、事務的業務は専門スタッフが担う仕組みが定着しているかもしれません。また教師の勤務形態多様化も考えられます。常勤講師・非常勤講師の制度を柔軟に活用し、フルタイムだけでなく短時間勤務の教員やジョブシェアリング(1つの学級を複数教員で受け持つ)など、新しい勤務モデルが普及している可能性があります。長期的には教員数そのものも増員され、少子化で余剰となった人員を活用して1人当たりの受け持ち業務量を減らす方向にシフトできるでしょう。何より、教員自身が心身ともに健康でやりがいを持って働ける環境になっていなければなりません。残業ゼロは難しくとも週休2日が確実に取れ、平日も家庭で夕食を食べられる、そんな当たり前の働き方を実現することがゴールです。その先には、教職が再び「魅力ある職業」として若者に選ばれるようになり、志望者が増え、好循環が生まれる未来が描けるでしょう。
もちろん、このロードマップの実現には多くのハードルがあります。しかし既に改革に成功しつつある先進事例が示すように、「本気で変えよう」という意思と具体策があれば着実に前進できます。国と自治体、学校と地域社会、そして教員自身が危機感と当事者意識を持って協力し合い、この難題に立ち向かっていくことが肝要です。
今日からでも実践できる「教員負担軽減+AI活用」チェックリスト
最後に、現場の教員や学校管理職、教育関係者が「今日からでも」実践できる負担軽減のポイントをチェックリスト形式でまとめます。できるところから少しずつ取り組んでみてください。
| 項目 | 具体策 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 業務の取捨選択 | 今年度やらなくても支障のない業務・行事を洗い出し、「要る/要らない」を話し合う場を設定。 🆕 生成 AI で議事録やアンケート結果の自動要約—無料で使える Gemini/ChatGPT の「要点抽出」機能を使うと会議時間も短縮 | 不要業務の廃止+会議短縮 |
| 定時退勤日を設定 | 週1回「○曜日は全員定時退勤」を徹底。管理職が率先して施錠。 🆕 学校チャット(Classi/Teams 等)のステータスを自動切替し「退勤後は通知をサイレント」にするルールを設定 | ワークライフバランスの習慣化 |
| 持ち帰り仕事ゼロ宣言 | 自宅持ち帰り禁止を宣言し、終わらない仕事は翌朝に回す。 🆕 AI 採点サービス(Classi・Qubena・サインウェーブの自動記述採点など)を導入して丸付け時間を最大 50 %圧縮 | 在宅残業の根絶 |
| ICT/AI ツールの活用 | - 連絡はメール・SNS一斉送信、プリント激減 🆕 Google スプレッドシート+翻訳 API で多言語一斉連絡(外国籍保護者向け)を自作 🆕 AI で教材自動生成:英語の読解問題や数式プリントをワンクリック生成(レシピー for School など) | 事務・教材作成時間の短縮 |
| 周囲に頼る・任せる | 早めに相談し仕事を分担。「申し送りノート」で引き継ぎ。 🆕 AI チャットボットを校内 FAQ に導入(LINE bot など)→新人や臨時講師が校務手順を即検索 | 引き継ぎロスの削減 |
| 自分の健康を最優先に | 定期健診・有休取得を遠慮しない。 🆕 メンタルケア用 AI チャットボット「AIさくらさん」などを導入—匿名・24 h 相談で早期ケア | 休職リスクの低減 |
| 情報収集とスキルアップ | 他校の成功事例を常にチェック。 🆕 UNESCO「AI 教員コンピテンシーフレームワーク」で AI リテラシー基準を自己点検 🆕 MEXT「生成 AI 利活用ガイドライン」最新版を共有—校内研修でリスク&活用法を学ぶ | AI 活用スキルの底上げ |
| 採点・評価の AI 化 | 自動採点モデル(Recursive×教育同人社 等)が出力する ○× データを成績ソフトへ連携 | 採点~成績入力の一体化 |
| ドキュメント自動化 | オンライン校務支援システム(EDUCOM C4th、tetoru など)で集金・出欠・成績をクラウド一元管理 | 二重入力と紙書類の激減 |
導入ステップのコツ
- 無料トライアル→小規模検証
多くの AI/校務 DX サービスは無償トライアルが可能。まずは1学年・1教科で試し、効果を数値化してから校内展開。 - 「削減時間=●時間」を可視化
時間削減効果をデータで示すと、次年度予算化が通りやすい 。 - ルール整備と研修をセットで
深夜通知オフや個人情報の扱いなど、ガイドライン遵守を徹底。MEXT の生成 AI 指針も必ず共有 。 - 教員の不安を対話で払拭
「AIに仕事を奪われる」という誤解が出やすい。AIは雑務を減らし本来業務に集中するための助手であることを共通認識に。
ポイント:AI 活用は「残業を減らし、子どもと向き合う時間を増やす」ための手段です。まずは丸付け・資料作り・連絡業務といった“時短インパクトが大きい領域”から導入し、成功体験を積み重ねていきましょう。
以上のチェックリストを参考に、できることから実践してみてください。一人ひとりの心掛けと小さな変化が集まれば、やがて学校全体の働き方も大きく変わります。教師が元気で笑顔でいられることは、子ども達にとって何よりの財産です。日本の教育を未来につなぐためにも、教員の負担軽減と働き方改革をみんなで進めていきましょう。
参考文献
- 文部科学省 (2023). 令和4年度教員勤務実態調査(速報値)【文部科学省 報道発表】
- 経済協力開発機構 (2019). 国際教員指導環境調査(TALIS)2018 結果概要【OECD/文科省 報告書】
- 朝日新聞 (2019). 「日本の教師は世界一多忙」OECD調査で判明【朝日新聞デジタル】
- 杉浦健太郎 (2021). 教員の職場環境の国際比較─TALISから見えてくるもの『日本労働研究雑誌』5月号, 70-80頁
- 朝日新聞 (2023). 教員の志願者、減少続く 過去最低の地域も「長時間労働を敬遠」【朝日新聞デジタル】
- 教育新聞 (2025). 〝2025年版〟教員不足の現状と解決策【教育新聞Web】
- 文部科学省 (2024). 公立学校教職員の人事行政状況調査(令和5年度)結果【文部科学省 報道発表】
- 山田博史 (2024). 教員の精神疾患休職、過去最多7119人 生徒指導など要因【教育新聞】
- 松井聡美 (2024). 新採教員の4.9%が1年で離職、約7割が小学校 東京都【教育新聞】
- 朝日新聞 (2023). 心病み休職の教員、過去最多7119人 新任の退職理由で3割超える【朝日新聞デジタル】
- 東洋経済education×ICT (2024). 残業代出ない「給特法」改正案を巡る議論【東洋経済オンライン】
- 朝日新聞 (2020). 教員に残業代を:給特法見直し論と財源問題【朝日新聞デジタル】
- BENESSE教育情報 (2023). 部活動の地域移行 賛成?反対?(リアルアンケート)【ベネッセ コーポレーション】
- 文部科学省 (2020). 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について(通知)【文部科学省】
- 神奈川県教育委員会 (2025). 神奈川の教員の働き方改革加速化宣言【神奈川県公式サイト】
- 東京都教育委員会 (2022). スクール・サポート・スタッフ活用事例集【東京都教育委員会】
- Digital庁 (2024). 校務DXダッシュボード【デジタル庁】
- School Voice Project (2023). 「教師不足をなくそう」緊急アクション調査報告【NPOスクールボイス】
- 参議院事務局 (2019). 教員採用試験における競争率の低下 – 処遇改善による人材確保の必要性『立法と調査』No.417, 18-24頁
- 日本教職員組合 (2018). OECD教員調査2018 日本の課題【日教組 報道】
