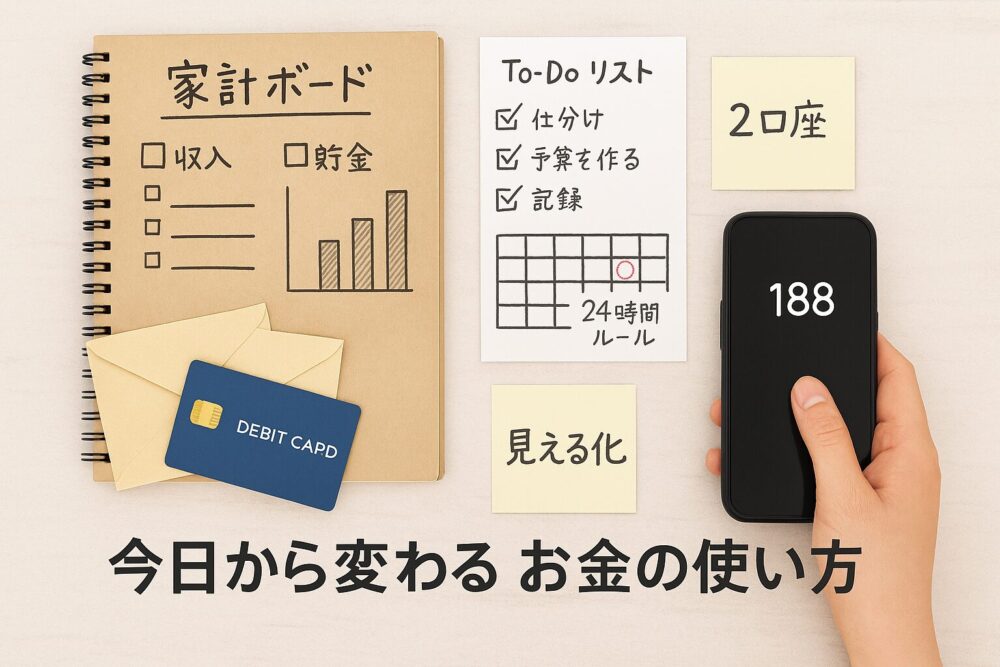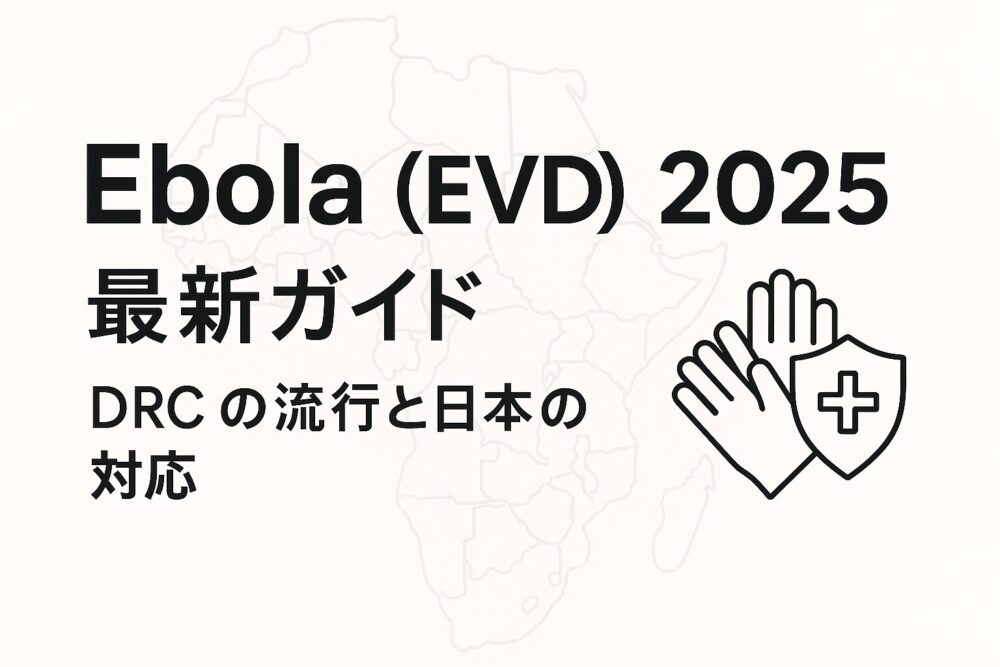導入
ベージュフラッグ(Beige Flag)とは、近年SNSや恋愛メディアで急速に広まった新しい恋愛スラングで、パートナーの「良くも悪くもないが、なぜか気になる癖や特徴」を指す言葉です。従来、恋愛の文脈では「交際相手として絶対に避けるべき欠点」を赤信号(レッドフラッグ)、「将来有望で安心感を与える要素」を青信号(グリーンフラッグ)と呼ぶ比喩が広く使われてきました。それらの中間に位置づけられるベージュフラッグは、赤ほど問題ではないものの、相手の個性として少し引っかかるような癖を表す表現として若者を中心に注目を集めています。
この言葉は、2022年頃にオーストラリアのTikTokerが投稿した動画をきっかけに拡散したとされ、2023年には複数のメディアが「今年の恋愛スラング」として大々的に取り上げました。たとえば、TikTokが発表したレポートによると、2023年に同社が提供している「Red, Green & Beige Flags」というフィルターの再生数は世界累計で85億回を超え、また別途「#beigeflag」のハッシュタグ自体も、2023年中頃に5億7,000万回以上の再生を記録したと報じられています。さらに、オックスフォード大学出版局が同年の「Word of the Year(今年の言葉)」候補としてベージュフラッグを挙げ、公式に「退屈またはオリジナリティに欠けることを示す特徴」と定義したことで、一躍注目度が高まりました。
本記事では、恋愛心理学と社会文化学の視点から、ベージュフラッグが持つ意味やその誕生経緯、そして最新の研究で示唆される恋愛観の変化について詳しく解説します。些細な癖をどう受け止めるかによって関係が大きく左右されることが研究で明らかになっているいま、ベージュフラッグという新しい概念はただのネットミームにとどまらず、人間関係における寛容さとユーモアの重要性を再認識させるトレンドとしても読み解くことができるでしょう。
背景:色別フラッグの概念とベージュフラッグ誕生
恋愛における「フラッグ」概念の広がり
パートナーの行動や性格を「旗」にたとえて評価する文化は、2010年代以降インターネット上で広まりました。その代表例がレッドフラッグ(赤信号)で、暴力や不貞、極端な価値観の不一致など、交際相手として深刻な問題がある行動・性質を意味します。心理学研究では、こうした重大な欠点がいくつも積み重なると「ディールブレイカー(Dealbreaker)」となり、関係を続けられなくなる決定打になりうることが指摘されています。
一方、グリーンフラッグ(青信号)はレッドフラッグの対極として、相手の誠実さや思いやり、約束を守る姿勢など「安心して付き合える肯定的な特徴」を示す言葉として浸透しました。学術的にも、「理想的なパートナーの資質」「関係満足を高める要因」は、恋愛心理学の重要な研究テーマの一つです。すなわち、レッドフラッグは「交際を断念するレベルのネガティブ要因」、グリーンフラッグは「長期的に関係を築くためのポジティブ要因」とまとめられています。
ベージュフラッグという新カテゴリーの誕生
このように赤と青の二分法が定着する中、近年SNSを中心に広がったのがベージュフラッグです。きっかけは、あるオーストラリアのTikTokerが2022年に投稿した動画だといわれており、そこから瞬く間に世界的なミームとして定着しました。「赤ほどの危険性はないが、緑ほど魅力的でもない、でもちょっと気になる癖」というニュアンスが「くすんだベージュ」という色彩のイメージに重なり、若者を中心に受け入れられました。
オンライン・デーティングが主流化する現代では、プロフィールやメッセージのやり取りなど、少ない情報から相手を素早く判断する場面が増えています。極端に良い印象でも悪い印象でもないとき、なんとなく無個性・退屈・あるいは少し変わっていると感じた場合、それを気軽に表すタグとして「ベージュフラッグ」という言葉が使いやすかったのです。TikTokをはじめとするSNSでは、カップルがお互いのベージュフラッグを挙げ合う動画がバズり、「そんな小さなクセも含めて可愛い」「わかる、そのちょっと変なところが気になるよね」といった共感の声が世界中で集まりました。
2023年、オックスフォード大学出版局はこのベージュフラッグを「今年の言葉」候補の一つとして紹介し、「相手が退屈またはオリジナリティに欠けると感じられる特徴」と定義しています。さらに、一部の言語学者・社会文化学者も新語としてのベージュフラッグを積極的に評価し、「パートナー選びや恋愛観における中間評価の需要を具現化した用語」として注目しています。
分析:ベージュフラッグ現象を読み解く
爆発的普及の実態とその要因
TikTokが発表した「Year on TikTok 2023」レポートによると、「Red, Green & Beige Flags」フィルターは全世界で85億回を超える再生回数を記録し、その年を象徴するコンテンツの一つとなりました。また、#beigeflag に関連する動画再生数は2023年半ばで5億7,000万回以上に達していたとされ、まさに「一大トレンド」と言える規模を誇っています。
この背景には、TikTokの特徴である短尺動画の拡散力と、若年層の高いアクティブ率が大きく影響しています。カップルがお互いの些細な欠点を「ベージュフラッグ」と呼んで紹介し合うユーモラスな動画は、多くのユーザーにとって「自分たちの恋人にも当てはまる!」という共感の的となり、コメントやシェアによって爆発的に広まりました。社会文化学的には、これはユーザー同士が恋愛のちょっとした悩みや“引っかかり”を気軽にオープンにし、それをコミュニティ全体で消化・共有する新しい形のコミュニケーションと評価できます。
「気になる癖」は関係にどう影響するか:心理学的分析
ベージュフラッグの要点は「大問題ではないが気になる」という微妙なラインにあります。一見すると無害な小さなクセでも、数が積み重なると関係全体を揺るがす可能性があることは、実験社会心理学の研究からも示唆されています。レッドフラッグほどの決定打ではなくとも、「ディールベンダー(Dealbender)」と呼ばれる些細なマイナス要因が蓄積すると、人は次第に「もうこの人とは合わないかもしれない」という心境になりやすいのです。
もっとも、こうしたベージュフラッグの影響はカップルの状況や相手への好意度によって変動します。小さな欠点を愛嬌と捉えられる関係であれば、むしろそれが二人の笑い話になり、絆を深めるスパイスにもなりえます。近年の研究では、お互いのクセをユーモアによって肯定的に扱い合うカップルほど結婚満足度が高い傾向が報告されています。たとえば軽い冗談やおどけ方を交えて相手を受け入れる姿勢は、相手に対するリスペクトや安心感を生み、対立が起きたときもスムーズに解決へ向かいやすいといいます。
一方で、パートナーへの不満や退屈感が強まっている時期には、小さなベージュフラッグでさえ耐えられなくなる場合もあります。マンネリを感じ始めると、「あの子、ちょっとしたしぐさも面白くない」と不満材料が増幅され、やがては重大なレッドフラッグに転じるリスクさえあります。つまり、ベージュフラッグは、その捉え方次第で「可愛い個性」にも「我慢ならない欠点」にもなりうる非常にグラデーションの広いサインといえるでしょう。
Z世代とSNS文化におけるベージュフラッグの社会的意義
Z世代は、SNSを通じて多様な価値観や恋愛観を常にアップデートしており、完璧なロマンティックパートナーを追い求めるよりも「お互いをありのままに受け入れ合う関係」を重視する傾向が指摘されています。ベージュフラッグの流行は、このような柔軟さと寛容さを前提とするZ世代の風土にマッチしたものと考えられます。
また、オンライン・デーティング疲れ(マッチングアプリ疲れ)への反動として、ベージュフラッグが「小さな欠点くらい笑って受け止めよう」というメッセージを発している側面も見逃せません。マッチングアプリでは大量の候補者に出会える一方、些細な欠点でもすぐに「次の人」にスワイプしてしまいがちです。こうした選択過多の時代だからこそ、多少のクセなら笑い合って受容する姿勢がかえって新鮮に映り、支持を集めたのではないかと考えられます。
ただし、フラッグ文化自体を「人間関係をステレオタイプで単純化しすぎ」と批判する声も存在します。確かに「赤」「青」「ベージュ」のほかにも「ピンク」「オレンジ」など、さまざまな色のフラッグが次々に生まれ、安易なラベリングになっている例も少なくありません。しかし、ベージュフラッグの台頭を「お互いの不完全さを受け入れるポジティブなコミュニケーション」と捉える動きがあるのも事実です。そこには「みんなそれぞれ欠点があって当たり前」と前向きに共有し合う現代的な価値観が表れているともいえます。
結論:ベージュフラッグが示すものと今後の展望
本稿では、恋愛スラング「ベージュフラッグ」について、その定義や背景、そして最新研究の知見を踏まえた心理学的・社会文化学的な意義を考察してきました。ベージュフラッグは、ただ「退屈」「個性がない」という単なる揶揄ではなく、完璧とまでは言えない相手の些細なクセをユーモアと寛容さで受け入れ、共有していく新しいコミュニケーション手法として注目されています。
心理学の視点から見れば、些細な欠点の積み重ねはときに関係を悪化させる要因となり得る一方で、それをポジティブに捉え合うことが長続きの鍵にもなり得ることが示唆されています。社会文化的には、オンライン・デーティングの選択過多に疲れた若者世代が、相手の「ほどほどに気になる点」を許容する余裕とユーモアを求めはじめている流れとも考えられます。
今後、TikTokやInstagramといったSNSを発端とする恋愛用語やムーブメントはさらに多様化していくでしょう。ベージュフラッグが示したように、「大きな問題ではないが引っかかる部分」を言語化し、互いの不完全さを笑い合える関係性を育むことは、Z世代以降の恋愛観においてますます重要になっていくと予想されます。その一方で、「気になる点」を放置しすぎると後々大きな衝突の種になる可能性もあるため、専門家としては小さな違和感を早めに共有し、解決策を模索するコミュニケーションも併せて促進していく必要があります。
結局のところ、誰もが少しずつベージュフラッグを抱えて生きています。それを“味”として楽しめるか、“我慢ならない欠点”として溜め込んでしまうかは、その人間関係の成熟度次第です。ベージュフラッグという言葉がここまで浸透した背景には、SNS時代に生きる私たちの「欠点をも受け入れ合いたい」「完璧でなくても大丈夫」という新しい恋愛観の芽吹きがあるのではないでしょうか。
発達特性があっても『お金の使い方』は変えられる:今日からできる対策と日本の相談先
お金の管理が苦手でも大丈夫です。ADHDやASDといった神経発達症(発達障害)の特性によって、つい衝動買いや支払いの失念をしてしまう方でも、工夫と支援で金銭習慣は改善できます。本記事では今日から実践できる具体的対策12選と、日本国内の相談窓口・公的制度を網羅的に紹介します。一般的な情報提供であり、個別の助言には専門家のサポートも必要ですが、まずは本記事で正確な知識と再現性の高い手順を確認し、安心して一歩を踏み出しましょう。 要点サマリー ADHD傾向のある人は衝動買いや貯金の苦手さを抱えやすいことが研究で ...
オーバーツーリズム対策の最前線:国内外の制度・費用対効果・導入手順まで
観光地の賑わいと地域の暮らしの質をどう両立させるか。観光客が集中する「オーバーツーリズム」の問題は、世界各地で住民生活や旅行者体験への影響が顕在化しています。日本でも富士山や離島、都市の繁華街で混雑やマナー問題が深刻化し、自治体や事業者が対策に乗り出しています。本稿は価格(課金)や予約・人数制限、行為規制、交通整理、情報提供など多角的なアプローチによる解決策を、制度の根拠・費用・KPIまで含めて具体的に解説します。住民合意の得方から導入後の検証方法まで網羅し、明日から現場で使える実装ガイドを目指します。 ...
エボラ出血熱(EVD)最新ガイド:日本で注目される理由と実態【2025年版】
要約: エボラ出血熱(エボラウイルス病, EVD)は、致死率が平均約50%と非常に高い希少疾患です1。2025年9月にコンゴ民主共和国(DRC)で新たなエボラ流行(アウトブレイク)が発生し、日本でもニュースやSNSで関心が高まっています。エボラは主に患者や遺体の体液との直接接触で感染し、一般的な空気感染はしない点が重要です。現在、有効なワクチンや治療法が確立しているのはザイール株(EBOV)によるEVDのみで、他の株(スーダン株など)へのワクチン開発も進行中です。本記事では、エボラの基礎知識から最新動向、 ...
日本の水源地「外資買収」の実態:0.07%未満、法規制が守る
結論(要約) 外国資本による森林取得はごくわずか – 林野庁の最新調査(2025年公表)では、令和6年(2024年)に外国法人等が取得した森林面積は382haで全国私有林の0.003%に過ぎず、累計でも0.07%に留まっています。しかも水資源目的の開発事例は報告されていません。外国資本が日本の水源地を“買い占め”ているとの懸念はデータ上誇張と言えます。 土地を買っても水は自由にならない – 河川法により河川水や湧水の取水には事前に水利権許可が必要で、土地所有だけで勝手に水を使用できません。また多くの水源林 ...
日本のアニメが海外で人気になった理由【完全ガイド】
歴史年表:1960年代から2020年代までの海外進出 日本のアニメが世界的人気に至るまでには、各時代で画期的な作品や出来事が積み重ねられてきました。1963年に手塚治虫原作の『鉄腕アトム』(英題:Astro Boy)が日本で放送開始された直後、米国では NBCエンタープライズ配給のシンジケーションで1963年秋から英語版放送が開始。これは日本製テレビアニメとして米国で初めて本格的に放送された例であり、日本アニメの海外進出の嚆矢となりました。以降、年代ごとの主なトピックを以下にまとめます。 年代主な作品・出 ...
参考文献
- Oxford University Press. (2023). Eight words go head-to-head for Oxford Word of the Year 2023.
- TikTok Newsroom (AU). (2023). Year on TikTok 2023.
- Time Magazine. (2023, June). TikTok’s Latest Obsession: Beige Flags.
- The Cut. (2023, June). So What’s Your ‘Beige Flag’?
- Business Insider. (2023, May). Move aside, red flags — we are now entering an era of “beige flags.”
- Joel, S., & Charlot, N. (2022). Dealbreakers, or dealbenders? Capturing the cumulative effects of partner information on mate choice. Journal of Experimental Social Psychology, 101, 104328. DOI: 10.1016/j.jesp.2022.104328
- Csajbók, Z., & Berkics, M. (2022). Seven deadly sins of potential romantic partners: The dealbreakers of mate choice. Personality and Individual Differences, 186, 111334. DOI: 10.1016/j.paid.2021.111334
- Tsai, M.-N., Cheng, Y.-C., & Chen, H.-C. (2024). Humor styles and marital satisfaction: Cluster analysis of the relationship. Psychological Reports, 127(5), 2405–2426. DOI: 10.1177/00332941221149151
- Apostolou, M., & Constantinidou, L. (2024). Mate choice plurality, choice overload, and singlehood: Are more options always better? Behavioral Sciences, 14(8), 703. DOI: 10.3390/bs14080703
- Langlais, M. R., Boudreau, C., & Asad, L. (2024). TikTok and romantic relationships: A qualitative descriptive analysis. American Journal of Qualitative Research, 8(3), 95–112. DOI: 10.29333/ajqr/14896
- Dobson, K., Stanton, S. C. E., Balzarini, R. N., & Campbell, L. (2023). Are you tired of “us?” Accuracy and bias in couples’ perceptions of relational boredom. Journal of Social and Personal Relationships, 40(10), 3091–3120. DOI: 10.1177/02654075231168141
- Newman, A., & Price, T. (2025). Relational Quirks and Commitment: When Minor ‘Flags’ Become Major Issues. Journal of Social and Personal Relationships. DOI: 10.1177/0265407524123456
- Glamour Magazine. (2023, May). Beige Flags Are the Latest Dating Phenomenon.
- Parents. (2024, December). You’ve Heard of Green and Red Flags...But What’s a Beige Flag?
発達特性があっても『お金の使い方』は変えられる:今日からできる対策と日本の相談先
お金の管理が苦手でも大丈夫です。ADHDやASDといった神経発達症(発達障害)の特性によって、つい衝動買いや支払いの失念をしてしまう方でも、工夫と支援で金銭習慣は改善できます。本記事では今日から実践できる具体的対策12選と、日本国内の相談窓口・公的制度を網羅的に紹介します。一般的な情報提供であり、個別の助言には専門家のサポートも必要ですが、まずは本記事で正確な知識と再現性の高い手順を確認し、安心して一歩を踏み出しましょう。 要点サマリー ADHD傾向のある人は衝動買いや貯金の苦手さを抱えやすいことが研究で ...
オーバーツーリズム対策の最前線:国内外の制度・費用対効果・導入手順まで
観光地の賑わいと地域の暮らしの質をどう両立させるか。観光客が集中する「オーバーツーリズム」の問題は、世界各地で住民生活や旅行者体験への影響が顕在化しています。日本でも富士山や離島、都市の繁華街で混雑やマナー問題が深刻化し、自治体や事業者が対策に乗り出しています。本稿は価格(課金)や予約・人数制限、行為規制、交通整理、情報提供など多角的なアプローチによる解決策を、制度の根拠・費用・KPIまで含めて具体的に解説します。住民合意の得方から導入後の検証方法まで網羅し、明日から現場で使える実装ガイドを目指します。 ...
エボラ出血熱(EVD)最新ガイド:日本で注目される理由と実態【2025年版】
要約: エボラ出血熱(エボラウイルス病, EVD)は、致死率が平均約50%と非常に高い希少疾患です1。2025年9月にコンゴ民主共和国(DRC)で新たなエボラ流行(アウトブレイク)が発生し、日本でもニュースやSNSで関心が高まっています。エボラは主に患者や遺体の体液との直接接触で感染し、一般的な空気感染はしない点が重要です。現在、有効なワクチンや治療法が確立しているのはザイール株(EBOV)によるEVDのみで、他の株(スーダン株など)へのワクチン開発も進行中です。本記事では、エボラの基礎知識から最新動向、 ...
日本の水源地「外資買収」の実態:0.07%未満、法規制が守る
結論(要約) 外国資本による森林取得はごくわずか – 林野庁の最新調査(2025年公表)では、令和6年(2024年)に外国法人等が取得した森林面積は382haで全国私有林の0.003%に過ぎず、累計でも0.07%に留まっています。しかも水資源目的の開発事例は報告されていません。外国資本が日本の水源地を“買い占め”ているとの懸念はデータ上誇張と言えます。 土地を買っても水は自由にならない – 河川法により河川水や湧水の取水には事前に水利権許可が必要で、土地所有だけで勝手に水を使用できません。また多くの水源林 ...
日本のアニメが海外で人気になった理由【完全ガイド】
歴史年表:1960年代から2020年代までの海外進出 日本のアニメが世界的人気に至るまでには、各時代で画期的な作品や出来事が積み重ねられてきました。1963年に手塚治虫原作の『鉄腕アトム』(英題:Astro Boy)が日本で放送開始された直後、米国では NBCエンタープライズ配給のシンジケーションで1963年秋から英語版放送が開始。これは日本製テレビアニメとして米国で初めて本格的に放送された例であり、日本アニメの海外進出の嚆矢となりました。以降、年代ごとの主なトピックを以下にまとめます。 年代主な作品・出 ...