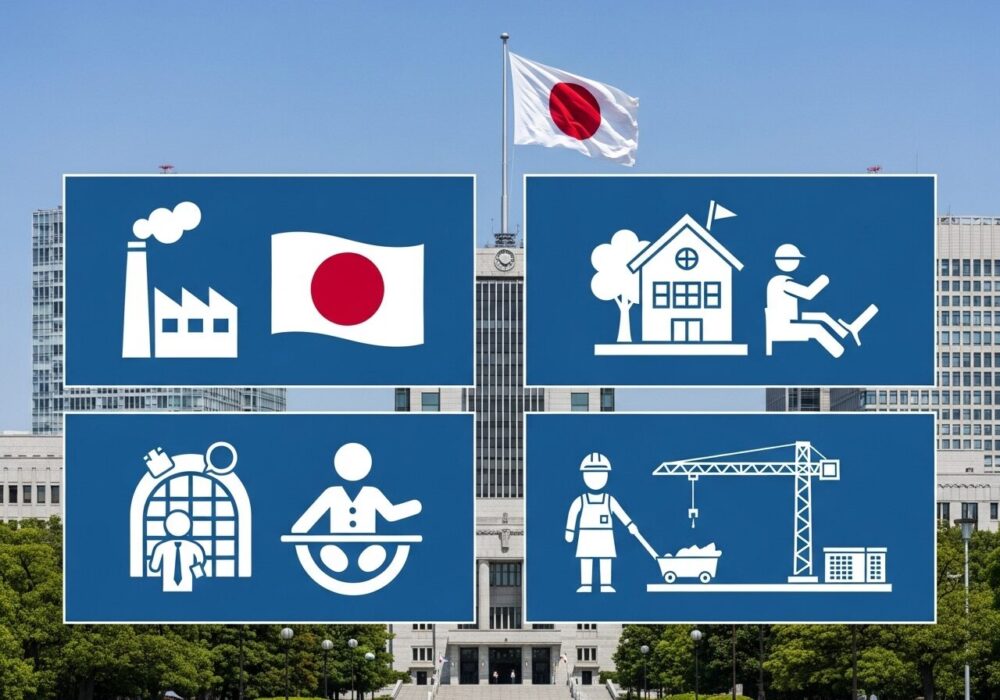
最終更新日:2025-09-17
要約
- 最新の制度改正を一次情報から整理: 技能実習制度は2024年改正法成立により育成就労制度へ移行予定。特定技能の対象分野拡大(12分野→16分野)と5年間の受入れ見込数見直し(約82万人)、難民保護では補完的保護制度創設や送還停止効の例外導入など大きな変更が進行中。各制度の改正日付・根拠を明記し最新動向を解説。
- 制度に潜む「穴」をデータで可視化: 技能実習生の失踪者数は2023年の9,753人(過去最多)から2024年は6,510人へ約33%減少。減少傾向にもかかわらず、仲介手数料の高額負担や賃金・人権問題が失踪の主要因と考えられ、制度上の断絶・監督の弱点が依然存在。複数の統計・調査結果から課題の全体像を提示。
- 実務と政策への提言: 企業は採用前の費用透明化や現場での適正待遇をチェックリスト化すべき。自治体・監理支援機関は多言語相談窓口や医療・住居支援を強化。中央政府には制度接続の円滑化・監督体制の拡充・データ公開の改善が求められる。国際協力では送り出し国とのMOC〔協力覚書〕に基づくブローカー規制の徹底が鍵。実効的な改善策を具体的に提案し、読者の実務・政策アクションにつなげる。
日本の「受入れ制度」全体像(2025年時点)
日本の外国人材受入れ制度は2025年現在、技能実習・特定技能・高度人材など複数の在留資格で構成され、改正入管法により2027年までに技能実習制度が廃止され「育成就労」新制度へ移行する見通しです。技能実習制度(正式名称「外国人技能実習制度」)は開発途上国への技能移転を名目に導入された制度で、2010年代以降に受入れ人数が大幅に増加しました。一方、2019年4月には人手不足分野で外国人就労を認める「特定技能」制度が新設され、中間技能人材の受入れ枠が拡大しました。この他、専門的・技術的分野の高度人材は在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで受け入れられています。
2020年代半ばには制度全体の見直しが進み、2024年には入管法等の改正法成立により技能実習制度を発展解消し、新たな在留資格「育成就労」を創設することが決定しました。育成就労制度は技能実習の後継として位置づけられ、外国人労働者を単なる研修生ではなく将来の戦力として「育成」し、一定の技能習得後に特定技能へ移行させることを目的としています。同改正法(令和6年法律第60号)は2024年6月14日に国会で可決・成立し、6月21日に公布されました。施行は公布日から3年以内(遅くとも2027年6月)と定められています。移行に関する経過措置の具体期間は政省令・告示で定められる段階で、施行日は現時点では未定です。したがって、現行の技能実習生と新制度の育成就労外国人がしばらく混在することになります。
図:主要な在留資格の関係(2025年時点)(※テキストによる簡易図示)
技能実習 (廃止予定) → (技能習得・試験合格) → 特定技能1号 → 特定技能2号(無期限・家族帯同可)
↓ (2027年より新規受入)
育成就労 (最大3年) ───┘(特定技能1号への移行が前提)
上図のように、技能実習制度は育成就労制度へ段階的に置き換えられ、特定技能1号との接続が強化されます。特定技能1号で一定の実務経験と技能試験合格を経た外国人は、分野によって特定技能2号へ移行し在留期限の上限がなくなる(事実上の長期定着ルート)仕組みです。特定技能2号への移行が可能な分野は当初「建設」「造船舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年6月の方針決定等を経て、特定技能2号の対象は『介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業』を除く11分野へ拡大されました。これにより、該当分野の外国人労働者は無期限の在留と家族帯同が可能となり、日本で長期就労・定着できる道が開かれました。
また、2023年(令和5年)の入管法改正では、難民認定制度や収容・送還の制度にも大きな変更が加えられています。難民条約上の難民に該当しないが保護が必要な人を救済する「補完的保護対象者」認定制度が創設され、これまで難民認定されず「人道的配慮」で在留を許可されていたケースを法制度上明確化しました。加えて、難民認定申請中の送還停止効(そうかんていしこう)に例外を設け、3回目以降の難民申請者や重大犯罪者等については審査中でも送還可能とする規定が新設されています。さらに、長期収容問題に対処するため収容に代わる監督付きの「監理措置」制度が導入され、一定条件下で被収容者を施設外で生活させつつ逃亡防止の監督を行う枠組みが整備されました。これら難民・収容関連の改正は2023年6月の国会で可決され、一部は2023年12月1日から施行されています。
表:外国人受入れ制度をめぐる主な法改正・政策決定(2000年代以降)
| 年月(決定日) | 改正・決定内容 | 概要 |
|---|---|---|
| 2009年7月 | 入管法改正(在留カード導入等) | 外国人登録制度を廃止し在留カード制度を導入。在留管理強化 |
| 2017年11月 | 「技能実習法」施行 | 技能実習制度の法制化:外国人技能実習機構(OTIT)設立、監理団体許可制、計画認定制など |
| 2018年12月 | 入管法改正成立(2019年4月施行) | 新たに「特定技能1号・2号」の在留資格創設。出入国在留管理庁(入管庁)発足 |
| 2019年4月 | 「特定技能」制度開始 | 特定技能1号で14業種の受入れ開始(受入れ見込数約34.5万人/5年) |
| 2021年5月 | 入管法改正案 審議見送り | 難民申請者の送還停止効例外規定等を含む改正案が与野党対立で廃案 |
| 2023年6月9日 | 入管法改正成立(難民・収容問題) | 補完的保護制度、送還停止効の例外、監理措置などを創設(2023年12月施行) |
| 2023年11月 | 有識者会議 最終報告書公表 | 技能実習制度を廃止し新たな育成就労制度創設を提言。特定技能制度の活用・改善も提言 |
| 2024年3月29日 | 政府方針決定(特定技能拡充) | 特定技能の受入れ見込数を5年間で82万人に再設定。対象分野を12分野→16分野に追加拡大 |
| 2024年6月14日 | 入管法等改正法成立(育成就労創設) | 育成就労法(技能実習法を改称)制定。技能実習の段階的廃止と育成就労への移行を決定 |
| 2024年6月21日 | 改正入管法等公布(令和6年法59号) | 公布日から3年以内施行を規定。育成就労制度の詳細は今後政省令で整備 |
| 2025年2月6日 | 有識者懇談会 原案提示(育成就労運用) | 送出機関手数料の上限(月給2か月分)設定案や都市部集中回避策など運用素案を提示 |
| 2025年4月28日 | 政省令案 公示(パブリックコメント) | 育成就労実施機関の都市部受入れ枠制限等を含む政省令案を公表。意見募集開始 |
| (参考)2027年 | 育成就労制度開始(予定) | 育成就労制度施行。技能実習制度での新規受入れ停止(移行期間開始) |
このように、ここ数年で日本の外国人材受入れ制度は大きな転換期を迎えています。以下では、主要な制度(育成就労・特定技能・難民保護)のポイントと課題を詳しく解説し、制度横断的に存在する「穴」(構造的な欠陥や運用上の課題)をデータに基づき検証します。
技能実習→育成就労:何がどう変わるか
2024年成立の改正法により、開発途上国支援を名目とした技能実習制度は廃止され、人手不足分野の人材確保と人材育成を目的とする育成就労制度に生まれ変わります。新制度「育成就労」は法律名称も「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)と改められ、その目的は「特定技能1号水準の技能を有する人材の育成」と「育成就労産業分野における人材の確保」です。これは従来の技能実習法が掲げていた「開発途上地域等への人づくり協力」という建前から国内産業の労働力確保へ明確にシフトしたことを意味します。
仕組みの変更点: 育成就労制度では、在留資格「技能実習」が廃止され、代わりに在留資格「育成就労」が新設されます。育成就労ビザでの在留期間は原則最長3年で、これは従来の技能実習(最長5年)より短縮されています。3年間の育成就労期間内に計画的なOJTを通じて特定技能レベルの技能を身につけ、所定の技能試験および日本語試験に合格すれば特定技能1号へ移行できます。試験合格が移行の必須条件となる点は技能実習制度との大きな違いで、旧制度では技能実習2号を良好修了すれば試験免除で特定技能に移行可能でしたが、新制度では試験合格が不可欠です。試験不合格は『相当の理由』に当たり、同一実施者の下で最長1年の在留継続(再受験猶予)が可能です。
育成就労では「育成就労計画」の認定制度が導入されます。受入れ企業ごとに外国人ごとの育成計画を作成し、出入国在留管理庁長官および厚労大臣の認定を受ける必要があります7。この計画には育成すべき主要技能(特定技能と同一の業務区分内で設定)や日本語習得目標などが盛り込まれ、計画に沿って3年間で特定技能水準に達することが求められます。具体的には1年目終了時までに技能検定基礎級および日本語A1試験合格、3年以内に技能検定3級または特定技能評価試験+日本語A2試験合格といったマイルストンが設定されます。計画の進捗は試験等で評価され、達成できない場合は延長なしで帰国となるため、実習生任せの形骸化した研修にならないようPDCAサイクルを厳格化した仕組みと言えます。
監理団体から監理支援機関へ: 新制度でも従来の監理団体は存続しますが名称が「監理支援機関」に変わり、その役割はほぼ同様に維持されます。監理支援機関は主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可制で事業を行い、受入れ企業(育成就労実施者)に対する指導監督や外国人への支援業務(生活指導、日本語学習支援など)を提供します(OTITに代わる『外国人育成就労機構』は別途設置予定)。用語上は変わっても、許可制・監理責任といった基本的枠組みは技能実習制度から引き継がれるとされています。ただし監理団体のガバナンス強化策として、監理費用や支援内容の透明化、悪質団体への許可取消し基準の見直し等が検討されています5。新名称の「監理支援機関」には単なる監視役に留まらず、外国人の日本での能力向上や生活支援に積極的に関与する期待が込められています。
転籍(企業変更)の可否: 技能実習制度では原則転籍禁止(やむを得ない事情のみ許可)でしたが、育成就労制度では転籍ルールが大きく緩和されます。まず、人権侵害・賃金不払いなどの「やむを得ない事情」による転籍は引き続き認められ、その判断基準が「契約と実態の労働条件が異なる場合」などまで拡大・明確化されました。さらに新制度では外国人本人の希望による転籍申出制度が新設され、一定の要件の下で自己都合転籍も可能となります。政府は「3年間同一機関で計画的育成することが望ましい」との方針を示しつつも、法律上は以下の条件を満たせば転籍を認めることとしています。
- ①分野一致:転籍先が現在と同じ業務区分(分野)であること。
- ②一定期間就労:元の受入れ機関で所定の期間以上勤務していること(分野ごとに1~2年の範囲で設定予定/③技能検定基礎級等と分野ごとに設定するA1~A2相当の日本語試験合格)。
- ③技能・日本語要件:技能検定基礎級および一定水準以上の日本語能力試験に合格していること(各分野でA1~A2レベル内で設定予定)。
- ④適正実施先:転籍先企業が育成就労を適正に実施できる基準を満たすこと。
- ⑤計画認定:転籍先で新たに育成就労計画の認定を受けること。
以上が主な条件です。②の「一定期間」は例えば少なくとも1年間などと想定されています。③についても基本的な技能試験合格と日常会話レベルの日本語力を転籍前に身につけている必要があり、簡単に転籍できる訳ではありません。それでも本人希望による企業変更を制度上認めた意義は大きく、劣悪な職場環境への「閉じ込め」に歯止めをかけることが期待されます。また、転籍に伴う課題として、初期渡航費用等を負担した元の受入れ企業の損失をどう補填するかがあります。政府案では転籍先企業による費用分担や元の企業への補償の仕組みも検討されており、詳細は政省令で規定予定です。
受入れ分野・人数: 育成就労制度で受入れ対象となる産業分野(育成就労産業分野)は、現行の技能実習の職種・作業区分を機械的に踏襲せず、特定技能制度の対象分野を基準に再編成されます。つまり、国内での人材育成に適する分野のみを選定し、特定技能1号への移行を見据えた一貫性のある分野設計が行われる予定です。季節性のある分野(農業・漁業)では、派遣形態による育成就労の実施が認められる方向です(※育成就労外国人が派遣社員の形で複数企業の繁忙期に就労することを容認する措置)。これは現行の技能実習制度下で農閑期に人手が遊休化する問題への対処といえます。
受入れ人数枠については、特定技能制度と同様に分野ごとの5年間の見込数(上限数)を政府が設定します。技能実習では公式な受入れ枠はありませんでしたが、育成就労では各分野ごとに上限管理される見込みです。政府は2023年末時点で日本に在留する技能実習生約40万5千人、特定技能外国人約21万人という状況を踏まえ、育成就労制度で受け入れる人数も相当規模になると見込んでいます。実際、特定技能について政府は2024年度から5年間の受入れ見込数を82万人と大幅増加(従来計画約34.5万人の2.4倍)に見直しました。育成就労から特定技能への円滑な移行が図られるとすれば、育成就労の受入れ総数も数十万人規模に上る可能性があります。
送り出し機関と費用負担: 新制度でも、外国人を募集・送り出す現地の認定送出機関の関与は続きます。ただし技能実習で深刻だった高額手数料や不透明な仲介費用の問題に対処すべく、政府は送出機関に支払う手数料に明確な上限を設ける方針を示しました。2025年2月の有識者懇談会原案では、送出手数料の上限を「来日後の月給の2か月分」とし、育成就労計画の審査段階で実際の手数料額を申告させる案が盛り込まれています。例えば月給20万円の場合、送出機関へ支払う手数料は最大40万円までとなり、過度な借金負担を軽減する狙いです。ただしこの上限設定は2025年時点での省令案段階であり、実施には送出国側との協調や現場での遵守確保が課題となります6。
費用透明化の観点では、送出機関に関する情報公開ルールも強化されます。既に日本は主要送出国との間で二国間協力覚書(MOC)を締結し、各国政府が認定した送出機関リストを相互に管理しています9。今後、育成就労計画の認定時に送出機関名や徴収費用を開示させ、日本側でも不適正事案を把握次第送出国政府へ通報するなどの連携が進む見込みです。実際、日本は2018年以降ベトナムや中国を含む15か国以上とMOCを締結し、2022年8月時点で送出機関の不正事案137件を通報するなどの対応を取っています9。しかし、送出国側の処分実効性にはばらつきがあり、制度の穴①「送り出し段階での規制不徹底」は依然残る懸念があります。この点は後節でデータと併せて詳述します。
転籍制限と地方偏在対策: 自由転籍を認めることで懸念されるのが、都市部への人材過集中です。日本語や待遇の良い都市企業に人材が流出すれば、地方の人手不足解消という目的が損なわれかねません。そこで政府案では、大都市圏で受け入れる育成就労外国人の数に上限枠を設けることや、地域別の受入れ推進策が検討されています。具体的には、転籍による都市部への移動を抑制するため、都市圏の企業が一定数以上の育成就労外国人を転籍受け入れすることを制限する省令を定める案です。同時に、地方企業に対しては受入れ人数枠を拡大し、優良な地方の受入れ機関には手続簡素化などインセンティブを与える方策も検討されています。この地方偏在対策により、育成就労制度が本来の目的である地域の人材確保に資するよう誘導する狙いです。
以上のように、育成就労制度は技能実習制度の欠点を是正しつつ、特定技能制度と接続する橋渡しとなるよう設計されています。ポイントは「計画的な人材育成」と「途中離脱の減少」であり、その達成には受入れ企業・監理支援機関・送出機関が一体となった実効ある運用が不可欠です。新制度は2027年開始予定ですが、今後2年間で詳細な政省令や分野別運用方針が定められていきます。本記事では最新情報に基づきアップデートを続け、企業・関係者が備えるべきポイントを提言します。
特定技能:分野拡大と5カ年見込数
特定技能制度(在留資格「特定技能」)は2019年に始まった比較的新しい受入れ制度ですが、2024年に対象分野の追加拡大と受入れ人数計画の大幅見直しが行われました。特定技能は深刻な人手不足分野で一定の技能・経験を持つ外国人に就労を認める制度で、1号と2号の2区分があります。特定技能1号(在留期間上限5年・家族帯同不可)は当初14業種(介護、外食、製造業等)でスタートし、その後建設分野の細分化などにより公式には「12分野」に整理されています。2024年3月29日の閣議決定で、この特定技能1号の対象分野に『自動車運送業』『鉄道』『林業』『木材産業』の4分野が新規追加され、合計16分野となりました。新たに追加された分野は物流・インフラ系を中心に、国内で人材不足が顕著な領域です。また既存分野についても、例えば外食業で調理補助以外の業務を解禁するなど業務範囲の拡張が検討されています。
5年間の受入れ見込数(上限数)の再設定: 特定技能制度では制度開始時に各分野ごと5年間の受入れ見込数(上限)を定め、実際の受入れ運用で上限として扱ってきました。【前回計画】2019年度~2023年度の5年間で全分野合計約345,150人という目標が設定されていましたが、実績として2023年末時点で在留中の特定技能外国人は約20.8万人に留まりました(コロナ禍による入国制限も影響)。これを受け政府は新たな5カ年計画として2024年度~2028年度に合計82万人を受け入れる目標に引き上げました。約2.4倍への増枠となるこの方針は2024年3月の閣議決定で正式に決まり、受入れ上限数82万人は各分野別に内訳が示されています。例えば製造業関連(「工業製品製造業」)17.3万人、飲食料品製造13.9万人、介護13.5万人、建設8万人、農業7.8万人など。このように幅広い分野で大幅増となり、「特定技能で年間16万人超ペース」の受入れを目指すことになります。背景には、ウィズコロナ下での国内労働力不足の深刻化と国際的な人材獲得競争への対応があります。
実際の受入れ動向を見ると、2024年6月末時点の特定技能在留者数は251,747人(速報値)です。制度開始から5年弱で20万人超となった計算ですが、新計画達成にはさらにペースアップが必要です。政府は特定技能試験の国内外での実施拡充、マッチング支援、地方での共生支援策など総合的な受入れ促進策を展開中です。また、特定技能制度を活用する企業側に対しても、待遇や日本人との同等報酬確保の指導、分野別協議会への加入義務化(育成就労法で新設)など、質の担保策が強化されます。特定技能は基本的に雇用契約ベースの制度であり、企業が即戦力人材を海外から直接雇用するルートとして期待されています。
特定技能2号の拡大: 特定技能制度の特徴の一つが、2号への移行で長期在留・家族帯同が可能になる点です。特定技能2号は「熟練した技能」を持つ外国人向けで、在留期間更新に上限がなく配偶者・子の帯同も認められます。当初は建設分野と造船・舶用工業分野の2分野だけが対象でしたが、政府は2023年6月に対象分野を一気に11分野へ拡大することを決定しました。追加された9分野には介護を除く特定技能1号の主要分野(ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報の製造3分野、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造など)が含まれます。これにより、例えば外食業や宿泊業で特定技能1号として経験を積んだ外国人も、試験等で一定の熟練を証明すれば特定技能2号に移行して長期在留できる道が開かれました。2023年6月9日付の閣議決定に基づき制度改正が進められ、追加9分野については2023年秋以降順次2号への移行手続開始となっています。特定技能2号への門戸拡大は、事実上の移民受入れ政策への一歩とも評されますが、人材の定着促進と技能継承には有効との期待が高まっています。
技能実習・育成就労との接続: 特定技能制度は育成就労制度と表裏一体の関係になります。育成就労は「特定技能1号への円滑な橋渡し」が目的であり、特定技能1号→2号→長期定着というステップの入り口に位置づけられます。政府の想定するモデルケースでは、送り出し国で基礎的日本語を学び育成就労で3年就労、その後特定技能1号として追加2年間就労、一部がさらに特定技能2号で無期限就労…という流れです。育成就労の段階で技能試験等に合格できなかった者については、最長1年の延長後に帰国となりますが、他方で技能実習2号良好修了者など既存の戦力は特定技能への直接移行も引き続き可能です。実際、特定技能1号の在留者約22万人の中には元技能実習生が相当数含まれており、制度接続の重要性が増しています4。2024年6月の育成就労法成立以降、技能実習から特定技能への移行数も急増しており5、移行試験の整備や情報周知が急務となっています。
受入れ企業側の留意点: 特定技能で外国人を受け入れる企業には、受入れ基準として(1)外国人と直接雇用契約を結ぶこと、(2)報酬額は日本人同等以上、(3)1号の場合は登録支援機関または自社による支援計画実施、(4)分野別協議会への加入などが求められます。特に2024年以降、育成就労法の規定で特定技能受入れ企業は分野別協議会加入が義務化される見通しであり、業界単位で受入れ環境整備に取り組む枠組みが強まります。企業にとっては単なる人手確保策ではなく、外国人材が長く活躍できる職場づくり(教育訓練、昇進機会、ハラスメント防止等)が重要です。特定技能2号への移行要件としては原則技能検定1級等の取得が必要なため、企業が計画的にOJTや技能試験受験をサポートする姿勢も問われます。
最新の受入れ状況: 2024年6月末時点で、特定技能在留者数は約25.2万人(251,747人)(うちベトナム・中国・フィリピンの順に多い)に達し、特定技能2号も数百人規模ながら建設・造船分野で徐々に増加しています。政府は2025年以降、特定技能制度をさらに拡充すべく「特定技能評価試験」のオンライン化や海外試験センターの増設、送り出し国とのマッチングイベント開催などを予定しています。一方で受入れ現場からは「日本語要件(原則N4相当)のハードル」や「在留期間満了後のキャリアパス不安」などの課題も指摘されています。これらについても、特定技能2号の拡大や育成就労との連携強化によって順次改善が図られる見通しです。
難民申請と補完的保護・監理措置
日本の難民認定制度は、近年ようやく認定者数が増加傾向を見せ始めたものの、申請数に比して極めて認定率が低い状況が続いています。法務省入管庁の統計によれば、2024年(令和6年)に難民認定申請を行った外国人は12,373人(前年比▲10.5%)で、そのうち正式に難民と認定されたのは190人(前年比▲37.3%)でした。認定率にすると約1.5%に過ぎず、欧米諸国と比べ非常に厳格です。ただし190人という数字自体は日本の過去実績では3番目に多い値で、特にアフガニスタン出身者102人とミャンマー出身36人が大半を占めました。これらの国では政変や人道危機が起きており、日本政府も近年は該当国出身者への保護に比較的前向きな対応を取っています(例えば2021年のミャンマー軍事クーデター後、在日ミャンマー人に在留延長特例を認めた等)。一方で、主な申請国はスリランカ、タイ、トルコ、インド、パキスタンといったアジア諸国で占められており、経済的理由での申請と見做されるケースが多いためか認定には至っていません。
補完的保護対象者制度: 2023年改正入管法で創設されたこの新制度は、「難民条約上の難民には該当しないが、本国に戻れば生命や身体に危害を受けるおそれがある者」を保護する仕組みです。具体的には、内戦や紛争から逃れてきた人(迫害理由が人種・宗教など条約難民の要件に当てはまらないケース)や、難民には該当しないが重大な人権侵害(拷問や死刑執行など)の危険がある人を想定しています。従来、日本ではそのような人々に対し明文化されたステータスがなく、法務大臣の裁量で「人道上の配慮」による在留特別許可が与えられていました。改正法ではこれを制度化し、「補完的保護対象者」に認定された場合は在留資格「特定活動」(1年更新)で滞在が許可されます。権利面では就労も可能で、社会保障なども難民認定者に準じた扱いとなります。初年度となった2024年には1,661人が補完的保護対象者に認定されました。その内訳を見るとウクライナ国籍が1,618人と大半を占めます。これはロシアのウクライナ侵攻後に日本が受け入れたウクライナ避難民が、この新制度によって公式に保護対象者として位置づけられたことを意味します。ウクライナ避難民以外にも、アフリカや中東の紛争地域出身者など数十名が補完的保護に認定されました。補完的保護制度は、国際基準でいう「紛争難民」「庇護申請者」への国内法上の保護枠を整備したもので、日本の難民政策の長年の課題であったグレーゾーンを一つ埋める措置と評価できます。
送還停止効の例外導入: もう一つの改正ポイントは、難民認定手続き中の強制送還停止ルールに例外を設けたことです。従来、日本では難民認定申請中であれば在留特別許可がなくても一律に強制送還を停止する運用(送還停止効)が取られてきました。これが逆手に取られ、意図的な難民申請の繰り返しによる送還回避(いわゆる「駆け込み申請」)が問題視されてきました7。改正法では、(1)過去に2回難民不認定となり3回目以降の申請をしている者、(2)無期または3年以上の実刑を受けた前科のある者、(3)テロリスト等については、難民申請中であっても送還停止効を適用せず強制送還を可能とする例外を定めました。ただし、これらの場合でも入管法53条3項の「ノン・ルフールマン原則(迫害のおそれある国への送還禁止)」は維持されます。つまり、たとえ3回目の申請者であっても本当に迫害リスクが高い国への送還はしないとされています。しかし人権団体や国連機関からは、この例外規定は難民条約の趣旨に反し乱用のおそれがあると懸念が示されています。特に「3回目以降申請は送還可」とする基準については、真に迫害から逃れてきた人でも複数回不認定となる場合がある(日本の難民認定率が極めて低いため)との指摘があります。政府は運用上、「例外該当でも難民該当性の判断は行う」と答弁していますが、適用には慎重さが求められます。
監理措置(非収容での監督制度): 収容・送還に関する改正の中で画期的なのが、収容主義を転換する「監理措置」制度です。日本の入管収容はこれまで「原則全件収容主義」と言われ、不法滞在者や退去強制手続き中の者は原則施設に収容されてきました。しかし長期収容問題が深刻化し、2021年には収容中のスリランカ人女性が死亡する痛ましい事件も起きています。監理措置制度は、一定の条件の下で被退去強制者を収容せず社会内で生活させながら手続きを進める新たな措置です。具体的には、逃亡や証拠隠滅を防ぐために身元保証人的な「監理人」を選任し、その監理の下で定期的な報告や住居制限などを課したうえで仮放免以上に長期間の社会生活を許容します。監理人には日本に住む家族や支援団体の職員などがなり得ますが、営利目的での就任は禁止され、1人の監理人が複数の被監理者を受け持つことも制限されています3。要件として入管当局が「逃亡の恐れが低い」と判断したケースに限られますが、適用されれば例えば難民申請中の人が収容施設に入らず自宅等で生活を続けられるメリットがあります。
監理措置の申請は原則として外国人本人から入管への申し出で開始されます。退去強制令書発付前(審査中)と発付後(仮放免中)で制度の位置づけは異なりますが、いずれにせよ入管が許可すれば監理人の監督下で地域社会での生活が認められます。監理措置の義務違反に対しては罰則(1年以下の懲役又は罰金等)が規定されています。収容に代わる措置としては世界的にも厳格な運用との指摘もあります。しかし、これにより一部とはいえ入管施設の長期収容者を減らし、被収容者の人道的待遇改善につながることが期待されます。2024年以降、監理措置の適用事例が徐々に出始めており、難民申請者のうち収容中だった人が監理措置で地域に出るケースも報告されています。
なお、なお、2023年改正では『退去命令制度(罰則付き)』が新設されました。これは、不法残留の外国人が自主的に出頭して帰国を希望する場合に一定の手続で退去を命じ、応じない場合は刑事罰を科すものです。従来、出頭して自費帰国した不法滞在者には上陸拒否期間短縮の優遇がありましたが、さらに確実に退去させる仕組みとして設けられました。これも送還忌避への対策の一環です。
難民認定手続の迅速化: 改正入管法には含まれませんでしたが、難民審査の迅速化・公正化も引き続き課題です。法務省は難民審査参与員(第三者有識者)が関与する異議申出審査を運用していますが、申請から結果通知まで平均で数年を要するケースが多々あります。出入国在留管理庁は審査官の増員やオンライン申請導入、出身国情報の充実などに取り組むとしています。2024年の統計では難民認定申請処理数8,377人(前年比+2.4%)と発表され、処理件数は一応増加傾向にあります。しかし依然として処理待ち案件は累積しており、申請者が結果を待つ間に就労も医療保障も不安定な状況が生じています。2025年以降、補完的保護制度の運用と併せて難民審査のプロセス改善が求められています。
データでみる「制度の穴」
日本の外国人受入れ制度には、設計上および運用上の「制度の穴」がいくつも指摘されています。この章では、統計データや調査結果から主要な課題を浮き彫りにします。
技能実習生の失踪問題:規模と要因
技能実習生の「失踪」問題は、日本の外国人労働者受入れ制度の信頼を揺るがす深刻な課題です。失踪とは、監理団体や受入れ企業が実習生と連絡不能になり所在不明となる事態で、多くはそのまま資格外活動(不法就労)や不法残留に移行するとみられています。以下は近年の失踪者数の推移です。
- 2014年(平成26年): 失踪者数 4,847人(在籍実習生約24万人、失踪率約2.0%)
- 2018年(平成30年): 失踪者数 9,052人(在籍実習生増加に伴い過去最多を記録)
- 2019年: 8,796人(前年比微減も高水準維持)
- 2020年: 5,885人(コロナ禍で新規入国停止の影響)
- 2021年: 6,182人(コロナ禍2年目)
- 2022年: 9,006人(入国再開で再び増加)
- 2023年(令和5年): 9,753人(前年比+~2,586人、失踪率約1.9%で過去最多更新)
- 2024年(令和6年): 6,510人(前年比▲3,243人、約33%減少し失踪率約1.2%に改善)
2023年に失踪者が1万人近くに達したことで社会問題化し、「年間1万人が消える制度」などと批判を浴びました。しかし2024年は一転して大幅減少となり、入管庁は「受入れ企業の待遇改善等の効果もあり得る」と分析しています。もっとも、この減少には裾野の変化も影響しています。技能実習生全体数は2023年末時点で約40.5万人とピークに達しており、2024年以降新規受入れ縮小が見込まれるため、今後失踪「率」ではなく絶対数自体が減る傾向が続く可能性があります。したがって、2024年の減少が必ずしも構造的改善を意味しない点には注意が必要です。
では、失踪の主な原因は何でしょうか。専門家の分析や関係機関の報告によれば、大きく以下の二点に集約されます。
- (1) 受入れ側の不適正な取扱い: 賃金の未払い・遅配、違法な長時間労働、劣悪な労働・生活環境、パワハラ・セクハラなどにより、実習生が職場に耐えられなくなるケースです。契約と異なる低賃金で働かされたり、人権侵害を受けたりすると、逃げ出してしまうのは自然な結果とも言えます。実際、厚労省の監督指導で毎年実習生受入企業の約7割で労基法違反が見つかるとのデータもあり、未払い残業代の是正勧告などが後を絶ちません。
- (2) 実習生側の経済的事情: 多くの実習生は来日するために母国の仲介業者へ高額の手数料を支払い、その多くは借金で賄われます。日本での収入は最低賃金レベルが多く、そこから月々借金を返済すると手元にほとんど残りません。そのため「もっと稼げる職場」を求めて失踪し、不法就労で高賃金を狙うケースが後を絶たないのです。
特に(2)の問題、送り出し時に背負う借金は失踪と強く相関します。出入国在留管理庁の実態調査によれば、来日前に送出機関等へ費用を支払った実習生は全体の約85%に上り、その平均額は約52万1,000円に達します。国別ではベトナムが平均約65万6,000円と突出して高く、中国・カンボジア・ミャンマーも57万円前後と報告されています。この費用は多くが借金で、利子を付けて返す必要があります。ところが日本の実習先で受け取る賃金は月12~15万円(手取り)程度が一般的で、そこから借金返済や仕送りをすると生活も苦しい状況です。「借金返済のためには違法でも高賃金の仕事に就くしかない」と実習先から逃げ出す心理は理解できるものです。
実際、国別の失踪率データは費用負担との関連を如実に示します。例えば2022年時点でフィリピン人実習生は約3万人在留していましたが、同年の失踪者はわずか70人(失踪率0.2%)でした。フィリピンは政府管理の送り出し制度があり、仲介手数料の上限制や徹底した教育で知られます。その一方、ベトナム人実習生は同年失踪率3.4%と突出して高く、台湾など他国でもベトナム出身労働者の失踪率が極端に高いことが確認されています。台湾では外国人労働者約75万人中、2022年に4万人以上が失踪しましたが、その83%がベトナム人だったとの報告があります。台湾では労働者の自由転職が認められているにも関わらず失踪が多発しており、要因はやはり「高額手数料の借金を抱えて来ているから」に他なりません。このことは、制度の穴②「仲介手数料・借金問題」が解決しない限り、転籍制限を緩和した程度では失踪防止に限界がある可能性を示唆します。
他にも、情報の非対称性(実習生が日本の労働法や相談先を知らず泣き寝入りしやすい)、監督体制の弱さ(監理団体やOTITによる抜き打ち検査の頻度・網羅性の問題)なども失踪を助長する要因とされています。さらには、一部で囁かれるブローカー組織の存在も無視できません。都市部には失踪者を集め不法就労先を斡旋する闇ブローカーがおり、「技能実習修了証」を偽造して職に就かせる事件も摘発されています。ベトナム人コミュニティではSNSを通じて失踪者同士が情報交換し、不法滞在のままコミュニティに潜む例も報告されています。こうした「闇市場」の存在は制度の穴③とも言えるでしょう。
政府もこの状況を重く見ており、送り出し国への働きかけ強化(例:ベトナム政府への規制促進)や、企業への周知(失踪防止マニュアル配布等)、失踪者発生時の迅速通報と警察連携など対策を講じています。2023年にはベトナムが送出機関手数料の国内上限制度を改正(上限額を従来の3,600ドルから「日本での3か月分給与相当額-送出機関への企業側手数料3年分」に変更)する動きもあり、日本側の要請に応じたものとされています。もっとも規制値は依然実態とかけ離れて守られていないとの指摘もあり、国際協調だけでは限界があります。
「制度の穴」マッピング
以上の失踪問題を中心に、技能実習・特定技能制度に横たわる主な課題(制度の穴)を整理します。
- 制度の穴① 設計上の断絶: 技能実習から特定技能への移行経路が限定的で、多くの技能実習生が5年在留後に帰国を余儀なくされてきました。2019年の特定技能創設で改善しましたが、依然一部業種では特定技能2号(無期限)に進めないなど断絶があります。また技能実習と特定技能で所管官庁やルールが異なり一貫性に欠ける問題もありました(育成就労制度で統合改善を図る予定)。
- 制度の穴② 仲介手数料と債務: 前述の通り、高額な送り出し手数料と借金が外国人を苦境に追い込み、失踪・不法就労の温床になっています。各国とのMOC締結や上限制導入は進んでも、実効性確保が難しくブローカーの排除が徹底できていません。情報格差を悪用した不当な金銭徴収を封じ込める具体策が不十分です。
- 制度の穴③ 運用上の監督・救済の弱さ: 労働法令違反に対する抑止力が十分でなく、悪質企業・監理団体への罰則も限定的です。仮に技能実習計画取消処分(レッドカード)が出ても、その企業への制裁は一時的受入停止に留まります。また被害に遭った実習生が安心して相談・救済を求められる窓口が十分でないとの指摘もあります。OTITや入管に訴えても在留継続が保証されない不安や言語の壁があり、泣き寝入りしがちです。
- 制度の穴④ 情報非対称と言語課題: 実習生・労働者が日本の法律や権利について十分知らされないまま来日し、企業側の一方的ルールに従わされるケースがあります。契約書が母語で提供されない、就業規則の理解支援がない等、外国人側が著しく不利な情報ギャップが存在します。また監理団体・企業側も外国人の文化・宗教への理解不足からトラブルになる例が散見され、相互のコミュニケーション不足が問題解決を難しくしています。
- 制度の穴⑤ データの不透明性: 技能実習生の賃金水準や失踪後の追跡、送出し時の費用内訳など、重要なデータが網羅的に公開されていません。制度改善にはエビデンスが不可欠ですが、現状は断片的な公表資料に頼らざるを得ず、政策評価や第三者検証が困難です。例えば失踪者のその後の所在(帰国か国内潜伏か)について統計がなく、実態把握が不十分です。
- 制度の穴⑥ 国際スタンダードとの乖離: ILOや米国務省など国際機関からは、技能実習制度の強制労働的側面を度々指摘されています。具体的にはパスポートの取上げ、自由転職不可、低賃金による債務労働などが「人身取引のリスク要因」とされ、日本は2020年以降TIP報告でTier2(改善努力必要)に格付けされています。こうした国際評価を真摯に受け止め、制度全体を人権尊重型にアップデートする視点がまだ不足しています。
以上のような制度的課題は互いに絡み合い、一朝一夕に解決できるものではありません。ただ、2024年の法改正と新制度設計はこれら制度の穴を一つ一つ埋めていく契機になると期待されます。次章では、具体的に各ステークホルダー(企業、監理支援機関、自治体、政府、国際機関)が取り組むべき改善策を提示します。
ステークホルダー別の実務対策
制度の穴を塞ぎ、外国人材が安心して働ける環境を整えるには、関係する全てのステークホルダーが役割を果たすことが不可欠です。ここでは、企業、監理支援機関・自治体、中央政府、そして国際協力の各レベルでの具体策を提案します。
企業(受入れ機関)へのチェックリスト
受入れ企業は外国人材との直接の雇用関係を担い、現場環境を左右する最重要プレーヤーです。企業が適切な対応を取れば、多くの問題は未然に防げます。以下、企業向けに採用前から就労中までのチェックリストをまとめました。
- 採用前:適正な送り出し機関選定 – 候補者がどの送出機関経由で来るかを確認し、可能な限り日本政府とMOCを締結している国・認定機関から受け入れる。契約書類は母国語翻訳付きで交付し、仲介費用の借金状況も把握しておく(借金ゼロを推奨)。候補者に対して事前に労働条件・待遇を丁寧に説明し、来日後のミスマッチを防ぐ。
- 受入れ初期:生活支援とオリエンテーション – 来日直後の外国人には住居確保・開設手続き(銀行口座、携帯契約等)を支援する。併せて労働法令・職場規則の教育を実施し、「残業代は必ず支払われる」「困ったときは社内外で相談できる」など基本的権利を周知。第三者相談先(労基署や入管庁相談窓口、JICA支援センター等)もリストで渡す。日本人従業員にも外国人と働く心得を共有し、文化習慣への理解を促す。
- 就労中:適正労務管理 – 契約賃金・時間外手当を確実に支払い、給与明細を本人が理解できる言語で提供する。また定期面談を実施し、職場での悩みや不満を吸い上げる体制を作る。ハラスメント防止研修を全従業員対象に行い、「外国人だから」と差別的扱いをしない企業風土を醸成。休日の過ごし方支援(地域交流イベント紹介等)も行い孤立を防ぐ。
- 能力開発:日本語と技能向上の支援 – 就業後も日本語学習の機会を提供する。勤務時間内研修の実施や、日本語学校の夜間講座費用を補助するなど検討。また、社内OJT計画を整備して技能検定試験への合格をバックアップする。これは育成就労計画や特定技能への移行にも直結する重要事項。技能実習生であれば、3年目終了時に基礎級試験、5年目に3級試験合格を目標に段階育成する。
- 評価と将来像:モチベーション管理 – 外国人材にも適正な人事評価と昇給昇格機会を与える。リーダー的役割を担えば手当を支給し、本人の成長を認識・承認する。特定技能2号取得の見込みがあれば、正社員登用や永住支援など長期ビジョンを提示して定着を図る。もし契約満了で帰国する場合も、修了証明や次のキャリアにつながる推薦状を発行するなど、本人の将来に資するサポートを行う。
- 転籍希望への対応: 本人から転籍希望の申し出があれば、頭ごなしに否定せずまずは理由を傾聴する。賃金不満や人間関係など解決可能な問題なら改善策を提示する。どうしても希望が強い場合は、育成就労法上認められた権利として尊重し、監理支援機関・入管と連携して円満に手続きを進める。転籍先企業に対して初期費用の一部補填を求める制度も活用し、自社の損失を最小化すると同時に本人のキャリアを応援する姿勢を示す。
- 緊急時対応: 失踪の兆候(無断欠勤や情緒不安定など)を察知したら、迅速に監理支援機関や本人の同郷者等と協力しフォローアップする。万一失踪した場合も警察・入管に即通報し、隠蔽しない。また災害・疾病など有事の際の安否確認フローを整備し、日本人従業員と同様に対応する。
以上のチェックリストを経営層から現場管理者まで共有し、定期的に実施状況を点検することが重要です。企業自身が「選ばれる受入れ先」になることで、優秀な外国人材の確保と定着につながり、結果的に生産性向上にも寄与します。実習生・特定技能の受入れ実績が豊富な企業では、人事担当者を外国人材専任にしたり、社内に相談ホットラインを設けたりと工夫が進んでいます。中小企業でも監理支援機関等と連携してこれら施策を取り入れ、外国人が能力を最大限発揮できる環境を整えましょう。
監理支援機関・自治体による支援策
監理支援機関(旧監理団体)と地方自治体は、外国人材を直接雇用する立場ではありませんが、第三者支援の要として重要な役割を担います。
監理支援機関の役割強化: 監理支援機関は法律上、受入れ企業への指導監督と外国人への支援を行うことになっています。実効性を高めるため、以下の取り組みが推奨されます。
- 定期巡回とヒアリング: 配属先企業を月1回以上訪問し、外国人と直接面談して困り事を聞き取る。通訳を介し母語で本音を引き出すことで、企業には言えない不満や体調不良なども早期に察知できる。面談内容は記録し、必要に応じて入管や労基署と情報共有する。
- 緊急相談ホットライン: 外国人材が24時間相談できるホットライン(多言語)を監理支援機関単独または複数団体共同で設置する。夜間・休日にも繋がる電話やSNS窓口を用意し、トラブル発生時に駆け込み先となる。相談があった場合は迅速に関係機関と連携し、解決に動く。
- 生活支援プログラム: 例えば日本語学習会の開催、地域ボランティアとの交流イベント企画、ゴミ出しや交通ルールなど生活マナー指導など、外国人の日常生活を支えるプログラムを組む。病気の際の病院同行や、銀行口座・税金手続き支援などきめ細かいフォローも行う。
- 転籍支援: 育成就労制度下では、監理支援機関が転籍希望をする外国人の申出受付や適切な転籍先紹介などに関与し得る。移籍を望む外国人が孤立して暴走しないよう、公正な仲介役を果たすことが期待される。既存のネットワークを活かして他の受入れ企業候補を探すなど、失踪させないセーフティネットとして機能する。
- データ分析と共有: 自団体で受け入れている外国人に関するデータ(国籍別人数、失踪者数、トラブル事例など)を蓄積し、定期的に企業や行政と共有する。傾向を把握して問題の予兆に早めに対処できるようにする。
地方自治体の多文化共生施策: 外国人材が増加する地域では、自治体も受入れ体制整備に乗り出しています。今後さらに重要となる自治体の取り組み例を挙げます。
- 多言語相談窓口: 市区町村役場や国際交流協会に多言語対応の相談窓口を設置し、在住外国人の生活相談に応じる。労働問題については法テラスや労基署と連携し、適切に専門機関につなぐ仕組みを作る。
- 日本語教育支援: 地域の日本語教室や日本語教師ボランティアをマッチングし、外国人材が無料または低廉で日本語を学べる場を提供する。自治体主催の日本語講座を夜間・週末に開講する事例もある。
- 医療・福祉アクセス改善: 医療機関での通訳派遣や、多言語での診療案内パンフレット配布を行う。妊娠・出産する外国人配偶者への支援、子どもの学校教育相談など、家族ぐるみの支援も視野に入れる(特定技能2号等で家族帯同が増えることへの備え)。
- 住居・金融サービス支援: 外国人がアパートを借りる際の保証人支援制度(自治体保証や居住支援協議会活用)を整える。また銀行口座開設やクレジットカード取得での拒否事例に関し、金融機関との協議の場を設けるなど社会インフラ利用の障壁除去に努める。
- 地域交流イベント: 地域住民と外国人の交流を促すイベントや多文化フェスティバルを開催し、相互理解を深める機会を提供する。偏見や差別を防ぐには草の根交流が有効であり、自治体が積極的に場を設けることが大切。
自治体によってリソースに差はありますが、近年は総務省や地方創生交付金等で多文化共生事業が推進されています。特に外国人労働者の多い自治体(愛知、静岡、群馬など)では、外国人コミュニティを交えた協議会を設置し、施策提言に活かしている例もあります。地域ぐるみで外国人を受け入れる体制構築は、日本社会の喫緊の課題です。
中央政府の制度設計・監督改善
政府(法務省入管庁および関係省庁)は、制度の立案・実施主体として包括的な対応を取る責任があります。前述の法改正を実効あるものにするため、以下のような施策が求められます。
- 制度間の垣根解消: 技能実習・育成就労・特定技能と分かれている制度を将来的に一元化するビジョンを描く。現状は経緯から制度が併存しますが、最終的には技能水準に応じたシンプルでわかりやすい在留資格体系に再編することが望ましい。有識者からは「特定技能に一本化すべき」との指摘もあるため、育成就労の成果を見ながら柔軟に検討する。
- 監督体制の強化: 入管庁と厚労省(労基署)による合同の抜き打ち監査を増やし、悪質な受入れ機関・企業・送出機関を厳正に処分する。監理支援機関への監査もOTIT任せにせず入管が積極関与し、レッドカード(許可取消)事例の公表範囲を拡大する。2023年には今治造船が技能実習計画2,134件取消という大規模処分を受けていますが、こうした事例を周知することで抑止力とする。
- 罰則の実効化: 技能実習法違反や人権侵害行為に対する刑事罰適用を躊躇なく行う。現状では労働法違反は行政指導に留まるケースが多く、悪質ブローカーも摘発が難しい状況です。警察庁とも連携し、偽装在留や組織的周旋には組織犯罪処罰法など適用して取り締まる。
- データ公開・利活用: 入管庁は毎年「在留外国人統計」や「難民認定数」を公表していますが、技能実習・特定技能についてはより詳細な情報公開が望まれます。例えば失踪者の職種・国籍別内訳や所在確認状況、送出機関ごとの手数料平均額、特定技能試験の合格率推移など、政策評価に資するデータを積極的に公開する。また、研究者や民間有識者とのデータ分析プロジェクトを立ち上げ、エビデンスに基づく政策立案(EBPM)を推進する。
- 難民審査の第三者性確保: 難民認定については法務省の内部審査だけでなく、独立した難民審査機関の設置を検討すべきとの声があります。少なくとも審査参与員の意見がより反映される制度に改善し、認定率が著しく低い現状を是正する。また庇護希望者が早期に就労許可を得られるよう(現在は申請6か月後)、審査期間短縮に努める。
- 特定技能の質担保と地方偏在是正: 82万人計画を実現するため、各分野の業界団体や地方公共団体と協力し、地域ブロックごとの受入れ目標を設定するのも一案です。都市部集中を避け、地方企業にも割当目標を設けることで、地方創生策とも連動させる。また、技能試験の品質管理も重要です。海外現地での試験に不正がないか監視し、必要に応じて資格試験機関に改善を促す。
- 国民理解の促進: 日本社会全体で外国人労働者を受け入れる機運を高めるため、政府広報や教育を通じた啓発も不可欠です。外国人材の貢献事例を紹介したり、多文化共生の成功例を発信したりして、受入れへの偏見や不安を和らげる努力が求められます。参政権など政治参加の議論は別としても、地域社会の一員として外国人を迎える意識づくりは政府主導でも進めるべきでしょう。
以上、政府には法整備から現場運用まで一貫したリーダーシップが期待されます。とりわけ入管庁は新設(2019年)以来、技能実習・特定技能・難民と幅広い課題に直面しています。人員拡充や職員研修を通じて体制強化を図り、「世界から選ばれる日本」の実現に向けた制度整備に努める必要があります。
国際協力による構造課題への対応
最後に、国際的な連携・協力の視点です。外国人労働者の受入れ問題は送り出し国側の事情とも表裏一体であり、一国だけで完結するものではありません。
- 送出国政府との連携強化: 日本は既に主要送出14か国以上と協力覚書(MOC)を締結済みですが、それを実効あるものにするフォローアップが必要です。具体的には、日本側から通報した不正送出機関への処分状況を定期的に確認し、公表する仕組みを作る。また、送出国内での日本語教育支援に日本政府が資金・人材協力する(例えばJICAを通じた日本語教師派遣)ことで、来日前教育の質を高める。
- 多国間枠組みの活用: ILO(国際労働機関)が提唱する「公平な採用」原則(求人者負担原則など)を国内制度に取り入れ、各国共通ルール化を主導する。APECやASEAN+日中韓といった地域フォーラムで外国人材移動に関するベストプラクティスを共有し、地域全体でブローカー排除や相互資格認証などを進める。
- 国際評価への対応: 米国務省の人身取引報告(TIP)や米議会の年次人権報告等で指摘された点に真摯に対応する。例えば技能実習制度が強制労働の温床と批判された件については、育成就労制度への移行と法改正をもって反論材料とする。OECDのレビュー報告では、日本の多層的な制度(監理団体や試験の仕組み)が一定評価される一方、高額手数料問題や転籍制限が課題と指摘されました。これら国際機関の提言を政策改善に活かし、対応状況を対外発信することで評価を向上させる。
- 他国制度との比較研究: ドイツの技能実習に類似したデュアル研修制度、台湾や韓国の雇用許可制(EPS)の仕組みなど、他国の受入れ制度を研究し長所を取り入れる。例えば韓国EPSでは政府間で送出しを管理しブローカーを排除しているため、日本でも政府直轄のマッチング機関を設けるなどの参考になるでしょう。カナダの一時就労者プログラムでは企業に労働市場テスト(LMT)を義務付け、賃金も行政チェックしていますが、日本も特定技能で人手不足証明や賃金基準を強化する余地があります。
- 開発協力との連動: 外国人材送出しが盛んな国は多くが新興国・途上国です。日本の開発援助(ODA)の中で、現地の雇用創出や人材育成を支援し、出稼ぎに依存しない自立的発展を後押しすることも長期的対策です。一方で当面は人材流出が避けられないため、送出国での出国前オリエンテーションをODAで支援し、日本の労働法や生活情報を事前教育するプロジェクトも考えられます。
総じて、「ウィンウィンの国際人材循環」を実現するには、日本だけでなく関係国・国際社会と協調し、制度の隙を突く悪徳業者に対抗することが重要です。日本は国際舞台で人権尊重や安全な労働環境確保を訴えており、国内制度においてもその責任を果たすことで国際的信用を高めることができるでしょう。
以上、制度上の課題と改善策を総合的に検討してきました。最後に、読者の疑問に答える形で「よくある誤解とQ&A」をまとめ、理解を深める助けとします。
よくある誤解とQ&A
Q: 技能実習制度はいつ廃止され、新しい育成就労制度はいつから始まるのですか?
A: 技能実習制度は2024年6月14日に成立した改正法で廃止が決定し、新制度の育成就労制度は遅くとも2027年6月までに開始される見通しです。改正法では「公布から3年以内の施行」と定められ、現在政府が詳細な政省令を整備中です。施行後も3年間(~2030年頃)は技能実習生と育成就労外国人が並存する移行期間が設けられます。つまり2027年4月頃から新制度スタート、2030年までに完全移行というスケジュールとされています1。
Q: 育成就労制度に変わると技能実習制度と何がどう変わるのですか?
A: 目的が「国際貢献」から「人材確保と育成」に変わり、在留期間や要件も大きく変わります。具体的には、技能実習ビザ(最長5年・原則帰国)は廃止され、育成就労ビザ(最長3年・特定技能への移行前提)が新設されます。育成就労では開始前に日本語A1レベル習得が要件となり、在留中に技能検定試験や日本語試験に合格しないと特定技能へ移行できません。また転籍(企業変更)が自己都合でも一定条件下で可能になるなど、技能実習より柔軟な運用になります。一方、基本枠組み(監理団体→監理支援機関、計画認定制など)は受け継がれます。要は「帰国前提の研修」から「定着前提の就労育成」へ大転換すると理解ください。
Q: 育成就労制度にはデメリットや懸念点はありますか?
A: 懸念点はあります。例えば在留期間が3年と短いため、特定技能への移行試験に落ちた場合3年で帰国せざるを得ないリスクがあります(1年延長猶予はあるものの)。また転籍が認められるとはいえ条件が厳しく、簡単に自由移動できるわけではありません。送り出し側の問題(高額手数料)も上限案はあるものの実効性が未知数ですngj.jp。さらに制度施行まで3年猶予があり、その間も技能実習生の処遇改善を怠ると「駆け込み失踪」が増える恐れも指摘されています5。つまり新制度自体に加え、移行期の運用に注意が必要です。
Q: 技能実習生の失踪は転籍(企業変更)を認めれば減りますか?
A: 一定の効果はありますが、それだけでは不十分でしょう。自己都合転籍が可能になれば、劣悪な企業から合法的に移る道が開けるため「逃げるしかない」状況は減ると期待されます。しかし、失踪の根本原因である高額な借金・手数料問題が残っていれば、より高賃金の不法就労を選ぶケースは続く可能性が高いです。台湾では転職自由にもかかわらず失踪が多発し、その大半が借金を抱えたベトナム人だった例があります。日本でも手数料上限設定や債務負担軽減を徹底しないと、転籍緩和だけでは失踪撲滅には至らないでしょう。
Q: 企業は外国人材受入れで具体的に何をすべきですか?
A: 上述のチェックリストにあるように、(1)適正な送り出し機関選定と事前説明、(2)来日直後の生活支援と労働法教育、(3)労働条件遵守と定期面談による不満把握、(4)日本語・技能習得の機会提供、(5)公正な評価と昇進機会、(6)転籍希望時の誠実な対応、(7)緊急時の通報・対処、これらを確実に実行することです。また社内に相談窓口を設置したり、多文化理解研修を実施したりするのも有効です。要は「自社だったら安心」と外国人に思われる受入れ先になることが、結果的に人材定着と生産性向上につながります。
Q: 特定技能とはどんな制度で、育成就労とどうつながるのですか?
A: 特定技能は2019年開始の在留資格で、人手不足分野で働く外国人向けです。一定の技能試験と日本語試験に合格すれば取得でき、特定技能1号は在留最長5年・家族帯同不可、特定技能2号は在留無期限・家族帯同可です(2号は熟練技能者向け)2。育成就労は特定技能1号に“たすき掛け”でつながる制度で、3年間の就労育成を経て特定技能1号にシームレスに移行させるのが狙いです。逆に言えば、育成就労で受け入れる分野は特定技能1号の分野に限定され、育成終了後は必ず特定技能へ連続する設計になっています。要するに育成就労=特定技能の予備軍という位置づけです。
Q: 日本は今後どれくらい外国人労働者を受け入れる計画ですか?
A: 政府は特定技能について2024年度から5年間で最大82万人の受入れを見込んでいます。従来計画(約34.5万人)の2.4倍にあたります。分野別では製造業17.3万人、飲食料品製造13.9万人、介護13.5万人などが上位です。また技能実習の代替となる育成就労でも、大まかに数十万人規模の受入れが予想されます。2023年末時点で技能実習生約40万人・特定技能約21万人が在留していますが、これらが順次育成就労・特定技能へ移行しつつ、新規受入れも加わる形になります。さらに留学生や高度人材も含めると、今後数年で在留外国人数は400万人超に達する可能性があります。
Q: 特定技能2号に移行できる分野が増えたと聞きました。家族も呼べるようになるのですか?
A: はい。2023年6月に特定技能2号の対象分野が2分野から11分野へ拡大され、介護を除くほとんどの特定技能分野で2号への移行が可能になります。特定技能2号になると在留更新回数の制限がなくなり、配偶者・子を帯同可能です。これは事実上、外国人労働者が永続的に日本で暮らせることを意味します。例えば外食業・宿泊業・製造業などでも、一定の経験と試験合格で2号となり、長期定着や家族帯同が叶う道が開けました(制度改正が順次施行されています)。ただし2号移行後すぐに永住権が得られるわけではなく、別途永住許可の要件(在留10年等)を満たす必要があります。
Q: 補完的保護対象者とは難民とどう違うのですか?
A: 補完的保護対象者は難民条約上の難民ではないが迫害のおそれがあり帰国できない人です。難民は「人種・宗教など特定の迫害理由」が必要ですが、補完的保護はそれ以外の理由(戦争や一般的暴力、死刑リスク等)でも認められます11。日本政府が補完的保護対象者と認定すると、在留資格「特定活動」が与えられ、就労可・在留期間1年更新・難民支援制度の一部利用などが可能になります3。権利はほぼ難民と同等ですが、条約難民ではないため難民旅行証明書(パスポート代替証)は発行されません。また人数も別枠管理です。簡単に言えば「広義の難民」に対する国内保護制度が補完的保護です。2024年には主にウクライナ避難民1,661人がこの認定を受けています。
Q: 2023年の入管法改正で、難民申請中でも送還されることがあると聞きました。本当ですか?
A: 特定の場合に限り、難民申請中でも強制送還が可能になりました。改正法で「送還停止効の例外」が導入され、(1)3回目以降の難民申請者、(2)重大犯罪で3年以上の実刑を受けた者、(3)テロリスト等については、難民審査中であっても例外的に送還ができる規定となっています。ただし実際に送還するかどうかは慎重に判断され、仮にその人が後に難民と判明すれば、日本以外の安全な第三国に送るなどの対応が取られると説明されています。なおノン・ルフールマン原則(迫害国への送還禁止)は維持されています。この規定は難民該当性の低い「濫用申請」対策として導入されましたが、人権団体から強い懸念が表明されており、実施にあたっては慎重さが求められます。
Q: 「監理措置」と「仮放免」はどう違うのですか?
A: 監理措置は2023年改正でできた新制度で、退去強制手続き中の人を収容せず社会内で生活させる代わりに監理人による監督下に置く措置です。一方仮放免は従来からある制度で、収容中の人を一時的に身柄解放するものですが、期限や監督者はなく、月1回の入管出頭義務などで管理されます。監理措置では逃亡防止に責任を負う監理人(身元保証人のような役割)が付き、違反すれば刑罰もあり厳格です。また監理措置は在留資格が与えられるわけではありませんが、逃亡の恐れが低いと判断された場合に長期間の社会生活を許容する点で、仮放免より安定した身分と言えます。要は、仮放免の制度化・強化版が監理措置です。2024年以降、仮放免者の一部が監理措置へ移行し始めています。
用語集(和英対訳)
- 育成就労制度(Ikusei Shuro制度):2024年改正法で創設された新在留資格制度。人材育成と確保を目的に外国人を最長3年間受け入れ、特定技能への移行を前提とする。技能実習制度の後継。
- 技能実習制度(Technical Intern Training Program):途上国支援名目で1993年開始の外国人研修・技能実習制度。発展的解消が決まり、2027年までに廃止予定。
- 監理支援機関(Supervising Support Organization):育成就労制度における旧「監理団体」。入管庁許可を受け、受入れ企業の指導監督と外国人の支援を行う。公益組織(例:商工会や協同組合)が担う。
- 育成就労計画(Ikusei Shuro Plan):育成就労外国人ごとに作成する計画書。習得させる技能や日本語目標、OJT内容を記載し入管庁長官等の認定を受ける。技能実習計画の後継。
- 転籍(Transfer of Host Employer):受入れ企業の変更のこと。技能実習では原則禁止だったが、育成就労では一定条件下で本人希望による転籍が可能となる。
- 送出機関(Sending Organization):外国人労働者の送り出しを行う現地仲介業者。日本と送出国政府のMOCに基づき各国で認定制度がある。送り出し手数料を巡る問題が多い。
- MOC(二国間協力覚書、Memorandum of Cooperation):外国人材の送り出しに関する日本と送出国政府の合意文書。認定送出機関リスト共有や不正時の通報・処分など協力事項を定める。日本は東南アジア中心に数多く締結。
- 送還停止効(そうかんていしこう、Suspensive Effect of Asylum Application):難民認定申請中は強制送還をしてはならないという国内ルール。2023年改正法で例外類型が設けられた。
- 補完的保護対象者(Person eligible for Complementary Protection):難民ではないが本国送還すれば生命・自由が脅かされるため、日本で保護される人。2023年法改正で新設され、在留資格「特定活動」で滞在が認められる。例:内戦避難民など。
- 監理措置(Supervisory Measures):2023年創設の収容代替制度。監理人の監督下で被退去強制者を社会内で生活させる措置。逃亡防止の要件付き仮釈放のような制度。
- 仮放免(Provisional Release):入管収容者を一時的に釈放する制度。在留資格はなく定期報告義務等あり。監理措置導入後も並行して存在するが、今後監理措置へ置き換わる方向。
- 特定技能1号(Specified Skilled Worker Type 1):2019年導入の在留資格。人手不足14業種(現在16分野)対象。試験合格者に最長5年の就労を認める。家族帯同不可(配偶者・子は不可)。
- 特定技能2号(Specified Skilled Worker Type 2):特定技能1号で一定の熟練技能を習得した者向け在留資格。建設・造船等限定(→2023年に11分野へ拡大)。在留期間の上限なく更新可能で、配偶者・子の帯同可。実質的に永住に近い地位。
- 入管庁(Immigration Services Agency):2019年4月に入国管理局から格上げされた法務省の外局「出入国在留管理庁」。外国人の出入国・在留管理、難民認定を所管。技能実習・特定技能行政も担う。
参考文献
- 「『技能実習制度』が『育成就労制度』に変わります」公益財団法人国際人材育成機構(アイム・ジャパン), 2024年7月4日imm.or.jp (育成就労法の成立日・制度概要)
- 「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」出入国在留管理庁, 2023年8月31日更新sunrize-tokuteiginou.netasahi.com (特定技能2号の分野拡大決定)
- 出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正法について」2023年6月, p.2sangiin.go.jp (補完的保護対象者・監理措置など新制度の概要)
- 「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について」出入国在留管理庁, 2024年3月29日 (閣議決定概要)moj.go.jp (特定技能受入れ82万人・16分野への拡大)
- 出井康博『外国人技能実習生の失踪、「利権の闇」有識者会議の「育成就労制度」提言はまやかしだ』PRESIDENT Online, 2023年12月2日president.jppresident.jp (失踪の原因分析と有識者会議報告批判)
- 「外国人材新制度 育成就労 大都市圏で受入れ制限 省令案」毎日新聞, 2025年4月26日 (都市部集中防止の省令案報道)ngj.jp
- 東京弁護士会「改正入管法による人権侵害の抑止を徹底した制度を求める会長声明」2023年5月18日sangiin.go.jpsangiin.go.jp (送還停止効例外規定等への人権上の懸念)
- 法務省入国管理局『技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書』2023年11月, pp.15-17 (技能実習制度廃止と新制度創設の提言)president.jp
- 法務省入管庁「技能実習制度の運用状況に関する論点」2022年8月 (MOC締結国への不適正事案通報件数等)moj.go.jp
- 朝日新聞「特定技能2号、11分野への対象拡大を閣議決定 家族の帯同も可能に」2023年6月9日asahi.commax-kyujin.com (特定技能2号拡大と在留者数)
- 難民支援協会「2024年(令和6年)の難民認定者数を受けてのコメント」2025年3月14日refugee.or.jp (補完的保護制度創設の評価と課題)
- 厚生労働省「令和3年外国人労働者働働実態調査」2022年3月 (企業の法令違反率や外国人相談窓口設置状況)
- OECD『Recruiting Immigrant Workers: Japan 2024』OECD Publishing, 2024年6月30日nippon.comnippon.com (日本の移民政策の国際比較評価と提言)
秋田県内25市町村の現状・構造的課題・実行可能な解決策:議会説明・予算要求・事業設計に直結する包括レポート
エグゼクティブサマリー 本レポートは、秋田県内25市町村について、人口・経済・行財政・医療福祉・交通・防災・エネルギーの現状を一次資料中心で統合し、自治体職員・政策立案者がそのまま議会説明・予算要求・事業設計に転用できるレベルで、実装可能な施策を整理したものである(作成日:2026-02-14)。人口面では、県推計で2026年1月1日現在の総人口875,323人、前年から17,067人の減少、自然減が大きく、社会減も継続している。 25市町村すべてで2025年1月1日→2026年1月1日に人口減 ...
中道改革連合はなぜ大敗したのか?急ごしらえ新党の誤算と選挙戦略の失敗
結論:大敗の背景と主要因 中道改革連合(※以下「中道」)が衆院選で歴史的惨敗を喫したのは、複数の要因が重なった結果です。主な敗因としては、(1) 結党から選挙までの期間があまりに短く、新党の認知浸透が追いつかなかったこと、(2) 支持基盤の融合に時間が足りず、従来の組織票(創価学会票など)を十分にまとめきれなかったこと、(3) 政策メッセージの一貫性不足や「寄せ集め感」への有権者の不信、そして(4) 高市早苗首相の登場による与党側の「旋風」や情報戦で圧倒されたことが挙げられます。以下、これらの要因をデータ ...
沖縄41市町村の現状と課題:地域・類型別にみる人口動態、経済構造、観光依存と持続可能な施策
1. 導入:島しょ県・沖縄の多様な地域構造 沖縄県は、沖縄本島(おきなわほんとう)と宮古列島・八重山列島など周辺離島からなる島しょ県です。本島は北部・中部・南部で地形や人口分布が異なり、周辺には有人離島が点在します。本県の人口は約146.7万人(2024年10月)で3年連続の減少に転じました(出典:総務省「人口推計」2025年4月公表)。特に2024年は前年度比▲0.11%(▲1,674人)と減少幅が拡大し、沖縄でも人口減少への危機感が強まっています。また合計特殊出生率は1.54(2024年)と過去最低を ...
茨城県44市町村の現状と課題をデータで読む――人口減少時代の地域戦略
茨城県は32市・10町・2村の計44市町村から成り、県北・県央・鹿行・県南・県西の5地域に区分されます。2025年10月時点の県人口は約279万1,000人で、9月中に454人減少しました。本記事では、この茨城県の市町村が直面する人口減少・高齢化や産業・財政・インフラなどの課題を、最新データと一次資料から徹底検証し、実行可能な解決策を探ります。結論として、地域ごとの特性に応じた「コンパクト+ネットワーク」戦略や広域連携による行政効率化が鍵となります。その具体像を以下で詳述します。 要点(ポイント): 人口 ...
【衆院選2026】自民「単独過半数」報道が相次ぐ一方、未定層は2〜3割――2月2日時点の情勢と議席レンジ
2026年2月8日投開票の衆議院総選挙は、現時点では自民党が単独で過半数(233)をうかがい、連立(自民+維新)が300前後まで伸ばす可能性を複数の情勢報道が示している。一方で、比例・小選挙区とも未定層が大きく、天候(降雪)や投票率、野党側の候補調整でブレ幅が拡大し得る局面だ。[1][3][7][8] 日程:公示 2026年1月27日、投開票 2月8日。[1][2] 制度:定数465(小選挙区289+比例代表176)。小選挙区と比例代表は同日実 ...





