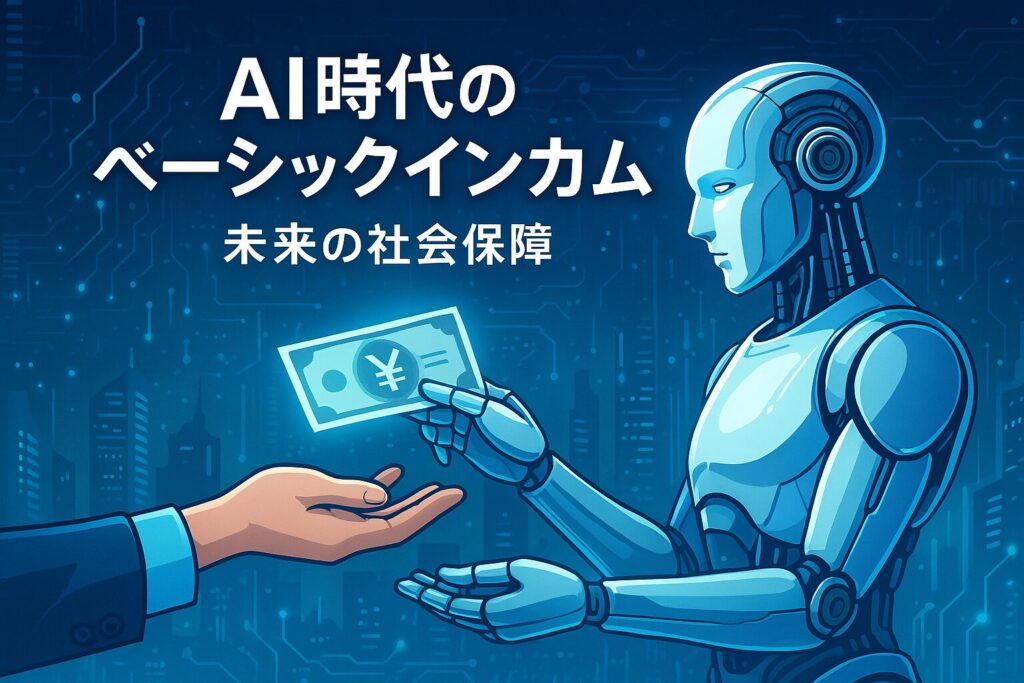
はじめに:AIと雇用の変化がもたらす課題
人工知能(AI)の急速な発達により、私たちの働き方や雇用環境は大きく変わろうとしています。過去には「日本の労働人口の49%が人工知能やロボットで代替可能になる」との衝撃的な試算も発表されました。実際、AI技術の進歩はホワイトカラー職種やクリエイティブ分野にまで及び、かつて「AIの脅威は低い」と思われた職業(例えばアナウンサーやグラフィックデザイナー)でさえ、現在ではAIがニュースを読み上げたりイラストを生成したりする状況です。一方で、AIタクシーの実用化は遅れ、10年前に消えると予測された職業(タクシー運転手やホテル客室係など)が存続しているという現実もあります。このように、AIによる代替のインパクトは職種によって様々で、当初の予測とは異なる展開を見せています。
こうした雇用環境の激変に対し、現行の社会保障制度も見直しを迫られています。雇用保険や年金など既存のセーフティネットは、長期安定雇用を前提に設計されてきました。しかし、ギグワークや非正規雇用が増えAIによる失業リスクが高まる社会では、現行制度ではカバーしきれない層が生じる恐れがあります。実際、2020年の新型コロナ禍では緊急支援として全国民への現金給付(特別定額給付金)が行われましたが、これは従来の制度の隙間を埋める措置とも言えます。AI時代の到来を受け、「無条件に最低限の生活を保障する収入を給付する」制度、すなわちベーシックインカム(BI)の導入を求める議論が国内外で活発化しています。本記事では、AIが雇用にもたらす具体的影響と、社会保障改革として注目されるベーシックインカムの必要性について、最新のデータと事例を交えながら詳しく解説します。読者の皆様は、AI時代における雇用の未来と、生き残るための社会保障のあり方について、深い洞察を得られるでしょう。
AIが雇用に与える具体的影響
AIによる自動化リスク:何人の仕事が奪われるのか?
AIと自動化技術が進歩するにつれ、「どれほどの仕事が機械に置き換えられるのか」という問いが度々取り上げられてきました。2015年の野村総合研究所とオックスフォード大学の共同研究では、「10~20年後には日本の労働人口の約49%の職業で、技術的にAIやロボットによる代替が可能になる」と推計されています。この49%という数字は米国(47%)や英国(35%)と比較しても高い値で、日本では技術的代替可能性が特に大きいことが示唆されました。
しかし、これはあくまで「技術的に可能」な範囲を示した値であり、実際に全てが置き換わるとは限りません。その後の研究では、より職業の「タスク(業務内容)」レベルに着目した分析が行われ、完全に自動化され業務内容が大きく変化するという現実的な試算も報告されています。要するに、AIが人間の仕事を完全に奪うケースは一部に留まるものの、多くの仕事でAIとの協働や業務再編成が起こり、仕事内容が大きく様変わりする可能性が高いということです。
では、具体的にどのような職種がAIに取って代わられやすいのでしょうか。野村総研の分析によれば、「専門知識や創造性が要求される仕事」「他者との協調・コミュニケーションが重要な仕事」はAIによる代替が難しく、逆に「高度な知識を必要とせず、データ分析や定型的作業が主な仕事」は代替可能性が高い傾向にあります。例えば、介護職や教育・医療など人間同士の触れ合いや高度な専門性を要する分野はAIでは代替しにくい一方、工場作業員や一般事務、レジ係など定型業務の多い仕事はAI・ロボット化が進みやすいと考えられます。
創造的職種への波及:生成AIがもたらす新たな衝撃
近年注目すべきは、生成AI(Generative AI)の登場によってクリエイティブ分野や知的労働にも自動化の波が押し寄せていることです。かつて野村総研のリストで「代替不可能性が高い安全圏」とされた職業の中には、漫画家やデザイナー、アナウンサーなどが含まれていました。ところが2020年代に入り、画像生成AIがプロ顔負けのイラストを描き、ChatGPTのような高度な言語AIが文章作成や要約をこなせるようになっています。実際、NHKではAIアナウンサーがニュースを読み上げる試みも現れ、漫画やシナリオ制作でもAIの活用が始まるなど、「創造性は人間の専売特許」と思われていた領域にもAIが進出しています。
2023年のある研究では、最新の大規模言語モデル(GPT-4など)が「米国の約80%の職業において、少なくとも10%のタスクを自動化可能」であり、「約19%の労働者にとっては業務の半分以上がAIの影響を受けうる」と試算しています。興味深いことに、高所得・高度専門職ほどAIの影響を強く受ける可能性が指摘されており、これは従来の「単純労働ほど機械に置き換えられやすい」という常識を覆すものです。すなわち、法律文書のチェックやプログラミング、デザイン、翻訳など知的労働・クリエイティブ労働もAIの得意分野となりつつあり、白衣や背広を着たエリート層の仕事がAIに代替される時代に入ってきたと言えるでしょう。
もっとも、技術的に可能だからと言って直ちに現実が追いつくわけではない点には注意が必要です。OECD報告も指摘するように、実際の自動化は技術の普及率やコスト、人々の受容度によって左右され、技術的に可能でも広く実装されないケースも多々あります。たとえば自動運転技術はかなり高度化したものの、法整備や安全性確保の問題からタクシー業界での本格導入は限定的です。また、新技術が生み出す新たな需要や職種もあり、「仕事が消える」だけでなく「新しい仕事が生まれる」動きも並行して起こるでしょう。重要なのは、AIによって仕事の内容や求められるスキルが大きく変化する転換期に来ているという認識です。こうした中で働き手が柔軟にスキルを磨き直し、社会としても労働者の再教育やセーフティネットを充実させることが不可欠になっています。
AI時代に求められる社会保障制度とその限界
日本の現行社会保障制度は、雇用保険・年金・生活保護など複数の仕組みで国民の生活を支えています。しかしその多くは「フルタイム雇用で定年まで勤め上げる」という昭和型モデルを前提としており、AI時代・ギグエコノミー時代の新たな働き方には十分に対応しきれなくなりつつあります。たとえば雇用保険は会社を辞めた際の所得補償ですが、フリーランスやギグワーカーには適用されにくいのが現状です。また年金制度も賦課方式(現役世代の保険料で高齢者を支える)で成り立っており、少子高齢化と労働人口減少が進む日本では制度の持続可能性が大きな課題です。
AIによる自動化が進んで失業や不安定就労が増えると、現行制度の“穴”からこぼれ落ちる人々が増加しかねません。フリーランスや短期アルバイトのような働き方をする人が増えれば、厚生年金や社会保険の適用外となるケースも増え、結果として十分な老後資金や医療保障を持てない人が増える恐れがあります。またAIに職を奪われた失業者が急増した場合、雇用保険だけで十分対応できるのか、あるいは生活保護に頼る人が爆発的に増えないかといった懸念もあります。
さらに、技術革新によって生産性が飛躍的に向上した社会では、「働かなくても基本的なニーズは満たせる」という状況が訪れる可能性も指摘されています。実際、ドイツの経済学者ゲッツ・ヴェルナーは「先進国では労働者の3分の1~半分が、生産性向上により潜在的には必ずしも働く必要がなくなる」と指摘しました。これはつまり、人々がフルタイムで働かずとも、社会にとって必要な財やサービスを十分生み出せる状態になりつつあるというのです。このような指摘は極端に聞こえるかもしれませんが、AI時代には「人々に十分な購買力を与えつつ、必ずしも全員が従来型の雇用に縛られる必要がない」という新たな社会モデルを模索する必要性を示唆しています。
ベーシックインカムへの期待
こうした背景から、AI時代の新たなセーフティネットとして「ベーシックインカム(BI)」が注目されています。ベーシックインカムとは、政府が全国民に対して無条件で一定額の現金を定期給付する制度のことです。収入や資産の有無、就労状況にかかわらず一人ひとりが生活の土台となる給付を受け取れるため、「最低所得保障」の究極の形とも言われます。
ベーシックインカムは近年突然生まれた奇抜なアイデアではなく、その思想的ルーツは18世紀の哲学者トマス・ペインの提案や、20世紀の経済学者ミルトン・フリードマンの負の所得税構想などに遡ることができます。1980年代には欧州で「ベーシックインカム地球ネットワーク(BIEN)」が結成され、本格的な研究・啓蒙活動が始まりました。当初は一部のリベラル思想家の議論という色彩が強かったものの、21世紀に入りリバタリアン(自由至上主義者)やシリコンバレーの起業家からも支持を集めるなど、支持層は左右のイデオロギーを超えて拡大しています。彼らがBIを支持する理由は様々ですが、共通しているのは「誰もが最低限の生活を営める収入を得られるようにし、人間の尊厳を守る」という理念でしょう。
現実の政策議論としてBIが脚光を浴び始めた大きな契機の一つが、AIブームによる将来の雇用不安です。テクノロジーの進歩によって将来的に多くの仕事が機械やAIに置き換えられる可能性に対し、「それならば働くか否かにかかわらず生活できる仕組みを作ろう」という発想は説得力を増しています。また2020年のコロナ禍では、スペインが低所得者向けの準ベーシックインカム的制度を創設するなど、緊急時の所得補償策として各国が現金給付を行ったこともBI議論を後押ししました。日本でも2020年に一律10万円給付が行われ、「手続きを簡略化すれば全国民に現金配布することは技術的に可能だ」と示されたことから、BI実現へのハードルが下がったとの見方もあります。
もっとも、ベーシックインカムを巡っては「バラ色の未来像」と「克服すべき課題」の両面があります。以下では、ベーシックインカムのメリットとデメリットを最新エビデンスに基づき整理した上で、日本における具体的導入シナリオや財源試算、そして他の代替政策との比較を行います。
ベーシックインカムのメリットと期待される効果
ベーシックインカムには、社会に様々な恩恵をもたらしうるという主張があります。その代表的なメリットを見てみましょう。
1. 貧困削減と所得再分配の効果
何と言っても最大のメリットは、貧困の削減と所得格差の是正です。全ての人に最低限度の収入を保証することができるため、現在の生活保護のような「受給のための厳しい要件」や「スティグマ(烙印)による利用忌避」がありません。BIであれば誰もが無条件にもらえるため貧困層の取りこぼしがありません。例えば、日本では生活保護の捕捉率(本来受給資格がある人で実際に受給している割合)は2割程度とも言われていますが、BI導入によりそうしたミスマッチを解消できます。また、一律給付により富裕層から貧困層への所得移転(再分配)が行われるため、所得格差の縮小も期待できます。ある推計では、BI導入によりジニ係数(格差指標)が改善し、高所得層と低所得層の差が縮まるとの分析もあります(※分析条件により異なるため諸説あり)。
2. 働き方の自由と自己実現の促進
BIがもたらすもう一つの恩恵は、働き方の自由度が増し、人々がより自己実現や創造的活動に時間を割けることです。最低限の収入が保障されるため、生活のために望まない仕事を無理に続ける必要が薄れます。結果として、ブラック企業や低賃金労働を拒否する交渉力が労働者に備わり、労働環境の改善にもつながるでしょう。実際、UBI(BI)支持者は「BIが導入されれば、人々は貧困から抜け出すために低賃金・過酷な労働を甘受する必要がなくなり、企業も待遇改善を迫られる」と主張しています。
また、BIによって生計が成り立つ安心感があることで、起業や転職、再教育への挑戦が容易になります。現状では「失敗したら生活できなくなる」という不安から新たなチャレンジを諦めている人も多いですが、BIが下支えとなればリスクを取って挑戦する人が増えるでしょう。その結果、イノベーションの促進や労働市場の流動性向上といったポジティブな効果も期待できます。さらに、専業主婦(主夫)や介護・ボランティアなど現在収入を伴わない活動に従事している人々の貢献が間接的に報われる側面もあります。例えば高齢の親を介護するため離職せざるを得なかった人でも、BIがあれば最低限の収入が得られるため精神的・経済的負担が軽減します。こうした「報われないケア労働」や「地域活動」に安心して取り組める環境作りという意味でも、BIは社会全体のウェルビーイング(幸福度)を高めるでしょう。
3. 精神的健康・社会的安定への寄与
BIは経済面だけでなく、人々の心理面や社会の安定にも良い影響を与えると考えられています。実証例としてしばしば引き合いに出されるのが、フィンランドのベーシックインカム実験およびアメリカ・カリフォルニア州ストックトン市の保証所得実験です。フィンランドでは2017~2018年にかけ、無作為抽出された失業者2,000人に毎月560ユーロ(約7万円)を無条件給付する国家実験を行いました。その結果、BI給付群の人々は就労状況が対照群とほぼ同じだった一方で、幸福度や健康状態の自己評価が明らかに向上しました。BI受給者は将来への不安が和らぎ、ストレスレベルが低下し、人生に対する満足感が高まったと報告されています。アメリカのカリフォルニア州ストックトン市のプロジェクト(SEED)では、低所得の125人に月500ドル(約6.5万円)を1年間支給したところ、BIを受給した人たちの就業率は対照群を上回ったほか、抑うつや不安の指標が有意に改善しました。さらに、支給された現金の使途を分析したところ、約99%が食費や光熱費、家賃など生活必需品に費やされ、浪費や遊興に回ったお金はわずか1%未満だったことも確認されています。
これらの実験結果は、「ただ現金を配ったら人々は働かなくなり怠惰になる」という懸念を実証的に否定するものです。むしろ最低限の収入保障があることで、人々の心理的な不安が軽減され、社会参加や経済活動に対して前向きになる傾向さえ見られました。BIがもたらす安心感が人々の意欲を削ぐどころか、自立や社会参加を後押しするという報告は各地で相次いでいます。このように、ベーシックインカムは社会的ストレスを和らげ治安や公衆衛生の改善にも資する可能性があり、ひいては社会全体の安定と連帯感の向上につながると期待されています。
また、ベーシックインカム導入により、複雑化した現行福祉制度を簡素化し行政コストを削減できるというメリットも指摘されています。日本の現行福祉制度は、年金や雇用保険、生活保護など多数の制度に細分化され、それぞれ異なる窓口や審査手続きが存在します。BIでそれらを一本化することができれば、行政手続きの煩雑さやコストを大幅に軽減できます。また、不正受給の監視や資力調査といったコストも不要になるため、行政の効率が上がるでしょう。特にデジタル技術の活用と組み合わせれば、マイナンバー制度やリアルタイム所得把握システムを用いることで、より正確かつ迅速に全国民への給付を実行できます。実際、英国の「ユニバーサル・クレジット」は所得情報と給付をリアルタイムで連携させた統合給付制度ですが、これにより手続きの簡略化と不正防止が図られています。日本でも、BI的な全国民給付を行えば、年金記録漏れ問題や生活保護の水際作戦(受給抑制策)といった現行制度の課題を一挙に解決できる可能性があります。ただし、既存制度をどこまでBIに統合するかは慎重な検討が必要です。例えば、障害者手当や介護サービス給付のように特定ニーズに応じた施策は、BIとは別立てで維持すべきとの指摘もあります。行政効率化のメリットを活かしつつ、BIだけでは賄えない特別な支援との両立を図る視点が求められます。
ベーシックインカムの課題と批判
多くのメリットが語られるベーシックインカムですが、実現には乗り越えるべき課題も存在します。ここでは主なデメリットや懸念点を整理します。
1. 財源確保の問題:100兆円規模の予算は可能か?
BI議論で避けて通れないのが財源の問題です。全国民に最低生活費を給付するとなれば巨額の予算が必要となり、しばしば「財政破綻する」という批判が出ます。試算の例を見てみましょう。
仮に日本で一人あたり月8万円のベーシックインカムを導入するとします(成人子ども一律と仮定)。年間給付額は1人96万円となり、1億2千万人強の国民全員では約120兆円もの支出が必要です。これは国家予算(一般会計)の総額に匹敵する規模であり、単純計算では現在の税収では到底賄えません。現実的な線として、経済学者の原田泰氏は「20歳以上に月7万円、20歳未満に月3万円」というプランを提案していますが、それでも必要予算は約96兆3千億円とされています。原田プランでは、この財源に対し(1)給与所得と事業所得に一律30%のフラット税を課す(約77兆円の税収増)、(2)現行の所得税を廃止してその税収約14兆円を充当、(3)年金・雇用保険・児童手当などBIで代替できる既存給付を全て廃止(約20兆円削減)、(4)公共事業や農林水産予算などの削減(約16兆円削減)――これらを組み合わせて賄う試算です。結果的に約35兆円の歳出カットと77兆円の増税で、96兆円の財源を捻出しようという大胆なシナリオになります。
しかし、これほどの大増税や歳出削減が政治的に実現可能かは大いに疑問です。消費税でまかなうとすれば、仮に消費税の税収弾性を単純に当てはめると消費税率を今の10%から50%近くに引き上げる必要があるとも言われます(1%あたり約2.8兆円の増収として試算)。また、全額を国債発行で賄えば毎年100兆円規模の赤字が積み上がり財政崩壊は避けられません。このようにBIは理念的魅力がある反面、財政面では極めて高いハードルが存在します。そのため現実論としては、「給付額を月3~5万円程度に抑えて部分的に導入する」「他の社会保障給付をかなり整理統合する」など工夫しつつ、段階的に制度設計する必要があるでしょう(財源シナリオについては後述)。
2. 勤労意欲への影響:人々は働かなくなるのか?
BI反対論として根強いのが「無条件でお金を配ったら、人々は怠け者になり社会の生産力が落ちる」という懸念です。「働かなくても生活できるなら仕事なんてしなくなるのでは?」という直感は理解できますが、実証研究の結果は必ずしもこの懸念を裏付けていません。前述したフィンランド実験やストックトン実験では、BI受給による労働参加率の低下は見られず、むしろ前向きな活動が増えたとの報告がありました。
また、1970年代にアメリカやカナダで行われた「負の所得税(NIT)実験」でも、参加者に一定の最低所得を保証しましたが、労働供給の減少は年に2~4週間程度労働時間が減るというごく穏やかなものに留まりました。特に多かったのは子育て中の母親が育児のために労働時間を減らすケースや、若年層が進学・職業訓練に時間を充てるケースであり、「遊んで怠けるために働かなくなった」と言えるような事例は限定的でした。むろん長期的・大規模に実施した場合の影響は不確実性がありますが、少なくとも「BI=人々が誰も働かなくなる」という単純図式はデータに照らして支持されていません。
とはいえ、心理的な勤労観への影響は慎重に見る必要があります。仕事には収入以外に「社会参加や自己実現の機会」という側面があり、人によってはBIによる安心感がかえって引きこもりや社会的孤立を助長するリスクも指摘されます。またBI導入後に労働力人口が減少すれば、労働集約的産業(介護やサービス業など)で人手不足が深刻化する可能性もあります。結局のところ、人々がBIを得た上でどう行動するかは多様であり、一概に全員が怠けるとも限らなければ、生産性が上がる保証もありません。勤労意欲への影響はBIの設計(給付水準や併用政策)や社会的価値観によって左右されるため、試行的な導入を通じて慎重に検証していくことが望ましいでしょう。
3. 他の社会保障との関係:全て置き換えられるわけではない
BIは究極の所得保障ですが、それだけですべての社会保障ニーズを満たせるわけではない点にも注意が必要です。例えば、重度の障害や持病を抱える方は、平均的な生活費以上の医療・介護コストがかかります。BI一本に統合してしまうと、そうした人々への十分な支援が行き届かなくなる懸念があります。そのため障害年金や介護保険、医療保険などはBI導入後も別途維持するか、BI給付額とは別枠で追加給付する仕組みが求められるでしょう。
また、教育や住宅、公共サービスといった分野では「ベーシックサービス」の充実というアプローチも重要です。現金給付のBIだけでなく、国民が等しく基礎的サービス(教育・医療・住宅など)を受けられるように公的インフラを整備することも、社会保障の大事な柱です。BI論者の中にも「一定水準のベーシックサービスを無料提供した上で、不足分をカバーするBIを支給すべき」と提唱する人もいます。つまり、現物サービスと現金給付をどう組み合わせるかというデザインの問題です。
さらに、年金に関しては「高齢者も現役世代もBI一律給付にして年金を廃止すると、高齢者への保障が薄くなりすぎる」との指摘もあります。この点、基礎年金部分をBIで置き換え、厚生年金や企業年金は上乗せで残すといったハイブリッド案も検討されています。いずれにせよ、BI導入の際には他の社会保障制度とのすみ分けを明確にし、脆弱な層が手当を失わないよう移行措置を講じることが不可欠です。
4. 政治的ハードルと国民理解
ベーシックインカムは社会契約の大転換を伴う制度だけに、政治的ハードルも非常に高いと言えます。特に財源確保のための大幅な増税や歳出削減は、有権者の理解を得るのが難しく、政治家も敬遠しがちです。実際、2016年にBIの是非を問う世界初の国民投票を行ったスイスでは、月額約27万円のBI導入案が約77%の反対で否決されました。反対派には政府も含まれており、その理由は「コストがかかりすぎ経済が悪化する」というものでした(一方、提唱者側はAIによる失業リスクへの備えや人間の尊厳向上を訴えていました)。この結果はBIに対する国民の不安を反映しています。
日本でも世論調査によってBIへの賛否はまちまちですが、「富裕層にも配るのは無駄では?」「働かない人にお金を与えるのは不公平」といった声は根強くあります。また、既得権益となっている現行の年金や生活保護を手放したくない層からの反発も予想されます。政治的現実としては、BIをいきなり全面導入するよりも、地域や特定層での試験導入から始めて成果を示し、徐々に拡大するといった戦略が考えられます。国民の理解を得るためには、実証実験の結果や財政シミュレーションの透明な開示を通じて、メリットとデメリットを丁寧に説明していくことが必要でしょう。
日本におけるベーシックインカム導入シナリオと財源試算
前述の通り、BIの完全実施には多大な費用がかかるため、現実的には段階的な部分導入から検討するのが一般的です。日本で議論されているいくつかのシナリオを紹介します。
シナリオ1: 限定的なベーシックインカム(部分導入)
まず考えられるのは、特定の年齢層や所得層に絞って給付する限定的BIです。一例として「子どもベーシックインカム」があります。これは18歳未満の子どもに限り毎月一定額を支給するもので、現行の児童手当を拡充・普遍化した形です。子どもの貧困対策として効果が高く、将来世代への投資になるという利点があります。財源規模も全世代対象に比べれば格段に小さく抑えられます(例えば子ども2000万人に月2万円なら年約4.8兆円)。実際、スペインは2020年に低所得世帯の子ども向け手当を大幅増額し実質的な子どもUBIと呼べる政策を導入しました。
他にも、失業者限定のBIや特定地域限定のBIといった案も考えられます。フィンランド実験は失業者が対象でしたが、日本でも不安定就労者やコロナ禍で収入減となった世帯への限定給付は行われました。また、自治体単位で独自にBI的施策を試みる動きもあります。例えば東京都のある区が単身高齢者に月数万円を支給するモデル事業を検討した例や、ベーシックインカム導入を公約に掲げる首長も現れています。これらは厳密には全国民を網羅するBIではありませんが、限定的な範囲で効果と課題を検証する実験として重要なステップとなるでしょう。
さらに、給付額を抑えたミニマムBIを導入する案もあります。例えば全国民に月3万円を給付するとなれば年間約45兆円となります。この程度の水準であれば、消費税の増収分や高所得者への増税、既存給付の転換などを組み合わせることで、現実味のある財源措置を検討できるとの指摘もあります。「最低限の最低限」とも言える小規模BIから始め、景気状況や財政余力に応じて徐々に給付水準を引き上げていくアプローチです。
シナリオ2: 普遍的ベーシックインカム(全面導入)
もう一つのシナリオは、社会保障制度を抜本的に再編し、ベーシックインカムを全面導入する大胆なプランです。これは前述の原田氏の提案のように、年金・失業給付・各種扶助を原則BIに統合し、財源も所得税や社会保険料を全面的に組み替えることを意味します。実現すれば制度は極めてシンプルになり、国民は生涯にわたり一貫した所得保障を得ることになります。働いても働かなくても一定の収入が保障されるため、職業選択や人生設計の自由度は飛躍的に高まります。
しかし、全面的なBI導入は文字通り「社会契約の書き換え」とも言える大改革です。財源問題と勤労インセンティブ問題を同時にクリアする必要があり、政治的ハードルも計り知れません。AIの発達が今後さらに加速し、失業率が急上昇するような危機的状況になれば、BI全面導入論が現実味を帯びる可能性はあります。例えば「2030年に雇用の○%がAIに代替され失業が大問題になった」という未来においては、BIは社会維持のための緊急避難策として支持を集めるかもしれません。しかし現状では、まず部分的なBIや類似制度で経験値を積み、社会の理解を深めてから段階的に拡大するのが現実的路線でしょう。全面導入シナリオはあくまで最終目標像として念頭に置きつつ、目前の政策としては次項で述べるような代替策やハイブリッド案との比較検討が重要です。
ベーシックインカムの代替・補完策:雇用保証制度や税額控除との比較
ベーシックインカム以外にも、AI時代のセーフティネットとして有力視される政策があります。ここではユニバーサル雇用保証(ジョブギャランティー)と給付付き税額控除(所得税のマイナス課税)の2つを取り上げ、BIとの違いを比較します。
ユニバーサル雇用保証(ジョブギャランティー)
ユニバーサル雇用保証とは、政府が「働きたい人全員に仕事を保障する」制度です。具体的には、公的部門が失業者に対し最低賃金以上の有給職を提供し、誰も失業で取り残されないようにします。BIが「お金を配る」のに対し、ジョブギャランティーは「仕事を配る」アプローチと言えます。
この制度のメリットは、強制的な失業ゼロの実現と社会に有用な仕事の創出です。働き手は仕事を通じて収入を得るだけでなく、社会参加やスキル向上の機会を得られます。近年、オーストリアのマリエンタールで世界初のユニバーサル雇用保証実験が行われましたが、長期失業者がゼロになり、参加者の幸福度や生活の安定が大きく向上したとの結果が報告されています。これは、公的に仕事を保障することで社会的包摂と地域活性化に寄与した好例です。
ジョブギャランティーのもう一つの利点は、政治的受容性が高い点です。BIに対してよく聞かれる「人々が怠けるのでは?」という批判も、「仕事を提供する」仕組みであれば和らぎます。社会に必要なケア労働や環境保全事業など、人手不足だが収益が見込めない領域に政府が雇用を生み出すことで、公共の福祉にも資するでしょう。
もっとも課題もあります。政府が全国民分の仕事を用意するのは行政負担が大きく、効率を欠く恐れがあります。適切な職務マッチングができなければ「税金で遊休人員を抱えるだけ」との批判も出かねません。また、働けない事情のある人(病気や障害など)には対応できず、結局そうした人々向けに別の所得保障策が必要です。さらに、ジョブギャランティーは景気変動に柔軟に対応できる設計(不況時は公的雇用が増え、好況時は民間就職に誘導する)が求められ、運用はBIより複雑です。財源面ではBIと同様に税金投入が必要ですが、政府が雇用する分、払った税が労働という形で還元されるとも言えます。
総じて、ユニバーサル雇用保証は「仕事を通じた社会保障」としてBIを補完・代替しうる有力案です。BIが直接の所得保障であるのに対し、ジョブギャランティーは「働く権利の保障」というアプローチで、人々に生産参加の機会を与える点が大きく異なります。AI時代には、人間にしかできないケアや創造の仕事を保証する政策として、BIと併用または組み合わせる議論も出てきています。
給付付き税額控除(負の所得税・EITC)
もう一つの注目政策が給付付き税額控除(Refundable Tax Credit)です。これは簡単に言えば「働いて所得を得た人に対し、低所得なら税の代わりに給付金を支給する」制度で、ミルトン・フリードマンの提唱した「負の所得税」に近い概念です。米国の「勤労所得税額控除(EITC)」や英国の「ユニバーサル・クレジット」がその代表例で、欧米では既に広く導入されています。
給付付き税額控除の仕組みを日本で説明すると、例えば年収200万円以下の人には所得税をマイナスにして給付を行うといった形になります。収入が増えるにつれて給付額は逓減し、ある水準以上では給付ゼロ(課税のみ)となります。これにより、低所得で働く人々の手取り収入を底上げし、労働インセンティブを高める効果が期待できます。BIが無条件給付なのに対し、給付付き税額控除は就労を条件とした所得補助であり、「働けば必ず得をする」というメッセージを与える制度です。
メリットとしては、財政負担を抑えつつ貧困対策ができる点が挙げられます。対象が低所得労働者に限られるため、BIのように富裕層にも給付する無駄がなく、給付額も必要最低限で済みます。日本でもこの制度を導入すれば、非正規労働者やワーキングプア層の可処分所得を増やし、労働意欲を損なわずに支援できるでしょう。またマイナンバー等で所得を捕捉して給付を自動化すれば、事務負担もそれほど大きくありません。
一方、デメリットは非就労者(失業者や専業主婦など)を救えないことです。収入がゼロの人には負の所得税もゼロなので、結局生活保護など別制度が必要になります。つまり「働けない人」「働かない人」には効果が及ばないのです。また、給付が徐々に減っていく際の高い累進率(生産性の罠)も問題です。例えば年収を100万円から150万円に増やしても、その分給付が減ってトータルでは手取りがほとんど増えない、といった逆転現象が起こりえます。これは勤労意欲をそぐ要因にもなるため、適切な設計(フェーズアウト率の調整)が必要です。
日本では2023年現在、給付付き税額控除は導入されていませんが、政府内でも検討が進んでいます。森永改革研究所の森永卓郎氏や東京財団の森信茂樹氏など専門家からは、「日本版EITC」をデジタル技術と組み合わせて実現すべきとの提言も出されています。将来的にはマイナンバーを活用し、リアルタイムで所得を捕捉して機動的に給付する「デジタル・セーフティネット」構築の一環としてEITC導入が期待されています。
総じて、給付付き税額控除はBIに比べ財政的に実現しやすく、勤労意欲に配慮した制度ですが、カバーできる範囲が限定的であるため、BIの完全な代替にはなりません。むしろBIと組み合わせ、「働けない人にはBI、働く人には税額控除で上乗せ支援」といったハイブリッド戦略も考えられます。現にカナダや欧州では低所得者向け税額控除と手当を組み合わせる政策が一般的で、日本も同様の道を模索する可能性があります。
国際的な動向:各国の実験と議論
世界に目を向けると、ベーシックインカムや類似の試みは各地で実施されています。先述のフィンランドの国家実験や米国ストックトン市のプロジェクトは特に有名ですが、それ以外にも注目すべき動向があります。
- アラスカ州(米国): 1982年から石油収入を原資とする「アラスカ恒久基金」により、州民全員に毎年1,000~1,500ドル程度の配当金を支給しています。金額は生活費を賄うには小さいものの、資源収入を全民に分配する先駆的事例として知られ、40年近い実績があります。
- イラン: 2010年に補助金改革の一環で、全国民に現金給付を行う政策を開始しました。石油収入の一部を原資に月約40ドルを支給し、実質的なBIに近い制度でした(近年は経済制裁等で縮小)。
- ナミビア・インドなど: ナミビアでは2008~2009年、貧困地域の村で全住民に月100ナミビアドルを給付する試験が行われ、栄養状態や就学率の改善など成果が報告されました。インドでも2011~2012年にマディヤ・プラデーシュ州で農村の住民に無条件給付する実験が実施され、健康指標や就業状況の改善がみられています。
- カナダ(オンタリオ州): 2017年にオンタリオ州で4,000人規模のBIパイロット(年収補足型で年最大C$17,000支給)が始まりましたが、政権交代により2018年に中止となりました。それでも参加者からは健康改善やストレス減少など肯定的な報告があり、研究者が分析を続けています。
- 韓国(京畿道): 韓国では京畿道が2019年より「青春基本所得」として、24歳の若者全員に年100万ウォン(約10万円)を支給する制度を開始しました。クーポン形式ではありますが事実上のBIで、若年層の起業活動や求職活動を後押しする効果が報告されています。
このように、世界各国でBIあるいは類似の制度が試行・検討され、その成果と課題が蓄積されています。2020年以降はコロナ禍を契機にBI論議が勢いを増し、スペインやスコットランド、ウェールズなどで新たな実験計画や部分導入の動きが見られます。国際的な潮流としては、「テクノロジーとグローバル化で変容する労働市場に対応するため、新たな社会的契約が必要」との認識が共有されつつあります。BIはその有力な選択肢として、今後も各国の政策議論で取り上げられていくでしょう。
おわりに:AI時代の新たな社会契約に向けて
AI時代における雇用と社会保障、そしてベーシックインカムの必要性について、現状のデータと議論を概観してきました。AIがもたらす雇用へのインパクトは計り知れず、従来の常識にとらわれない発想で社会保障制度を再構築する必要性が高まっています。ベーシックインカムはその最先端のアイデアとして、賛否両論ありながらも世界的に注目を集めるようになりました。
結論から言えば、ベーシックインカムは万能薬ではありません。財源の問題、勤労意欲の問題、政治的実現性の問題など、克服すべき課題は少なくないのも事実です。しかし同時に、フィンランドや各地の実験が示すように、「人間らしい生活の安心」を無条件に保障することが個人と社会にもたらすポジティブな効果も無視できません。AIとロボットによって富が生み出される社会において、その恩恵を広く行き渡らせ、人々の尊厳と安定を守る仕組みを作ることは、人類全体の課題と言えるでしょう。
日本においても、ベーシックインカムの完全導入は容易ではないものの、一部導入や段階的拡充、あるいは他制度との組み合わせによって実現に近づける道はあります。例えば子ども基本所得や給付付き税額控除といった施策からスタートし、それらを土台に将来的なBIへ発展させるシナリオも考えられます。重要なのは、現状の社会保障をこのまま惰性で維持するのではなく、AI時代にふさわしい新たな「社会的連帯」のあり方を模索する姿勢です。
ベーシックインカムの議論を進める過程で、雇用の価値や働くことの意義について社会全体で考え直す契機にもなるでしょう。すべての人が安心して生活基盤を築けるようになれば、AIと人間が共存する未来社会においても、創造性や思いやりといった人間らしさを発揮できる余地が広がるはずです。BI導入はゴールではなく、真に包摂的で持続可能な社会への出発点となり得ます。AI時代における雇用と社会保障の在り方を模索する上で、ベーシックインカムという選択肢は今後ますます重要性を帯びていくでしょう。私たち一人ひとりも、この壮大な社会実験の行方を注視し、議論に参加していくことが求められています。
関連書籍の紹介
・『AI時代の新・ベーシックインカム論』井上智洋(光文社新書) – 経済学者である井上氏が、AIによる雇用への影響を分析しつつ、日本にベーシックインカムがなぜ必要かを論じた一冊です。最新のAI動向と経済モデルをもとに、現実的な導入プランや課題にも踏み込んで解説しています。AIとBIの関係を深く知りたい方におすすめです。
・『ベーシック・インカム 国家は貧困問題を解決できるか』原田泰(中公新書) – エコノミスト原田泰氏によるベーシックインカム入門書。日本でBIを導入する場合の財源試算や制度設計について具体的な数字を挙げながら議論しています。メリットだけでなく問題点にも丁寧に触れており、BIの現実性を客観的に考えるのに役立ちます。
・『ベーシックインカムへの道 正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには』ガイ・スタンディング(作品社) – 世界的なBI提唱者であるガイ・スタンディング教授による著書。各国で進むベーシックインカム運動や実験結果を紹介しつつ、BI実現への具体策とその意義を説いています。グローバルな観点でBIを捉えたい方に適した一冊です。
・『ベーシック・インカム』フィリップ・ヴァン・パレース(教育評価研究所/現代書館) – ベーシックインカム研究の第一人者ヴァン・パレース氏による理論書。BIの思想的背景から制度設計上の論点、よくある批判への反論まで網羅的にまとめられています。やや専門的ですが、BIについて体系的に学びたい読者にとって貴重な参考書となるでしょう。
参考文献
- 野村総合研究所 「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に」(2015年12月)
- OECD “Automation, skills use and training” (2018年)】
- OpenAI “GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact of LLMs” (2023年3月)
- 鈴木貴博 「ホテル客室係やタクシー運転者の仕事は消滅しなかった…」(東洋経済オンライン, 2025年3月)
- CNET Japan 「10~20年後、日本の労働人口の49%が人工知能やロボットで代替可能--NRI調べ」(2015年12月)
- World Economic Forum 「Finland's basic-income trial found people were happier, but weren't more likely to get jobs」(2020年5月)
- Stockton SEED 実験結果(Results for America, 2021年)
- 朝日新聞SDGs「ベーシックインカムとは?メリット・デメリット、実現の可能性を解説」(2022年3月)
- ロイター通信 「スイスで最低限の所得保障めぐる国民投票、反対多数で否決」(2016年6月)
- 森信茂樹 「ベーシックインカムと給付付き税額控除 ―デジタル・セーフティネットの提言―」(『フィナンシャル・レビュー』2024年8月号)
- INET Oxford 「World’s first universal job guarantee boosts wellbeing and eliminates long-term unemployment」(2022年12月)




