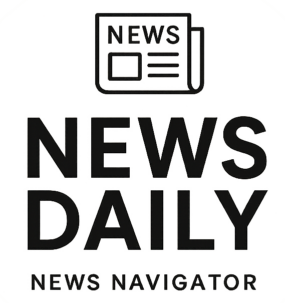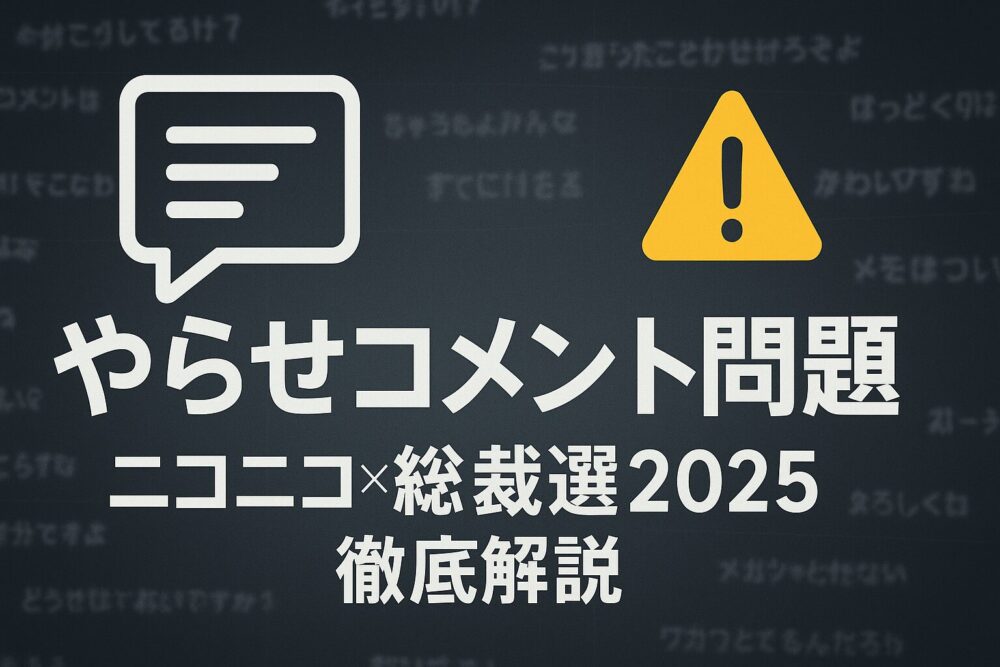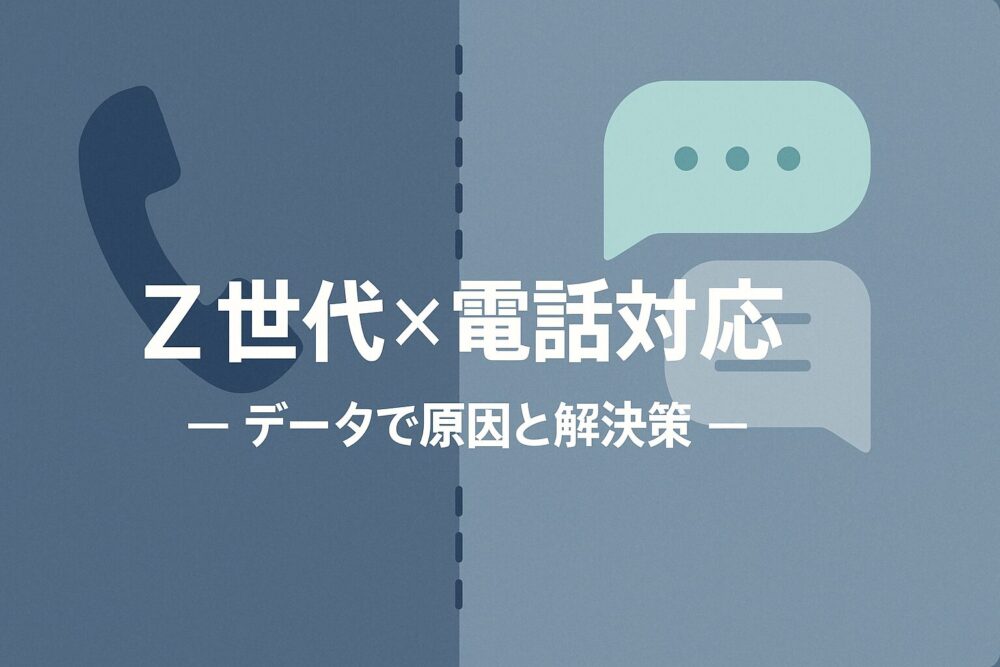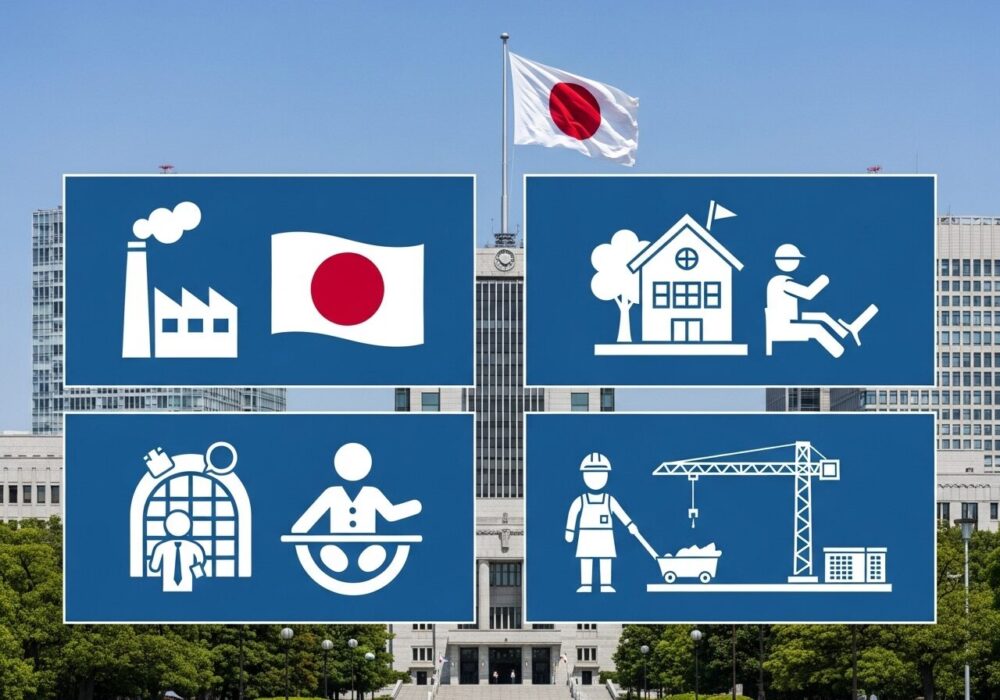自民党総裁選2025【最新】討論内容と候補者比較まとめ
更新日:2025-09-28 09:00 JST 結論: 自民党総裁選2025は、石破茂首相の退陣を受けて5人が争う混戦となっています。主要争点は物価高対策や減税策で、9月27日のネット討論では賃上げや減税の是非を中心に論戦。全候補がガソリン税の一部廃止など家計支援策で一致する一方、小泉進次郎氏の“好意的コメント要請”問題への質疑では各候補が慎重な姿勢を示し、党内融和を優先する姿勢が浮き彫りになりました。総裁選は10月4日に投開票され、新総裁は事実上次期首相となる見通しです。 速報・直近の重要ポイント 9 ...
小泉進次郎陣営「やらせコメント」問題を徹底解説 ニコ動ステマ指示24例の波紋
自民党総裁選2025に出馬中の小泉進次郎農水相の陣営が、動画サイト「ニコニコ動画」で小泉氏を称賛する好意的なコメントを書き込むよう支援者に依頼していたことが発覚しました。牧島かれん氏の事務所から送られたメールに24種類の参考例が記載され、一部に「ビジネスエセ保守に負けるな」など、他候補への批判と受け取れる表現が含まれていた。9月26日に小泉氏は記者会見で事実を認めて陳謝し「行き過ぎた表現があった」「再発防止を徹底する」と述べました。この「ステルスマーケティング(ステマ)」疑惑は党内外に波紋を広げ、陣営の牧 ...
日本の水源地「外資買収」の実態:0.07%未満、法規制が守る
結論(要約) 外国資本による森林取得はごくわずか – 林野庁の最新調査(2025年公表)では、令和6年(2024年)に外国法人等が取得した森林面積は382haで全国私有林の0.003%に過ぎず、累計でも0.07%に留まっています。しかも水資源目的の開発事例は報告されていません。外国資本が日本の水源地を“買い占め”ているとの懸念はデータ上誇張と言えます。 土地を買っても水は自由にならない – 河川法により河川水や湧水の取水には事前に水利権許可が必要で、土地所有だけで勝手に水を使用できません。また多くの水源林 ...
【2025年版】日本版ユニバーサルクレジット導入ロードマップ
TL;DR(要約):英国のユニバーサルクレジット(UC)の特徴である「55%テーパ+就労控除(ワークアローワンス)」と月次算定を軸に、日本でも“働けば手取りが増える”一体給付制度(仮称:就労連動一体給付)の導入を提言します。英国UCの成功例(就労インセンティブ強化)を取り入れつつ、初回5週間待機などの失敗からは学び、日本では初回給付の迅速化(無利子の橋渡し給付)や総合マイナポータル連携による効率化を図ります。制度は段階的に導入し、パイロット検証→全国展開まで緻密なロードマップを設定。最終的に所得階層全体で ...
Z世代社員が会社の電話に出られない理由と解決策【最新データで徹底解説】
要約 Z世代の新入社員が会社の電話に出られない・出たがらない理由は、幼少期からデジタルネイティブ世代としてテキストコミュニケーション中心で育ち、固定電話や音声通話に馴染みが薄いことが大きな要因です。実際、最新調査では約5割の若手社員が電話対応を苦手と感じており、その理由は「電話マナーに自信がない」「普段使わないから」「家に固定電話がなかった」などが挙げられます。一方、企業側も電話対応を巡る課題(新人の離職リスクや在宅勤務時の電話運用)に直面しており、コロナ以降はメール・チャットへの移行や電話自動化が進んで ...
2025年ベーシックインカム論の包括的分析と日本の実装可能性
最終更新日:2025-09-23 要約(結論の要点) ベーシックインカム(BI)の定義 – 政府が全国民に無条件かつ定期的に一定額の現金を支給する最低所得保障制度。完全BIだけでなく部分的なBI(一部世代や低所得層対象)や負の所得税(NIT)・給付付き税額控除など類似制度も議論される。 実証結果 – 主要なBI実験では労働供給への大きな悪影響は確認されず、むしろ主観的幸福度や健康・教育面の改善が多く報告。ただし雇用への有意な増加効果も限定的で、エビデンスの範囲は限定的。 最新動向(2024–25) – 欧 ...
自動運転タクシー完全ガイド:WaymoやZoox、国内外の最新動向を徹底解説
自動運転タクシー(ロボタクシー)の仕組みから最新動向、安全性の実績、各国の規制と主要企業の展開状況まで、2025年9月21日現在の一次情報に基づき徹底解説します。最新のサービス提供エリアや今後の課題にも触れ、導入を検討する自治体・事業者が押さえるべきポイントを網羅しました。 要点(TL;DR) 自動運転タクシーとは何か? 自動運転タクシー(ロボタクシー)は、運転者が乗車せずに走行する完全自動運転(SAEレベル4以上)のタクシーサービスです。2023年に日本でも限定条件下で初の商用レベル4運行が実 ...
選択的夫婦別姓(選択的夫婦別氏)をめぐる賛否と論点の完全ガイド
最終更新:2025年9月19日 要約: 選択的夫婦別姓(選択的夫婦別氏)とは、結婚後も夫婦それぞれが結婚前の姓(氏)を名乗ることを選べる制度です。現行の民法では婚姻時に夫婦は必ず同じ姓を名乗らねばならず(民法750条)、実際には約94%の夫婦で妻が夫の姓に改姓しています。この仕組みをめぐり、「個人の尊厳やキャリア継続のため選択肢を増やすべきだ」という賛成意見と、「家族の一体感や子どもの姓の扱いなど伝統との整合性が損なわれる」という反対意見が対立しています。本記事では、選択的夫婦別姓制度を巡る用語解説から制 ...
日本の外国人受入れ制度2025:改革の現状と制度の穴
最終更新日:2025-09-17 要約 最新の制度改正を一次情報から整理: 技能実習制度は2024年改正法成立により育成就労制度へ移行予定。特定技能の対象分野拡大(12分野→16分野)と5年間の受入れ見込数見直し(約82万人)、難民保護では補完的保護制度創設や送還停止効の例外導入など大きな変更が進行中。各制度の改正日付・根拠を明記し最新動向を解説。 制度に潜む「穴」をデータで可視化: 技能実習生の失踪者数は2023年の9,753人(過去最多)から2024年は6,510人へ約33%減少。減少傾向にもかかわら ...
2035年までの日本の未来予測:ベース・楽観・慎重シナリオ分析
結論サマリ: 日本は今後15年間で急速な人口減少と高齢化に直面しつつ、産業構造の転換とグリーントランスフォーメーション(GX)を迫られます。政府は2035年までに新車電動化100%や温室効果ガス削減目標を掲げ、防衛費を国内総生産(GDP)の2%へ倍増させる計画です。一方で出生数減やインフラ老朽化など構造課題も深刻です。本稿ではベース(現状趨勢)・楽観(改革成功)・慎重(リスク顕在化)の3シナリオで日本の2035年像を予測し、主要指標のレンジと確信度、および考え得るリスクと対策を考察します。 2035年の日 ...