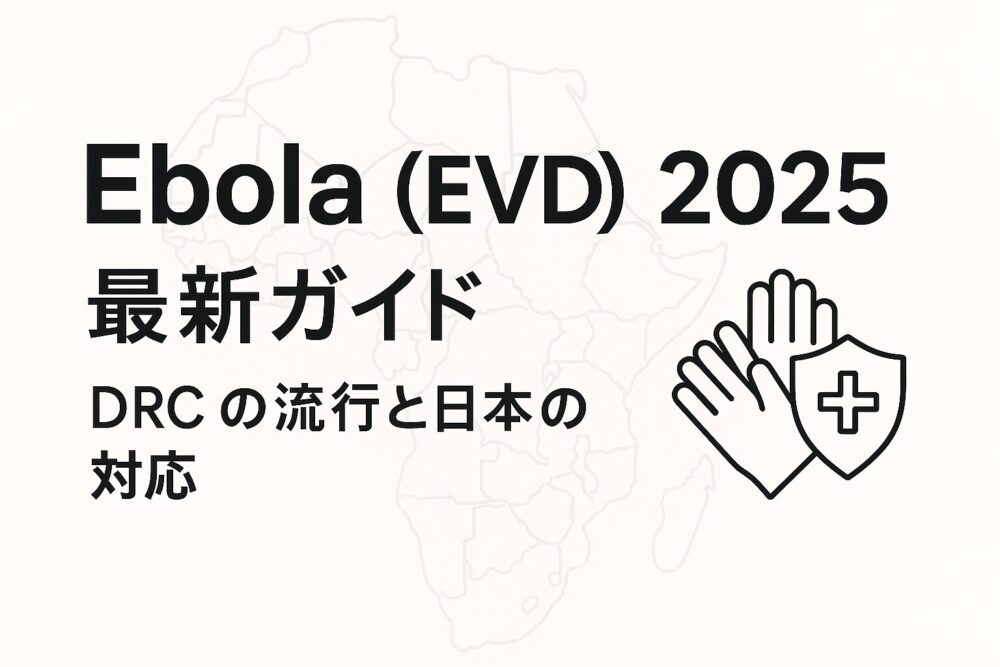
要約: エボラ出血熱(エボラウイルス病, EVD)は、致死率が平均約50%と非常に高い希少疾患です1。2025年9月にコンゴ民主共和国(DRC)で新たなエボラ流行(アウトブレイク)が発生し、日本でもニュースやSNSで関心が高まっています。エボラは主に患者や遺体の体液との直接接触で感染し、一般的な空気感染はしない点が重要です。現在、有効なワクチンや治療法が確立しているのはザイール株(EBOV)によるEVDのみで、他の株(スーダン株など)へのワクチン開発も進行中です。本記事では、エボラの基礎知識から最新動向、日本国内のリスクと対策、誤情報の検証までを詳しく解説します。
なぜ今エボラが日本で話題?
2025年9月、アフリカ中部のコンゴ民主共和国(DRC)カサイ州で新たなエボラウイルス病(EVD)の流行が確認されました。エボラ出血熱は感染すると致命的になり得るため、このニュースは日本でも大きく報じられています1。DRC保健省とWHOは9月4日付で同国カサイ州ブラペ保健区域およびムウェカ保健区域におけるエボラ出血熱のアウトブレイク発生を宣言しました2。現地では患者の急増を抑えるため、一部地域で移動制限(封じ込め措置)も行われています。また、SNS上では「エボラが空気感染する」「致死率90%で世界的流行になる」などの不確かな情報が拡散され、不安を煽る状況も見られます。しかし専門家は、エボラは基本的に空気感染せず流行地域も限定的であるため、日本を含む世界全体へのリスクは現時点で低いと強調しています2。本記事では、こうした最新動向を踏まえ、エボラ出血熱の正しい知識と実態について解説します。
エボラウイルス病(EVD)とは
エボラウイルス病(Ebola Virus Disease, EVD)は、エボラウイルス属(オルソエボラウイルス属)に属するウイルスによって引き起こされる重篤な感染症です。エボラウイルスは細長い形状を持つRNAウイルスで、1976年にスーダン(当時のスーダン南部)およびコンゴ民主共和国(当時ザイール)で初めて確認されました。その際、コンゴの流行地近くを流れるエボラ川にちなんで「エボラ出血熱(Ebola hemorrhagic fever)」と命名されました。症状の重篤さ(後述)から「出血熱」と呼ばれてきましたが、出血症状は必ずしも起こらないことが分かり、近年はエボラウイルス病(EVD)と呼ぶ方が適切とされています(呼称は異なっても同じ病気を指します)。
ウイルスの種類と分類
エボラウイルス属のウイルスは現在6種類が知られており、そのうち人に重篤な疾患を起こすのは主に次の3種です1。
- ザイール株 (Ebola virus, EBOV) – 最も病原性が強く、典型的なEVD(エボラウイルス病)を引き起こします。2014年西アフリカ大流行や2018–2020年DRC大流行もこの株でした。
- スーダン株 (Sudan virus, SUDV) – スーダンウイルス病(SVD)を引き起こします。2022年~2023年ウガンダで流行した株で、致死率はザイール株に次ぐとされます。
- ブンディブギョ株 (Bundibugyo virus, BDBV) – ブンディブギョウイルス病(BVD)を引き起こします。2007年ウガンダのブンディブギョ地区で確認されました。
この他にもタイ森林株(タイフォレストウイルス)やレストン株(アジアのサルで確認、ヒトでは症状報告なし)、ボンバリ株(宿主や病原性は未解明)があります3。ザイール株が最も致死率が高く、感染拡大を起こしやすいことが知られています3。一方、日本国内でエボラ患者が発生した例はこれまで一度もありません3。
症状・経過・致死率の幅
エボラウイルス病は潜伏期間(感染から発症まで)が2~21日(平均約1週間)とされています2。発症は突然で、最初は発熱、悪寒、全身倦怠感、筋肉痛、頭痛、咽頭痛などインフルエンザのような症状ではじまります。その後数日かけて嘔吐、下痢、腹痛など消化器症状が現れ、患者によっては発疹が出ることもあります2。中枢神経系への影響で意識の混濁や興奮、攻撃的行動が見られる場合もあります。
出血症状は必ずしも起こらない。 病名に「出血熱」とあるものの、実際には出血(内出血・外出血)は後期症状で、全患者の中で頻度は高くありません1。重症例では病状が進行してから消化管からの出血、歯茎や鼻からの出血、注射部位からの出血などが見られることがありますが、初期から出血するケースは少ないのです1。出血傾向が顕著になると血圧低下や多臓器不全、ショックに陥り、致命的となります。
致死率(致死率)はアウトブレイクの状況やウイルスの株、患者への治療体制によって大きく変動します。WHOによれば、エボラウイルス病の平均致死率は約50%です1。過去の流行では25%から90%という幅で報告されており1、特に医療体制が整っていなかった初期のザイール株流行では90%前後に達した例もあります。一方、近年の例では致死率が20~60%程度に収まることが多く、例えば2025年にウガンダで発生したスーダン株(SUDV)の流行では致死率29%(14例中4例死亡)でした。このように、エボラは依然として非常に高い致死率を持つ疾患ですが、適切な早期治療と支持療法により生存率を上げることも可能です1。
感染経路と予防
エボラウイルスの主な感染経路は、患者や感染動物の「体液への直接接触」です。具体的には、発症している患者の血液、嘔吐物、下痢便、尿、唾液、汗、母乳、精液などに皮膚の傷や粘膜(目、口、鼻など)を通じて触れることでウイルスが体内に侵入します5。患者の体液に汚染された衣類や寝具、医療器具などの物品に触れて感染することもあります6。また、エボラウイルスに感染した野生動物(コウモリ、サル、ゴリラ、森林に生息する大型の哺乳類など)の血液・臓器や体液に触れた場合にも、人への感染が起こり得ます1。アフリカの一部では、果物コウモリ(オオコウモリ科)がエボラウイルスの自然宿主ではないかと考えられており、ウイルスを保有する野生動物との接触(捕獲・食用の際の解体など)を通じて人への最初の感染(spillover)が起きるとされています1。
空気感染はしない? 一般的にインフルエンザや新型コロナのように飛沫やエアロゾルを介した空気感染は、エボラでは起こらないとされています5。エボラウイルスは咳やくしゃみの飛沫中にも検出され得ますが、それだけで遠く離れた他人に感染が広がるエビデンスはありません。実際、症状が出ていない潜伏期間中の人から他者へ感染することは通常ありません(性的接触など特殊な場合を除く)6。したがって、日常生活で患者と近距離で長時間接触しない限り、空気を吸っただけで感染するリスクは極めて低いです。ただし、医療現場では気管挿管や吸引処置などでエアロゾル(微小な飛沫)が発生しうるため、エアロゾル対策を含む厳重な感染防護具(PPE)の着用が求められます6。過去のアウトブレイクでは、患者の看護や処置にあたった家族・医療従事者への二次感染が多く報告されています1。特に患者の遺体に直接触れる葬儀は高リスクであり、感染者の家族や関係者が葬儀で感染する例が後を絶ちません1。
予防策: エボラウイルスへの感染を防ぐためには、流行地域で次のような対策が推奨されます71。
- 患者・感染が疑われる人との接触を避ける: エボラ流行が発生している地域にはできるだけ近づかず、やむを得ない場合でも患者やその疑いがある人の体液に触れないよう十分注意します。患者には必ず防護具(手袋、マスク、ゴーグル、ガウン等)を着用して対応します。
- 遺体の適切な取り扱い: エボラで亡くなった方の遺体には高濃度のウイルスが存在します。専門訓練を受けたチームによる安全かつ尊厳ある埋葬(Safe and Dignified Burial)が不可欠であり、一般の人が遺体に触れることは厳禁です1。
- 野生動物との接触回避・食品管理: コウモリや霊長類など野生動物との不用意な接触を避けることが重要です。特に流行地域でブッシュミート(野生動物の生肉)を扱ったり食べたりすることは感染リスクを高めます。十分に加熱調理されていない野生動物の肉は、エボラのみならず他の病原体の感染源にもなり得るため非常に危険です6。
- 基本的な衛生対策: 手洗い・消毒の徹底が何よりも重要です。アルコールベースの消毒剤の使用に加え、流水と石鹸で手指をしっかり洗うことはエボラ予防にも有効です6。患者の体液で汚染された可能性のある環境(衣服やリネン類、トイレなど)の清掃・消毒も適切に行います。
以上の点を踏まえ、流行地域においては患者発生地域には決して近寄らないこと、感染者またはその疑いがある人との接触を避けること、そして野生動物(特にコウモリや猿類)の肉や体液に触れない・摂取しないことが基本的な予防策となります7。
検査・診断の流れ
エボラ出血熱の症状は当初マラリアやチフス、コレラ、重症のデング熱など他の感染症と区別がつきにくいため、臨床症状だけで診断を確定することは困難です1。そのため、患者の症状と感染地域への渡航歴・接触歴から「エボラ疑い例」と判断された場合、確定診断のためウイルス検査が行われます。
主な検査法はRT-PCR法(遺伝子増幅検査)によるウイルス遺伝子の検出です1。患者の血液やスワブ(咽頭ぬぐい液等)を採取し、エボラウイルス特有の遺伝子配列を増幅して検出します。この他、抗原検出(ウイルス抗原を捉える迅速検査キット等)や抗体検出(ELISA法)による血清学的検査、また高度な施設ではウイルス分離培養なども行われます1。検体は感染リスクが極めて高いため、最高度のバイオセーフティーレベル(BSL-4相当)の設備で厳重な防護下に検査が実施されます1。
日本国内ではエボラウイルスを扱える施設が限られており、国立感染症研究所(村山庁舎)のBSL-4実験室などで確定検査が行われます。検疫や医療機関でエボラ疑い患者が発生した場合、直ちに保健所・厚労省に連絡のうえ、感染症指定医療機関に隔離搬送され、同時に検体が国立感染症研究所などに送られてPCR検査が実施される流れです。なお、検査結果が判明するまで患者は厳重な感染対策下で隔離管理されます。
治療:支持療法とモノクローナル抗体
支持療法(対症療法)
エボラ出血熱に対しては、長らく特異的な治療薬が無く、支持療法(対症療法)が中心でした3。支持療法とは、患者の生命維持と症状緩和を目的として行う治療全般を指します。具体的には輸液による脱水補正、電解質バランスの維持、血圧管理、酸素投与、疼痛管理、二次感染(敗血症や他の併発症)への対処などがあります8。エボラ患者は激しい嘔吐下痢により大量の体液が失われるため、点滴による十分な補液と、必要に応じ輸血や昇圧剤の使用が重要です8。また、DIC(播種性血管内凝固)や多臓器不全が起こればそれぞれ専門的集中治療が施されます。これら集中的治療ケアを早期から行うことで生存率が改善することが経験的に知られており1、WHOも「最適化された支持療法(optimized supportive care)」の重要性を強調しています。
特異的治療薬(モノクローナル抗体療法)
近年になり、エボラウイルス(ザイール株)に対する特異的な治療薬がついに実用化されました。それがモノクローナル抗体医薬です。現在、米国FDAなどで承認されているエボラ治療薬は次の2製品があります8。
- インマゼブ (Inmazeb<sup>®</sup>) – エボラウイルスに対する3種類のモノクローナル抗体のカクテル療法薬です。3種の抗体(アトルリビマブ、マフチビマブ、オデシビマブ)が協調してウイルス表面の糖タンパク質に結合し、ウイルスの細胞侵入を阻止します。
- エバンガ (Ebanga<sup>®</sup>) – 有効成分アンスルビマブ(mAb114)という単一のモノクローナル抗体製剤です。患者由来の抗体から開発され、同じくウイルス表面抗原に結合して作用します。
これらの抗体療法は、2018年~2019年にDRC北東部で行われた臨床試験で有効性が確認され、エボラ患者の死亡率を有意に下げる効果が示されました8。エバンガおよびインマゼブはいずれもザイール株のエボラウイルスに感染した患者の治療にのみ効果が証明されており、他の株(スーダン株やブンディブギョ株など)には効果が確立していません8。実際、米CDCは「これら治療薬の効果はザイール種オルソエボラウイルス以外には証明されていない」と明言しています8。そのため、2022年のウガンダ(スーダン株)流行時には両薬は使用されませんでした。
治療の適用: モノクローナル抗体治療は早期に投与するほど効果的とされ、エボラ感染が確認された患者には可能な限り迅速に投与開始されます。静脈投与(点滴)で大量の抗体を体内に入れるため、設備の整った治療センターで管理下に行われます。また副作用として一時的な発熱や発疹、胃腸症状が報告されていますが、エボラ自体の重症度に比べればリスクは小さいと考えられています。
他の治療候補: 上記抗体薬以外にも、抗ウイルス薬のレムデシビル(エボラにも一部効果の可能性が検討されたが効果限定的)や、回復期血漿(エボラから回復した人の抗体を含む血漿を輸注する治療)などが試みられてきました。しかし現時点で明確な有効性が確認されたのはモノクローナル抗体療法のみです。スーダン株などに対しても現在、類似の抗体治療薬(Mapp社のカクテル抗体など)の開発・臨床試験が進められています4。
ワクチン:Zaire株向けとSudan株向けの現状
エボラウイルスに対するワクチンは長年存在しませんでしたが、2010年代後半に初めて有効性が確認され、現在は実用化されています。ただし利用可能なワクチンはザイール株専用であり、他の株(Sudan株等)に対してはまだ公的承認されたワクチンがありません。
Ervebo(ザイール株ワクチン)
現在世界で承認・使用されているエボラワクチンは主にErvebo(エルベボ)という製品です。Merck社が開発した生ワクチンで、遺伝子組換え弱毒化したVSV(ウシのウイルス)にエボラザイール株の表面抗原を組み込んだウイルスベクターワクチンです。2019年にEUや米国で承認され、エボラウイルス病(ザイール株)による感染予防を目的に18歳以上(EUでは後に1歳以上まで拡大)の接種が認可されています9。Erveboはザイールエボラウイルス種によるEVDの予防にのみ適応があり、他のエボラウイルス種には効果が期待できません9。
Erveboワクチンは1回接種型で、2015年のギニアでの臨床試験で高い予防効果(推定100%の有効率)を示しました。その後、DRCやグイネーでのアウトブレイクにおいて「リングワクチネーション(患者の濃厚接触者とその周辺に接種)」という戦略で用いられ、流行拡大防止に大きな貢献をしました。2014年以降の西アフリカ・中部アフリカの流行では、このワクチンが数万人規模で緊急接種され、ワクチンが利用可能になって以降のエボラ流行は速やかに封じ込められるケースが増えています10。
現在、WHOやGavi(ワクチンアライアンス)はErveboを中心としたエボラワクチンの国際緊急備蓄(ストックパイル)を整備しており、常時50万回分以上の在庫が世界に用意されています10。流行発生国から要請があれば、国際調整グループ(ICG)を通じて迅速にワクチンが供給される仕組みです7。例えば今回のDRCカサイ州の流行でも、キンシャサに備蓄されている約2,000回分のErveboワクチンがただちに現地へ輸送され、患者の接触者や医療従事者への予防接種が開始されています2。
なお、Ervebo以外にヤンセン(Janssen)社の2回接種型ワクチン(Zabdeno+Mvabea)もEUで承認を取得しています1。こちらは1回目にアデノウイルスベクター、2回目にMVAウイルスベクターを8週間あけて接種するもので、長期的免疫を狙ったものです。ただ緊急時に8週間待つのは現実的でないため、主に予防目的(流行が起きていない時に医療従事者へ前もって接種)として位置づけられています。実際、2023年7月のWHO専門家会合では、エボラ高リスク地域の医療従事者等に対しErveboやヤンセンワクチンを用いた予防的ワクチン接種プログラムが推奨されました1。Gaviも2024年より対象国のハイリスク者への定期的予防接種を支援する方針を示しています。
Sudan株向けワクチンの開発状況
Sudanエボラウイルス(SUDV)に対する承認済みワクチンはまだ存在しません。しかし近年のウガンダでのSUDV流行を受け、ワクチン開発・試験が急ピッチで進められました。2025年初めのウガンダ流行時には、世界中の研究機関・企業が協力し3種類のワクチン候補(アデノウイルスベクターやVSVベクターなど)を緊急に用意しました。そのうちIAVI(国際エイズワクチンイニシアティブ)が開発したワクチン候補などが現地で臨床試験(『Tokomeza SVD』試験)に投入されました4。【Tokomeza】とは現地語で「撲滅する」の意で、ウガンダ保健省・WHO・ワクチン開発機関が連携し、流行宣言後わずか4日で試験接種を開始するという異例のスピード対応が行われました4。試験では患者の接触者を「リング」に区分し、一部には即時接種を行い、他は一定期間遅らせてから接種するというプロトコルでワクチンの有効性・安全性を検証しました4。幸いこの流行自体が小規模で早期に終息したため明確なワクチン効果は統計的に示せませんでしたが、今後の大規模流行に備えてデータが蓄積されています。
また、スーダン株に対しては上述のモノクローナル抗体治療薬もまだ承認品はありません。ウガンダでは米Mapp社の抗体療法候補や抗ウイルス薬レムデシビルも用意されましたが、抗体療法候補は治験実施の許認可上の問題から使用に至らず、レムデシビルのみ緊急治療として投与されました。このようにSudan株・Bundibugyo株などザイール株以外への医療手段は発展途上ですが、WHOは研究開発の加速のため国際共同体を組織し、優先的に開発すべきワクチン・治療薬の選定と臨床試験の枠組み(COREプロトコル)を整備しています1。近い将来、Sudan株にも有効なワクチン・治療薬が実用化されることが期待されています。
2025年の最新状況(DRCカサイ州など)
2025年9月にエボラのアウトブレイクが報告されたコンゴ民主共和国カサイ州の地図(薄赤色が影響地域)。Bulape保健区域とMweka保健区域を中心に患者が発生している(2025年9月5日時点)2
コンゴ民主共和国(DRC)カサイ州で発生したエボラ出血熱の最新状況についてまとめます。DRC保健省は2025年8月下旬にカサイ州ブラペ地区の病院で原因不明の出血熱患者(34歳妊婦)が発生したとの報告を受け、検体を国立生物医学研究所(INRB)に送りました。その結果、9月3日にエボラウイルス(ザイール株)の遺伝子陽性が確認され、9月4日付で同国政府とWHOがエボラ出血熱の流行を公式発表しました2。【今回の流行はDRCにとって通算16回目】であり、同国では約3年ぶりのエボラ発生となります2。
発生地域は南西部カサイ州のBulape(ブラペ)保健区域およびMweka(ムウェカ)保健区域です。首都キンシャサからは遠く離れた内陸の農村地帯で、道路事情が悪く外部からのアクセスが困難な地域です2。流行初期(~9月4日)時点で28件の疑い症例(うち15件が死亡、致死率54%)が報告されており、その中には医療従事者が4名含まれていました2。患者の約8割は15歳以上の年齢層で、男女比は公表されていません。このうち5件の血液検体と1件の死亡患者スワブ検体でエボラ陽性が確認済みです2。
その後も積極的な監視と接触者調査が行われ、症例数は徐々に増加しています。米CDCの更新によれば、2025年9月10日時点で疑いまたは確定症例は58人、死亡者は20人(死亡者中4人が医療従事者)に上っています11。依然として流行はDRC国内の限られた地域(ブラペ及びムウェカ周辺)に局在しており、周辺国や他地域への拡大は確認されていません。WHOは今回のアウトブレイクによる公衆衛生リスク評価を「国内では高いが、地域レベルでは中程度、グローバルな拡大リスクは低い」と評価しています2。
対策: DRC当局は発生を受けて直ちに国家緊急対応チームを現地派遣し、患者隔離治療、接触者追跡、感染予防策の徹底などに着手しました2。WHOやアフリカCDCも専門家を派遣し、個人防護具(PPE)や医療物資、移動式検査設備など約2トンの支援物資が現地に届けられています【参考:ブルームバーグ報道】。また、前述のようにErveboワクチン約2,000人分が用意され、9月上旬より患者の接触者とその周辺の住民、そして流行対応にあたる医療・支援スタッフへのリングワクチネーションが開始されました2。治療面では、確定患者に対しモノクローナル抗体治療薬(InmazebやEbanga)の投与も実施可能な体制が整えられています2。
幸い、DRC政府と国際機関の協働により対策は迅速に講じられており、流行地域が都市部から離れていることもあって大規模拡散には至っていません。WHOアフリカ地域事務局の担当者は「致死率は50~60%と高いものの、パニックになる必要はない。DRCは豊富な経験と能力を持つ」と冷静な対応を呼びかけています【参考:WHO Africa / Bloomberg報道】。今後も状況は流動的ですが、現地当局は引き続き監視・検査体制を強化し、周辺諸国とも協力して拡大防止に努めています。
他地域の状況: なお、2025年にはこのDRC以外にもエボラ関連の出来事がありました。上述のウガンダでのスーダン株(SUDV)の流行がそれで、同国では2025年1月末に首都カンパラでSUDV感染が確認されました4。幸い、ウガンダ政府と国際支援によってこの流行は4月末までに終息宣言が出され、最終的な患者数は確認12名・死亡4名(他に疑い2名)という小規模に抑え込まれました4。エボラ出血熱は常にアフリカの限られた地域で散発的に発生するリスクがあり、国際的な監視と迅速対応が欠かせません。2024年~2025年にはガーナやコートジボワールなど西アフリカ諸国でもエボラ疑い患者の調査報告がありましたが、いずれも陰性で事なきを得ています。【以上、NIID及びWHO状況報告より】
日本の制度・渡航者向け情報
日本国内の法制度: エボラ出血熱は日本では「一類感染症」に指定されています3。一類感染症とは感染症法で定める最も危険性の高い疾患カテゴリで、他にはクリミア・コンゴ出血熱やペスト、ラッサ熱、マールブルグ病などが含まれます。一類感染症患者または疑い例を診断した医師は直ちに最寄り保健所に届け出る義務があり、行政当局は強制的な入院隔離や就業制限などの措置を講じることができます。指定された特定感染症指定医療機関(高度な隔離病床を持つ病院)での治療が原則となり、医療費は公費負担です。また、検疫法においてもエボラ出血熱は検疫感染症(一類相当)に指定されており、空港・港湾で発熱等の症状を呈した渡航者がいた場合は検疫官による隔離・停留の対象となります。
日本での発生状況: 前述の通り、日本国内でエボラ出血熱の患者が確認されたことはこれまで一度もありません3。2014年の西アフリカ大流行時には、アフリカからの帰国者で発熱した方が何例か調査・隔離された事例がありますが、いずれも陰性で感染は確認されませんでした(デング熱など他疾患と判明)。国内のサーベイランス(監視)においてもエボラ感染例は報告されていません。
渡航者向け情報: 外務省や厚生労働省検疫所は、エボラ流行国への渡航者・在留者に対し注意喚起を行っています。2025年9月5日には外務省が「コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生」と題したスポット情報を発出し、流行地域(カサイ州ブラペ及びムウェカ)には決して近づかないこと、感染者や感染疑い患者との接触を避けることを強く促しました7。またアルコール消毒や石鹸による手洗いの徹底、患者の体液・遺体・汚染物や野生動物に触れないこと等、基本的な予防策の徹底を呼びかけています7。厚労省検疫所「FORTH」も、エボラ出血熱を含む危険な感染症発生地域への渡航を控えるよう勧告しています。
用語補足: 厚労省検疫所の情報によれば、近年は出血症状の頻度が低いことから「エボラ出血熱」ではなく「エボラウイルス病(EVD)」と呼称する動きがあるとされています6。日本の法律上は依然「エボラ出血熱」という名称ですが、国際的文脈ではEVDの語が一般化しつつあります。
日本で万一患者が発生した場合: 仮に日本国内でエボラ患者または疑い例が確認された場合、速やかに国立感染症研究所での確定診断が行われるとともに、特定感染症指定医療機関(高度感染症指定医療機関とも)に搬送され厳重な感染対策下で治療が行われます。空港等の検疫段階で発見された場合も同様です。医療従事者はPPEを着用し二次感染の防止に努めます。エボラは人から人への持続的な感染拡大(パンデミック)は起こしにくい病気ですが、一旦国内発生すれば社会的インパクトは極めて大きいため、国として最高レベルの体制で備えがされています。
海外安全情報の確認: エボラ流行国へ渡航予定の方や滞在中の方は、必ず外務省「たびレジ」や在留届を通じて最新の安全情報を入手してください7。現地で不調を感じた場合は早めに医療機関に連絡し、必ず渡航歴を申告して指示を仰ぐことが重要です。日本帰国後も21日間は健康状態に注意を払い、発熱など症状が出た場合は直接医療機関に行かず事前に保健所に相談してください。
誤情報のファクトチェック(空気感染?致死率90%?)
エボラ出血熱に関しては、その劇症性ゆえに様々な誤解やデマが広まりがちです。ここでは代表的な誤情報について、事実をもとに検証します。
- 誤解①「エボラは空気感染するので、近くにいるだけでうつる」 – これは誤りです。前述の通りエボラウイルスは主に患者の体液との直接接触で感染し、インフルエンザのような空気感染(飛沫核感染)は通常起こしません5。患者の咳やくしゃみによる大きな飛沫が粘膜にかかれば感染リスクはありますが、それはかなり密接な距離で長時間接触した場合です。実際、潜伏期の無症状者から周囲に感染した例は報告されていません6。エボラ患者と同じ部屋にいるだけで必ず感染するわけではなく、正しい感染防護策(手袋・マスク・アイシールド等の着用、手洗い)を取れば過剰に恐れる必要はありません。ただし患者の体液には高濃度のウイルスが含まれるため、医療現場では空気感染対策も含め厳重な管理が必要です。
- 誤解②「エボラは致死率90%で、感染=死亡を意味する」 – これは極端な誇張です。確かに過去のアウトブレイクの中には致死率80~90%に達した例もあります5。しかしそれらは医療資源が乏しい状況下での数字です。平均的な致死率は約50%であり1、最新のデータでは30~60%程度に収まることもあります(例:2025年ウガンダ流行では29%4、2025年DRC流行では現時点で54%2)。早期に適切な支持治療を受けた患者は生存の可能性が十分あります。実際、2014~2016年の西アフリカ大流行では約2万8千人が感染し、そのうち約1万7千人が回復して生還しました。近年は治療薬の登場もあり、EVDは「必ず死ぬ病気」ではなくなりつつあります。ただし依然として非常に重篤で危険な疾患であることは間違いなく、症状が進行した重症例の致死率は極めて高い点には留意が必要です。
- 誤解③「有効な治療法やワクチンが存在しない」 – これは一部誤りです。前述のようにザイール株のエボラに対しては有効性が証明された治療薬(Inmazeb・Ebanga)やワクチン(Ervebo)が既に実用化されています89。これらは2018年以降のアウトブレイクで実際に使用され、患者の死亡率低下や流行封じ込めに成果を上げています10。一方で他の株(Sudan株・Bundibugyo株など)にはまだ承認済みの薬・ワクチンがなく、この点が「治療法がない」という誤解を生んでいるようです4。現在も新たなワクチン・治療薬の開発が進められており、2022年のスーダン株流行では候補ワクチンが試験導入されました(結果は今後解析)4。つまり「全く治療法が無い」わけではなく、特定の株に対しては既に対抗手段があり、そうでない株に対しても研究開発が進行中というのが正しい状況です。
- 誤解④「エボラ出血熱とエボラウイルス病は別の病気?」 – 同じ病気です。 Ebola Virus Disease (EVD) は直訳すると「エボラウイルス病」で、日本では従来「エボラ出血熱」と呼ばれてきたものと同一です。最近になって国際的に「出血熱」の名称を避ける傾向があり、WHOやCDCは公式名称をEVDに統一しています6。日本でも専門家の間ではEVDと表記されることが増えていますが、法令上の病名はエボラ出血熱のままです。いずれもエボラウイルスによる重症感染症を指します。
以上のように、エボラに関する情報は正しくアップデートされたものを参照することが大切です。不確かな噂に惑わされず、信頼できる公的機関(WHO、CDC、厚生労働省など)の発表や専門家の解説を基に判断してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. エボラ出血熱とエボラウイルス病(EVD)は何が違うのですか?
A1. 呼び方が違うだけで同じ病気です。近年、出血症状は必ずしも起きないことが分かったため「エボラウイルス病(EVD)」と呼ぶのが国際標準になりつつあります6。日本では法令上「エボラ出血熱」という名称ですが、WHOやCDCは公式にEVDの用語を使っています。記事中では両者を同じ意味で扱っています。
Q2. どんな症状が出ますか? 初期症状と重症化した場合は?
A2. 潜伏期間は2~21日(平均約1週間)で、その後突然高熱を発し体調が悪化します。初期は頭痛、筋肉痛、倦怠感、喉の痛みなど風邪に似た症状が多く、その後嘔吐、下痢、腹痛、発疹などが現れます2。重症化すると意識障害や出血症状(体内外の出血)、低血圧・ショックが起き、多臓器不全に陥ることもあります1。ただし出血は全患者に起こるわけではありません。症状が進行すると致命的になり得ますが、早期治療での生存例も多数あります。
Q3. エボラはどうやって感染しますか?空気感染しますか?
A3. 主な感染経路は患者や動物の体液との直接接触です5。血液、嘔吐物、下痢便、尿、唾液、汗などに触れて粘膜や傷口からウイルスが侵入します。使用済みの注射針や汚染された寝具からもうつる可能性があります。一般的な空気感染(飛沫核感染)はしません。咳やくしゃみの飛沫で近距離にいる人にウイルスが飛ぶことはありえますが、それだけで空気中を漂って広範囲に感染が拡大することはありません5。患者に触れなければ感染リスクは極めて低いですが、患者の看護や処置をする際には必ず防護具を着用する必要があります。
Q4. 潜伏期間中でも他人にうつりますか?
A4. 潜伏期間(症状の出ていない状態)で人に感染させることは基本的にありません。エボラウイルスは患者が発症して初めて体外に多量に排出されるようになります6。したがって、症状が出ていない人から日常的に感染が広がることはないと考えられています。ただし、回復者の体内にはウイルスがしばらく潜む場合があり、特に男性では精液中に最長で数百日ウイルスが残存する可能性が報告されています2。そのため、男性のエボラ回復者には退院後も一定期間コンドーム使用など安全な性行為を行うよう指導されます。
Q5. 治療法はありますか?エボラにかかったら助からないのでしょうか?
A5. いいえ、治療法がありますし、助かる可能性も十分あります。エボラ出血熱はかつて有効な薬がなく致死率も高い病気でしたが、現在は有効な治療薬(モノクローナル抗体治療)が開発されています8。ザイール株に対してはインマゼブやエバンガという薬が患者の生存率を大きく向上させることが分かっています。これらが使えない株の場合も集中的な支持療法(点滴・酸素投与・各種臓器サポート)によって救命が図られます1。実際、最近の流行では半数以上の患者が回復しているケースもあります4。感染=死亡では決してなく、早期に適切な治療を受けることが何より大切です。
Q6. ワクチンはありますか?一般の人も接種できますか?
A6. ザイール株に対するワクチンはあります。Merck社の「Ervebo」というワクチンで、2019年に承認されました9。エボラ流行時には患者の周辺にこのワクチンを接種することで感染拡大を防ぐ戦略が取られています(リングワクチネーション)。一方、一般の人が予防的に接種する機会は通常ありません。エボラが流行していない国では接種プログラムが存在せず、備蓄ワクチンは主に流行国への緊急用として提供されています10。ただし、今後はエボラ流行地域の医療従事者など高リスク者に対する事前接種も検討されています。なお、Sudan株など他の株に有効なワクチンは現在開発中で、2025年時点では公的承認済みのものはありません4。
Q7. 日本でエボラ患者が出たらどうなりますか?
A7. エボラ出血熱は日本では一類感染症に指定されており3、もし疑い患者が発生した場合は国が直ちに対応します。具体的には、患者は厚生労働省指定の特定感染症指定医療機関(高度な隔離設備を持つ病院)に搬送され、厳重な感染防御の下で治療を受けます。周囲の接触者も保健当局が21日間健康観察を行います。国内にはエボラウイルスを検出する検査体制(国立感染症研究所のBSL-4施設等)もあり、検査結果が出るまで患者は隔離管理されます。エボラは人から人への感染力が非常に高いわけではないため、適切に隔離・防疫すれば国内で大流行する可能性は低いと考えられます。政府も定期的にシミュレーション訓練を実施しており、万一の発生時に備えています。
Q8. 流行国に渡航予定なのですが、気を付けることは?
A8. まず最新の渡航情報を確認してください。外務省の海外安全ホームページや厚労省検疫所「FORTH」で、エボラ流行状況や注意事項が更新されています76。流行地域には可能な限り近づかないことが最善ですが、やむを得ず行く場合は以下を厳守してください:1) 手洗い・消毒の励行、2) 現地で動物や病人の体液に触れない(患者の看護は専門防護具なしに行わない)、3) 葬儀で遺体に触れない、4) 野生動物の肉を生で食べない。また、渡航中および帰国後21日間は自身の健康状態に注意し、もし発熱や体調不良を感じたらすぐに現地の医療機関に連絡し、エボラ流行地にいたことを伝えて指示を仰いでください。帰国後に症状が出た場合も、直接病院に行かず事前に保健所に電話相談しましょう。
まとめ
- エボラ出血熱(EVD)は致死率が平均約50%と高いものの、感染は主として患者・遺体の体液等への接触で起こり、通常は空気感染しません16。冷静な感染対策が重要です。
- ザイール株(EBOV)による流行には有効なワクチン(Ervebo)と治療薬(Inmazeb/Ebanga)が存在し、早期治療によって生存率の向上が期待できます98。アウトブレイク時にはリング接種などで拡大防止が図られています。
- Sudan株などその他のエボラウイルス病には、現時点で公的承認されたワクチン・治療薬がなく、支持療法が中心です。ただしワクチン候補や治療薬候補の開発・臨床試験が進められており、将来的な実用化が期待されます14。
- 2025年9月現在、コンゴ民主共和国カサイ州でエボラ流行が発生中(疑い症例58件・死者20人)ですが、WHOは当該流行の国際的拡大リスクを低いと評価しています211。現地ではワクチン展開や接触者隔離など封じ込め対策が継続されています。
- 日本国内ではエボラ患者の報告はなく、法的に最も危険度が高い「一類感染症」に指定されています35。万一の患者発生時には即座に隔離治療・周辺の検疫強化が行われる体制です。海外渡航者は最新情報を確認し、現地での予防策と帰国後の健康管理を徹底してください。
参考文献
- 世界保健機関(WHO) 「Ebola disease ファクトシート」 (2025年4月24日更新) 【WHO Newsroom】Ebola disease – Key Factswho.intwho.int ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27
- 世界保健機関(WHO) 「Disease Outbreak News: Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo, Kasai Province」 (2025年9月4日) 【WHO DON】DRC declares Ebola outbreak; 28 suspected cases and 15 deaths as of Sep 4who.intwho.int ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19
- 国立感染症研究所・国立健康危機管理研究機構 「エボラ出血熱 総説」 (2025年6月26日更新) 【NIID】エボラウイルスは6種(ザイール、スーダン等)に分類され、日本では患者報告なし。感染症法で一類感染症id-info.jihs.go.jpid-info.jihs.go.jp ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
- 世界保健機関(WHO) 「Disease Outbreak News: Sudan virus disease – Uganda」 (2025年4月26日) 【WHO DON】2025年ウガンダのSVD流行は12確認+2疑例で4人死亡(致死率29%)。他種向けワクチン・治療薬開発のため、候補ワクチンの臨床試験(Tokomeza SVD)が発足who.intwho.int ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14
- 厚生労働省 「エボラ出血熱について」 (公式サイト) 【厚労省】エボラ出血熱は主として患者の体液に触れることで感染する。ウイルスによって致死率は異なるが高いものは80–90%との報告mhlw.go.jpmhlw.go.jp ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
- 厚生労働省検疫所 FORTH 「エボラウイルス病(Ebola virus disease)」 (2024年3月更新) 【FORTH】出血症状がまれなため最近は「エボラ出血熱」でなく「EVD」と呼ばれる。感染症法では一類感染症forth.go.jpforth.go.jp ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12
- 外務省 海外安全ホームページ 「コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生」 (スポット情報, 2025年09月05日) 【外務省】DRCカサイ州でエボラ発生を宣言(9月4日)。同日までに28疑例・15死亡を報告、原因はザイール型エボラウイルスと確認anzen.mofa.go.jpanzen.mofa.go.jp ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
- 米国疾病予防管理センター(CDC) 「Clinical Guidance for Ebola Disease」 (2025年1月30日更新) 【CDC】FDA承認の治療(Inmazeb®とEbanga®)はザイール株エボラウイルスに対するもののみ。有効性は他のウイルスでは確立していないcdc.govcdc.gov ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
- 欧州医薬品庁(EMA) 「Ervebo – Product Details」 (2019年承認) 【EMA】Erveboは「ザイールエボラウイルスによるEVDの予防」を適応とするワクチンema.europa.eu ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
- Gaviワクチンアライアンス 「Vaccine Profile: Ebola」 (2025年4月15日) 【Gavi】2014年以降、エボラワクチンと迅速な対策により流行は速やかに封じ込め可能に。既存ワクチンは他の3種には無効で、Sudanウイルス用ワクチンも試験開始gavi.orggavi.org ↩ ↩2 ↩3 ↩4
- 米国疾病予防管理センター(CDC) 「Ebola Outbreak in the DRC: Current Situation」 (2025年9月10日更新) 【CDC】As of Sept 10, 2025: 58 suspected/confirmed cases and 20 deaths in Kasai Provincecdc.gov ↩ ↩2
