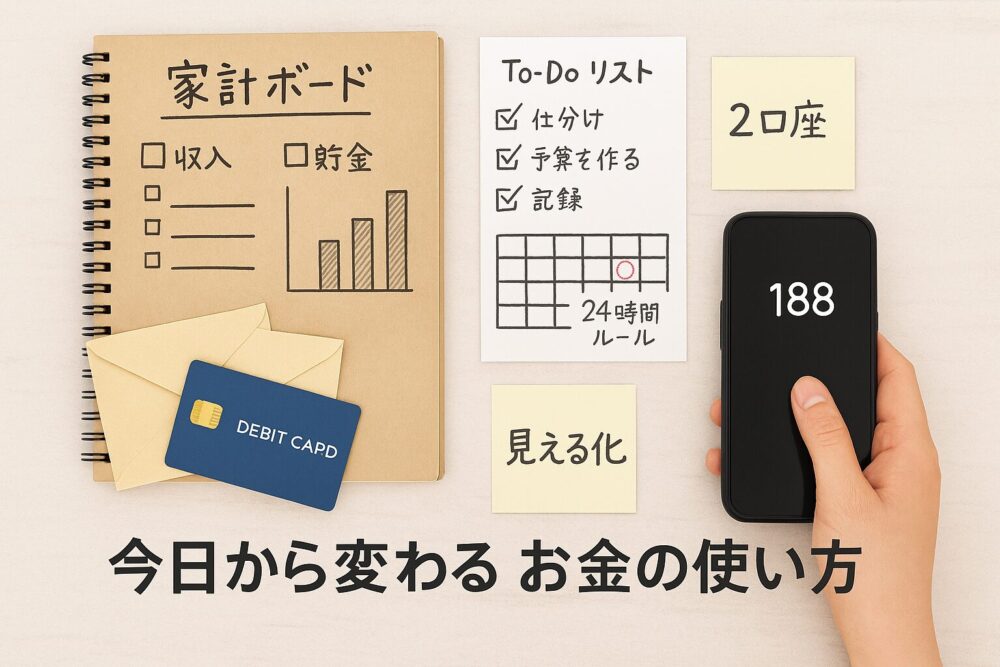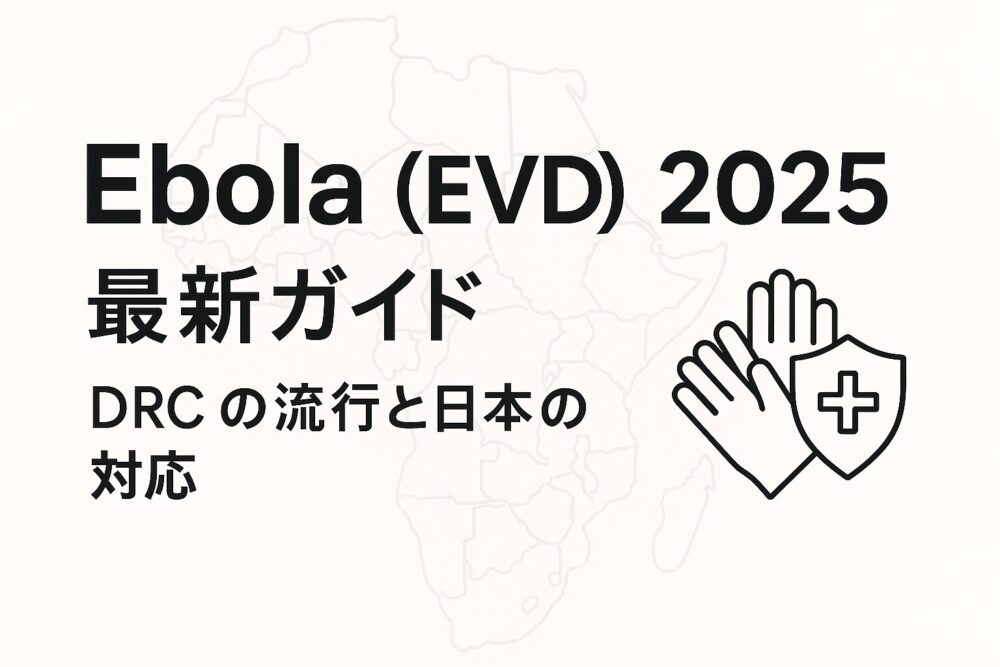会社勤めから離れ、日本で自給自足の暮らしを目指す人に向けた実践ガイドです。生活費の考え方から法的手続き、土地やインフラ整備、農作物の年間計画、収支管理、安全対策まで幅広く網羅し、初心者でも一歩ずつ進められるよう解説します。日本の制度や地域差に沿った最新情報に基づき、現実的で役立つノウハウをまとめました。
1. 自給自足のリアル:生活像・収入像・時間配分
自給自足生活では、現金収入は必要最低限に抑え、食料やエネルギーを自給することで生活費を減らす暮らしになります。生活費の内訳を見直し、住居費や食費、光熱費など固定費を極力削減することが重要です。また、農作業や生活維持のために費やす時間が大部分を占めるため、日々の時間配分も会社勤め時代とは大きく異なります。
生活費の内訳と節約の考え方: 自給自足では以下のような費目ごとに支出を最小化する工夫をします。
- 住居費: 空き家を活用したり、安価な古民家を改修することで住宅ローンを回避します。固定資産税や維持管理費のみで済むような物件選びを検討します。
- 食費: 主食や野菜を自給することで市場購入を減らします。調味料や不足する食材は季節ごとの特売や地域の直売所で安価に入手し、自家製の保存食で補います。
- 光熱費: 太陽光発電や薪ストーブ、プロパンガスの併用で電気代・燃料費を削減します。断熱改修や省エネ家電の利用でエネルギー消費量自体を下げる工夫も大切です。
- 通信費: 格安SIMや地域の公衆Wi-Fi活用で通信コストを抑えます。不要なプランやサービスは解約し、最低限のインターネット環境に絞ります。
- 保険・税金: 国民年金保険料や健康保険料、固定資産税など不可避な支出は計画的に確保します。節税策として青色申告などを活用し、医療費控除等も漏れなく申請します。
- その他費用: 医療や教育、交際費は地域の公的サービス(公立病院、図書館、児童館など)を活用し、過剰な出費を控えます。趣味・娯楽も自然の中で楽しめるものにシフトし、費用負担を減らします。
ミニマム生活の時間割: 自給自足では生活と仕事の境目がなくなり、1日の大半を生活維持と生産活動に充てます。平日・週末の区別も薄れ、季節や作物の生育状況に応じて時間配分が変化します。以下は平常時の日課の一例です。
- 早朝 (日の出~8時): 起床後に鶏など家畜の世話、水汲みや井戸ポンプの点検、朝食の準備を行います。夏場は涼しいうちに農作業を開始し、畑の見回りや収穫も朝のうちに済ませます。
- 日中 (8時~16時): 午前中は本格的な農作業時間です。畑の耕耘、種まき・定植、草取り、灌水など季節に応じた作業を集中して行います。正午前後に昼食と小休止を挟み、午後も引き続き農作業や薪割り、建物の補修作業などを進めます。季節によっては収穫物の保存加工(干物づくりや瓶詰め作業)を合間に行います。
- 夕方~夜 (16時~就寝): 日没前に家畜の最終見回りと戸締り、水槽や太陽光システムのチェックをします。夕食後、天候や翌日の作業計画を確認し、農作業日誌や家計簿を簡単に記録します。夏は夜間に採れた作物の選別や出荷準備、冬は読書や情報収集の時間に充てて早めに就寝します。
繁忙期(田植えや収穫期)は日の出前から作業し、休日も返上になることがあります。一方、農閑期や天候不良の日は道具のメンテナンスや帳簿付け、地域行事への参加などに時間を使います。年間の時間配分は季節ごとの優先作業によって決まり、天候に左右される柔軟なスケジュール管理が求められます。
2. 退職直後の必須手続き(時系列チェックリスト)
会社員を退職したら、速やかに社会保険や税務の切替手続きを進めます。以下に退職後すぐに行うべき主要な手続きを時系列で整理します(退職日翌日を起点)。漏れのないようチェックリスト形式で確認しましょう。
- 健康保険の切替(退職後14日以内): 会社の健康保険を抜けた後は、2つの選択肢があります。任意継続被保険者として以前の健康保険に引き続き加入する場合、退職日の翌日から20日以内に健康保険協会または健康保険組合へ申請書を提出します(期限厳守)。もしくは国民健康保険に加入する場合、退職日翌日から14日以内に居住地の市区町村役所で加入手続きを行います。任意継続は保険料が全額自己負担(在職時の約2倍)となる一方、保険給付内容は在職時と同様です。どちらを選ぶかは保険料負担や今後の収入見通しを考慮して判断しましょう。なお、健康保険証の発行までは時間がかかるため、手続き完了までは退職時に会社から受け取る「健康保険資格喪失証明書」を医療機関受診時に提示することで保険適用が可能です。
- 国民年金への加入種別変更(退職後14日以内): 会社員時代は厚生年金の第2号被保険者でしたが、退職によりその資格を喪失します。会社をしばらく離れる場合、自営業者などと同様に国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納める必要があります。退職後は年金手帳(基礎年金番号通知書)と退職証明書等を持参し、市区町村役所で第1号被保険者への種別変更届を提出してください。配偶者が会社員でその扶養に入る場合は、第3号被保険者への種別変更手続きとなります。同時に、保険料の支払い方法(口座振替等)も手続きを行います。収入が大幅に減る場合は、申請により保険料免除や納付猶予の制度も利用可能です(失業による特例免除制度あり)。未納のまま放置すると将来の年金受給に影響するため、納付が難しい場合でも必ず免除申請等を行いましょう。
- 税金関係の変更: 退職に伴い住民税の納付方法が「特別徴収(給与天引き)」から「普通徴収(自分で納付)」に切り替わります。退職時期によっては残りの住民税を一括精算するケースもありますが、自治体から改めて送付される納税通知書に従い、指定期日までに納付してください。また、退職した年の所得税の年末調整が不完全になるため、翌年2~3月の確定申告で精算が必要な場合があります(医療費控除等があれば申告)。
- 雇用保険・年金関連書類の受領: 退職時に会社から交付される「離職票」は、失業手当の申請や国民健康保険料の軽減措置(退職者本人の国保料減免)に用いる大切な書類です。速やかに受け取り、ハローワークや市区町村に提出する手続きに備えます。また、「厚生年金資格喪失届出済通知」等は年金種別変更に必要となる場合があるため手元に保管します。
- 開業届・青色申告の手続き(退職後できるだけ早く): 自給自足生活の一環で農業や小規模ビジネスを始める場合、個人事業の開業届を税務署へ提出します。提出期限は法律上「開業から1ヶ月以内」とされていますが、多少遅れても受理されます。開業届提出と同時に青色申告承認申請書も提出しましょう。青色申告を希望する年の3月15日まで(1月1日~1月15日に開業した場合)または開業日から2ヶ月以内のいずれか遅い方が申請期限です。青色申告の承認を受ければ、65万円の所得控除や損失の繰越控除など税制上のメリットが得られます。なお、農業で生計を立てる場合、確定申告上は原則「農業所得」として扱われますが、青色申告の適用を受けることで記帳による経費計上が認められ、収支管理の精度向上にもつながります。
- 労災保険の特別加入・共済制度への加入(随時): 自営業者や一人親方として農作業や建設作業に従事する場合、労災保険の特別加入を検討しましょう。農業者向けには特例で労災保険に任意加入できる制度があり、各都道府県の農業者等労災組合(JA等が窓口の場合もあります)を通じて申し込めます。特別加入すれば農作業中のケガにも労災保険給付が適用され、万一の事故時に治療費や休業補償を受けられます。また、将来の備えとして小規模企業共済(経営者の退職金制度)に加入することもできます。これは個人事業主が毎月積み立てを行い、事業廃止時に共済金(退職金)を受け取る国の共済制度で、掛金は全額所得控除の対象となります。退職金代わりの蓄えとして検討しましょう。
以上の手続きは退職後早めに取り掛かるべき事項です。特に健康保険と国民年金の切替は期限が短いので注意してください。これらを済ませることで公的なセーフティネットを確保し、安心して自給自足の準備に専念できます。
3. 土地選び:ハザード・法規・地域コミュニティ
自給自足の基盤となる土地選びでは、安全性と法的適合性に細心の注意が必要です。具体的には、自然災害リスクの少ない土地かどうか(ハザードマップの確認)、農地や森林としての法的規制の有無(農地法・森林法の許可要否)、および地域コミュニティへの適応(移住支援策や近隣関係)を総合的に検討します。
ハザードマップの読み方: 候補地が見つかったら、まず国や自治体が公開するハザードマップで自然災害リスクを確認しましょう。国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では住所を入力して各種災害リスクを地図上に重ねて表示できます。確認すべき主なハザード情報は以下の通りです。
- 洪水リスク: 河川の氾濫想定区域に入っていないかを調べます。色分けされた洪水浸水想定図で、計画高水時に想定される浸水深や流速を確認します。目安として、自宅建設予定地が50年~100年に一度の規模の洪水想定区域外であると安心です。どうしてもリスクのある土地を選ぶ場合は、高床式にする・土嚢を常備するなど対策が必要になります。
- 土砂災害リスク: 山裾の土地では土石流や地滑りの警戒区域に指定されていないかを確認します。土砂災害警戒区域や特別警戒区域(レッドゾーン)に該当すると開発行為や建築に制限がかかる場合があります。斜面下の土地を選ぶ際は、擁壁の有無や排水状況もチェックし、必要なら補強工事を検討します。
- 津波・高潮リスク: 沿岸部では津波浸水想定エリア、内湾部では高潮浸水想定エリアを確認します。標高が低い海岸近くの土地は避け、過去の津波到達履歴や避難経路も下調べします。自治体によってはハザードマップに過去の災害史も記載されているので参考にしましょう。
- その他のリスク: 火山の降灰予測圏内(火山灰堆積厚の想定)、断層帯の近接による揺れやすさ(地震の最大震度分布)なども公開情報をもとに把握します。可能であれば地盤の強度(表層地盤のゆれやすさマップ)も参照し、液状化や軟弱地盤の心配が少ない土地を優先します。
こうしたハザード情報は市町村の防災マップでも詳細に確認できます。不動産業者や売主から提供される「重要事項説明書」にもハザード情報が記載されるようになりましたが、自分でも事前に調べて納得した上で土地購入に臨むことが大切です。
農地法の基本(農地を扱う場合): 自給自足で野菜や米を育てるために農地付きの土地を選ぶケースもあるでしょう。その際は農地法の規制を理解しておかなければなりません。農地法は農地の無秩序な転用を防ぎ、優良農地の確保を図るための法律です。ポイントは農地の売買・貸借と転用(農地以外への用途変更)に厳格な許可制があることです。
- 農地法第3条(権利移動の許可): 農地を耕作目的で他人に売ったり貸したりする場合に適用されます。例えば、農家から自給自足希望者が農地を購入する際は、第3条許可が必要です。許可権者は都道府県知事(または市町村農業委員会)で、地域の農業委員会が申請内容を審査します。許可の要件として、買主が農業経験や経営計画を持ち、取得後も適切に耕作を行う見込みがあることが重視されます。遊休化防止の観点から、単なる資産保有目的での農地取得は許可されません。
- 農地法第4条・第5条(農地転用の許可): 農地を農地以外に転用する場合、第4条または第5条の許可が必要です。第4条は「自分の農地を自ら他用途に転用する場合」、第5条は「農地を他者に渡し、その者が転用する場合」に適用されます。例えば、農地上に自宅を建てる、駐車場にする、といったケースは転用許可が要ります。許可権者は都道府県知事等で、地域の農業委員会が現地の農地評価や土地利用計画との整合性を審査します。市街化調整区域などでは基本的に農地転用は難しく、農業上支障ない場所へ用途を誘導する考え方がとられています。市街化区域内の農地に限っては例外で、農業委員会への事前届出のみで許可不要となるケースもあります(市街化区域はむしろ宅地化を優先するため)。
- 無許可転用の禁止: 農地法に違反して許可なく農地を宅地化した場合、厳しい罰則や原状回復命令が科されます。違反転用は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)と定められており、悪質なケースでは実際に刑事罰が適用されています。絶対に無届で農地を転用しないよう注意してください。土地探しの段階で農地が含まれる場合は、購入前に農業委員会に相談し、転用が可能か許可の見込みを確認することをおすすめします。
森林の扱い(林地・山林の場合): 候補地に山林が含まれる場合や、自給自足のために山林を購入する場合も法令上の手続きがあります。日本の森林は「森林法」により適正管理が求められ、伐採や開発には届出・許可制が導入されています。
- 伐採及び造林の届出: 個人であっても、森林所有者等が森林内の立木を伐採するときは事前に「伐採及び伐採後の造林の計画届出」を提出する義務があります。提出先はその森林所在地の市町村長で、伐採開始の90日前から30日前までに行います。あわせて、伐採後にどのように植林するか(造林計画)も記載します。伐採が終わった後は、伐採後の森林の状況報告を30日以内に、造林完了後も造林完了の状況報告を30日以内に市町村に提出する必要があります。これは商用・自家用問わず適用され、例えば自宅用の薪を確保するために数本木を切る場合でも、規模によっては届出対象となります(森林法上「森林」とみなされる土地であれば1本でも届出が必要です)。届出を怠ると罰則がありますので、山林を管理・利用する際は自治体林務担当に事前相談しましょう。
- 森林所有者届出制度: 平成24年以降、新たに森林の土地を取得した人は、取得後90日以内に市町村長に所有者届出をすることが義務付けられました。これは、誰がどの森林を所有しているかを行政が把握し、適切な森林管理に活かすための制度です。売買・相続・贈与などで森林を手に入れた場合が対象で、面積の大小に関係なく届出が必要です(※国土利用計画法に基づく大規模土地取引の届出を別途行っている場合は重複を避けるため不要となることがあります)。取得時には登記事項証明書や契約書の写し、土地の位置図を添付して所定の様式で提出します。森林を取得した際にはこの届出も忘れないよう注意しましょう。
- 林地開発許可: 森林を宅地や農地に転用する「開発行為」を行う場合、一定規模以上では林地開発許可が必要です。原則として1ヘクタールを超える面積の森林を他用途に転用する場合、都道府県知事の許可が求められます(地域森林計画対象森林の場合)。小規模でも保安林(治山や水源涵養のため指定された森林)に指定されている土地では、転用や伐採は別途厳しい許可制です。自給自足用の山林を開墾して畑や宅地にしようとする際は、これら林地開発規制に該当しないか事前に確認してください。違法な大規模開墾は罰則に加え、植林などの原状回復命令が下る可能性があります。
地域コミュニティと移住支援: 自給自足は地域の中で営むものです。地域選びでは、単に土地の条件だけでなくコミュニティとの相性や行政の移住支援策も考慮しましょう。
- 空き家・空き地バンクの活用: 国土交通省支援のもと、多くの自治体が空き家バンクを運営しています。これは地域の空き家情報を登録し、移住希望者に紹介する仕組みです。自治体によっては空き家バンク経由で成約すると補助金が出たり、改修費助成、家賃補助などの特典がある場合があります。インターネット上で全国の空き家バンク情報をまとめたポータルサイトもありますので、「全国版空き家・空き地バンク」で検索し、希望エリアの物件を探してみましょう。空き家バンク登録物件は比較的安価で、すでに農地や井戸が付属している場合もあり、自給生活のスタートに向いています。
- 移住・交流支援窓口(JOIN等): 自治体レベルでは、移住希望者向けに地域おこし協力隊制度の募集や、お試し移住体験、移住相談会の開催など積極的な支援策があります。総務省所管の「移住・交流推進機構(JOIN)」では全国の移住支援情報を発信しており、UIターンフェアやオンライン相談にも対応しています。移住支援金(自治体によって数十万円~百万円単位)を支給する地域もあるので、自治体ホームページの移住定住促進ページを確認しましょう。
- 地域との付き合い: 農村地域では自治会や隣組活動、共同作業(草刈りや祭礼準備など)が日常に根付いています。移住先ではこれら地域活動に積極的に参加し、顔を覚えてもらうことが円滑な人間関係の第一歩です。近隣住民への挨拶はもちろん、年始の集まりや盆踊りなどにも顔を出し、「地域の一員」として信頼を得る努力をしましょう。田舎は助け合いが大切で、農作業の知恵や災害時の協力など、良好な関係が自給自足生活を支える大きな力になります。
以上のように、土地選びではハザードリスクの低減と法令順守、そして地域に受け入れられる素地作りが重要です。「安全な土地を、正しく利用し、地域と調和して暮らす」ことを念頭に、慎重かつ積極的に準備を進めましょう。
4. 住まいとインフラ(オフグリッドを含む)
自給自足の住まいづくりでは、都市の既成概念にとらわれず、必要最低限の住宅性能とインフラを自前で確保する発想が求められます。日本の建築・設備関連法規を踏まえつつ、可能な範囲でオフグリッド(電力や水道を公的インフラに頼らない)を目指します。このセクションでは、建築の許可や各種インフラ(給水・排水・電力・熱源)について基本事項と実践ポイントを整理します。
建築基準法と小規模建築: 住宅や小屋を新築・改築する場合、建築基準法上の手続きが必要かどうかを確認します。原則として、都市計画区域や準都市計画区域内で延べ面積が10㎡を超える建築物を建てるときは、工事前に建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けなければなりません。具体的には一般的な居住用建物であればほぼ該当します。ただし、地域や構造によって一部緩和措置も存在します。
- 都市計画区域内の場合: 現在は法改正により、木造2階建て以下・延べ面積200㎡以下の住宅であっても、2025年以降は構造安全性や省エネ基準の審査が原則必要となりました(いわゆる「4号特例」の縮小)。つまり、従来簡略化されていた小規模木造住宅でも、基本的には建築確認のプロセスで構造や断熱の適合をチェックされると考えておくべきです。よって都市計画区域内で住居を建てるなら、延床10㎡を超えるものはほぼ建築確認申請が必要と見込み、建築士に設計を依頼して適法な建物にする必要があります。
- 都市計画区域外の場合: 区域外の山間部などでは、建築確認の対象は限定的です。法律上は区域外であっても建築基準法そのものの適用はありますが、確認申請が必要となる範囲が狭まります。改正後の基準では、区域外でも2階以上または延べ200㎡超の建物は確認申請が必要になりました。裏を返せば、区域外で平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物であれば、確認手続きを経ずに建てることが可能です(ただし耐震・防火など最低限の基準には適合させなければなりません)。例えば山奥の農地に10㎡程度の物置や、小規模なタイニーハウス(平屋)を建てるケースでは、区域外であれば確認申請は不要となる場合があります。
- 増改築・用途変更: 既存建物を改修して住む場合も注意が必要です。大規模なリフォーム(耐震補強や構造に影響する改造)は建築確認が必要になる場合があります。2025年の法改正で、木造住宅の屋根・外壁の大規模改修や床の改修も確認申請対象に含まれました。無届けで改築してしまうと違反建築となり、最悪使用禁止や是正命令の対象となりえます。古民家を改装する際も専門家に相談し、必要な手続きを経るようにしましょう。
- 違法建築のリスク: なお、無許可で小屋や増築部分を造ったままでは金融機関の融資や火災保険が受けられないなどの不利益があります。行政に発覚すれば除却命令など法的措置もあり得ます。よって、「小さいから大丈夫」と安易に考えず、必ず地域の建築主事や役所に相談してから建て始めることが重要です。
水の確保と衛生: 上水道が引かれていない山間部などでは、自前で飲料水や生活用水を確保する必要があります。主な方法は井戸の掘削と雨水の貯留利用です。
- 井戸の掘削: 地下水に恵まれた地域では井戸を掘ることで生活水を確保できます。井戸には浅井戸(比較的浅い地下水層から汲み上げる)と深井戸(深い帯水層まで掘削する)があります。掘削にあたって法令上は届出義務はありませんが、自治体によっては地下水保全条例により、大口の井戸(吐出量が一定以上、例えば日量100トン超など)を設置する場合は事前届出や許可が必要なことがあります。個人利用の井戸であれば通常届出不要ですが、事前に自治体環境課等に確認すると安心です。井戸掘り工事は専門業者に依頼し、工事費用は深さや地質によりますがおおむね数十万円~百数十万円かかります。完成後、水質検査を必ず行いましょう。厚生労働省の「飲用井戸等衛生対策要領」に基づき、飲用井戸の所有者は年1回程度の定期水質検査が指導されています。検査項目は一般細菌、大腸菌、亜硝酸性窒素、有機物など水質基準項目全般です。自治体の衛生研究所や保健所経由で検査可能なので積極的に利用し、水質に問題があれば浄水器設置や煮沸などで対応します。
- 雨水の利用: 屋根に降った雨を集めて貯留し、生活雑用水として使うことも有効です。雨水タンクや地下システムを設置し、トイレ洗浄水や園芸用水、防災用水に活用できます。簡易計算式として、
雨水年間回収量(ℓ) = 屋根面積(m²) × 年間降水量(m) × 回収効率
例えば屋根面積100㎡・年間降水量1.5m・回収効率0.8なら、年間120㎥(=120,000ℓ)の雨水を集められる計算です。雨水は基本的に雑用水向けですが、濾過・煮沸により非常時には飲用にも転用できます。利用の際は蚊の発生防止(密閉型タンクを使う、メッシュを張る)や、タンクの凍結対策も考慮してください。 - 浄化槽の設置と維持: 水道が無く公共下水道も通っていない場合、生活排水は浄化槽で処理します。浄化槽はトイレ汚水や生活雑排水を微生物の働きで浄化する設備で、設置には都道府県知事への届出と指定工事店による施工が必要です。補助金制度がある自治体も多いので問い合わせてみましょう。設置後は浄化槽法により維持管理義務が課されます。具体的には年1回の法定検査(知事指定の検査機関による水質検査等)、数ヶ月ごとの保守点検(専門業者による機能点検と薬剤補充等)、そして年1回以上の清掃(汚泥の汲み取り)を実施しなければなりません。例えば一般家庭用の5人槽合併浄化槽では、通常年3~4回の点検と年1回の清掃が必要です。これらを怠ると処理性能が落ち、公害の原因となるだけでなく法的にも罰則の対象です。点検・清掃契約を地元業者と結び、維持費(月数千円程度)を予算に入れておきましょう。
電力:太陽光発電と蓄電システム: 自給的生活では商用電力網に頼らず自前で電力を賄うオフグリッド電源を検討します。一般的なのは住宅用太陽光発電の設置です。10kW未満の太陽光発電システムであれば電力会社との系統連系なしに自家消費用として設置できます。太陽光パネルと蓄電池を組み合わせ、日中発電した電気を夜間や悪天候時に使えるようにします。必要容量の目安は次の式で算出可能です。
1日必要発電量 (kWh) = 家庭1日消費電力量 ÷ (平均日射量 × システム効率)
蓄電必要量 (kWh) = 1日消費電力量 × 希望自立日数 ÷ DoD (許容放電深度)
例えば、家庭の1日消費が5kWh、地域の平均日射量が4kWh/㎡、システム効率80%(0.8)の場合、必要発電量は約15.6kWh(5÷(4×0.8))。希望自立日数2日、蓄電池のDoDを0.8とすれば蓄電必要量は約12.5kWh(5×2÷0.8)となります。この計算をもとにパネル容量や蓄電池容量を決定します。
- 施工と技術基準: 太陽光発電設備も電気設備の一種です。出力10kW未満の住宅用太陽光は電気事業法上「一般用電気工作物」に分類され、設置工事には電気工事士(第一種または第二種)の資格が必要です。自家用(50kW以上)ほどではありませんが、2021年施行の省令により住宅用太陽光でも技術基準への適合義務が明確化され、経済産業省への事前届出は不要なものの、設備は安全基準に沿って維持する義務があります。よってオフグリッドであっても、パワーコンディショナーや配線は国家資格者が適切に施工し、安全を確保しましょう。素人施工で発火事故等が起きれば損害が甚大です。
- 売電か独立か: 余剰電力を電力会社に売るFIT売電を行う場合は系統連系契約が必要で、逆にオフグリッドで完全独立運転する場合は蓄電池容量を大きめに積む必要があります。最近では売電価格が低下し、蓄電池の価格も下がってきたため、自家消費メインで設計するケースが増えています。夜間や雨天のバックアップとして、小型のエンジン発電機や、近年普及しているポータブル電源も備えておくと安心です。
熱源と住環境: 暮らしに欠かせない熱エネルギー(暖房・調理・給湯)についても、自給と安全のバランスを考えます。
- 断熱と通風: まず住宅そのものの性能として断熱性・気密性を高め、冬暖かく夏涼しい工夫をしましょう。古民家の場合は隙間風対策や襖・障子の補修、天井裏への断熱材敷設などが有効です。夏は窓の簾(すだれ)やグリーンカーテン、通風路の確保で冷房に頼らない工夫をします。
- 暖房: 山間部など寒冷地では薪ストーブが定番です。薪は自分で山から調達できれば燃料費はほぼゼロですが、毎年乾燥させた薪を十分量確保し、煙突掃除などメンテナンスも必要です。薪ストーブは遠赤外線で身体を芯から暖めてくれますが、一酸化炭素中毒防止の換気や火災防止策に注意してください。石油ストーブや石油ファンヒーターも即暖性があり停電時にも使えますが、灯油代と換気が課題です。LPガス暖房(ガスファンヒーター)は都市ガスが無くても利用できますが、ガスボンベの調達と費用負担がかかります。
- 調理と給湯: 調理はプロパンガスコンロか薪・炭火が主になります。プロパンは都市ガスより割高ですが、ボンベ1本で長期間使え、災害時も強みです。かまどを作って薪炊きで調理するのも趣がありますが、夏場の室温上昇や煙の問題があります。給湯は太陽熱温水器を屋根に載せておけば晴天時は燃料いらずでお湯が作れます。冬期や日照不足時は薪ボイラーやガス給湯器と併用して安定供給します。
- リスクとコスト比較: 各熱源ごとに利点と課題があります。薪は燃料費こそ安いものの、集材・乾燥・薪割りの手間が非常にかかり、また近隣への煙の配慮が必要です。石油やガスはコストと補給の手間(買い出しや配送)があります。太陽熱や断熱への初期投資は掛かりますが、長期的には経費節約と快適性向上に寄与します。地域の先達の知恵も参考に、複数の熱源を組み合わせて無理なく運用するのがおすすめです。
以上を踏まえ、自給自足のインフラ構築では「ローコスト・ローエネルギーで暮らせる住まい」を目標に計画しましょう。建築や設備のプロにも相談し、安全第一で無理のないオフグリッド化を進めることが肝要です。
表1:初期費用内訳(例) 自給自足生活を始める際にかかる主な初期コストの一例を示します。地域や物件状態で幅がありますが、目安としてご覧ください。
| 項目 | 費用レンジ(万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 土地取得 | 0~300 | 空き家バンクなら実質0円も(登記費用等別途) |
| 建物準備 | 50~500 | 古民家改修なら100~200、新築小住宅なら300以上 |
| 井戸掘削 | 50~150 | 地質・深度で変動。ポンプ・水槽含む |
| 浄化槽設置 | 50~100 | 5人槽程度。補助金考慮せず |
| 太陽光発電+蓄電池 | 100~300 | 5kW前後+蓄電池5~10kWh相当 |
| 農具・作業機械 | 10~100 | 耕運機、刈払機、チェーンソー等(中古活用で安価に) |
| 寒冷地対策設備 | 0~50 | 薪ストーブ一式や断熱材、二重サッシ設置など |
| 予備費 | 30~100 | 想定外の修繕・医療・車両購入等へのバッファ |
※上記は目安。地域物価や家族人数、既存資源の有無で変動します。自治体補助や中古品の活用で費用を抑える余地もあります。
5. 食の自給:作付け計画・保存・小動物
食料の自給自足は、自ら生産する作物の年間計画と、収穫物を無駄なく保存・活用する知恵が鍵となります。また、小規模な家畜(鶏など)やミツバチの飼育も食料供給源として有益です。このセクションでは、日本の気候に合わせた栽培カレンダーの立て方、主食・副食の必要量と面積目安、収穫物の保存方法、そして養鶏・養蜂のポイントを解説します。
年間栽培カレンダーの作成: 日本は南北に長く、地域ごとに気候が大きく異なるため、栽培計画もそれに応じて調整します。まず、地域を大まかに寒冷地(北海道・東北高冷地), 温暖地(本州中部・関東以西の平野部), 亜熱帯(沖縄・南西諸島)の3つに分け、それぞれの平均的な気象条件を把握します。目安となる1991~2020年の平年値では、例えば札幌(寒冷地)の初霜日は10月下旬、東京(温暖地)は12月下旬、那覇(亜熱帯)では霜が降りることはありません。同様に初雪日は札幌で10月中旬、東京で1月上旬(年によっては降雪なしもあり)、沖縄は降雪ゼロです。初霜日は露地野菜の生育終了の目安となり、初雪日は越冬野菜の収穫期限の目安になります。
こうしたデータを踏まえて、地域別に作付けスケジュールを組み立てます。下記に三地域の代表的な年間サイクル例を示します(播種=種まき、定植=苗の植え付け、収穫=収穫時期、保存=保存加工時期)。
表2:地域別 作付け計画カレンダー(例)
| 月 | 寒冷地(北海道型) | 温暖地(関東・中部型) | 亜熱帯(南西諸島型) |
|---|---|---|---|
| 1月 | ビニールハウス内で葉物播種開始(ホウレンソウ等) 雪中ニンジン収穫 | 露地は閑散期(防寒対策) ハウスで苗作り準備 | 秋作サツマイモ収穫・保存 露地トマト播種開始 |
| 2月 | ハウスでジャガイモ種芋植付け 育苗器で夏野菜播種 | 早春野菜の播種(エンドウ等) 水田代かき準備 | トマト苗定植 春作キュウリ播種 |
| 3月 | 雪解け後、露地タマネギ定植 育苗したキャベツ定植 | 稲の育苗開始 春ジャガイモ植付け 夏野菜播種 | 春作野菜収穫始まる 水稲育苗開始 |
| 4月 | 水稲直播き(遅霜注意) 露地ニンジン播種 | 田植え(上旬~中旬) 夏野菜苗定植 | 梅雨入り前の収穫最盛期 夏バテ野菜準備 |
| 5月 | 遅霜終了、露地キュウリ・トマト定植 田植え完了 | 夏野菜管理(摘芽・誘引) 梅雨対策開始 | 夏野菜植え替え マンゴー収穫 |
| 6月 | 春まき小麦収穫・乾燥 一番草の牧草収穫 | 梅雨期:病害虫防除 タマネギ収穫・乾燥 | 台風期前半:防風対策 サトウキビ植付け |
| 7月 | 夏野菜最盛期収穫 ジャガイモ収穫・貯蔵 | 夏野菜収穫盛期 梅雨明け後乾燥保存 | 台風期:畑養生 バナナ収穫・出荷 |
| 8月 | 夏野菜片付け 秋播きキャベツ種まき | 二期作米の田植え(温暖地の一部) 秋ナス接ぎ木 | 夏野菜更新 甘藷植え付け |
| 9月 | 秋小麦播種 稲刈りと脱穀・籾摺り | 稲刈り・天日干し サツマイモ収穫・乾燥 | 台風明け秋植え準備 野菜種まき再開 |
| 10月 | ジャガイモ二期作収穫 根菜類の収穫貯蔵開始 | 冬野菜定植(ハクサイ等) 落花生収穫乾燥 | 秋野菜植付け 稲二期作収穫 |
| 11月 | 初霜~初雪:露地野菜収穫終了 ハウスへ移行 | 落ち葉堆肥づくり 冬野菜収穫開始 | 秋野菜収穫 ビニールで保温栽培開始 |
| 12月 | ハウス栽培中心(ホウレンソウ等収穫) 雪対策 | 冬野菜収穫最盛期 年内農作業納め | 冬作準備(沖縄でもやや閑散) サトウキビ刈り |
(注:上記は典型的な例です。品種選びや栽培方法でずれが生じますので、地域の農業改良普及センター等が公表している栽培暦を参照してください。)
主食と副食の必要量と面積目安: 自給自足生活では、カロリー源となる主食作物と栄養バランスを補う副食作物の両方を計画的に育てます。一般的な成人1人あたりの年間食料消費の目安から、生産すべき量を逆算し、必要な栽培面積を見積もります。
- 主食作物: 日本の主食といえば米ですが、他にもイモ類や麦類が挙げられます。1人の1年間の玄米消費量は約60kgが目安です。水稲栽培では10a(=1反=1000㎡)あたり玄米収量が約450~600kg得られます。したがって、米だけで1人分を賄うなら10aあれば十分ですが、現実には畑地での作業主体なら水田確保は難しいこともあります。その場合はサツマイモやジャガイモで主食カロリーを補完します。サツマイモは10aあたり2~4トンの収穫があります。可食部の水分を飛ばした乾燥芋なら保存も効き、1日あたり200~300g摂取すれば主食カロリーをかなり賄えます。小麦については、パンや麺の自給用に栽培するなら1人あたり年間20kg程度の小麦粉があるとよいでしょう(10aで小麦は約300~400kg収穫できますが、脱穀・製粉の手間を考えると自給難易度は高めです)。
- 副食作物: タンパク質源やビタミン・ミネラル供給源として、豆類・野菜・果樹を計画します。大豆は「畑の肉」と呼ばれるタンパク源で、1人年間10kgの大豆を収穫できれば豆腐・味噌・納豆など加工して重宝します(大豆の収量は10aで200~300kg)。野菜類は多品目を少しずつ長期間収穫できるよう、葉茎菜類(ホウレンソウ、コマツナ等)、果菜類(トマト、ナス等)、根菜類(ダイコン、ニンジン等)を時期をずらして播種します。概算では、常時10~15種類ほどの野菜を作付けし、延べで5a(500㎡)程度あれば一家の野菜はほぼ自給可能です。果樹は植えてから収穫まで年数がかかりますが、柿や栗、梅など手間の少ない在来果樹を数本植えておくと秋の味覚や保存食材料が得られます。柑橘類は温暖地であればミカン・レモンなど育てられ、ビタミン補給源になります。
収量は天候や栽培技術で変動するため、初めのうちは目標の1.5倍程度の種をまいて余裕を持つとよいでしょう。余剰が出れば保存食や近隣へのおすそ分け、交換にも役立ちます。
収穫物の加工・保存: 四季のある日本では、収穫期が集中する作物も多いです。それを無駄なく保存し、季節外れでも食べられるようにする工夫が昔から発達しています。主な保存方法とポイントを押さえておきましょう。
- 乾燥保存: 穀物や豆類、乾物野菜に適した方法です。米や麦は収穫後に天日干し・乾燥させてから貯蔵します。トウモロコシや小豆なども乾燥保存可能です。野菜ではダイコンやカボチャを薄切りにして干し、大根切干や干しカボチャにすると長期保存できます。乾燥させることで水分活性が下がり、カビや腐敗を防げます。コツは晴天続きの時期に行うことと、夜間は室内に取り込んで露を避けることです。
- 塩蔵・漬物: 塩漬けは古典的な保存法です。梅干しや沢庵漬け、味噌漬けなど、野菜や果実を塩や発酵力で保存食に変えます。大量の塩を使う「塩蔵」は強力な方法で、野菜重量の20%前後の塩で漬け込むと雑菌の繁殖が抑えられます。塩抜きしてから利用します。漬物は塩だけでなく、糠床や麹、酢なども活用し風味付けと保存性向上を両立します。衛生面では、容器の洗浄・消毒(熱湯や焼酎で拭く)や、雑菌が入らないよう手指を清潔にすることが重要です。
- 発酵保存: 味噌・醤油・酢・酒など、発酵を利用した食品は長期保存が効くだけでなく栄養価も高まります。自給自足では手づくり味噌や漬物は是非チャレンジしたいところです。味噌なら大豆と米麹、塩があれば1年仕込みで完成します(毎年仕込んで持ち越していくサイクル)。発酵食品作りは温度管理と塩分濃度がポイントです。カビが生えたら早めに取り除き、空気を遮断することで被害を広げないようにします。
- 冷凍・冷蔵: 電力に余裕があれば、冷凍庫・冷蔵庫も有効に使いましょう。冬にまとめて仕留めたジビエ肉を冷凍しておいたり、夏野菜を下茹でして冷凍保存すれば、オフシーズンにも食べられます。冷蔵は短期保存向きですが、根菜類は砂に埋封して冷暗所に置くなど電力に頼らない方法もあります。じゃがいもや玉ねぎは風通し良い冷所で吊るして保管するのが伝統的です。
保存については、食品衛生にも留意します。特に密閉保存する瓶詰め(ジャムやシロップなど)ではボツリヌス菌など食中毒リスクがゼロではないため、事前に煮沸消毒を行い、加熱充填や真空シールを確実に行います。保存食には日付ラベルを貼って古いものから消費し、異臭・異変があれば勇気を持って廃棄してください。
養鶏の導入: ニワトリを数羽飼えば、新鮮な卵を毎日得られ、肉もいざというとき食料になります。家庭での少数飼育でも留意すべき点があります。
- 衛生管理基準: 日本では家畜伝染病予防法に基づき、鶏など家禽の所有者は飼養衛生管理基準を守る義務があります。営利か非商用かを問わず1羽でも飼えば適用対象です(2025年から非商用飼育者向け基準も制定されました)。具体的には、「鶏舎への部外者立入制限」「飼育施設の清掃消毒」「野鳥やネズミの侵入防止」「飼養記録の作成」「異常発生時の家畜保健衛生所への通報」など多岐にわたります。特に高病原性鳥インフルエンザ対策として、渡り鳥が集まる水場を鶏に近づけない、発生地域への移動自粛、鶏舎の消石灰散布等が推奨されます。小規模養鶏でも密飼いの防止(適切な飼育密度)や定期的なワクモ(ダニ)駆除は欠かせません。
- 飼育環境: ニワトリ小屋(鶏舎)は日当たりと風通しの良い場所に作ります。夜間はイタチやキツネ、野良猫から守るため施錠できる構造にします。地面飼いの場合は床に厚めに敷料(もみ殻やウッドチップ)を敷き、定期的に天地返しして清潔を保ちます。餌は配合飼料が市販されていますが、米ぬかや野菜くず、虫などを与えても構いません。ただし偏った餌は栄養不足を招くので、配合飼料をベースに補助的に家庭残渣を与える程度にします。水は常に清潔なものを飲めるよう、毎日交換します。
- 産卵と世代管理: 複数羽飼う場合、雌鶏だけで構いません(受精しなくても卵は産みます)。若鶏は生後5~6か月で産卵を開始し、2~3年が産卵の盛期です。徐々に産卵数が減るため、卵用に飼うなら数年ごとに若い鶏と入れ替える計画も必要です。雄鶏は繁殖用以外は不要ですが、一緒に飼うと受精卵が取れヒヨコを孵すこともできます。孵化には孵卵器が必要ですが、自然に抱卵させる方法(抱卵癖のある品種なら自ら温める)もあります。
- 糞の処理: 鶏糞は良質な有機肥料になります。敷料と混ぜて堆肥化すれば畑に還元できます。ただし生のままだとアンモニア臭が強く近隣迷惑になるので、鶏舎周りの掃除はこまめに行いましょう。堆肥化には数ヶ月かかるため、野積みにせずコンポスト容器等を使い臭気を抑える工夫をします。
養蜂の導入: ミツバチを飼えば自家製ハチミツが得られるだけでなく、作物の授粉にも役立ちます。日本では養蜂にも一定のルールがあります。
- 届出義務: 各都道府県では「養蜂に関する届出制度」を設けており、蜂場(巣箱の設置場所)や飼養蜂群数を届け出ることが求められます。これはミツバチ伝染病(アカリンダニ症や腐蛆病など)の発生時に迅速に防疫措置を講じるためです。例えば○○県では年に1回、養蜂家(趣味レベル含む)は所定の様式で知事に届出しなければなりません。自宅敷地で1箱だけ飼う場合でも対象になりますので、開始前に必ず県の畜産担当部署へ確認・届出を行いましょう。
- 飼育方法: 初心者はセイヨウミツバチよりも在来のニホンミツバチから始めると管理が楽です。ニホンミツバチは攻撃性が低く、自然群を捕獲して飼う方法(待ち箱設置)も盛んです。一方セイヨウミツバチは大量のハチミツを蓄えますが、巣箱管理や分蜂対策、女王蜂の人工交替など手間がかかります。巣箱は太陽を背に受ける向き(南東向き)に設置し、夏は直射を避ける工夫をします。水場を近くに用意し、周囲に農薬散布が少ない環境が望ましいです。
- 周囲への配慮: ミツバチは基本的におとなしい生き物ですが、巣箱付近に人やペットが頻繁に近づく環境だと刺す事故のリスクがあります。隣家との距離を取り、必要に応じて目隠し塀を立てて蜂の飛行経路を上空に誘導します。巣箱には所有者名を表示しておくことが望ましいです(万一刺傷事故等が起きた際の責任所在明確化のため)。収穫したハチミツを販売する場合は食品衛生法の表示基準なども守る必要がありますが、自家消費の範囲ならそこまで気にする必要はありません。ただしハチミツは満1歳未満の乳児に与えてはいけない(ボツリヌス症予防)点は周知のとおりです。
- 病気と対策: ミツバチにも病気やダニ寄生が発生します。代表的なのがバロア病(ミツバチヘギイタダニ)やノゼマ病、ヨーロッパ腐蛆病などです。これら法定伝染病が疑われる場合はすみやかに家畜保健衛生所に連絡し、指示に従います。日頃から巣箱の観察を怠らず、異変(女王不在・幼虫の異常・ダニの付着など)に気付いたら早めに養蜂先輩や専門機関に相談しましょう。適切に管理すればミツバチは毎年増え、美味しい蜂蜜と豊かな受粉効果をもたらしてくれます。
以上、自給用の作物栽培と小動物飼育について概観しました。「多様な食糧源を少しずつ持つ」ことが、自給生活の安定につながります。自然の声を聞きながら、無理のない範囲で徐々に取り組んでみてください。
6. 自家製を売る:許可・衛生・表示の勘所
自給自足で生産した農産物や加工品を自家消費するだけでなく、一部を販売できれば貴重な現金収入となります。ただし食品を販売するには、食品衛生法その他の規制を守り、必要に応じて行政への許可・届出を済ませる必要があります。ここでは小規模な食品販売に関わる衛生管理や許可の境界線について解説します。
食品衛生法とHACCP的衛生管理: 2021年6月以降、改正食品衛生法により規模を問わずすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。小規模な生産者や個人の農産加工についても例外ではありません。ただし経営規模や業態に応じて2段階の基準があり、大規模事業者には厳密なHACCPプランの策定が求められる一方、小規模事業者等には簡略化した「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」で良いとされています。
- 小規模事業者の衛生管理: 農家が副業で漬物やジャムを作って直売所で販売するといった場合は、この簡易HACCPに沿った衛生管理を行います。具体的には、業界団体や行政が作成した手引書(例えば「小規模な一般飲食店向け手引書」「郷土料理店向け手引書」など)を参考に、自分の作業工程で注意すべきポイントを押さえて衛生計画を立て、日々の衛生管理を記録するというものです。例えばジャム製造なら「原料果実の選別洗浄」「瓶の煮沸消毒」「中心温度◯℃で◯分加熱」「キャップの真空シール確認」「完成品のラベル日付管理」などをルール化し、その通り実施・記録します。難しく感じるかもしれませんが、手引書に沿ってチェックリストを作り日誌に書いていけば問題ありません。「記録して証拠を残す」ことがHACCPの根幹なので、面倒でも実施しましょう。
- 地域の制度サポート: 各地の保健所は小規模営業者向けにHACCP導入講習会や個別相談に応じています。また農産物直売所によっては、出荷者に対して簡易的な衛生管理計画書の提出を義務付けている場合もあります。販売を始める前に一度保健所に相談し、どの程度の衛生管理と届出が必要か確認しておくと安心です。
生鮮農産物の販売: 自分で栽培した野菜や果物の生鮮品(加工していないもの)を販売すること自体には、基本的に許可や届出は不要です。農作物の販売は食品衛生法上の「営業」には当たらず、生産者が自ら行う直売は自由にできます。ただし販売方法によって必要な手続きがあります。
- 直売所やマルシェで販売: 多くの地域に農産物直売所があります。出荷者登録をすれば、収穫した野菜を委託販売してもらえます。手数料(売上の10~20%)が引かれますが、不特定多数の消費者にアプローチできるメリットがあります。出荷の際は品質表示(品名、産地、氏名、収穫日など)を所定のシールに記載します。直売所によっては出荷者講習会を実施し、栽培記録の提出や農薬使用履歴の記帳などを求めることがあります。安全な農産物を提供するためのルールですので遵守しましょう。
- インターネット販売(ECサイト等): 野菜セットなどをインターネットやSNSを通じて販売する場合、青果物はクール便等で発送します。青果はクール冷蔵扱いで食品衛生法上の許可は不要ですが、販売者として食品表示法に基づく表示を行う義務があります。生鮮食品の場合、一般的に「生鮮食品品質表示基準」に沿って、生産地、名称、包装者(または販売者)の情報を明記する必要があります。ネット販売なら商品説明ページや同梱チラシにそれらを記載します。また、特定商取引法に基づき通販サイトには販売業者情報や返品特約などを表示する義務があります。
- 食品衛生管理上の注意: 生鮮でも例えばカット野菜(カットサラダ)のように一度加工し袋詰めすると「加工食品」扱いとなり、保健所の許可が必要になる場合があります。自宅の台所でカット野菜を作って販売することは原則できません。どういう形なら許可不要か曖昧な場合は、事前に保健所に確認しましょう。「土付き野菜を洗って袋に詰めただけ」は生鮮扱いでOKですが、「一口大に刻んでミックスしたサラダセット」は加工食品と判断されアウト、といった線引きがあります。迷ったらプロに聞くのが賢明です。
農産加工品の販売: 野菜そのものではなく、ジャム・ピクルス・干し野菜・米粉パン・菓子類など加工品を販売するには、一層留意が必要です。原則として、これらは製造するための営業許可または営業届出が必要になります。
- 許可が必要な加工品: 飲食店営業、菓子製造業、食品製造業など業態ごとに食品衛生法の営業許可が定められています。例えばジャムやジュース、漬物、味噌などを製造販売するには「そうざい製造業」や「飲料製造業」等の許可が必要でした。ただ、2021年の改正で許可業種が見直され、一部は許可ではなく届出制になりました(低リスクの食品を扱う業種)。小規模な農家加工の場合、対象とする食品がどの業種に当たるかで対応が変わります。基本的には自宅とは別に衛生管理ができる加工場(ミニキッチンでも基準を満たせば可)を用意し、保健所に設備図面や工程を書類提出して審査を受けます。基準を満たせば営業許可証が交付されます。初期費用はかかりますが、一度許可を取れば販路拡大も可能になります。
- 許可が不要なケース(グレーゾーン): 自家製品の範囲内で譲渡する場合など、許可がいらない例もあります。例えば蜂蜜は採取して容器詰めするだけなら食品衛生法上「採取業」として許可不要です(ただし表示義務あり)。また年間の販売額がごく少額で、営利というより趣味的な頒布である場合などは行政指導も緩やかです。ただ、公衆に販売する以上は「万一健康被害を出したら」という責任を常に意識してください。たとえ法的に許可不要であっても、先述のHACCPに沿った衛生管理は当然求められます。消費者の信頼を得るためにも、製造施設や製品の清潔さ、適切な表示は不可欠です。
- 表示のポイント: 加工食品を販売する際は食品表示法に基づき、ラベルに「名称」「原材料名」「内容量」「賞味期限」「保存方法」「製造者(又は販売者)名・住所」「アレルゲン表示(義務7品目)」などを記載します。例えば手作りジャムなら「いちごジャム」「原材料名:いちご(自家栽培)、砂糖、レモン果汁」「内容量:○○g」「賞味期限:〇年〇月〇日」「要冷蔵(10℃以下)」「製造者:○○ファーム 山田太郎 住所○○」「本品製造工房では小麦・乳成分を含む製品も製造しています(コンタミ注意喚起)」等をラベルに書きます。表示は一見煩雑ですが、一度ひな形を作れば使い回せます。なお、誇大表示(薬効があるなど)は景品表示法で禁止されています。「無農薬」「オーガニック」などの表現もガイドラインに沿って適切に使用しましょう(証明がなければ「農薬不使用(自社圃場にて)」程度に留めるなど)。
直売・EC・委託販売の実務: 最後に、販売チャネル別の実務ポイントをまとめます。
- 直売(対面販売): 農産物直売所への出荷や朝市・マルシェへの出店などです。対面でお客さんの反応を聞けるメリットがあります。釣銭管理や簡易な売上帳簿の準備を忘れずに。慣れたら顧客名簿を作り、リピーターには次回出店を案内するなど関係構築すると良いでしょう。
- インターネット販売(EC): 自分のネットショップやフリマアプリ等で販売する場合、注文管理・入金確認・梱包発送といった事務作業が発生します。特に生鮮品は発送日の調整やクール便指定など気を遣います。農繁期に販売対応が過度な負担とならないよう、商品数や受付期間を調整してください。発送時には品質保持のため保冷剤や緩衝材を使い、到着希望日を確認するなど、きめ細かな対応が信頼につながります。トラブル時(配送遅延や品違い)はすぐにお詫びと代替提案を行い、誠実な姿勢を示しましょう。
- 委託販売(店舗や加工所への提供): 自分では小売しない代わりに、地域のパン屋に小麦を卸す、飲食店に野菜を出荷する、といったルートです。この場合は取引先との契約を交わし、数量・価格・納品頻度を取り決めます。品質にムラがないよう、規格を揃える努力が必要です。対面販売より単価は低めになりがちですが、安定取引となれば生産計画を立てやすいメリットがあります。信用第一なので、納期厳守と安定供給に努めましょう。
いずれの形態でも、「安全・安心な食品を提供する」ことが最優先です。無理のない範囲で始め、慣れてきたら徐々に販路を広げると、自給自足生活の一部が立派な事業にも育ち得ます。法律を守りつつ、自慢の自家製品を届けてください。
7. お金のリアル:収支モデルと税務
自給自足生活では現金収入が減る一方、生活費も抑えられるため大きな収支は発生しません。しかし完全な無貨幣生活は現実的でないため、最低限の収入確保と計画的なお金の管理が必要です。このセクションでは、年間収支のモデルケース、農業所得等の税務上の扱い、そして利用できる補助金・融資制度について述べます。
月次キャッシュフローのサンプル: まず自給自足家計の概算を掴んでみましょう。以下に単身者が山里で自給生活する場合の月次収支表(サンプル)を示します。
表3:月次ランニング費用と収入(例)
| 区分 | 項目 | 月額費用(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 支出 | 食材購入費(塩・調味料等) | 5,000 | 主食野菜は自給、購入は調味料・油・嗜好品程度 |
| 燃料費(ガス・灯油・ガソリン) | 8,000 | プロパンガスボンベ代、発電機用ガソリン等 | |
| 水道・メンテナンス | 1,000 | 井戸ポンプ電気代、浄化槽点検代の積立 | |
| 通信費(電話・ネット) | 3,000 | 格安SIM+ネット(シェア回線など) | |
| 保険料(国民健康・国民年金) | 30,000 | 任意継続健保と国民年金(免除なしの場合) | |
| 税金(住民税・固定資産税等) | 5,000 | 収入少なら住民税非課税、固定資産税は年額の月割り | |
| 医療・衛生費 | 2,000 | 通院や薬代の積立 | |
| 交際費・近隣協力費 | 1,000 | 冠婚葬祭や地域行事の参加費 | |
| 教育・娯楽費 | 2,000 | 図書購入や移動費、学習費等 | |
| 予備費(更新・修繕積立) | 5,000 | 太陽光設備更新、作業機械修理などに備える | |
| 支出合計 | 62,000 | ||
| 収入 | 農産物・加工品販売収入 | 30,000 | 直売所売上(月) ※季節で変動 |
| アルバイト収入 | 20,000 | 繁忙期以外に在宅ワークなど(月数日程度) | |
| 給付金等(農業支援・助成) | 5,000 | 年間6万円の交付金がある場合(月割り) | |
| その他(年金、一時収入) | 0 | (該当なし) | |
| 収入合計 | 55,000 | ||
| 収支 | (収入)-(支出) | ▲7,000 | 月平均では赤字。ただし貯蓄や季節収入で補填 |
上記モデルでは月平均で若干赤字となっていますが、例えば繁忙期には農産物収入が月5~6万円に増えるなど季節変動があります。退職前の貯蓄や、臨時収入(不用品売却、たまの帰省時の短期バイト等)で年間収支をトントンに合わせるイメージです。家族がいる場合は支出は増えますが、児童手当や家族労働力での生産増など補う要素もあります。
農業所得・事業所得・雑所得の整理: 自給自足で得る収入は税法上どのように扱われるでしょうか。基本的に、自分で生産物を販売した場合は農業所得または事業所得として確定申告します。
- 農業所得: 農作物や農産加工品の販売による所得は、営利性があり継続して行うものであれば「農業所得(広義には事業所得の一種)」になります。農業所得は収入金額から必要経費を引いて計算します。経費には種苗代、肥料代、農具代(減価償却)、燃料費、直売所手数料などが該当します。赤字でも申告は必要ですが、青色申告なら損失の繰り越しが可能です。
- 事業所得 vs 雑所得: 農業以外に手工芸品を売ったり、在宅の内職収入がある場合、それらも本格的に事業として行っていれば事業所得にできます。事業所得と認められれば青色申告特別控除など有利な点があります。一方、規模が小さく反復継続性が低いものは雑所得として申告することもあります。例えば年に数回フリマで手作り品を売って2~3万円程度なら雑所得扱いでしょう。基準は明確ではないですが、おおむね生活の主たる収入になるものは事業所得、副収入程度なら雑所得というイメージです。税率自体は所得合算なので同じですが、青色申告できるか等で違いがあります。
- 青色申告の活用: 可能な限り青色申告の承認を受けておくことをおすすめします。前述の通り、開業後2ヶ月以内(遅くとも申告年度の3月15日まで)の届出が必要ですが、これにより最高65万円の控除や家族従事者への給与計上、損失3年繰越など節税に有利な制度を使えます。記帳と帳簿保存が義務になりますが、最近はスマホアプリや会計ソフトで簡単にでき、農業所得向けの出納帳テンプレートなども普及しています。もちろん、規模が小さく白色申告でも税が発生しない場合は無理に青色にしなくても構いません。ただ、いざ利益が出るようになったときに備え、早めに帳簿付けに慣れておくと良いでしょう。
補助・給付・融資制度の活用: 自給自足的な暮らしにもマッチする公的支援制度がいくつか存在します。特に、新規就農者を支援する国や自治体の制度は手厚いものがあります。
- 新規就農支援資金(経営開始資金): 農林水産省では新規就農者(原則独立・自営就農かつ45歳未満)に対し、最長5年間にわたり年間最大150万円の給付を行う制度があります【要件:青年等就農計画の認定など】。夫婦で就農する場合は2人分受け取れる場合もあります。本格的に農業で成形を立てる意思があるなら、この「農業次世代人材投資資金」(旧青年就農給付金)にチャレンジする価値があります。自治体農政課に相談すると手続きや研修情報を教えてくれるでしょう。
- 自治体移住支援金: 都市部から地方への移住促進策として、多くの自治体が移住世帯に移住支援金を支給しています。例えば東京23区から地方圏へ移住し、地域で定める就業条件を満たした場合、単身で60万円、世帯で100万円を支給する、といった例があります。起業支援金を上乗せする自治体もあります。条件(転入前の年数や就業業種など)は自治体ごとに違うので、各自治体の移住支援金情報を確認してください。自給自足は数値化しにくいですが、地域おこし協力隊に応募して給与をもらいながら活動し、その延長で定住するようなケースもあります。
- 農業関係の融資・資金: 農地取得や機械購入には、政策金融機関(日本政策金融公庫)の農業経営基盤強化資金や自治体の農業改善資金など低利融資制度が利用できます。無利子または数%程度の金利で借りられるものもあります。もちろん借金は慎重に検討すべきですが、どうしても初期投資が足りない場合は、計画を練った上で相談してみましょう。また、農協(JA)の組合員になれば、購買部で資材を安く買えたり、農機のリース利用、共済加入による災害補償などサービスを受けられます。一人で抱え込まず、使える制度や組織は上手に活用するのが賢明です。
税・社会保険の対策: 収支と並んで重要なのが税金と保険です。第2章で触れたとおり、国民年金・国保はきちんと継続して支払い、万一のときに備える必要があります。収入が低ければ国民健康保険料の減免や国民年金保険料の免除制度もありますから、市町村に相談してみましょう。住民税についても、所得が一定以下なら非課税になります。なお、退職後に地域で事業を始めた場合、事業税(都道府県税)の対象になることがありますが、農林水産業は事業税非課税です。副業で小売業等をして一定所得超なら事業税が課税される可能性がありますので、一度税務署や税理士に確認しておくと安心です。
最後にお金に関する心得として、「お金をかけずに暮らす工夫が最大の収入」と覚えておきましょう。収入アップを焦るより、支出ダウンの工夫がそのまま可処分所得の増加につながります。とはいえ、想定外の出費(医療費・自然災害の被害など)にも備え、わずかでも貯蓄を続ける習慣が大切です。収支表をつけて現状を見える化し、持続可能な自給自足ライフのために金銭面でも健全な計画を維持しましょう。
<a id="section8"></a>
8. リスク管理(自然災害・衛生・労災・近隣)
自給自足生活には、自然相手ならではのリスクや、社会保障の手薄さに伴う不安がつきものです。しかし事前に対策を講じ、備えを怠らなければ多くのリスクは軽減できます。この章では、自然災害への備え、衛生管理、作業中の安全、そして近隣トラブルの防止策について整理します。
自然災害への備え: いつどこで起きるか分からない自然災害ですが、ハザードマップで把握したリスクごとに対策を講じます。
- 水害・土砂災害: 洪水が想定される地域では、非常時に避難できるよう最低3日分の水・食料・常備薬を備蓄し、避難経路とタイミングを家族で確認しておきます。床上浸水が心配な家では、貴重品や食料を2階など高所に保管、止水板や土嚢の準備も有効です。土砂災害警戒区域に住む場合、豪雨時は早めの自主避難を心がけ、裏山の亀裂や濁り水の湧出など前兆現象に注意します。防災行政無線やスマホの警報は必ず受信できるようにしておきましょう。
- 地震: 全国どこでも起こり得る地震に備え、耐震性の確保と家具の転倒防止を徹底します。古民家の場合、筋交いや金物で簡易耐震補強する、重い瓦屋根を軽量化するなどで倒壊リスクを減らせます。非常用発電機や太陽光がある場合でも、燃料備蓄やバッテリーの健全性チェックをしておきます。井戸があれば断水時の水源になりますが、ポンプが電動なら手押しポンプを予備で用意するといった多重対策も有効です。
- 台風・暴風: 亜熱帯地域では台風シーズンの対策が重要です。飛ばされやすい農業用資材や工具は物置にしまい、ビニールハウスなどは補強ロープで縛っておきます。停電に備えて発電機や蓄電池の点検を事前に行いましょう。台風の進路次第では早めに雨戸を閉め、風で割れそうな窓には養生テープやベニヤ板で補強します。倒木の恐れがある老木は日頃から伐採・剪定しておくことも大切です。
- 火山灰・寒冷: 火山の近くでは降灰用にゴーグルや簡易マスク、雨樋保護ネットなど用意します。寒冷地では暴風雪や吹き溜まりに警戒し、発電機用の防雪囲い、除雪具の準備、暖房燃料の多めの備蓄を冬前に済ませます。
また、公的な自然災害共済・保険への加入も検討しましょう。農業者なら収穫物の災害共済(例えば「農業共済(NOSAI)」)に加入すれば、台風や雹で農作物が被害を受けた際に補填が出ます。自宅建物も火災保険に水災補償を付けておくと洪水時に支えになります。費用と相談ですが、「備えあれば憂いなし」です。
衛生ルーチン: 前章でも触れましたが、衛生管理は毎日の小さな積み重ねで大事に至るリスクを防ぎます。
- 水回り衛生: 井戸水を飲用に使う場合、定期的な水質検査と必要に応じた浄水処理は欠かせません。大雨の後は井戸水が濁ったり病原菌が侵入しやすいので、煮沸してから使うなど慎重に。雨水タンクもボウフラ発生を防ぐためにフタ付きのものを使用し、清掃も行います。浄化槽は前述のとおり点検清掃を怠らず、悪臭がしたら直ちに業者に相談します。トイレの汚泥を自家処理することは法律上禁止なので、必ず許可業者に汲み取ってもらいましょう。
- 動物由来感染症: 鶏やヤギなど動物を飼っていると、人畜共通感染症のリスクがあります。例えば鶏糞に存在するカンピロバクター菌は食中毒原因となりえますし、放し飼いの鶏が鳥インフルエンザに感染する場合もあります。日々の作業では手袋を着用し、作業後は必ず石鹸で手洗いをします。動物由来の食品(生卵、生乳など)を生で口にするときは新鮮清潔なものに限ります。万一飼育動物が大量死したり異変があれば、迷わず獣医師や保健所に報告してください。狂犬病などは日本ではまれですが、野生動物(コウモリやアライグマなど)が家屋に入り込まないよう屋根裏や床下の穴は塞ぎます。また、マダニ媒介感染症(日本紅斑熱等)に注意し、草むら作業時は肌を露出しない・帰宅後シャワーで流すなどの対策を習慣づけましょう。
- 食品衛生: 自給用の台所でも食中毒には用心します。野菜はよく洗い、肉や魚は中心まで十分加熱するのが原則です。とくに鶏肉やジビエ肉は内部までしっかり火を通してから食べます。ハチミツは前述の通り乳児には絶対与えない。保存食を開封したらカビや異臭をチェックし、おかしいと思ったら「もったいない」より「安全第一」ですぐ廃棄します。夏場は調理後すぐ冷蔵、残り物は翌日持ち越さないなど、家庭内でもHACCP的な衛生管理意識を持ちましょう。
作業安全と労災加入: 自給自足ではチェーンソー作業、草刈機運転、屋根の雪下ろしなど危険が伴う作業も多々発生します。安全第一の心構えと、もしものときの補償準備が必要です。
- 農業機械・道具の安全: チェーンソーを使う際は防護ズボン・ヘルメット・防護メガネ・防振手袋などフル装備し、キックバックや挟み込みに注意した正しい姿勢で作業します。草刈り機も小石飛散などで失明事故が起きないようゴーグルや防護ネット付きフェイスシールドを着用します。高所作業(樹上や屋根)は命綱を必ず結び、単独でなく複数人で行うのが望ましいです。重作業は無理せず休憩を取り、熱中症や過労による判断ミスを防ぎます。農作業事故は毎年多く報告されており、特に高齢者が巻き込まれる傾向があります。作業開始前に機械の点検と作業手順の再確認、「ヒヤリハット」の共有などを習慣化しましょう。
- 労災保険の特別加入: 先にも述べましたが、自営農業者や家族従事者でも労災保険に特別加入できます。具体的には「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」等の区分があり、農業従事中や農業機械運転中の事故に対して労災と同等の補償を受けられます。加入には労災保険事務組合(多くは農業協同組合や農業委員会が窓口)を通す必要があります。保険料は給付基礎日額に応じて年額数万円程度ですが、万一大怪我をして就労不能になった場合の給付金(休業補償給付や障害補償年金)を考えれば、加入のメリットは大きいでしょう。ケガだけでなく、熱中症や蜂刺されといった疾病も労災範囲に入る可能性がありますので、自己判断せず医師に「仕事中の発症」と伝えてください。なお、兼業的に事業を行う場合は中小事業主等として特別加入する方法もあります。
- 保険・共済の検討: 労災以外にも、例えばJAの「農機具共済」に加入すれば草刈機や耕運機の盗難・破損時に補填されます。高額なトラクター等を持つ場合は入っておくと安心です。また、作業中に第三者に怪我を負わせてしまった場合の賠償責任保険(個人賠償責任保険)も、自動車保険や火災保険の特約で付けられます。チェーンソー作業中に倒木で隣家の屋根を壊した、飼い犬が人に噛み付いた、といったケースに備えるものです。年数千円の特約なので、いざというときのため検討してください。
近隣との関係: 最後にソフト面のリスク管理として、人間関係について触れます。田舎では人付き合いが濃密である反面、一度トラブルになると孤立してしまうこともあります。
- 騒音・臭気の配慮: 鶏やヤギを飼うと鳴き声が響きます。近隣が住宅密集地なら頭数を抑える、朝晩はできるだけ屋内に入れるなど配慮します。草刈機やチェーンソーは朝早くや夕暮れ時の使用を避け、長時間連続運転もしません。堆肥の臭いも風向き次第で集落に流れるので、発酵促進剤を使う、水分量を調整するなどして悪臭化を防ぎます。井戸水ポンプの振動音も意外と響くので、適切な防振ゴム設置や稼働時間帯の調整を行います。自分では気付きにくいので、率直に隣人に尋ねてみる姿勢も大事です。
- 境界と通行: 田畑の区画や山林の境界は曖昧な場合があります。隣地との境界杭を確認し、トラブルになりそうなら公費で境界確認測量を行うのも手です。また自分の土地であっても、地域の農道や水路沿いにある場合は共同管理の意識を持ちます。農道に私物を置いて通行の邪魔をしない、水路が詰まれば率先して泥上げする、といった行動が信頼につながります。
- 情報共有: 集落内の回覧板や寄り合いには極力参加し、地域の動きを把握します。自分の活動(例:◯日に里山で間伐作業をします 等)を事前に周知しておくと、音や出入りへの理解が得られやすくなります。対話を重ねておけば、逆に近隣から何か困り事があった際に打ち明けてもらえ、早期解決できます。
結局のところ、リスク管理の基本は「想像力」と「対話」です。最悪の事態を想像して事前策を講じ、周囲と対話して協力関係を築く。これによって多くのリスクは顕在化する前に抑え込むことができます。自給自足とは自然との対話であり、また人との対話でもあることを忘れず、安全で安心な暮らしを続けていきましょう。
9. はじめの365日:0–30–90–180–365日ロードマップ
自給自足への道のりは長く感じられるかもしれませんが、最初の一年間で基盤を固めることができればその後がぐっと楽になります。ここでは、退職から1年後までのロードマップを、期間ごとの目標と達成すべきチェックリスト形式で示します。各段階で起こりがちな失敗例も挙げ、回避策を考えてみましょう。
0日(退職時点): 会社員生活を終えたその日から準備開始です。
- 到達指標: 社会保険関連の書類一式を手元に揃えている(離職票、年金手帳、健康保険喪失証明など)。移住予定地がおおよそ決まっているか、下見の計画が立っている。
- 主なタスク: 退職日に健康保険証を返却。会社からもらう書類をチェック。移住先のハザード情報を収集開始。家族がいる場合は学校や仕事のスケジュール調整を始める。
- 失敗例と対策: 失敗例: 退職の達成感でしばらく何もせず過ごし、各種手続き期限を逃す。→ 対策: 気持ちを切り替え、章2のチェックリストに沿って翌日から役所を回る。スケジュール帳に14日・20日の期限を書き込んでおく。
1ヶ月(退職後30日): 生活の土台を固めるフェーズです。
- 到達指標: 年金と健康保険の切替手続き完了。住民票移転(予定地が決まっていれば)。農業委員会や役場移住担当との初回相談済み。可能なら仮住まいを確保。
- 主なタスク: 国民年金1号種別変更届を提出し、保険料納付開始。国民健康保険加入or任意継続完了し、新しい保険証を取得。移住先を現地訪問、空き家物件を数件内覧。地方銀行口座やJA口座を開設しておく。簡易な事業計画(何をどれくらい育てるか、初年度に必要なものは何か)を書き出す。
- 失敗例と対策: 失敗例: 収入が無くなる不安から公的手続きよりアルバイト探しを優先してしまい、肝心の準備が疎かになる。→ 対策: 数万円の収入より数十万円の支援策や制度の方が重要。まず補助金や支援を最大化できる準備を優先する。バイトは手続き完了後でも遅くない。
3ヶ月(退職後90日): 移住〜生産基盤づくりの開始時期です。
- 到達指標: 新居に入居済み(または入居日決定)。農地や作業場の確保完了。基礎的な農具類を購入。第一弾の作付けプラン決定。
- 主なタスク: 物件契約・引越し。森林や農地の権利取得の場合は必要届出(森林所有者届出など)を提出。耕作を始める畑の土壌を確認し、必要なら石灰や堆肥を投入して地力改良開始。4〜5月スタートの場合、ジャガイモ植え付けや夏野菜の種まきを適期に行う。近所へ挨拶回りし、地域行事に顔を出す。
- 失敗例と対策: 失敗例: 移住直後に張り切りすぎて、一度に広い畑を耕し種をまいたが手が回らず雑草だらけになる。→ 対策: 最初は小さい面積から始め、徐々に拡大する。除草・灌水などメンテナンスの手間を見積もり、背伸びしすぎない計画にする。また、隣家との境界に勝手にフェンスを立てトラブルになる例も。まずは現状を尊重し、勝手な工作物は設置しない。
6ヶ月(退職後180日): 生活と作業のリズムが定まり始める時期です。
- 到達指標: 春〜夏の収穫物を得て、自給的食生活が軌道に乗り始めている。副産物の保存食を数種類仕込んだ。収支表をつけ始め、半年間のお金の流れを把握。
- 主なタスク: 初夏〜夏野菜の収穫・保存(梅干し漬け、ジャム作り、干し野菜等)。鶏を飼い始めるならヒナの導入と育成開始。害獣(鳥獣)対策の柵設置や忌避剤散布を実施。役所に農業者として経営開始届を提出(※一定規模以上の場合や補助金申請のため必要なとき)。青色申告用の帳簿に半年分の記帳をまとめる。
- 失敗例と対策: 失敗例: 最初の夏に体を壊す(熱中症、腰痛など)ケース。慣れない農作業で無理を重ね、寝込んでしまい世話が滞る。→ 対策: 早朝作業+日中休息+夕方作業のメリハリをつけ、決して無理をしない。困ったときは素直に近所の人に助けを求める(案外助けてくれる)。休むのも仕事くらいの意識でセルフケアする。
また、イノシシ被害で畑が全滅する失敗も。→ 対策: 被害が出る前提で対策を準備。電気柵やネットを早めに設置し、猪が好むサツマイモ等は柵内だけで栽培する。
12ヶ月(退職後365日): いよいよ一年経過です。四季を一通り経験し、次の年の課題が見えてくる頃です。
- 到達指標: 自給できる食材が食卓の過半数を占めるようになった。1年分の収支を総ざらいし、大きな赤字なく乗り切れた。地域で顔馴染みが増え、困り事を相談し合える関係ができた。
- 主なタスク: 秋の収穫・保存(米の脱穀・精米、根菜の収穫埋蔵、味噌仕込み等)。収穫祭や直売所イベントに出品してみる。冬支度として薪・燃料の確保、断熱補強の点検。退職から年度を跨ぐ場合、確定申告を初めて行う準備(青色なら決算書作成)。1年間で痛んだ箇所(工具や設備)を点検し、更新計画を立てる。
- 失敗例と対策: 失敗例: 1年で燃え尽きてしまい、翌年以降の計画を立てず成り行きになる。→ 対策: 1年目は試行錯誤で当然。うまくいったこと・失敗したことをノートに整理し、2年目のプランに反映させる。来年挑戦したい作物や取り組みを書き出し、冬の間に計画を練る時間を持つ。
もう一つ、地域との関係で孤立する失敗も。最初は物珍しさで皆親切だったが、受け身でいるうちに距離ができた…という例。→ 対策: 2年目からは自分が地域に何を提供できるか考える。余剰野菜を配ったり、草刈りボランティアを買って出たり、小さなことでも役立つ行動をする。人間関係はGive&Takeで長続きするもの。
ロードマップはあくまでモデルケースですが、節目ごとに目標を立てて検証することはモチベーション維持に有効です。予定通りに行かないことも多いですが、焦らず一歩ずつ進めば確実に自給自足力は上がっていきます。1年後には、あの会社勤めの日々が遠く感じられるほど、充実した暮らしが待っていることでしょう。
10. ケーススタディ(3例)
人それぞれ置かれた状況が違えば、自給自足へのアプローチも変わってきます。ここでは典型的な3つのケースを例に、想定されるプランや課題を見てみましょう。
ケース1:単身・貯蓄300万円・30代男性
会社勤めに区切りをつけ、30代で早期リタイアして地方移住するパターンです。体力もあり、独身ゆえ身軽に動けるのが強みです。
- 土地・住居: 空き家バンクで家賃月2万円の古民家を借り受ける想定。農地は借家の庭と近隣の耕作放棄地を0.5haほど借用。初期費用は農機具購入(管理機やチェーンソー等)に50万円、太陽光3kW+蓄電池に150万円、井戸掘り無しで上水道利用。
- インフラ: 電気は太陽光+蓄電池+発電機でほぼ自給、ただし冬場ピークや連日の雨天には系統電力もバックアップ利用。水は上水道に接続済みだが節約のため雨水をトイレ洗浄などに併用。移動は軽トラック1台購入し、農作業と兼用。
- 作付: 1人なのでコメは5a(50㎡)の小区画で試験的に栽培、主食はジャガイモ・サツマイモで賄う計画(合わせて10a)。副食野菜は20種類程度を延べ5aで時期をずらし栽培。大豆1a、麦2aもトライし、味噌・醤油づくりに挑戦。裏山の竹林からタケノコや山菜も活用。
- 収支: 貯蓄を取り崩しつつ、はじめ2年は直売所に夏野菜を出荷して年20万円程度の収入目標。ゆくゆくは露地野菜の品目を絞り、もう少し出荷量を増やして年50万円ほど稼ぐ計画。支出は単身なので月5~6万円に抑え、年間収支は貯蓄取り崩し10~20万円程度に収める。
- 時間配分: 平日はフルに農業・林業作業に充てる。本人の趣味が狩猟なので冬場は狩猟免許を取得し、有害鳥獣駆除のボランティア兼副収入にもつなげる。繁忙期以外は読書やブログ執筆(発信を収入化できる可能性も)に時間を充てる。
- 課題: 一人暮らしゆえ病気やケガの際のリスクが高い。近隣に信頼できる人を作り、緊急時の助け合い体制を築くこと。また独身であるため将来設計(結婚や老後)が不透明。万一を考え、小規模企業共済で積立を開始。地域活動には積極参加し、「何かあったらお互い様」の関係を目指す。
ケース2:夫婦+幼児あり・40代
都会から地方へのIターン移住。小さな子どもがおり、教育や医療も気になる世代です。夫婦協力して自給生活を目指します。
- 土地・住居: 希望する地方都市近郊で古民家を購入(価格200万円)しリフォーム。敷地内に100坪ほどの菜園スペースあり。別途、車で10分の田園地帯に貸し農園500㎡を確保。市街地にも近いため上下水道・電気などインフラは整っている。
- インフラ: 住宅は築50年の木造で耐震補強と断熱改修に100万円投資。太陽光5kWを設置し売電もしながら光熱費ゼロ化を狙う。冬は薪ストーブ導入、薪は近隣林業者から原木を譲ってもらい自伐する。通信は在宅ワーク等もあるため光回線を引く。
- 作付: 家族3人分のコメ消費は年間約100kgと見込み、地元の認定農業者から田んぼ0.1haを借りて本格的に稲作挑戦。夫婦で農業研修プログラムにも参加して知識習得。畑では子供も食べやすいミニトマトや果樹(ブルーベリー、イチジク)などを育て、家族の楽しみとする。鶏は5羽飼って毎朝の卵を確保。
- 収支: 夫は自営でIT系の在宅仕事を継続(月5~8万円収入)、妻は農産物加工品(焼き菓子やジャム)を直売所に出荷して月2万円収入を目標。2人とも国民年金第1号で保険料免除申請せず全額納付。児童手当や子育て支援金を活用し、子供の教育費に積み立てる。自給により減らせた生活費分でトントンの経済を目指す。
- 時間配分: 夫は午前中在宅ワーク、午後農作業、妻は午前中子育てと家事、午後に交代で畑作業という形で分担。繁忙期は祖父母に子守を頼むなど柔軟に対応。子供は自然の中で走り回り、アトピーが改善するなど効果も(これは実例としてよく聞かれる)。
- 課題: 子供の病気や教育機会確保。幸い車で20分に総合病院、小学校も徒歩圏内。PTA活動や近所づきあいにも参加し、地域子育てネットワークに入る。夫婦とも慣れない農作業で腰痛など起こしがちなので、無理せず休養日を設定。行政の新規就農者研修や補助も2人で情報収集し、条件が合えば利用を検討。
ケース3:Uターン実家活用・50代
子供も独立し、地元に残る実家(農家)にUターンする夫婦の例です。親から受け継ぐ土地やノウハウを活かしつつ、セミリタイア的に自給自足へ移行します。
- 土地・住居: 実家は田舎の広い家で、田畑合わせて1ha以上所有。これを相続し、自分たちで管理開始。住宅は親が使っていたが空き家期間が長く、一部リフォーム(給湯設備更新やバリアフリー化)に50万円投入。
- インフラ: 元々水田用水や井戸があり水は豊富。上水道も来ているが、飲み水は井戸と湧水を活用。電気は既存のまま(屋根が茅葺きで太陽光困難)。代わりにマイクロ水力発電を検討(敷地内の用水路落差で200W程度発電見込み)。軽トラは親の代からの物を整備して継続使用。農機具類(耕耘機・ポンプなど)一式揃っている。
- 作付: 先代が作っていた米0.5haを引き継ぎ、まずは自家米+親戚用に年間300kg生産を目標。残りの田は休ませるかレンタル田んぼとして都市住民に貸し出す。畑はハウスが2棟残っており、有機野菜栽培に挑戦。出荷先はJAに拘らず、知人ネットワークで直接販売。梅や栗など古木の管理も復活させ、特産品加工(梅干し・渋皮煮など)にも着手。養蜂箱も父の遺品があるため、ニホンミツバチの捕獲を試みる。
- 収支: 50代夫婦は厚生年金を満期まで掛けていたので、60以降の年金見込み額があり完全無収入でも老後は安定。ただ、それまでの5~10年を農業収入で一部補いたい。米と野菜で年間50万円程度の売上、片方がパート勤め(月5万円程度)を数年継続して黒字運営を図る。親から受け継いだ農機等の維持費や修繕費もあるので、共済積立で備える。
- 時間配分: 親世代の知人が多く、地域行事や寄合の誘いが頻繁にある。以前は都会で忙殺されて地域関係が希薄だった分、この機会に積極参加。ただし当人たちも50代後半で体力が若者ほどないため、早朝と夕方メインの作業リズムで日中は無理をしない。週末は孫が遊びに来ることもあるので、そのときは農作業は休み家族サービスにあてる。
- 課題: 古い人間関係のしがらみや、地域役員が回ってくる負担が増えること。地元は楽しい面もあるが、プライバシーが少ない面もある。→ 自分のペースを守りつつ、周囲の期待にも適度に応えるバランスを取る。農業技術も自己流では限界があるので、JAや先輩農家のアドバイスを素直に受け入れ、最新技術にもアップデートする姿勢が必要。
以上3例、それぞれ事情は異なりますが「地に足の着いた計画」と「環境への適応」が共通の成功ポイントです。自分自身のケースに置き換えたとき、強みは何か、弱点はどこかを分析し、できれば家族や知人ともシミュレーションしてみてください。必ずや自分なりのベストプランが見えてくるはずです。
<a id="section11"></a>
11. よくある質問(FAQ)
Q: 退職して健康保険証が手元にない期間、病院にかかったらどうなるの?
A: 会社の健康保険を辞めると、資格喪失日の翌日から国民健康保険や任意継続に加入するまでの間は「無保険」状態になります。ただし多くの場合、手続きを速やかに行えば保険証が手元になくても遡って保障されます。例えば任意継続の申請を20日以内に行えば退職翌日にさかのぼって加入となり、その間の医療費は後日保険適用分が払い戻されます。国民健康保険も同様です(手続きが14日を過ぎても、未納期間の保険料を払えば適用されます)。万一手続き前に病院に行く場合は、一旦全額自費で支払い、後日保険加入後に領収書を持って役所で還付申請ができます。理想は無保険期間を作らないことですが、数日のズレであれば救済措置があるので落ち着いて対処しましょう。
Q: 国民年金を払う余裕がないとき、免除しておいて後から払うことはできる?
A: はい、可能です。国民年金保険料は申請により全額または一部が免除(または猶予)される制度があります。免除を受けた期間は将来の年金額には反映されませんが、10年以内であれば後から追納することができます。追納すればその期間も納付期間とみなされ、年金額も増えます(追納時には当初の保険料に加算額が付きます)。免除を受けておけば未納扱いと違って年金受給資格期間にはカウントされますし、障害年金等もカバーされます。したがって払えないときは免除申請を必ず行い、経済的に余裕ができたときに追納することを検討するとよいです。
Q: 「鶏を1~2羽飼うくらいなら許可もいらない」と聞いたけど本当?
A: 日本の法律では、飼う羽数にかかわらずニワトリは家畜伝染病予防法の対象動物です。ですから「許可」はそもそも不要ですが、飼養衛生管理基準を遵守する義務があります。また自治体によっては家禽飼育の届出を条例等で定めている場合もあります(特に都市近郊で環境悪化を防ぐ目的)。少数飼育だから何もしなくて良い、とはなりません。ただ、現実問題として趣味鶏程度で行政が積極的に指導に来ることは少ないです。近隣に迷惑をかけず、鶏が健康に過ごせるよう衛生管理していれば問題になるケースはまれでしょう。なお、鶏卵や食肉として販売する場合は別途食品営業許可(食鳥処理業など)が必要になる点には注意してください。
Q: 井戸水は毎年検査しないといけないの?
A: 法律上の義務ではありませんが、強く推奨されます。厚生労働省が定めた指針では、個人飲用井戸でも年1回の定期水質検査を行いましょうとされています。自治体によっては保健所で井戸水簡易検査(10項目程度)を低額で実施していますし、検査センターに依頼すれば50項目以上の精密検査も受けられます。費用は簡易検査で数千円、精密なら数万円です。特に小さな子供が飲む場合や、周囲に農薬を使う田畑がある場合などは定期検査が安心です。また検査結果に異常がなくても、井戸の周囲の蓋や筒に隙間ができていないか、動物の死骸が落ちていないか等、日常点検も忘れずに。もし水質に問題が見つかったら、浄水器設置や井戸浄化措置を取りましょう。
Q: 電気工事士などの資格は取っておいた方がいい?
A: 自分で太陽光発電設備を設置したり家庭の配線を触るつもりなら、第二種電気工事士の資格があると役立ちます。法律的にも、600V以下の一般用電気工作物の工事は有資格者でないと行えません。したがって資格なしで自家配線すると違法になる可能性があります。ただ、資格取得には勉強と試験合格が必要で、容易ではありません。現実的には、太陽光設備は購入時に工務店や業者に設置してもらい、増設や修理もお願いするのが安全でしょう。高圧ガス(プロパン)設備についても、資格者が定期点検しています。無資格で手を出すのは事故のもとなので、DIYの範囲とプロに任せる範囲を見極めましょう。もしキャリアチェンジとして田舎で電気工事店をやる気概があるなら、資格取得も視野に入るでしょうが、必須ではありません。
Q: 自家製の野菜や加工品をおすそ分けしたら、お礼にお金をもらった。これも確定申告するの?
A: ご近所へのおすそ分けに対する謝礼程度であれば、税務上はほぼ問題にならないでしょう。厳密に言えば、それも対価として受け取ったなら雑所得になり得ますが、金額が微々たるものなら申告しなくても実害はありません(所得税は1円単位まで課税ではありますが、少額だと基礎控除内に収まるでしょう)。ただし継続的に販売している場合との線引きは自覚しておく必要があります。好意のお礼なのか、実質的な売買なのかです。後者なら申告すべき収入になります。日常的な物々交換や地域内の助け合いは、都会の経済活動とは異なるグレーな部分があるものです。税務署もすべてを把握しているわけではありません。常識の範囲内で、社会通念上問題ない程度のお金のやり取りなら神経質になることはないでしょう。ただ、SNS等で販売を公言すると誰でも閲覧できるため、申告漏れを指摘される可能性は高まります。公に商売とするなら襟を正して確定申告する、そうでなければ相手の厚意に感謝して素直に受け取る、とメリハリをつけましょう。
Q: オフグリッド生活に憧れるけど、真冬や長梅雨でも本当にやっていける?
A: 正直なところ、完全なオフグリッド(外部エネルギーに一切頼らない生活)は日本の気候ではハードルが高いです。冬の太陽光不足や夏の極端な高温多湿など、自然は容赦なく、人力だけではしのぎにくい場面があります。したがって、「普段は極力自給だが非常時は無理せず頼る」くらいの柔軟さが現実的です。例えば冬場は電力消費の大きい暖房は薪ストーブに任せつつ、どうしてもの時は発電機や商用電力も使う。長雨で太陽光発電ができないときは、冷蔵庫の中身を減らし停電に備えつつ、夜間は電力網から電気を買うなど切り替える。水も枯渇したら給水支援に甘える。要は無理のないハイブリッドが長続きのコツです。災害でライフラインが寸断されても数日は自立できるくらいのオフグリッド力があれば十分とも言えます。憧れは大切ですが、絶対無菌主義ならぬ「絶対自給主義」にならず、自然とも社会とも調和する暮らしを目指しましょう。
Q: 将来また就職したくなったら、ブランクが不利にならない?
A: これは多くの人が不安に思う点です。自給自足で数年過ごした後、資金が尽きたり心境変化で再就職を希望することもあるでしょう。確かに職種によってはブランクはマイナスに見られる可能性があります。しかし最近は「スローライフ経験者歓迎」の地方企業や、農的暮らしのスキルを評価する風土も一部に出てきました。何より、自給自足で培った逞しさや創意工夫はどんな仕事にも活きます。履歴書には「自営農業」などと書けばブランクとはなりませんし、小規模でも事業収入を得て確定申告していれば個人事業主として扱えます。むしろ独立開業経験として評価されるかもしれません。仮に希望する業界がブランクに厳しい場合でも、真摯に学び直す覚悟を示せば道は開けるものです。一度きりの人生ですから、やりたいことに挑戦した経験はきっと糧になります。ブランクを恐れてチャンスを逃すより、挑戦して得たものを次に繋げる前向きさを持ちましょう。
以上、よくある疑問に答えてきました。他にも疑問点が出てきたら、本記事の「参考文献」を手がかりに一次情報を当たることをおすすめします。また先輩自給者のブログや書籍も参考になります。疑問を一つ一つ解決しながら、不安を潰して一歩踏み出してください。
付録
- 週間タスク表テンプレート: (例)月曜:鶏餌・堆肥撹拌、火曜:草刈り、…日曜:休養日、など曜日ごとに定型タスクを割り振り、反復作業を漏れなく管理。
- 装備チェックリスト: (例)農作業着、長靴、安全帽、刈払機用チップソー替刃、チェーンソー替刃&オイル、救急箱、常備薬、雨具、防寒着、発電機燃料、消火器 等。
- エネルギー計算ワークシート: 太陽光や蓄電池容量を見積もるためのExcelシート。消費電力リストに家電ごとのW数・使用時間を入力すると日負荷計が出る。地域の日射量係数を入力し必要パネル枚数を算出。蓄電希望日数とDoDから蓄電池容量も自動計算。
こうしたツールを活用し、計画と実践の精度を上げていきましょう。付録は自作して使いやすいよう改変して構いません。継続的な改善が自給生活をより楽しく、安定したものにしてくれます。
参考文献
- 農地転用許可制度の概要|農林水産省|2025年7月
- 伐採及び伐採後の造林の届出等の制度|林野庁|2022年4月
- 森林の土地の所有者届出制度|林野庁|2012年4月(改正2021年10月)
- ハザードマップポータルサイト|国土交通省 国土地理院|2023年3月
- 建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し|国土交通省|2024年10月
- 飲用井戸等衛生対策要領の実施について|厚生労働省|1987年1月(改正2019年10月)
- 浄化槽の維持管理について|神奈川県|2025年10月
- 太陽電池発電設備の設置手引き|経済産業省|2021年4月
- HACCP制度の施行について|厚生労働省|2021年6月
- 小規模事業者向けHACCP手引書|日本食品衛生協会|2020年6月
- 会社を退職したときの国民年金の手続き|日本年金機構|2023年2月
- 任意継続被保険者制度の案内|全国健康保険協会|2023年4月
- 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁|2023年6月
- 農業者のための特別加入制度|厚生労働省|2022年3月
- 小規模企業共済制度について|中小企業庁|2025年8月
- 平年値(1991~2020)初霜・初雪等|気象庁|2021年5月
- 空き家・空き地バンク総合情報|国土交通省|2025年6月
- JOIN移住支援情報|移住・交流推進機構|2025年7月
- 飼養衛生管理基準(家きん・非商用)|農林水産省|2025年9月
- 養蜂の届出制度と防疫対策|農林水産省|2025年4月
会社員をやめて始める「日本の自給自足」完全ガイド
会社勤めから離れ、日本で自給自足の暮らしを目指す人に向けた実践ガイドです。生活費の考え方から法的手続き、土地やインフラ整備、農作物の年間計画、収支管理、安全対策まで幅広く網羅し、初心者でも一歩ずつ進められるよう解説します。日本の制度や地域差に沿った最新情報に基づき、現実的で役立つノウハウをまとめました。 1. 自給自足のリアル:生活像・収入像・時間配分 自給自足生活では、現金収入は必要最低限に抑え、食料やエネルギーを自給することで生活費を減らす暮らしになります。生活費の内訳を見直し、住居費や食費、光熱費な ...
発達特性があっても『お金の使い方』は変えられる:今日からできる対策と日本の相談先
お金の管理が苦手でも大丈夫です。ADHDやASDといった神経発達症(発達障害)の特性によって、つい衝動買いや支払いの失念をしてしまう方でも、工夫と支援で金銭習慣は改善できます。本記事では今日から実践できる具体的対策12選と、日本国内の相談窓口・公的制度を網羅的に紹介します。一般的な情報提供であり、個別の助言には専門家のサポートも必要ですが、まずは本記事で正確な知識と再現性の高い手順を確認し、安心して一歩を踏み出しましょう。 要点サマリー ADHD傾向のある人は衝動買いや貯金の苦手さを抱えやすいことが研究で ...
オーバーツーリズム対策の最前線:国内外の制度・費用対効果・導入手順まで
観光地の賑わいと地域の暮らしの質をどう両立させるか。観光客が集中する「オーバーツーリズム」の問題は、世界各地で住民生活や旅行者体験への影響が顕在化しています。日本でも富士山や離島、都市の繁華街で混雑やマナー問題が深刻化し、自治体や事業者が対策に乗り出しています。本稿は価格(課金)や予約・人数制限、行為規制、交通整理、情報提供など多角的なアプローチによる解決策を、制度の根拠・費用・KPIまで含めて具体的に解説します。住民合意の得方から導入後の検証方法まで網羅し、明日から現場で使える実装ガイドを目指します。 ...
エボラ出血熱(EVD)最新ガイド:日本で注目される理由と実態【2025年版】
要約: エボラ出血熱(エボラウイルス病, EVD)は、致死率が平均約50%と非常に高い希少疾患です1。2025年9月にコンゴ民主共和国(DRC)で新たなエボラ流行(アウトブレイク)が発生し、日本でもニュースやSNSで関心が高まっています。エボラは主に患者や遺体の体液との直接接触で感染し、一般的な空気感染はしない点が重要です。現在、有効なワクチンや治療法が確立しているのはザイール株(EBOV)によるEVDのみで、他の株(スーダン株など)へのワクチン開発も進行中です。本記事では、エボラの基礎知識から最新動向、 ...
日本の水源地「外資買収」の実態:0.07%未満、法規制が守る
結論(要約) 外国資本による森林取得はごくわずか – 林野庁の最新調査(2025年公表)では、令和6年(2024年)に外国法人等が取得した森林面積は382haで全国私有林の0.003%に過ぎず、累計でも0.07%に留まっています。しかも水資源目的の開発事例は報告されていません。外国資本が日本の水源地を“買い占め”ているとの懸念はデータ上誇張と言えます。 土地を買っても水は自由にならない – 河川法により河川水や湧水の取水には事前に水利権許可が必要で、土地所有だけで勝手に水を使用できません。また多くの水源林 ...