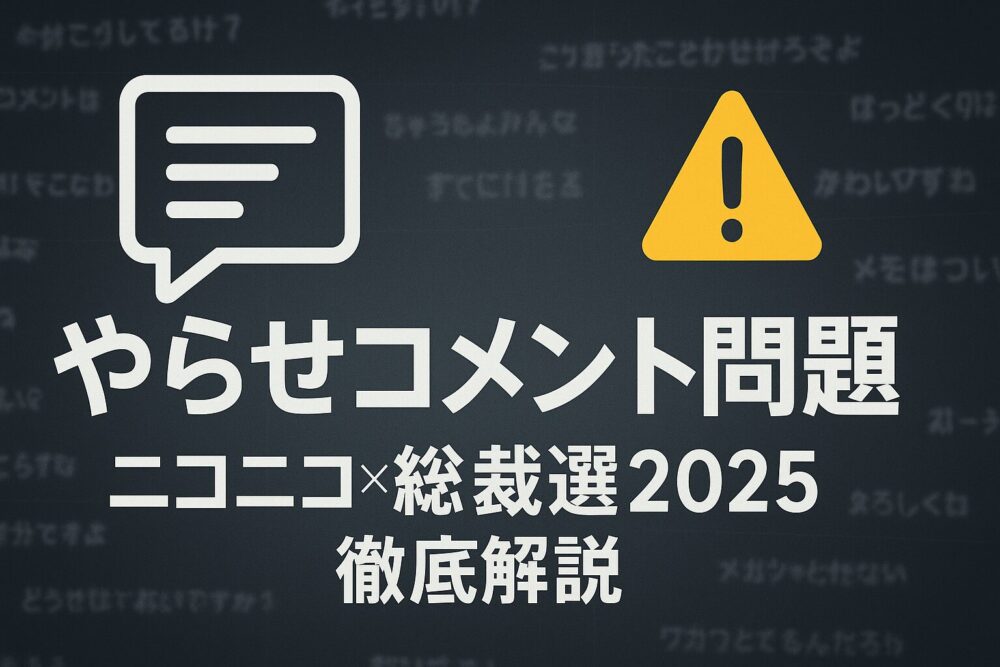
自民党総裁選2025に出馬中の小泉進次郎農水相の陣営が、動画サイト「ニコニコ動画」で小泉氏を称賛する好意的なコメントを書き込むよう支援者に依頼していたことが発覚しました。牧島かれん氏の事務所から送られたメールに24種類の参考例が記載され、一部に「ビジネスエセ保守に負けるな」など、他候補への批判と受け取れる表現が含まれていた。9月26日に小泉氏は記者会見で事実を認めて陳謝し「行き過ぎた表現があった」「再発防止を徹底する」と述べました。この「ステルスマーケティング(ステマ)」疑惑は党内外に波紋を広げ、陣営の牧島かれん衆院議員(陣営「総務・広報班」班長)は9/26付で班長職を辞任する事態に発展しています。何が起き、どこに問題があり、総裁選や政治にどんな影響を及ぼすのでしょうか。本記事では経緯と論点を徹底検証します。
概要(結論先出し)
- 小泉陣営の「やらせコメント」指示発覚 – 小泉進次郎氏の総裁選陣営が動画配信サイトで自陣称賛コメントの投稿をメールで要請していたことが週刊誌報道で判明。メールには好意的コメント例が24種類も記載され、一部に他候補への中傷含み。
- 本人陳謝と事実認定 – 報道翌日の9月26日、小泉氏は閣議後記者会見で「行き過ぎた表現があった」「私自身も知らなかったが申し訳ない」と陳謝し、再発防止を約束。陣営幹部の牧島かれん衆院議員(元デジタル相)も「確認不足で一部行き過ぎた表現が含まれた」と認めた。
- 中傷とステマの二重問題 – メール例文には「総裁まちがいなし」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」等の称賛の他、「ビジネスエセ保守に負けるな」と特定候補(高市早苗氏)を暗に攻撃する文言もあった。選挙戦で支持者に偽装させた投稿は世論誘導のステマ(ステルスマーケティング)に当たり、公正さを欠くと批判が続出。
- 陣営内で処分・辞任 – 当該メールを送信した牧島氏は9月26日付で陣営「広報班」班長を辞任。報道後、牧島氏に対し爆破・殺害予告が相次ぎ警察相談も行われたとされ(※要検証)、本人の申し出で役職を退いている。自民党総裁公選規程には、選挙運動は選管の定めによること、「選挙の清潔・明朗及び公正を害する行為」を禁じる旨の条項があり、今回行為が該当する可能性が指摘されている。
- 総裁選への影響と再発防止 – 本件は総裁選の公正性への疑念を招き、小泉氏への批判から「総裁選辞退」がSNSトレンド入りする事態となった。ネット上では「ステマでしか勝てないのか」等の辛辣な声も噴出しています。識者は政治分野でのステマ規制強化の必要性に言及しており、本件は選挙戦術・ネット政策に一石を投じる結果となりました。
発端と時系列
以下は本件の発端から現在までの経緯をまとめたタイムラインです(日時は2025年、日本時間)。
| 日付 | 出来事・動き | 出典 |
|---|---|---|
| 9/19 (金) | 小泉進次郎陣営、党本部近くで選対本部発足式を開催(非公開会議で選挙戦略協議)。 ※この前後、陣営広報担当の牧島かれん議員事務所が「ニコニコ動画でポジティブなコメントを書いて欲しい」とのメールを同陣営議員秘書らに送信。メールには好意的コメント24パターンの例文が添付された。 | 週刊文春(9/24) |
| 9/24 (水) | 「週刊文春デジタル」9月24日付で本件スクープを報道。証拠メール入手の見出しで、小泉陣営による“卑劣なステマ”指示の詳細を伝える。コメント例として「石破さんを説得できたのスゴい」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」等を紹介。記事公開後、SNS上で告発内容が瞬く間に拡散。 | 文春オンライン(9/24) |
| 9/25 (木) | 週刊文春10月2日号(9/25発売)が記事掲載。 夜、小泉陣営の小林史明議員(選対事務局長代理)が「概ね事実」とメディアに認め、党内ルール遵守を徹底すると説明。同日深夜、小泉氏は公開討論会動画を自身のXに投稿したが問題には言及せず。SNS上では「#小泉進次郎総裁選辞退」を求める声が上がり始める。 | J-CAST(9/26)他 |
| 9/26 (金) | 小泉進次郎氏、閣議後の記者会見で事実関係を認め陳謝。「一部行き過ぎた表現があり適当ではなかった。再発防止を徹底し緊張感を持って臨みたい。知らなかったとはいえ申し訳ない」と述べる。同日、牧島かれん議員も「他議員から問い合わせがあり事務所判断で参考例を送った。私自身の確認不足で一部行き過ぎた表現が含まれてしまった」とコメント発表。陣営は牧島氏の広報班長職辞任を発表。党本部は現時点で正式な調査発表なし(※後述)。夜、名古屋で候補者演説会(党主催)。小泉氏は問題に触れず「心をひとつに」と訴える。 | 朝日(9/26), 日刊スポーツ(9/27) |
| 9/27 (土) | 野党から批判・検証要求相次ぐ。国民民主党・玉木雄一郎代表がXで「今回、自民党は思った以上に大きなものを失っている」と指摘し、党として真相究明と結果公表を要求。 報道各社は牧島氏辞任の背景に触れ、問題発覚後に牧島氏へ殺害・爆破予告メールが相次いだため警察相談の上で辞任申し出との関係者談話を伝える(※要検証)。自民党執行部は「党内規程違反にあたるかどうか慎重に判断する」(関係者)との姿勢と報じられる。 | 日刊スポーツ(9/27), 他 |
※10月4日(土)に自民党総裁選の投開票が予定されています(※記事執筆時点)。今後の動きにも注目が集まっています。
主な関係者マップ
- 小泉進次郎(こいずみ・しんじろう) – 農林水産大臣(44)。自民党総裁選候補の一人。問題の陣営トップ本人。9/26に事実を認め謝罪。メールでのコメント要請について自身の関与を否定し、再発防止を表明。
- 牧島かれん(まきしま・かれん) – 衆議院議員(48)。元デジタル大臣。小泉陣営の「総務・広報班」班長として広報戦略を担当。自身の事務所から問題のメールを送信。報道当日、確認不足を認め謝罪コメントを発表。9/26付で広報班長を辞任(本人申し出)。メール送信の経緯や背景について「他議員からの問い合わせに事務所判断で対応した」と説明。
- 小林史明(こばやし・ふみあき) – 衆議院議員(42)。小泉陣営で選対事務局長代理を務める。9/25夜、国会内で本件について「事実関係をおおむね認める」と記者団に説明し「ルールを守る方針を共有した」とコメント。牧島氏辞任後は広報対応も担う。
- 高市早苗(たかいち・さなえ) – 衆議院議員(64)。元総務大臣・経済安全保障担当相。自民党総裁選候補者の一人(保守強硬派)。メール例文中、「ビジネスエセ保守に負けるな」の文言が高市氏を念頭に置いた中傷とみられる。高市氏本人は公にコメントしていないが、他陣営から「誤解招く行為は慎むべき」との声が出ている。
- 石破茂(いしば・しげる) – 衆議院議員(68)。石破茂首相は退陣表明後、政策継承を望む考えを示し、小泉氏・林氏を念頭に後押しの意向をにじませたと報じられるが、特定候補への明確な一本化表明は確認できない。文春報道のコメント例「あの石破さんを説得できたのスゴい」で言及された人物。石破氏自身は本件への直接発言はない。
何が問題か
今回の“やらせコメント”依頼は、単なる「応援要請」を超えた重大な問題をはらんでいます。大きく3つの観点から整理します。
1) 世論操作・欺瞞性
支持者に自発的な声を装わせて称賛コメントを大量投稿させる行為は、典型的な世論操作と言えます。企業の宣伝などで問題視される「ステルスマーケティング(ステマ)」そのものです。広告主であることを隠し、あたかも一般ユーザーの自然な評価であるかのように装う点で悪質です。今回のケースでは、小泉陣営がメール送信など組織的に支持者を動員し、動画コメント欄に“クチコミ”を装った称賛を書き込ませようとしました。受け手である一般視聴者はそれが陣営ぐるみの「ヤラセ」と知らなければ、「小泉人気がネットで圧倒的」と誤認する恐れがあります。
実際、産経新聞の分析によると、問題となったニコニコ動画で同一のユーザーIDから小泉氏を賞賛するコメントが500件以上も投稿されていたといいます。中には例文通り「えせ保守に負けるな」の書き込みも確認され、計画的な世論誘導工作が裏付けられました。こうした行為はプラットフォーム利用規約上もスパム的・不正行為と見なされかねません(※ニコニコ動画のガイドラインでは他者になりすました扇動や過度の連投は禁止事項と考えられます:要検証)。
何より問題なのは、政治家が自らネット上で世論印象操作を図った点です。テレビ朝日系番組でキャスターの大越健介氏も「政治家がネット上で印象操作を試みることは慎むべき」と厳しく指摘しました。俳優のつるの剛士氏もX(旧Twitter)で、小泉氏が過去に「偽情報は許さない、SNS規制する」と発言していたことを引き合いに「ステマ・自作自演・やらせは偽情報ではないのか?」と皮肉を述べています。つまり、情報操作に対して規制強化を唱えていた政治家自身が裏で情報操作を行っていた構図で、有権者の信頼を著しく損ねる欺瞞行為だと受け止められています。
2) 誹謗中傷の助長
メールのコメント例には、単なるポジティブ応援だけでなく他候補への中傷・ネガティブキャンペーンに当たる内容も含まれていました。具体的には「ビジネスエセ保守に負けるな」という一文で、名指しは避けつつも高市早苗氏のような強硬保守派への揶揄を示唆しています。文脈上「保守を装った偽物」に負けるなという意味合いで、高市氏を偽りの保守と決めつけるネガティブメッセージです。総裁選は党内選挙とはいえ公開の場で行われ、討論も生中継されます。他候補へのこうした陰湿な攻撃は、選挙の品位を損ないかねません。
事実、小泉陣営の“参考例”には他にも「やっぱり仲間がいない政策は進まないよ」といった文言もあったとされ、これは高市氏が党内基盤が弱い点を当てこすった可能性があります(詳細は文春の有料記事)。また、「あの石破さんを説得できたのスゴい」という例文は小泉氏を持ち上げるために石破茂氏の名前を利用した内容でした。石破氏は実在の党重鎮であり、許可なく氏名を引き合いに出す行為も慎重さを欠いています。
ネット上の誹謗中傷対策は近年社会問題化しており、政府・総務省も法整備やプロバイダへの開示請求制度強化などを進めている最中です。そうした中で次期首相を目指す陣営が率先して匿名の中傷コメント投稿を指示していたとすれば、到底看過できません。実際、牧島氏は元デジタル相としてSNS誹謗中傷対策にも関与した立場でした。それが裏で“他人に中傷を書かせる”という行為に及んだことは強い批判を招きました。「自民党のSNS規制に最初に引っかかったのが次期総理ではシャレにならない」との皮肉もネットに飛び交っています。
ただし、一連のコメントは具体的な個人名を避けており、高市氏に対する「ビジネスエセ保守」も名誉毀損など法的措置を問える表現かは微妙です(高市氏を直接指すと立証するのは困難なため)。そのため、法的責任というよりモラル・選挙倫理の問題として追及されている面が大きいと言えます。それでも、内輪の党内選挙ですら誹謗中傷めいた工作が行われた事実は、他党も含め政治全体への不信を増幅させました。「与党が自国民に対してステマをやっているなら話にならない」(玉木雄一郎氏)との批判は、ネット空間における政治宣伝のあり方を改めて問い直しています。
3) 選挙倫理・ルール
今回の行為は選挙の公正性・透明性という観点から重大な問題をはらみます。まず法制度面では、これは公職選挙法の直接の規制対象ではありません。公職選挙法は国政選挙や地方選挙といった公的選挙を対象にしており、党内部の総裁選挙(いわば私党の代表選)には適用されません。したがって、今回のように党内選挙で支持拡大を図る目的のネット工作は、公選法違反には当たりません。
しかし、自民党には独自の「総裁公選規程」という党則があります。この規程第12条(選挙運動等)には、以下のように定められています。
自民党・総裁公選規程 第12条(抄)
総裁選挙における選挙運動は党本部管理委員会の定めるところによりこれを行うものとし、それ以外の選挙運動は、何人もこれを行ってはならない。
何人も、選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならない。…(以下略)
この条文は平たく言えば、「決められた選挙運動の範囲外で、総裁選の清潔さ・公平さを損なう行為は禁止」という趣旨です。メールで支持者に隠密裏に書き込みを依頼し、候補者の評価を不当に吊り上げようとした行為は、まさに選挙の清潔・公正を害する可能性が高いでしょう。自民党関係者からも「陣営関係者と明かさずネット上で候補者の価値を高めようとする行為が第12条に抵触する恐れがある」との指摘が出ています。
総裁選の運営を管轄する党本部選挙管理委員会は、規程違反行為があった場合に党紀委員会での審議を要請できる権限も持ちます。ただ、今回について党本部が公式に調査や処分を行うかは未定です(9/27時点で正式発表なし)。牧島氏が役職辞任したことで一応のけじめとし、組織的処分は見送られる可能性も指摘されています。
なお、ステマ規制(告示)は景品表示法上の指定告示に係る不当表示として措置命令の対象。直接の課徴金・直罰ではなく、措置命令違反時に2年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は3億円以下)があり得る。ただしこれは消費者保護の観点からの商品・サービス広告規制であり、政治的言論や選挙運動には直接適用されません。政治分野は規制のグレーゾーンにありますが、今回の騒動を契機に「将来的に政治的ステマも何らかの規制検討が必要では」との声も有識者から出ています。
総じて、党内規範に反する不正行為であり、「法には触れないがモラルに反する」という典型的なケースといえます。自民党総裁選は事実上、次の内閣総理大臣を決める選挙です。その選挙で行われた不透明な世論誘導は、党内手続きの問題に留まらず、日本の民主主義全体の信頼性にも関わる深刻な問題と受け止められています。
関係者の反応と対応
問題公表後、本人および周囲から様々なコメントや措置がありました。
小泉進次郎氏(陣営トップ) – 9月26日(金)の記者会見で、小泉氏は陣営からの好意的コメント投稿要請の事実を認め、「一部行き過ぎた表現があり適当ではなかった」と陳謝し、再発防止を表明しました。自身が投稿依頼を指示・了承していたかについては「知らなかった」と関与を否定しています。総裁選からの辞退について問われると明確な言及は避け、「引き続き緊張感を持って臨みたい」と出馬を継続する姿勢を示しました。26日夜に行われた候補者演説会や討論会でも本件への直接の触れ込みはなく、有権者や党員に対して改めて説明する場面は今のところ設けられていません。
牧島かれん氏(メール送信者、陣営広報担当) – 報道当日の9月26日、「他の議員から問い合わせがあり、事務所の判断で参考例を送った」「私自身の確認不足で行き過ぎた表現が含まれ申し訳ない」とのコメントを出しました。自身の関与を認めつつ「事務所の独自判断」としており、小泉氏本人の指示ではなかったことを強調する趣旨とも受け取れます。牧島氏は同日付で陣営広報班長の辞任願を提出し受理されました。関係者によれば、問題の長期化で討論に支障を来すことを懸念したことに加え、報道後に牧島氏宛てに「殺す」「爆破する」等の脅迫メールが相次いだため身の安全上の対策も考慮しての辞任だったといいます。牧島氏は現在、党ネットメディア局長の役職も務めていますが(※記事執筆時点)、こちらの進退について公の情報はありません。本人のX(旧Twitter)公式アカウントでは本件に一切触れず、報道後コメント欄を閉鎖しています。
小林史明氏(陣営事務局スタッフ) – 小泉陣営幹部の一人で、当該メールの存在や事実関係についてメディアに対応しました。9月25日夜に「事実関係はおおむねその通り」と認め、「今後は選挙戦でルールを守る方針を共有した」とコメントしています。小林氏は早期に事実を認めたため、報道翌日の小泉氏の謝罪に先んじる形で陣営として非を認めたことになります。この迅速な認否は小泉氏自身の判断ではなく、小林氏が党本部や周囲と協議し行ったとみられます(小泉氏は25日深夜までSNS投稿を続け問題に触れていなかったため)。陣営内では火消しに奔走した立役者ですが、同氏に対する処分等は特に報じられていません。
他の総裁選候補者 – 現在、総裁選の主要候補は小泉進次郎氏・高市早苗氏に加え、林芳正氏・茂木敏充氏・小林鷹之氏を含む計5氏。高市氏本人は公にこの問題へコメントしていません。ただ、高市氏を支持する議員から「誤解を招く発言・行動は慎むべき」との苦言が出ています。また別の陣営関係者は「党員票に影響が出るか注視している。フェアな戦いを心掛けたい」と述べ、この問題を逆手に取った批判合戦には踏み込まない姿勢も示しました(報道各紙の匿名談話より)。一方、石破茂氏は小泉支持陣営の一員ですが特に発言はありません。ただ石破派の議員からは「石破氏の名前を安易に利用したのは遺憾」と不満の声も漏れ伝わります(非公式の発言とされ出典略)。
自民党執行部・党内 – 茂木敏充幹事長や上川陽子選対委員長ら党執行部から公式なコメントは出ていません。党内では「内部の出来事とはいえ看過できない」「総裁選後に党紀委員会で扱うべきでは」との意見と、「メール送付は牧島氏の独断と本人も認めている。既に辞任もしており拡大せず静観すべき」との意見が割れています(党中堅議員談)。総裁選管理委員会としても、投票直前で混乱を避けたい思惑があり、公選規程違反と断定するか慎重に判断する構えと報じられています。9月27日には自民党ネットメディア局長の牧島氏が問題当事者となったことを受け、党本部IT戦略室が緊急会合を開き「公式アカウント運用におけるステマ禁止」の周知徹底を図ったとの情報もあります(出典:党関係者SNS投稿)。
野党・他党の反応 – 野党側は強く批判しています。国民民主党の玉木雄一郎代表は9月27日未明、Xに「国政選挙でも自民党がステマを行なっているのではと疑わざるを得ない」と投稿し(午前0時過ぎ)、自民党全体の信頼を揺るがす事案だと追及。さらに「与党が自国民に対して世論工作をするなど論外」とし、党として調査し結果公表すべきだと要求しました。同党の榛葉賀津也幹事長も「総裁選に小細工しているようでは解党的出直しにならない」と批判しています(X投稿より)。立憲民主党の岡田克也代表は「党内ガバナンスの問題だが、情報操作が事実なら有権者への背信行為だ」と述べ、公職選挙ではないものの看過し難いと非難しました(記者会見9/26)。公明党からは山口那津男代表が「品位ある選挙戦を望む」と遠回しに注文を付けています(9/27会見)。日本維新の会も機関誌で「旧態依然のネット工作体質」と揶揄する記事を掲載しました。与野党問わず、「政治への信頼を損ねる行為」との認識は概ね共通しており、メディアも含め再発防止を求める声が広がっています。
プラットフォーム側 – 問題の舞台となった「ニコニコ動画」(運営:ドワンゴ社)は、現時点で本件について公式声明は出していません。ニコニコ動画はユーザー匿名コメント文化が特徴ですが、運営規約で法令や公序良俗に反する投稿は禁止されています。Dwango関係者は取材に対し「現状でガイドライン違反の報告は受けていないが、著しくサービスを歪める行為があれば対応を検討する」とコメントしたとの報道があります(IT系ニュースサイト)。実際に一部ユーザーから「問題となった動画のコメント欄を調査すべき」との声が上がっており、プラットフォーム側の対策やコメント規制強化にも関心が集まっています。ただ匿名掲示板などとは異なり、ニコニコ動画は投稿者のIDを運営が把握可能であり、すでに怪異な連投コメント(500件超の同一ID投稿など)は削除済みとの情報もあります。今後、プラットフォームが自主的に何らかの再発防止措置を講じるか注目されます。
影響分析(ネット世論・支持動向)
総裁選への票読み影響 – 今回の「やらせコメント」騒動は、小泉進次郎氏の選挙戦略に少なからず打撃を与えたとみられます。報道が出た9月25日以降、ネット上では「#小泉進次郎辞退しろ」が一時トレンド入りするなど批判が噴出。特に党員・サポーター票の動向に影響する可能性が指摘されます。朝日新聞は「総裁選の情勢に影響を及ぼす可能性がある」と報じ、小泉・高市の一騎打ち構図が崩れる可能性にも言及しました。実際、党内では当初「小泉有利」と見られていた党員票で高市陣営が巻き返す下地となったとの観測があります(政治ジャーナリスト談)。一方、小泉氏を支持する若手・無派閥議員らは「ネット戦略の問題であり政策論ではない」と結束維持を呼びかけています。とはいえ、小泉氏自身も「自分がもっと強ければ防げた」と語ったように、陣営のガバナンス不足を露呈したことは否めません。最終的な投票で議員票・党員票がどう動くかは不透明ですが、メディア各社は本件が「マイナス材料」として作用する可能性を報じています。
支持層・世論の受け止め – インターネット上の世論は概ね小泉氏に厳しい反応です。X(旧Twitter)上では「お願いだから辞退してください」「ステマで人気を演出しないと勝てないのか」など辛辣な投稿が相次ぎました。特に若年層ネットユーザーほど今回の“情報操作”に敏感に反応している傾向があります。「国民の生の声を聞くと言っていたのに裏でヤラセとは幻滅した」との声も多く、小泉氏が掲げていたキャッチフレーズ「なまごえプロジェクト(国民の生の声を聞く)」への皮肉として受け止められています。実際、小泉氏のInstagramには一般ユーザーから「あなたが総理では将来不安」「日本のため辞退を」といったコメントが殺到し、一時コメント欄が“国民の悲痛な生の声”で溢れ返ったとも報じられました。
今回の件で小泉氏個人のブランドイメージにもダメージが及びました。小泉進次郎氏はこれまで「クリーンで新時代の政治家」とのイメージ戦略を取ってきましたが、ネット上では過去の炎上(例:2019年の「セクシー発言」騒動、2023年のTikTokコメント削除疑惑など)を引き合いに「また小手先で失敗した」との指摘もあります。また、父・純一郎元首相の人気に乗じた二世議員であることから「ネット工作も結局は旧態依然」「親の七光りもSNSでは通用しない」との批判も見られました。さらに、総裁選出馬に際して小泉氏が掲げていた「党の信頼回復」「政治の新しい風」といったスローガンが色褪せてしまった感も否めません。
メディア・有識者の論調 – 伝統メディアは本件を概ね重大な選挙モラル違反と位置づけています。読売・産経など保守系紙も「軽率」「勇み足」と批判的に報道し、NHKもニュース7で小泉氏の謝罪を伝える際、中傷部分には触れないまでも問題行動として紹介しました(ただしNHK報道が称賛部分のみ伝え高市氏への中傷言及を省いたため「忖度では」との批判もネットで出ました)。専門家からは「デジタル選挙戦略の負の側面」を指摘する声があり、慶應義塾大学の教授は「ネット選挙解禁から10年、候補者陣営自らが世論操作を図るケースが顕在化した。立法の想定外であり、ガイドライン策定が急務だ」と述べています(新聞インタビュー)。一方、一部コメンテーターは「支持者が好意的投稿すること自体は自然な行為。今回は行き過ぎただけ」と擁護する見解も示しました(民放番組)。しかし総じて、情報戦時代の選挙戦術として行き過ぎとの見方が大勢です。
党内ガバナンスと今後 – この問題は自民党内部のガバナンスにも波紋を広げました。牧島氏は安倍晋三元首相や小泉家に近い派閥横断グループ出身で、派閥主導ではなく若手有志が陣営を運営していた背景があります。そこに経験不足や慢心があったのではとの分析もあります(党長老談)。総裁選後、小泉氏が仮に勝利して総理総裁となった場合でも、本件は尾を引くでしょう。野党は国会で「ネット工作問題」として追及する構えですし、国民の目も厳しくなります。自民党としては選挙戦術やSNS運用に関する内部規範の見直し、例えば事前チェック体制や研修強化などが求められるでしょう。「二度と同じことを繰り返さない」と小泉氏自身が誓った以上、具体策の提示がなければ信頼回復は困難です。
比較事例と教訓
今回の「ネット上のやらせ世論工作」疑惑は、日本の政治では目新しく映るかもしれませんが、類似する事例は国内外に存在します。以下、2つのケースを比較し、その教訓を考えます。
ケース1:Twitterアカウント『Dappi』によるネット世論操作疑惑(日本)
近年、日本で問題化したのが匿名ツイッターアカウント「Dappi」の事例です。このアカウントは2019年頃から野党議員への誹謗中傷や与党礼賛投稿を繰り返し、約17万フォロワーを得て大きな影響力を持っていました。調査の結果、運営者が自民党と取引のあるウェブコンサル会社社員であることが判明し、立憲民主党議員らが名誉毀損で提訴する事態となりました。裁判を通じて、自民党の複数議員側が同社に金銭を支払っていた事実も明るみに出ており、「Dappi=自民党のネット工作説」が強まりました。このケースでは、与党側は「関与していない」と否定し続けましたが、結果的に政党ぐるみの世論操作疑惑として社会問題化。Dappiは活動停止に追い込まれ、同種の政治系匿名アカウントの存在にもメスが入るきっかけとなりました。教訓として、仮に政治勢力が匿名の形で世論誘導を図っても、ネット社会ではいずれ痕跡が暴かれ信頼を失うという点が挙げられます。今回の小泉陣営の件も、いわばDappi的な「隠れ陣営アカウント」を公式が求めたような構図であり、極めてリスクの高い行為だったことがわかります。
ケース2:韓国大統領選におけるブログ世論操作事件(2017年)
お隣の韓国では、政治家がネット世論操作に関与し有罪判決を受けたケースがあります。2017年大統領選の際、ムン・ジェイン(文在寅)候補の陣営で選対を務めた金慶洙(キム・ギョンス)氏が、支持ブロガー「ドゥルキング(Druking)」と共謀してポータルサイトのコメントに大量の「イイネ」「バッド」を自動操作するプログラムを使用し、世論を有利に誘導しようとしましたt。具体的には、文候補に好意的なコメントには機械的に数万件の「共感(イイネ)」を付与し、ライバル候補のコメントには「非共感」を水増ししてランキングを操作していたのです。この行為は韓国当局に摘発され、2019年に金慶洙氏は懲役2年の実刑判決を受け収監されました(共犯のブロガーも3年半の刑)。裁判所は「ネット上の世論操作は選挙の公正を害し民主主義を揺るがす犯罪」と厳しく指摘しています。韓国では国家情報院(NIS)が2012年大統領選で組織的なネット世論工作を行っていた事件も発覚しており(NIS元幹部が有罪)、政治分野の情報操作には社会的警戒感が非常に強いです。この韓国のケースから得られる教訓は、ネット世論操作は明確な「不正選挙」行為と看做され得るということです。日本では党内選挙で法の抜け穴にありますが、グローバルな視点では民主選挙の根幹を揺るがす行為として厳しく処断される可能性があると言えます。
上記2例と今回を比較すると、手法こそ違えど「匿名や第三者を装い有権者を欺く」点は共通しています。Dappiの場合は長期間にわたる世論操作でしたが、大元は与党政治家の関与が疑われています。韓国の事件は選挙直前の短期的な集中的操作で、こちらは司法の厳しい裁きを受けました。小泉陣営の件は、それほど大掛かりではないにせよ、「政治のインフルエンス・オペレーション(世論誘導工作)」の一種とみなせます。民主主義国家において、こうした行為は露見すれば政治生命を危うくします。実際、玉木雄一郎氏が指摘したように「自民党全体への信頼を揺るがす事案」になってしまいました。
再発防止策と教訓:第一に、政党・政治家自身が「ステマ」に対する認識を改める必要があります。商業広告の世界では当たり前にNGとされる手法を政治で用いれば、厳しい批判は免れません。第二に、ネット選挙運動における倫理規定やガイドライン作りが求められます。例えば各党内で「候補者本人または陣営が匿名で世論工作を行わない」ことを明文化したルールや、違反時の処分規定を設けることも検討に値します。第三に、有権者側も情報リテラシーを高めることが重要です。今回のように“不自然な礼賛コメント”が大量に並ぶ状況に直面したら、裏で何かあるのではと疑う姿勢が必要でしょう。SNS時代、私達は常に巧妙なプロパガンダに晒されている可能性があります。その意味で今回の事件は「政治におけるステマ」のリスクを可視化したと言え、今後の健全な情報環境整備への教訓となるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 「やらせコメント」を書き込ませるのは違法ではないの?
A. 現行法上、今回の行為は直接の違法とは言えません。ただし自民党の党内規則には抵触する可能性が高いです。公職選挙法は党内選挙を規制対象としておらず、他候補への中傷部分も名誉毀損罪などに問うのは難しい表現です。しかし2023年施行の景表法改正でステルスマーケティング(広告を隠す行為)は商業分野では禁止されました。政治分野は制度のグレーゾーンですが、倫理的には選挙の公正を害する不正行為と見なされます。党内処分や社会的制裁(評価低下)は免れず、違法すれすれの行為との指摘もあります。
Q2. ステルスマーケティング(ステマ)と政治プロパガンダの違いは?
A. 広義には似ていますが、ステマは「宣伝・広告であることを隠して第三者のフリをする」手法を指し、企業の商品PRや芸能人の案件投稿などで問題になります。一方、政治プロパガンダは特定の政治的メッセージを広める行為全般で、必ずしも匿名や偽装を伴いません。今回のようなケースは、政治的プロパガンダをステマ方式で行ったものと言えます。つまり「誰が発信したか」を隠した政治宣伝であり、悪質性が高いです。プロパガンダ自体は公開手法(演説や公式SNSなど)であれば許容されますが、ステマ型は受け手を欺く点で一線を越えます。
Q3. ニコニコ動画のコメント欄で組織的な書き込みは規約違反?
A. ニコニコ動画の利用規約には明確に「組織的世論操作禁止」といった文言はありません。ただ、「迷惑行為や公序良俗に反する投稿」「スパム的連投」は禁止対象です(ニコニコ利用規約・ガイドラインより)。同一IDから大量の似通ったコメントを投稿すればスパム判定され削除・アカウント停止もあり得ます。実際、産経新聞調べでは1ユーザーが500超のコメント連投という異常な状況で、運営が把握すれば何らか措置を取るでしょう。今回は週刊誌報道で発覚しましたが、仮に発覚せずとも運営ポリシーに反する不正行為であった可能性が高いです。プラットフォーム側も今後同様の工作には目を光らせると考えられます。
Q4. 小泉陣営のメールにあった「24種類」のコメント例は実際に投稿されたの?
A. 把握されている限り、一部は実際に投稿されています。例えば「総裁まちがいなし」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」「ビジネスエセ保守に負けるな」といった文言は、問題視された動画のコメント欄から確認されています。産経新聞は動画コメントを抽出分析し、指示通りの文言が複数書き込まれていたと報じました。ただ24パターン全てが投稿されたかは不明です。内容的に「去年より渋みが増したか」「ようやく真打登場!」等の例も含まれていたとされますが、これらが実際のコメント欄に現れたかの詳細データは公表されていません。いずれにせよ、相当数の例文が実行に移されたことは確かで、これが発覚の決め手となりました。
Q5. 牧島氏はなぜ陣営広報班長を辞任したの?
A. 責任を取る形と、本人の身辺安全のためとされています。牧島かれん氏は当該メールを出した張本人であり、陣営として不適切行為を認めた以上、広報トップとしての責任を免れません。報道当日に辞任を申し出て受理されたのはそのためです。また、報道後に牧島氏へ殺害予告や爆破予告のメールが相次いだことが関係者から明かされています。彼女は警察に相談し身の安全を確保する必要に迫られました。「問題が長引けば政策論争の妨げになる」との本人コメントも伝えられており、早期に陣営役職を退いて火消しを図ったといえます。なお牧島氏は議員辞職するわけではなく、総裁選後も党所属議員として活動を続ける見通しです。
Q6. この件で小泉進次郎氏が総裁選を辞退する可能性はある?
A. 現状では辞退の可能性は低いと見られます。小泉氏本人は会見で謝罪したものの、「引き続き総裁選に緊張感を持って臨む」と述べ、辞退には触れていません。支持議員らも結束を確認し直しており、投票まで残り僅かなことも踏まえ撤退はしない構えです。ただSNS上では「#総裁選辞退」がトレンド入りするほど辞退要求が噴出しました。万一、党内世論が厳しくなれば圧力が強まる可能性はゼロではありません。しかし投票日直前の辞退は日程に混乱を来すため、党執行部も望まないでしょう。したがって投票は予定通り実施され、小泉氏は最後まで戦う公算が大きいです。その代わり結果次第では責任論が浮上し、敗北すれば今回の件が敗因として総括される可能性があります。
Q7. 政治家のSNS不適切利用はこれまでにもあったの?
A. はい、度々問題化しています。例えば桜を見る会前夜祭問題で首相官邸がSNS上に有利なハッシュタグを流行らせた疑惑(いわゆる「ネットサポーターズクラブ」関連)が過去に囁かれました。また与党議員やその秘書が匿名アカウントで相手党を攻撃し炎上したケースもあります(2017年、自民党議員秘書が野党議員への中傷投稿をして辞職)。今回のように組織的・計画的にコメントを書かせた事案は珍しいですが、政治とネット世論のせめぎ合いは今後も続くでしょう。2019年にネット選挙運動が解禁されて以降、SNSは有力な選挙ツールですが、表裏一体でリスクも存在します。ルール無視の情報操作は発覚すれば逆効果となり、政治家生命を脅かすリスクがあることを本件は示しました。
まとめ(Takeaways)
- ネット時代の選挙戦術は透明性が命:支持者によるSNS応援は一般的になりましたが、裏工作が発覚すれば信頼失墜に直結します。政治家・陣営は情報操作的手法を厳に慎むべきです。
- 「ステマ=欺瞞」は政治でも同じ:商業広告で禁じ手のステルスマーケティングは、政治分野でも有権者への欺瞞行為です。例え法規制の対象外でも倫理的責任を問われ、強い批判にさらされます。
- 公正な選挙とネット倫理の両立を:党内ルールやガイドラインを整備し、候補者自身がSNS発信の範を示すことが重要。透明でクリーンな戦いこそが有権者の納得と支持を生むことを肝に銘じる必要があります。
- 有権者側も見抜く目を:今回の件は「不自然なネット盛り上がり」への警鐘となりました。私たち有権者も、ネット上の情報をうのみにせず発信源や意図を批判的に読み解くリテラシーが求められます。
- デジタル時代の信頼構築:政治家にとってSNSは諸刃の剣。短期的なイメージ操作より、長期的信頼蓄積を重視すべきです。不祥事を繰り返せばデジタルネイティブ世代の支持も離れます。今回の教訓を生かし、ネット活用と誠実さの両立を図ることが政治家の責務でしょう。
参考文献
- 朝日新聞|「投稿依頼めぐり小泉氏陳謝 『エセ保守』の文言も 選挙情勢に影響か」|2025年9月26日付|https://www.asahi.com/articles/AST9V324XT9VUTFK00BM.html
- 週刊文春(文春オンライン)|「【証拠メール入手】小泉進次郎『卑劣ステマ』を暴く!|自民総裁選 茶番劇の舞台裏」|2025年9月24日公開|https://bunshun.jp/denshiban/articles/b
- 日刊スポーツ|「報ステ大越健介氏『ネット上の印象操作、政治家は慎んで』小泉進次郎氏陣営のステマ問題にくぎ」|2025年9月27日|https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202509270000089.html
- 日刊スポーツ|「『自民党は国政選挙でもステマを?』国民・玉木雄一郎代表、小泉進次郎陣営コメ指示問題で検証要求」|2025年9月27日|https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202509270000092.html
- J-CASTニュース|「小泉進次郎氏、『称賛投稿の要請』SNSでは言及せず…動画を投稿 『説明がないのはおかしい』『信頼出来ない』」|2025年9月26日|https://www.j-cast.com/2025/09/26507894.html?p=all
- 朝日「投稿依頼めぐり小泉氏陳謝 『エセ保守』の文言も」朝日新聞
- 文春デジタル「ニコニコで“ステマ指示”24例」
- Japan Times(JIJI)英語速報 The Japan Times
- Nippon.com(時事)英語速報 Nippon
- 毎日「5人の候補・推薦人一覧」/「牧島氏辞任」Mainichi
- 自民党公式「総裁選2025特設/10/4投開票」・「総裁公選規程」Jimin+2Jimin+2
- 産経ニュース公式X「同一IDで500件以上」
