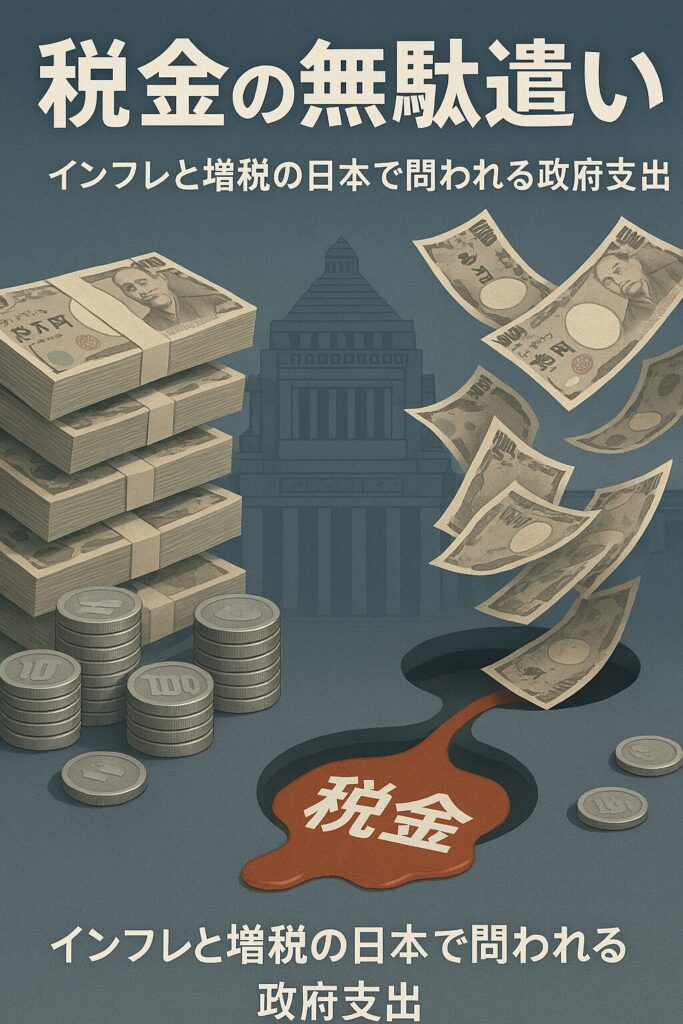
物価高と増税で浮き彫りになる「税金の無駄遣い」
日本では近年、エネルギー価格や円安の影響もあってインフレ率が上昇し、生活必需品の値上げが相次いでいます。それに加え、社会保障費や防衛費の財源確保のために増税が検討・実施され、国民の負担は増す一方です。家計が苦しくなる中、「果たして税金は有効に使われているのか」という視線で政府支出の在り方がこれまで以上に厳しく問われています。実際、会計検査院(国の監査機関)が公表した令和4年度(2022年度)の決算検査報告でも、344件・約580億円もの不適切支出が指摘されました。中でも新型コロナ対策交付金で調達したマスクや防護服が一度も使われずに在庫となり、約112億円の税金が無駄になっていたことなどが判明しています。こうした指摘は氷山の一角に過ぎず、各方面で「不要」「非効率」「中抜き」と批判される事業が存在しています。本稿では、国民負担が増える経済状況下で問題視されている政府支出の具体例を挙げ、その費用対効果や構造上の問題点、政府監査や世論の動きを検証します。
不要と指摘される主な公共事業
無駄遣いの代表例としてしばしば俎上に載るのが、大規模な公共事業です。日本では高度成長期以降、経済対策や地方振興の名目で数多くの公共事業が実施されてきましたが、中には時代にそぐわない不要不急な計画や、費用が肥大化したまま見直されないプロジェクトもあります。ここでは、最近とくに議論の的となっている二つの事例――明治神宮外苑の再開発と米軍普天間基地の辺野古移設――を見てみます。
明治神宮外苑再開発:歴史的緑地の商業化に批判
東京の明治神宮外苑は、100年の歴史を持つイチョウ並木やスポーツ施設で知られる都心の貴重な緑地です。しかし現在、この外苑エリアで大規模な再開発計画が進行中で、樹齢100年級の樹木を含む数百本規模の伐採や高層ビル・ホテル建設を伴う計画内容に対し、市民や有識者から「本当に必要な事業なのか」と疑問の声が上がっています。開発を主導するのは土地所有者である宗教法人明治神宮と大手デベロッパーの三井不動産ですが、東京都も都市計画の変更などで関与しており、公共性の高い歴史的環境を営利目的で改変することへの批判が渦巻いています。
この計画では当初、高さ50メートル超のビル建設や神宮球場の建て替えに伴い743本もの樹木を伐採する計画と報じられました。しかし国内外からの反対運動(作曲家・坂本龍一氏やユネスコ関連団体ICOMOSの提言など)の高まりを受けて、東京都は2023年に事業者へ計画見直しを要請。伐採予定の樹木を619本に削減し、新球場の配置をイチョウ並木から離すなどの修正案が示されています。とはいえ依然600本以上の木が失われる見通しであり、2024年10月にはついに樹木の伐採工事が開始されました。計画完了は2036年と長期にわたる予定で、環境破壊に加え工事期間中の安全面や景観悪化も懸念されています。
もう一つ問題視されているのが、プロセスの不透明さです。再開発計画は東京都が正式提案を受ける以前から事業者と非公式な協議が重ねられていたとされますが、都は「協議記録がなく、いつ把握したか定かでない」と説明し、住民説明会では「そんなわけないだろう」と怒号が飛ぶ一幕もありました。行政が経緯を記録していないという不可解な対応に、住民は強い不信感を抱えています。こうした経緯から、神宮外苑再開発は「不要不急で公共性に欠ける開発」かつ「進め方も不誠実」として、透明性・説明責任の欠如を象徴する事例と指摘されています。
辺野古新基地建設:膨れ上がる費用と見えない完成
もう一つの典型例が、沖縄の米軍基地移設計画です。老朽化・危険性が指摘される普天間飛行場の移設先として、名護市辺野古沿岸部に新基地を建設する計画が進められています。しかし、地元沖縄県や市民の強い反対運動もあり、工事は大幅に遅延、事業費も当初見込みを大きく超えて膨張しています。
政府は当初、辺野古新基地建設に約3,500億円の費用を見込んでいましたが、2019年に軟弱地盤の存在が判明すると、必要な改良工事のため約9,300億円へと試算を引き上げました。しかしこの9,300億円という試算でさえ楽観的だった可能性が高まっています。2024年末時点で埋め立て工事の進捗率はわずか16%程度(計画全体の埋め立て土砂の約17%)に留まる一方、予算の約8割を消化済みという状況が明らかになりました。防衛省は2025年度末までに約7,543億円を支出する計画で、これは試算額の81%に相当しますが、肝心の工事進捗はとても8割には達しません。野党議員から「このままでは総事業費が1兆2千億円規模に膨らむ」と追及されたのに対し、防衛相も「今後、費用想定の変更があり得る」と費用超過の可能性を認めました。にもかかわらず、現時点で正式な総額見直しは示されておらず、政府は真の事業費を公表していないのが実情です。
費用面だけでなく、完成までの見通しが立たない点も問題です。軟弱地盤改良の難工事(7万本以上の砂杭打設)には未知のリスクが伴い、県の埋め立て承認撤回を巡る法廷闘争も続いています。「2030年代半ばまで完成しない」との見方や、「技術的に実現困難」として計画中止を求める声も根強いです。辺野古新基地は巨額の税金投入にもかかわらず進捗がわずかで、住民合意も得られないまま迷走する典型例となっています。
このように公共事業の領域では、環境や地域社会への影響に見合わない不要不急のプロジェクトや、計画が杜撰で費用対効果が著しく低下しているケースが散見されます。神宮外苑や辺野古の例は、とりわけその傾向が顕著であり、インフレと財政難の時代に「本当に続けるべきなのか」という根源的な問いを投げかけています。
科学技術・環境分野の巨額プロジェクトと費用対効果
公共事業以外にも、国家主導の大型プロジェクトで費用対効果の疑問視されるものがあります。とりわけ科学技術やエネルギー関連の一部事業では、莫大な予算を投じたにもかかわらず成果が乏しく、“失敗事業”と評されるケースがありました。その代表格として、日本の原子力政策に絡む**高速増殖炉「もんじゅ」と核燃料サイクル施設「六ヶ所再処理工場」**の例を取り上げます。
高速増殖炉もんじゅ:1兆円投じて発電実績わずか
高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市)は、日本が「夢の原子炉」として1980年代から開発を進めてきた実験炉です。核燃料サイクル(使用済み核燃料からプルトニウムを取り出し、新たな燃料を生み出す循環)の中核を担う技術として期待され、1994年に初臨界に達しました。しかし、1995年のナトリウム漏れ事故とその後の対応失敗による長期停止、2010年にも運転再開直後のトラブル発生と度重なる不祥事により、稼働日数は極めて限られました。実際、稼働から20年で発電できたのはわずか1時間程度とも言われ、ほとんど成果を出せないまま計画は行き詰まりました。
それにもかかわらず維持費はかさみ続け、2010年末時点で累計1兆円超(約1兆800億円)もの予算が投じられていました。最終的に政府は2016年12月にもんじゅの廃炉を正式決定し、長期に及ぶ「失敗の総決算」を迎えます。当然、廃炉にも莫大な費用がかかり、少なくとも3750億円以上の追加支出が見込まれています。つまり兆円規模の投資がほぼ無駄になった計算で、日本の原子力技術政策に大きな損失と教訓を残しました。
この決定に際し、地元福井県知事は「唐突な方針転換は政府への不信感を招く」と抗議しましたが、国内外の専門家や世論の多くは「高速増殖炉の実用化は現実的でない」とみなしており、与党内からも「核燃料サイクルという不可能な夢は終わりにすべきだ」との声が上がったほどです。もんじゅの失敗は、計画段階での見通し甘さやリスク管理の不足、そして政策継続の判断が遅れた結果として、巨額の国家予算を浪費した典型例となりました。
核燃料サイクルと六ヶ所再処理工場:終わりなき巨費投入
もんじゅと並ぶ核燃料サイクル政策のもう一つの柱が、青森県六ヶ所村に建設中の六ヶ所再処理工場です。こちらは使用済み核燃料からウラン・プルトニウムを化学的に分離する施設で、1993年に着工しました。当初は1997年の完成を目指していましたが、度重なる設備トラブルや安全審査の強化などで完成時期が幾度も延期され、2020年代半ばの現在に至っても本格稼働に至っていません。
遅延に伴い建設費も膨張の一途を辿っています。建設当初の予算見積もりは約7600億円(※報道による試算)でしたが、度重なる工事追加により2020年時点で約2兆2,000億円を費やし、さらに安全対策工事に7,000億円を追加投入する計画となっています。合計すると約2兆9,000億円(約3兆円)もの巨費が投じられる見通しで、完成までに投入される総額は当初想定の数倍に達します。まさに「際限なきコスト増」です。
巨額投資にもかかわらず、核燃料サイクル政策そのものの実現性にも疑問符が付いています。日本政府は、福島第一原発事故後も核燃料サイクル推進の旗を下ろしていませんが、肝心の再処理工場が動かず政策は事実上破綻状態との指摘もあります。実際、国内の原発は使用済み燃料の貯蔵容量が逼迫しつつあるものの、再処理工場が動かなければ行き場のない核燃料が増える一方です。それでもなお国は方針転換せず工事を突き進めており、ある意味では「政策ありき」で費用対効果が二の次にされている状況とも言えます。
六ヶ所再処理工場については、2023年にようやく規制委員会の安全審査に合格し稼働に一歩近づいたものの、「完成→試運転→本格稼働」に至るまでさらに時間と費用がかかる見込みです。もし仮にこの先稼働できたとしても、回収したプルトニウムの利用計画(MOX燃料の消費先)が定まらないなど課題は山積しており、今後も追加コストが発生するリスクがあります。六ヶ所村の大型施設は、日本のエネルギー政策における費用対効果の低さと意思決定の問題を象徴する存在として、厳しい目が向けられています。
新型コロナ対策費用の検証:効果と無駄の両面から
緊急時の大規模支出も、事後に検証すれば無駄や非効率が浮かび上がるケースがあります。新型コロナウイルス感染症への対応では、国は2020~2021年度にかけて前例のない規模の財政出動(真水ベースでGDPの数割規模とも言われる巨額支出)を行い、国民生活と経済を下支えしました。その迅速な支援自体は必要なものでしたが、一方で計画の甘さや実行段階での不備から「税金の無駄遣いではないか」と後に批判される施策もいくつか存在します。ここでは、特に議論を呼んだ布マスク配布事業(いわゆる「アベノマスク」)、中小事業者支援の持続化給付金事業、そして医療提供体制強化の病床確保支援事業の3点を振り返ります。
布マスク配布やGoTo事業に見る課題
新型コロナ初期に実施された全世帯向け布製マスク配布(俗称アベノマスク)は、その象徴的な名称とともに後世まで語り継がれるであろう政策です。感染拡大でマスク不足が深刻化する中、急場の対応として企画されたものですが、配布枚数や効果に対して費用が過大だったことが強く批判されました。厚生労働省と文科省による布マスク配布には総額1,044億円もの予算が投じられていましたが、品質不良も相次ぎ(混入異物の報告が全国635市町村から寄せられるなど)、十分行き届かないまま約8,200万枚もの在庫を余らせて終了しています。会計検査院の検証によれば、契約時に仕様書を作成せず口頭のやりとりで製造を進めたため不良品対応の契約条項がなく、結果として後から追加の検品費用が発生するなど、杜撰な契約管理でコストが膨らんだことも明らかになりました。結局、配布されたマスクは感染防止に大きな寄与をしたとは言い難く、巨額の税金投入に見合う成果が得られなかった典型例とされています。
また、感染拡大が一段落した2020年後半には経済対策として観光需要喚起策「Go To トラベル」事業が実施されましたが、この事業も途中で感染再拡大により中断を余儀なくされ、費用対効果の点で疑問を呈する声があります。7,000億円規模の予算が投じられましたが、需要喚起策としてのタイミングの悪さや、大手旅行代理店への過度な恩恵(宿泊割引よりも事務委託費が多すぎるのではとの指摘)などが問題視されました。実際にGoTo事業では、委託先の法人に約1,895億円の事務委託費が支払われ、その多くが広告会社などに再委託されたことが判明しており、「中抜き」批判も起きています(※GoToトラベル事務局は大手旅行業者が中心の共同企業体が受託し、その広報等で電通等に再委託)。こうしたコロナ関連の需要喚起策は急造ゆえの不整合もあり、後の検証で改善点が指摘されています。
持続化給付金と病床確保支援:緊急支援の光と影
コロナ禍では、営業自粛要請等で打撃を受けた中小企業・個人事業主への支援策として持続化給付金事業も行われました。これは売上が急減した事業者に最大200万円(個人事業者は最大100万円)を給付するもので、迅速な資金繰り支援策として約423万件、総額5兆5,500億円が給付されました。政策目的自体は妥当で多くの事業者を救った一方、その執行プロセスに深刻な「中抜き」問題があったことが後に判明します。
持続化給付金事務を受託したのは一般社団法人サービスデザイン推進協議会という団体でしたが、実態は受託額の99.8%を電通など大手広告代理店に再委託し、さらにその先で9次下請け・延べ723社もの企業が関与していたのです。いわば受託団体自身は丸投げ同然で、中間マージンが多重に発生する構造でした。これでは事務効率の管理も困難になるため、会計検査院は再委託の範囲や適切性を明確化するよう強く求めました。緊急時とはいえ、巨額の給付事業が不透明な形で外注に丸投げされ、中間経費がかさんだ事実に対し、国民や野党は猛反発。行政の委託契約の在り方に一石を投じる結果となりました。
さらに医療提供体制の強化策として実施された病床確保支援事業(コロナ患者受け入れの病床確保料補助)についても、その効果と費用が議論されています。国は2020~2021年度にかけて全国の医療機関に対し合計3兆3,847億円もの巨額の補助金を交付し(約3,483病院が対象)、民間病院も含め病床を確保するための協力金を支払いました。当時は医療崩壊を防ぐため手厚い支援が必要でしたが、会計検査院の分析によれば補助金を受けた医療機関の2021年度決算は平均7億円の黒字となっていたことが分かっています。補助金によりコロナ患者用の予備病床を増やせたものの、人手不足などで実際に患者受け入れに使われたのは多くても確保病床の5~6割程度に留まり、稼働率が低い病床にも満額の補助金が支払われていた実態が浮かび上がりました。結果として、コロナ対応で収支が大幅に改善し潤沢な黒字を計上した病院も出たのです。検査院は厚労省に対し「補助金設定の妥当性を検証し見直すべき」と求めており、今後類似の緊急支援策を設計する際には、より実態に即した制度設計と効果検証に基づく調整が課題となっています。
以上のように、コロナ対策費用の事後検証からは、緊急時ゆえのやむを得ない側面もある一方で、計画の詰めの甘さや執行段階での中抜き・非効率が招いた無駄も浮き彫りになりました。巨額の財政支出に対し、事後にでもきちんと検証・監査を行い、次の危機への教訓とすることは極めて重要です。
多重下請け構造(中抜き)の弊害と透明性の問題
上述した持続化給付金の例にも見られるように、事業費が途中で中間業者に抜き取られてしまう「中抜き」構造は日本の行政事業の根深い問題です。政府の委託事業や補助金事業では、業務を外部に任せる際に一次受け・二次受け…と多重の下請け構造が生まれやすく、結果として本来の目的以外のところでコストが積み上がる傾向があります。これは民間の商取引でも見られる慣行ですが、こと税金を原資とする事業で過度な中抜きが行われれば税金の無駄遣いそのものです。
持続化給付金は極端な例でしたが、他にも例えば2022年度に実施された燃料油価格激変緩和対策事業(ガソリン価格高騰を抑える補助金事業)でも、似たような構図が指摘されました。経産省から委託を受けた一般社団法人全国石油協会が博報堂に運営を再委託し、博報堂は受託額の77.0%を別の大手広告代理店に再委託していたのです。この事業は補助金申請処理や全国約2万8,500のガソリンスタンド価格調査などを伴う大規模事務でしたが、結局主要部分を外部業者に丸投げする形になっていました。審査を担当した会計検査院は「多重階層では受託者による管理が困難」であるとして、再委託の範囲や妥当性の明確化を提言しています。
なぜこのような多重下請けが横行するのか。その背景には、日本の行政が抱える専門人材の不足や前例踏襲、そして特定業者への依存があります。ITシステム構築や大規模給付事務など、官庁の内部リソースだけでは処理しきれない業務が増えた際、経験のある大手企業にまとめて委託するのが手っ取り早いという発想です。しかし、大手企業(元請け)は実際の作業を系列子会社や協力企業に流すことが多く、そこで重層的な下請け構造が生まれてしまいます。結果として、現場で実務を担うのは末端の下請け企業なのに、中間マージンが多重に発生しコストばかり膨らむという非効率が発生します。国民から見れば「最初から実作業をする企業と直接契約すれば安上がりなのではないか」と映るでしょう。
さらに厄介なのは、そうした中抜き構造の存在が事業の透明性を低下させることです。元請けと下請けの契約関係が複雑になると、最終的に税金がどこに流れたのか把握しづらくなります。情報公開請求や国会質疑で問われても、省庁は「再委託先まで含めた詳細は把握していない」などと答弁しがちで、結果として責任の所在もあいまいになります。持続化給付金のケースでは、野党議員の追及で初めて具体的な再委託率や関与企業数が明らかになりましたが、本来であれば事前にそうした契約内容のチェックや制限を設けておくべきでした。
この問題に対し、行政側でも対応が取られ始めています。2021年以降、各府省は大型事業の委託契約時に再委託の状況を把握・公開するよう指針を見直し、過度な多重下請けを是正する動きがあります(例えばデジタル庁はシステム調達で中間業者を排した直接契約の拡大を掲げています)。しかし根本的解決には、入札・契約制度の改革や官民の人材交流による行政の実行力強化などが必要との指摘もあります。会計検査院は引き続きこうした委託事業の検査を強化し、「国民の期待に応える検査に努めたい」と述べています。中抜き防止と透明性確保は、限られた財源を有効活用する上で避けて通れない改革課題と言えるでしょう。
結論:説明責任を果たし、真に必要な支出へ集中を
インフレと増税で国民の負担感が高まる中、政府には今一度、「聖域なき支出改革」を断行することが求められています。神宮外苑再開発や辺野古基地建設に見る不要不急の事業の見直し、高速増殖炉もんじゅや六ヶ所再処理工場に見る巨額プロジェクトの撤退判断の適切化、そして持続化給付金や病床確保支援に学ぶ制度設計の改善と執行プロセスの透明化――いずれも避けては通れない課題です。
幸い、会計検査院による監査報告やメディアの調査報道、国民の声が契機となり、政府が方針を転換した例も少しずつ出てきています。高速増殖炉もんじゅの廃炉決定や、持続化給付金事務委託の再発防止策、コロナ禍の巨額予備費の使途公表などは、その一端と言えるでしょう。国民の信頼を回復するには、政府自らが費用対効果の検証と情報公開に努め、説明責任を果たすことが不可欠です。無駄を削りつつ、本当に必要な政策には大胆に投資するというメリハリの利いた財政運営が求められています。
日本は今、少子高齢化による社会保障費の増大や、防衛力強化の必要性、経済成長の停滞といった難題に直面しています。だからこそ、限られた財源を無駄なく使い、将来への投資や国民生活の安定に振り向けることが重要です。政府のあらゆる事業を俎上に載せ、「それは本当に必要か?効率的か?」と問い直す姿勢を持ち続けることが、持続可能な財政と公正な税負担の実現につながるでしょう。私たち有権者・納税者も監視の目を緩めず、建設的な提言を行うことで、この国の政策をより良い方向に導いていくことが求められています。
関連商品のご提案
政府支出の無駄や改革の必要性についてさらに詳しく知りたい方には、『無駄だらけの社会保障』(日本経済新聞社調査報道班 著)がおすすめです。本書は社会保障分野を例に、膨張する国家支出の裏側でどのような無駄が生じているかを綿密な取材で明らかにしています。年金・医療・介護といった身近なテーマから国家財政の課題を考えることができ、政策に関心のある読者には示唆に富む内容でしょう。専門的な内容を平易な筆致で解説しており、行政のどこにコスト改善の余地があるのか学ぶのにも最適な一冊です。
ぜひこの機会に手に取ってみてください。政府の予算の使われ方に対する理解が深まれば、ニュースや行政発表を見る目も変わり、自分たちの税金がどう活かされるべきか主体的に考える助けになるでしょう。
参考文献
【日本経済新聞出版社】『無駄だらけの社会保障』日本経済新聞社調査報道班books.rakuten.co.jp(2022年)
【会計検査院】令和4年度決算検査報告 - コロナ対応交付金の未使用マスク等112億円分を含む不適切支出を指摘fnn.jpfnn.jp(2023年11月)
【FNNプライムオンライン】「コロナマスク不使用など国の不適切支出344件580億円 会計検査院が報告書」fnn.jp(2023年11月7日)
【ダイヤモンドオンライン】「神宮外苑再開発に透ける明治神宮と三井不の『金儲け主義』」岡田悟・大根田康介diamond.jp(2022年1月)
【共同通信】“Tree cutting begins for Tokyo's controversial Jingu Gaien redevelopment”english.kyodonews.netenglish.kyodonews.net(2024年10月28日)
【琉球新報】「ホントは一体いくら?辺野古新基地、正確な事業費の公表なく、政府試算超え濃厚」明真南斗ryukyushimpo.jp(2024年12月28日)
【しんぶん赤旗】「沖縄の辺野古新基地建設費/想定超過の可能性も/防衛相答弁 赤嶺氏が中止を要求」jcp.or.jpjcp.or.jp(2025年2月6日)
【Reuters】“Japan pulls plug on Monju, ending $8.5 billion nuclear self-sufficiency push”reuters.com(2016年12月21日)
【朝日新聞】「完成延期重ね、費用約3兆円 突き進む六ケ所再処理工場」桑原紀彦asahi.comasahi.com(2020年7月27日)
【Newsweek日本版】「田中弥生・会計検査院長に聞く『コロナ対策の事後検証』」newsweekjapan.jpnewsweekjapan.jp(2024年12月18日)
【朝日新聞】「コロナ病床確保の医療機関、平均7億円黒字に 国の補助金で収支改善」asahi.com(2023年1月15日)

