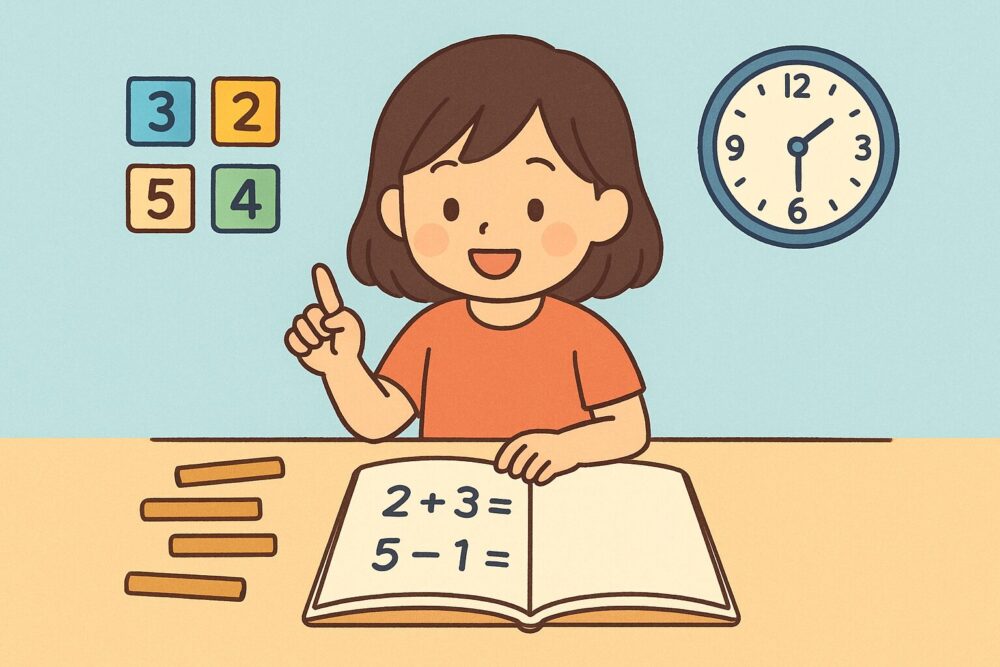
小学校1年生の算数は、数の数え方から始まり、たし算・ひき算の基礎や図形・長さ・かさ(体積)・時計の読み方など、生活に直結する学びが詰まっています。本記事では、1年生算数の全単元について、学校で「できるようになること」とおうちでできるサポート方法をわかりやすく解説します。お子さんの「わかった!できた!」を引き出し、算数が楽しくなる家庭学習のコツまでカバーします。
要点まとめ
- 年間の学習全体像: 1年生算数では 数と計算(0〜100までの数の基礎〔0〜20→20〜40→100〕、繰り上がり足し算・繰り下がり引き算)と 図形(身近な立体と形)、 量と測定(※領域名はC:測定)(長さ・かさの比較、時計の「〜時」「〜時半」(教科書によっては「〜時何分」まで))を学びます。
- つまずきポイント: 10のまとまり(10を作る感覚)をつかめていないと繰り上がり・繰り下がりで苦戦します。また、文章題では絵図で場面をイメージできないと「足し算か引き算か分からない」状態になりがちです。
- 克服する対策: 具体物や図を使って「10の補数(10になる組み合わせ)」を遊びながら覚える。文章題はキーワード頼みではなく絵や図を描いて考える習慣をつける。短い家庭学習を毎日続け、お子さんが自分で考えるヒントを対話で与えることが大切です。
- 家庭学習のコツ: 1日 10〜20分を目安に、計算ドリルや身近なものを使った数遊びを取り入れましょう。短時間でも毎日継続する習慣が効果的。具体物→図→数字の順で練習し、できたら全力で褒めることでお子さんの自信を育てます。
- 単元別練習問題つき: 記事後半では各単元ご家庭で練習できる問題(解説つき)を掲載。お子さんの理解度チェックやつまずき発見にお役立てください。
1年算数の全体像(年間でできるようになること)
▶︎結論: 小学1年生では、数の概念と計算の基礎(数を数える・書く・比べる、足し算引き算の初歩)を習得します。また図形では身近な物の形から基本図形への気づき、量の比較では長さ・広さ・かさの直接比較と簡単な測定、時計では「〜時」「〜時半」の読み方を学びます。これらはすべて日常生活と結びついた内容で、「算数っておもしろい!」と感じられる土台づくりの一年です。
▶︎根拠: 文部科学省の学習指導要領解説によれば、1年生ではA:数と計算・B:図形・C:測定・D:データの活用 の4領域の基礎を扱います。特にA:数と計算では「20や100までの数の読み書き・大小比較・簡単な加減計算」を指導し、B:図形では「身近な形の観察・構成」を通じて三角形・四角形・円などへの気づきを促し、C:測定では「長さ・面積・体積の直接比較」やや「身の回りの物を単位にした比較」「時計の時刻読み」を経験させるとされています。D:データの活用として簡単な文章題にも触れます。
▶︎具体例: 年間指導計画の例では、1学期に「ものの数え方・いくつといくつ」「ひと桁の足し算引き算(繰り上がりなし)」、2学期に「繰り上がりのある足し算」「身の回りの形遊び」「繰り下がりのある引き算」、3学期に「大きい数(100くらいまで)」「広さ比べ」といった単元が配当されています。例えば2学期に「たしざん(繰り上がりあり)」を10時間かけて学び、その後「形あそび」で箱や缶を使った立体工作を行い、11月に「ひきざん(繰り下がりあり)」を学習するといった流れです。
要点Q&A(全体像)
- Q: 小1算数で身につけるべき一番大事な概念は?
A: “10のまとまり”です。10という基準を理解すると、繰り上がり・繰り下がり計算や2年生以降の位取りがスムーズになります。 - Q: 1年生で習う図形の内容は?
A: 箱や缶など身近な立体の形に親しみます。そこから三角形・四角形・丸など平面図形の特徴に気づく活動をします。 - Q: 時間はどこまで理解しますか?
A: アナログ時計の「○時」と「○時半」が中心です。教科書によっては1年の後半に「○時○分」も扱います。短針と長針の役割を知り、日常生活で時刻が読めることを目標とします。
数と計算の土台
▶︎結論: 数と計算の単元では、まず数の意味をしっかり理解することが土台です。「いくつといくつ」の学習で、数を分解・合成する感覚(例:5を3と2に分ける)が身につきます。この基礎の上に10のまとまりを意識する力を育て、繰り上がり足し算では「10を作って計算する」、繰り下がり引き算では「10から引いて計算する」方法を学びます。これらの考え方は、小学校算数の計算全般の要となる重要ポイントです。
▶︎根拠: 教科書では、最初に1対1対応で数を数える活動や数字の読み書きから始め、次に「いくつといくつ」(数の分解)で5や10の構成を学習します。文部科学省の解説も、1年で「1位数同士の加法とその逆の減法」を確実に身につけることを目標としています。繰り上がりのある足し算では「『10といくつ』の数の見方に基づいてできることを理解」させ、実際の指導でも加数を分解して10を作る方法(9+4なら4を1+3に分けて9+1=10, +3=13)を重視しています。繰り下がり引き算では被減数を分解して10から引く減加法(13−9なら13を10+3に分けて10−9=1, +3=4)の考え方が指導されます。
▶︎具体例: たとえば「7は いくつといくつ?」といった問いに対し、1年生はブロックを分けたり指を折ったりして 「7は3と4」「7は5と2」などと全て言えるようになります。繰り上がりの足し算では 9+4 の計算で「4を1と3に分けて、まず9+1で10を作り、残りの3を足して13」というステップを学びます。繰り下がりの引き算では 13−9 の計算で「13を10と3に分けて、10−9=1、残りの3を足して4」と求めます。これらの方法を数図ブロックやおはじきなど半具体物と図を用いて練習することで、計算の意味を理解していきます。
なかまづくり・1対1対応/0〜10の数・「いくつといくつ」
ここは基礎中の基礎! お子さんが最初につまずきやすいのは「数の概念」です。まず、ものを1つ1つ対応させて数える練習(1対1対応)から始めます。例えばリンゴとお皿を1個ずつペアにしていき、「ちょうどぴったりなら同じ数、余る・足りないなら数が違う」といった具合です。続いて0から10までの数字を読み書きし、それぞれの数が実際「ものの個数」としてどんな意味かを体感します。
- 1対1対応: 物と物をペアにすることで数の大小を比べます。例えば「りんごとお皿、どちらが多い?」と聞き、お皿にリンゴをそれぞれ置いて、余るお皿やリンゴがないか確認します。これで「同じ数」や「〇〇の方が1つ多い/少ない」を理解します。
- 0という数: 最初は「何もない」という概念が難しいのですが、例えば箱の中の積み木を全部出して空っぽにし、「今、積み木はいくつ?」と問う体験で0を実感します。「0は何もないことを表す数」という説明も短く伝えます。
- いくつといくつ: 5はいくつといくつ?といった問題で、5個のブロックを分けたり合わせたりする練習をします。全部で5個ある中で赤と青に分ける遊びをすると、例えば「5は2と3」「5は4と1」と分解パターンを発見できます。これが数の合成・分解の第一歩です。
🎓 豆知識: 集合数(ものの個数)と順序数(何番目か)は区別が必要です。1年生では主に集合数としての数を扱いますが、「何番目」の学習も少しだけ出てきます(例:「○番目の人」)。混乱しやすいポイントなので、家庭ではお子さんが順番を数える練習も取り入れると良いでしょう。
家庭でできること:
- 日常で一緒に数えるクセをつけましょう。階段を上るときに段数を数える、野菜を袋に入れながら「今何個?」と聞くなど、楽しく数唱やカウントを繰り返します。
- かぞえてバスごっこ: おもちゃの車にお人形を乗せ、「バスに◯人乗れます。今△人乗ったから、あと何人乗れるかな?」といった遊びをします。「あと◯人だね」と自然に残りの数を考える力が育ちます。
- おはじき並べ: 0の理解には、おはじきを並べて数を減らす遊びが効果的です。最初5個並べて1個ずつ取り除き、「0になったね、何もなくなったね」と体験させます。逆に0個から1個置けば「1になる」ことも教えられます。
10のまとまりと数の見方(“10をつくる”感覚)
「10」を制する者が計算を制す! 1年生算数で特に重視したいのが「10」というまとまりです。10は位取りの基準であり、10を単位に考える力はこの先の算数すべての基盤となります。ここでは10より大きい数(11〜20程度)の学習と並行して、「10を作って考える」練習をします。
- 10より大きい数: 11以上の数は「10が1つと◯」という言い方で教科書に登場します。例えば「12は10と2」という表現で、位取りの考え方を初歩的に経験します。ブロックを10個一束にして、それと余りのブロックで11〜19を表す活動もします。
- 10の補数: 「あといくつで10になるか」を即答できるよう訓練します。例えば7にいくつ足せば10?と聞いて3とすぐ答えられることが理想です。これは10の補数と呼ばれ、繰り上がりや繰り下がり計算で頻繁に使います。おはじき遊びでは、10個のうち何個か隠して「見えているのが3個なら隠れているのはいくつ?」と推理させるゲームが効果的です。
- 十の位と一の位: 1年生の段階では「十の位」「一の位」という言葉は本格的には習いませんが、10は一束でひとまとめにできることを体感します。例えば10玉そろばん(百玉そろばんの一部分)を使い、珠を全部右に寄せた状態から1珠、2珠...と左に出して「1段目は1と9で10、2段目は2と8で10...」と10の階段を作る視覚教材があります。これで1と9/2と8/…10と0といった組合せを視覚的にインプットできます。
つまずき注意: 10の補数が身についていないと、8+5のような計算で毎回指を折って数えることになります。指でのカウントから抜け出せない場合、具体物➡半具体物(図やドット)➡数字と移行する練習が必要です。「ゾウが5頭もアリが5匹も同じ●●●●●(ドット5個)だ」という具体から抽象への変換を経験させましょう。
家庭でできること:
- 10になるペア探しゲーム: トランプやカルタで1〜9のカードを使い、2人で交互に「10になる組」を作ります(例: 4を出したら6を出せるか探す)。余ったカードが負け。遊びながら組み合わせ暗記ができます。
- 百玉そろばん的なおはじき: 10個のおはじきを一列に並べ、「○と△で10」と声に出しながら両端からペアを作らせます。例えば1と9をくっつけ、2と8をくっつけ…とすると5組できます。「全部で5組できたね」と伝えつつ、自然と10の補数を覚えられます。
- 10の歌・暗唱: 「♪1と9で10、2と8で10…♪」のようなリズムや音読で補数を暗記するのも効果的です。寝る前のちょっとした時間にクイズ形式で「7と?で10」→「3!」「正解!」とやるとゲーム感覚で身につきます。
たしざん(繰り上がりの考え方:被加数分解→10のまとまり)
1年生最大の山場、繰り上がりです。たし算(加法)自体は前半で導入しますが、繰り上がりを伴うもの(答えが10を超える足し算)は中盤〜後半で登場します。9+◯や8+◯で10を超える場合、ここまで培った「10のまとまり」の力が試されます。指導では「加数分解」といって 足す側の数を分ける 方法が取られます。
- 繰り上がりとは: 一桁同士の足し算で答えが10以上になるとき、位が繰り上がって二桁になります。例えば 9 + 4 = 13 で、一の位を超えた「1」を十の位に繰り上げます。筆算では小さい「1」を書きますが、1年生では筆算は使わず意味理解を重視します。
- 加数分解: 繰り上がり計算では、足される数(加数)を10に足りない分と残りに分ける方法を教えます。例: 9+4 は「4を1と3に分けて、まず9+1=10を作り、残り3を足して13」とします。この時、「9は10の手前であと1足りない」という感覚をしっかり意識させます。
- 被加数分解(別解): 教科書によっては足される側(被加数)を分ける考え方も扱います。例: 7+8 を「7を7=2+5に分け、2+8=10、残り5足して15」とする方法です(※「被加数分解」)。実際には加数分解の方が一般的ですが、どちらも10のまとまりに着目している点は同じです。
指折りからの脱却: 繰り上がり計算で指を使っているようなら、まだ数の分解が定着していません。例えば「9+4」で9から指を4本伸ばして数えているうちは、繰り上がりを理解したとは言えないのです。指を使わずに答えを導けるよう、「あといくつで10」かを常に考える癖をつけましょう。
つまずき例: 「繰り上がりってなにが繰り上がるの?」と混乱する子がいます。これは十の位に1が移る感覚が掴めていないのです。ブロック10個で一まとめの図を描き、「ここが10になるから、10は次のくらいに繰り上がるんだよ」と視覚的に示しましょう。
家庭でできること:
- 計算カード: 1桁同士の足し算カードを作り、テンポよく口答させます。特に9に足す数や8に足す数は集中的に練習します(9+2,9+3,…9+9など)。狙いは補数を反射的に答える訓練です。
- おはじき計算: 例えば9+4を、おはじきを9個と4個に並べて、まず1個を9の方に移動させて「10」を作る様子を一緒にやります。「10ができたね!あと残りはいくつ?」と尋ね、答え3を足して13と導きます。複数回繰り返し、自分でおはじきを動かせるようにします。
- 言葉で説明させる: 計算ドリルで繰り上がりの答え合わせをするとき、ただ○付けするだけでなく「どうやって考えたの?」と聞きましょう。お子さんが「○と△で10を作って…」と説明できれば合格です。もし「うーんと、指で…」となれば、もう一度具体物に立ち戻って練習しましょう。
ひきざん(繰り下がりの考え方:減加法/10からの引き)
引き算(減法)のヤマ場が、この繰り下がりです。11以上-一桁で位をまたぐ引き算が該当し、例えば 13−9 などの計算です。1年生の後半で学習し、ここでも「10のまとまり」が威力を発揮します。繰り下がりでは「減加法(げんかほう)」と呼ばれる引き算を加法に言い換える考え方が指導されます。
- 繰り下がりとは: 2桁から1桁を引いて結果が1桁になる場合、十の位から繰り下げて一の位に10を借りてくる操作です。例えば 13−9 を筆算的に考えると、3から9は引けないので十の位の1を0にし、一の位に10を繰り下げて13−9=4とします。ただし1年生は筆算をまだ習わないので、この現象を数の分解で理解させます。
- 減加法: 「引き算を足し算に置き換える」方法です。たとえば問題 13−9 は、「9にいくつ足せば13になるか」を考える発想です。9に?を足して13になる?は4なので答え4、と求めます。このやり方は逆思考になるため難しく感じる子もいますが、「9から10までは1、10から13までは3、合わせて4」というステップにすると分かりやすくなります。
- 被減数分解: もう一つの一般的な教え方が「10から引く」方法です。13−9で13を10+3に分けて、10−9=1、残りの3を足して4とする解き方です。これは結局、引かれる数(被減数)を分解している点で加法の繰り上がりと対称的です。教科書では、まずこの被減数分解による説明が行われ、併せて減加法的な考え方も紹介されます。
よくある誤答: 「13−9」のつもりが「13−3=10」 として答え10を書いてしまう子がいます。これは一の位同士を引いてしまったミスです(3−9はできないのでとりあえず9−3=6で…と誤魔化すケースも)。こうした場合、具体物か絵で確認させましょう。13個のブロックから9個取り除かせ、「残りいくつ?」と聞くのです。実物操作で納得させた上で、「13を10と3に分けて考える」と繋げます。
「ひくのに足すの?」: 減加法の考えを初めて聞くと「引き算なのに足し算するの?」と戸惑うかもしれません。しかし求めるものが違うだけで、やっている計算自体は正しい加法です。これを理解させるには、「9にいくつ足せば13?」と足し算の問題に言い換えてみせ、「答えが同じになるでしょう?」と確認するのが効果的です。
家庭でできること:
- おはじきで補数引き: たとえば「12−8」を、おはじきを12個並べて8個取り除く代わりに、「8個から10個にするには2個必要、12個にするにはさらに2個必要、だから合わせて4個必要」と計算させます。増やしてから減らす感覚を体験できます。
- 引き算ビンゴ: 答えが0〜9になる繰り下がり引き算問題を用意し、子供とビンゴゲームをします。問題例カード(「11−8」など)を引いて計算し、出た答えのマスを埋める形式です。ゲーム性で集中して解くうちにパターンに慣れます。
- 言葉に出す: 計算の途中経過を必ず声に出して言わせましょう。「13を10と3に分けて…10−9は1、で、あと3あるから…4!」という具合です。声に出すことで理解が整理され、親御さんもどこでつまずいているか発見できます。
図形(身の回りの立体→面の形に着目/形づくり)
▶︎結論: 図形の分野では、まず身の回りの物に注目して形を捉えることから始めます。1年生では積み木や箱・缶など立体に直接触れ、その形の特徴や用途(転がる、積める 等)に気づかせます。そこから、それら立体の表面の形(例えば缶のふた=まる、箱の面=四角)に注目し、平面図形(円・三角形・四角形)の存在に気づきます。要するに「いろいろな形があるんだ!」という発見と、基本的な形の名前を楽しく学ぶのが狙いです。
▶︎根拠: 文部科学省の解説では、1年生の図形は「身の回りのものの形を認め、特徴をとらえる」ことをねらいとしています。具体的には、子供たちが例えば「さんかく」「しかく」「まる」と呼んでみる活動を通して、図形への興味を育てるとされています。教科書単元名では「かたちあそび」「かたちづくり」といったタイトルで、空き箱・積み木・紙片などを使った構成遊びや絵描き(スタンプ)が扱われますt。東京書籍の教科書では、空き箱や筒を組み合わせて乗り物や建物を作り、形を抽象化して分類する流れが示されています。
▶︎具体例: 授業でよくある活動に「形のスタンプ」があります。子供たちは底が平らな箱や筒に絵の具を付けて紙に押し付けます。すると四角や丸のスタンプができます。「この四角は○○の箱の面の形だね!」と発見し、平面図形の存在に気づきます。「三角のスタンプは作れるかな?」と問い、三角形の面を持つ積み木を探したりもします。さらに、「積み木を転がしてみよう。丸い棒はコロコロ転がるね、四角い箱は転がらないね」と立体の特徴(円柱は転がる、直方体は転がらない)にも気づかせます。
要点: 1年生では図形の正式な用語(頂点・辺・面など)は扱いません。あくまで感覚を豊かにする段階です。「ころがる」「積み重ねられる」「とがっている」「まるい」など、子供の言葉で特徴を表現させます。この表現する活動自体が数学的な見方の第一歩です。
家庭でできること:
- 形しらべ: おうちにある箱や缶を集めて、「これは何の形?」「丸いところはどこ?」とクイズを出します。箱ティッシュ→長四角の面、缶→丸いふた、など形当てゲームにすると盛り上がります。
- 積み木遊び: 立体図形の構成遊びは、お子さんの創造力も育みます。親子で一緒に積み木やブロックで「高い塔を作ろう」「お城を作ろう」とチャレンジしましょう。できあがったら「どんな形のブロックが使われている?」と尋ねてみます。
- お絵描き: お子さんに宝探しマップを描いてもらうとき、家や木を三角や四角で描くことがあります。それを見て「上手に三角描けたね」などと褒め、名前と形を結びつけてあげましょう。気づいたら一緒に教科書に出てくる図形の名前(さんかく、しかく、まる)に触れておきます。
量と測定
▶︎結論: 量と測定(※領域名はC:測定)の領域では、長さやかさ(容積)といった量を比べる方法を学びます。1年生では物差しやメジャーカップといった標準単位は使わず、「どちらが長い?」「どちらが多く入る?」を直観的・経験的に比べる活動が中心です。具体的には直接比較(物を直接並べて比べる)と間接比較(ひもや容器など媒介物を使って比べる)を経験し、任意単位(例えばクリップ何個分など)で長さやかさを測る基礎感覚を養います。また時計の読みにも入門し、アナログ時計で「◯時・◯時半」を読めるようになります。
▶︎根拠: 文科省の指導要領解説では、1年生で長さ・面積・体積の直接比較と、身の回りのものの大きさを単位にした比較を指導するとあります。実際の指導案でも「長さくらべ」の単元で「直接比較や間接比較、任意単位による測定の方法」を理解させることが目標とされています。例えば長さでは「端と端を揃えて比べる」「ひもに写し取って比べる」「紙片や体を使って大まかに測る」といった内容です。かさ(体積)についても、1年生は直接容器を比べるか同じ容器に移し替えて比べる程度で、標準単位(リットル等)は登場しません。時計では、「長針が12を指していれば『ちょうど◯時』、長針が6なら『◯時半』」という読み方を教え、短針の位置で時間を判断する練習をします。
▶︎具体例: 長さくらべでは、子供たちは2本の鉛筆を実際に並べて「どっちが長いかな?」と比較します。曲がったリボンと直線のストローでは、リボンをまっすぐ伸ばしてから比較することを学びます。さらに、教室の机の縦と横のどちらが長いかを、紙ひもに写し取って比べるなど間接比較も行います。かさくらべでは、500mLペットボトルと背の高い細瓶のどちらが水を多く入るかを実際に水を移し替えて確かめる活動があります。「見た目では細瓶の方が背が高いけど、移してみたらペットボトルに全部入ってさらに余裕があるね」と、目分量の危うさと比較の工夫を体験します。時計では模型の時計を動かし、「短い針が3と4の間、長い針が6のとき『3時半』」等を読み上げる練習を繰り返します。
家庭でできること:
- なんでも長さ比べ: おうちの中で「いちばん長いもの探し」をします。リモコンとお箸、どっちが長い? 紐で壁の横幅を測ってみよう、など遊び感覚で比較の工夫を促します。長さ比較では必ず片方の端を揃えることを約束させましょう。
- 測ってみよう: 任意単位の感覚を養うには「手」「足」「おもちゃ」何個分かで測るのが一番。例えば「机の長さはゆうた君の足👣何足分かな?」と質問します。足を並べて「5足分くらいだ!」となれば「ゆうた君の足5つ分が机の長さだね」と褒めます。これで「〇〇個分」という表し方に慣れます。
- お風呂で容積遊び: 大小のカップや容器を湯船に浮かべて、「どっちがたくさん入るかな?」と水を移し替えて遊びます。同じ小コップで何杯入るか数えるのも良いでしょう。「こっちは3杯、あっちは5杯入ったね。じゃあ後者の方がたくさん入るんだ!」と自然に学べます。
- 時計の読み方練習: 家のアナログ時計を指し、「長い針が12、短い針が8を指しているときは?」などクイズを出します。デジタル時計も併用し、「8:00は8時、じゃあ8:30はどこかな?」と対応させると理解しやすいです。
長さくらべ(直接比較/間接比較・任意単位の基礎)
長さくらべの基本は「ぴったり揃えて比べる」ことです。子供は見た目の錯覚で斜めになった物を「長い」と感じたりしますので、まず端と端を揃えて比べる直接比較を教えます。それが難しい場面(例: 部屋の幅など)は間接比較としてひもや紙を媒介に使います。また、定規は使わずとも「○○が何個分」といった任意単位で長さを表す練習も行います。
- 直接比較: 2つの物の長さを比べるときは、一方の端をもう一方の端に合わせると分かりやすいことを指導します。曲がった物(例: ひもやリボン)はまっすぐ伸ばしてから比べます。子供には「ずる」をせず正確に揃えることの大切さも教えます。
- 間接比較: 離れた場所や大きすぎる物同士は直接比べられません。その場合、ひもや棒を使って一方の長さを写し取り、それをもう一方に当てて比べる方法を学びます。例えば机と椅子の高さを比べるには、椅子の高さをひもで測って机に当ててみる、といった具合です。
- 任意単位で測る: 長さを数字で表す初歩として、子供の身長を「〇〇さん何人分」とか鉛筆の長さを「消しゴム何個分」といった測り方を体験させます。これにより、「長さも数で表せるんだ!」と気づきます。例えば電車のおもちゃの長さを小さい車両(任意単位)で測れば「この電車は車両3つ分の長さ」といった表現ができます。
身につけたい感覚: 長さ比べでは「一直線にする」ことと「ズレを揃える」ことの2点です。例えば園児さんだと、リボンを適当に置いて定規を当て「同じくらい」と言いがち。それを矯正するのが1年生の役割です。「曲がってると正しく比べられないよ」「スタートがずれてるとダメだね」と声掛けします。
家庭学習: 折り紙の長さを手で測る遊びはいかがでしょうか。折り紙を1辺に沿って指でマークし、その指の開きを他の物に当てて「折り紙と同じ長さかな?」と調べます。自分の体を道具にすることで、より身近に感じます。
かさくらべ(容器・並べ替えで比較/量感を育てる)
かさくらべ(容量比べ)では、見た目に惑わされない経験を積むことが重要です。細長いコップとずんぐりしたマグカップ、どちらが「たくさん入る」かは、注いでみないと分かりません。1年生では直接比較として「一方の容器に水を入れて他方に移す」ことをやってみせます。また任意単位として小さいカップで計量し「○杯分」という表し方も体験します。
- 直接比較(移し替え): コップAとコップBの水の量を比べるには、片方の容器からもう片方に水を移すのが確実です。BにAの水を全部注いでみて、まだ余裕があればBの方が大きい、溢れたらAの方が大きい、ぴったりなら同じ、と判断します。「やってみないと分からないね」を実感させる活動です。
- 間接比較(同じ容器に移す): 形状が違う容器同士では、共通の容器を使って測る方法も教えます。例えばペットボトル500mlに両方の水を移して測る、といった具合です。これは実質的には簡易な計量で、容量の保存概念(入れ物が変わっても量は同じ)も学べます。
- 任意単位(○杯分): 小さなお玉やカップで、水を何杯移せるか数えて比較します。「こっちは5杯、あっちは3杯で溢れたから、こっちの方がいっぱい入るんだね!」と、数値で量を表現する練習になります。
発展: 1年生では単位(mLやL)は教えませんが、「牛乳パックは1リットル」「ペットボトルは500ミリリットル」など実生活の単位に触れてもOKです。特に料理の手伝いで計量カップを使うと、「200mL計って」と言われて自然と単位の感覚が身につきます。
注意: 水遊びになると授業が脱線しがちです。家庭でやる際も、水がこぼれても大丈夫なようお風呂場や庭で行いましょう。こぼしたり溢れさせたりも経験です。「全部入れようとして溢れちゃった!」という失敗から学ぶこともあります。
とけい(「なんじ/なんじはん」短針と長針の関係)
時計の学習は、1年生ではアナログ時計の読み方が中心です。デジタルは読めてもアナログが苦手な子は多いので、ここでしっかり教えます。ポイントは長い針(長針)と短い針(短針)の役割です。長針が12を指していれば「ちょうど○時」、6を指していれば「○時半」であることをまず覚えます。そして短針が指す数字で時間を読みます。ただし「○時半」のとき短針は数字の間にありますので、一つ前の数字を読む約束を学びます。*教科書によっては「○時○分」も扱います。
- ○時(きっかり): 長針が 12 のとき、短針がちょうど指している数字がそのまま時刻です。「長い針が12を指しているね。このときは『○時ちょうど』だよ。」と繰り返し練習します。例えば短針3・長針12なら「3時」です。
- ○時半: 長針が 6 を指していると「半(30分)」です。短針はちょうど数字には指していませんが、次の数字に向かう途中にあります。このとき短針が超えていない方の数字が今の時です(例: 短針が8と9の間・長針6なら「8時半」)。ここを間違えやすいので、時計モデルで動かして体感させます。
- 練習方法: 教科書では、まず時計盤に数字を配置するところから始めることもあります(数字カードを貼っていくなど)。そして実際に可動式時計で針を動かして、親が時刻を言い子が合わせる、子が合わせて親が読む、といった相互練習をします。「短い針しか見てなかった!」などのミスをその場で修正します。
つまずきがちな点: 「長針が6のときは半」は比較的すぐ覚えますが、短針の読み取りが難関です。半のとき短針は次の数字に少し入っているため、子供は「9に近いから9時?」と勘違いしがちです。これには「短針さんは次の数字に向かって歩いている途中なんだよ。でもまだ次の時間にはなってないから、前の数字を読むんだよ。」とストーリー仕立てで教えると理解しやすいです。
家庭でできること:
- 時計合わせ遊び: おうちにあるアナログ時計(または玩具の時計)を使い、「○時にセットして!」「○時半にしてみよう!」と遊びます。最初は親御さんが針を動かし、お子さんに読み取らせる方がいいでしょう。「短針はどの数字とどの数字の間かな?」など問いかけて考えさせます。
- 毎正時・30分に声掛け: 日常生活で整った時刻(○時ちょうど、○時半)になったら「今○時半だね」「○時だよ」と実際の時計を指して教えます。リアルな場面での繰り返しが定着を助けます。
- デジタル併用: デジタル時計も見せ、「今は7:30と表示されているね。アナログでは7時半と読むんだよ」と対応付けます。お子さんがデジタルに慣れている場合は特に、両者を結びつけると早いです。
文章題の読み解き方(絵図→式→言葉で説明)
▶︎結論: 文章題(文章問題)は、多くの子が苦手意識を持ちやすい分野です。1年生では文章題を通じて、算数的に状況を読む力と式を作る力の初歩を養います。指導のキモは、問題文をただキーワードで解釈するのではなく、絵や図に表して考えること。つまり文章→イメージ(絵図)→式→答えというプロセスを一つ一つ練習します。足し算・引き算それぞれに典型的なパターン(加える/合わせる/残り/差/補うなど)があることも教え、混乱を減らします。
▶︎根拠: 指導要領解説でも、「数量やその関係を言葉・数・式・図などに表したり読み取ったりする」資質を育てるとされています。1年生では特に加法・減法が用いられる場合の意味理解に焦点を当て、簡単な文章題に取り組みます。教育現場の声として、「これまでは『合わせて』『残り』など言葉のキーワードで立式する子が多かったが、絵や図を活用して答えを求める態度を育成したい」という指導改善も報告されています。実際、文章題には足し算2タイプ(合併・追加)、引き算3タイプ(求残・求差・求補)があると整理され、キーワードだけでは誤る問題(例:「〜だったのは初め何個?」)もあるため、場面を図式化して考える指導が重要だとされています。
▶︎具体例: 「みかんが5個あります。2個食べました。残りはいくつですか?」という典型的な求残(残りはいくつ)問題では、多くの子がイメージしやすく、5−2=3と式を立てられます。「きいろい風船が7個、あかい風船が5個あります。きいろい風船は何個多いですか?」という求差(差はいくつ)問題では、絵を描かせると多くの子が7個と5個の並びを描き、並んだ分以外の余りに着目して「2個多い」と導きます。一方、「たけしくんはりんごを2個食べました。でもまだ3個残っています。はじめ何個ありましたか?」という隠れた加算の問題はとても難しく、キーワードだけ見ると「食べた→減法」と勘違いし、誤って5−2=3と式を書いてしまう例があります。これを防ぐには、?個 - 2 = 3の図(または3+2の図)を描いて考える練習が有効です。「残り3個はもともとあった中の一部、食べた2個もその中の一部、合わせれば元の数になるね」と視覚的に理解させます。
要点: 低学年の文章題克服には、以下のステップが有効です:
- 音読して状況把握: 問題文をゆっくり音読し、登場人物・もの・出来事を整理する。
- 絵や図に描く: ストーリーを絵にしたり、テープ図(線分図のようなもの)で数量関係を表す。
- 式にする: 絵や図を見ながら、自分で「〇〇だから足し算(引き算)しよう」と判断して式を立てる。
- 言葉で答える: 「○こです」「○にんです」など単位も含め、文で答えを書かせる。
これらを訓練すると、子供自身が「なぜその式になるのか」納得できます。
家庭でできること:
- お話を絵に: 文章題を読み聞かせて、お子さんに絵を描いてもらう練習をします。「うさぎが3わ、りんごが2こ落ちて…」など架空の話でもOKです。描けたら「じゃあどう計算する?」と聞き、絵を見ながら式を導かせます。
- ブロックで再現: ブロックやおはじきで問題の場面を再現させます。「5人いて2人帰ったら…ブロックでやってみよう」といった具合です。体を動かすことで理解が深まり、式にも移行しやすくなります。
- 質問で誘導: 答えを急がず、「何を求める問題かな?」「今分かっている数はどれとどれ?」など問いかけて、一緒に考える習慣をつけます。ポイントはお子さん自身に考えさせること。親がすぐ「だから足し算ね」と言うのはNGです。ヒントは出しつつ、最後は子供の発見に任せましょう。
家庭学習の進め方(1日10分の型/具体物→半具体→記号の順)
▶︎結論: 小1の家庭学習は短時間でも毎日コツコツが鉄則です。目安は「学年×10分+10分」とも言われ、1年生なら1日20分程度が理想。実際には宿題除き10分でもOKです。大事なのは決まった時間に継続する習慣と、「できた!楽しい!」というポジティブな体験です。学習内容は、学校の進度に合わせて具体物→半具体(図)→記号(数字式)へと段階的に進めましょう。はじめはおはじきや絵で理解し、徐々にドリルの筆算形式に移ると効果的です。
▶︎根拠: 「毎日の家庭学習時間は学年×10分+10分」説は一般的で、1年生なら20分程度が望ましいとされています。しかし実態調査では7割の家庭が30分未満しか勉強しておらず、それでも成果は出ています。「疲れている日は無理せず短く」という柔軟さも推奨されています。鹿沼市立西小学校の校長先生も「具体物に頼る段階から半具体物への変換、そして数字への変換が必要」と述べ、象5頭もアリ5匹も同じドット5個で表せるよう具体→抽象の橋渡しを丁寧にすることを提言しています。このように、初学の算数では具体物操作を大事にしつつ、最終的には数字という記号で考えられるよう支援するのが家庭学習のポイントです。
▶︎具体例: 計算の習得では、例えば「今日はリンゴ模型を使って足し算の意味を理解 -> 明日は絵(○で描いたリンゴ)を見て計算 -> 最後は数字だけのドリルを解く」といった3段階を踏むと定着しやすくなります。また習慣化として、食後10分だけ勉強タイムを設けたり、毎朝登校前に1問解く約束をする家庭もあります。短くても毎日の積み上げで、「宿題以外も勉強する」習慣が自然と身につきます。どんな学習でも、できたときはハイタッチ&大げさに褒めましょう。成功体験の積み重ねが、子供の学習意欲を長続きさせます。
親御さんへのアドバイス: 勉強を見ていると、つい「なんでできないの?」と言いたくなる場面もあるでしょう。そこをグッとこらえ、代わりに「どう考えたのか教えて?」と聞いてみてください。お子さんの考えのプロセスが分かれば、適切なヒントを与えやすくなります。また、学校で習っていない先の内容を焦って詰め込む必要はありません。基礎基本の徹底(特に計算と読み書き)が1年生時点では最重要です。
忙しい保護者向け: 時間が取れない日は、市販のドリル1ページでも十分です。寝る前5分に今日習ったことを簡単に質問するだけでも効果あり。「今日習った足し算、○○ちゃん問題出してみて!」と逆に出題してもらうのもいいですね。親子の短いコミュニケーションが、子供の「もっとやりたい」を引き出します。
単元別練習問題&解説(各単元3問、最後に答え)
各単元の理解を深めるための練習問題です。お子さんと一緒に取り組んでみましょう。問題文はやさしい言葉で書いてありますので、お子さん自身に読ませてもOKです。カッコ()に入る答えを考えて、式や考え方もできる範囲で話し合ってみてください。すぐ下に解説がありますが、まずは自力でチャレンジさせてあげてくださいね(答えは記事末にもまとめてあります)。
数と計算:練習問題
- いくつといくつ(合成・分解) – みかんが全部で 5 こあります。お皿Aに3こ、皿Bに( )こ置くとちょうど5こになりました。( )に入る数はいくつ?
- 解説: みかん5このうち、3こを皿Aに置いたので、残りが皿Bの数です。「5は3といくつ?」という問題なので、5−3を計算します。5−3=2 なので答えは 2。式は 5=3+2 と表せます。お皿AとBの個数を合わせると 3+2=5 になり、確かにちょうど5こです。
- 繰り上がりの足し算 – 9 + 5 を計算しましょう。ポイント:「まず9に( )を足して10をつくる。」(式と答えも書きましょう)
- 解説: 9に1を足すと10になります。5を 1と4 に分け、9+1で10、残り4を足して14です。式で書くと 9 + 5 = 14。
(考え方):「あと1で10だから、5を1と4にわけて 9+1=10、10+4=14」となります。
- 解説: 9に1を足すと10になります。5を 1と4 に分け、9+1で10、残り4を足して14です。式で書くと 9 + 5 = 14。
- 繰り下がりの引き算 – 12 − 9 を計算しましょう。ヒント:「12を( )と( )に分けて考える」。
- 解説: 12を 10と2 に分けて考えます。10−9=1 に、残りの2を足して答えは 3 となります。式は 12 − 9 = 3。
(考え方):「12を10と2に分け、まず10から9を引いて1、あと2を足して1+2=3」です。減加法で考える場合、「9に3足すと12になるから答え3」と捉えてもOKです。
- 解説: 12を 10と2 に分けて考えます。10−9=1 に、残りの2を足して答えは 3 となります。式は 12 − 9 = 3。
図形:練習問題
- 形さがし – 次の中からころがせるものをぜんぶえらびましょう。
ア: サイコロ(立方体のサイコロ) イ: ビー玉(まり) ウ: 缶ジュース(円柱) エ: 移動ポケット(四角いポーチ)- 解説: ころがせるのは、まるい面を持つ形です。イ:ビー玉(まんまるなので転がる)と ウ:缶ジュース(円柱は側面が曲面なので転がります)が正解です。ア:サイコロや エ:四角いポーチは角ばっているので、そのままでは転がりません(少し傾けてもゴロゴロ転がる動きにはなりません)。身近な立体の特徴として、球や円柱は転がり、直方体/立方体は転がらないことを確認しましょう。
- スタンプで出る形 – 丸いふたをした箱をインクにつけて紙にスタンプしました。紙にうつった形は次のどれでしょう?
① しかく(四角形) ② さんかく(三角形) ③ まる(円)- 解説: 丸いふたを押せばまる(円)の形が映ります。したがって答えは ③ まる(円)です。箱のふたが円形=平面図形の円ということですね。同様に、サイコロの面をスタンプすれば四角形、三角定規の面なら三角形が映るはずです。
- 形の名前 – 下の図は、おうちにある形を黒いかげにしたものです。それぞれ何という形か書きましょう。
- 📐(図:三角定規の影)… ( )
- 🔵(図:おはじきの影)… ( )
- 解説: 三角定規の影は三角形です。おはじきの影は円(まる)です。1年生ではまだ「正三角形」など詳しい分類は習いませんが、とがった角が3つあれば「三角(さんかく)」、まるければ「まる」と、大まかに捉えられればOKです。
長さくらべ:練習問題
- 直接くらべ – 太郎くんは15cmのえんぴつと12cmのクレヨン、どちらが長いか比べたいです。正しい比べ方を次から選びなさい。
A. ふたつを斜めに交差させて持ち比べる B. ふたつの端っこをそろえてまっすぐ並べる- 解説: 長さ比べは端と端をきちんとそろえて、一直線に並べるのが正しい方法です。したがって B が正解です。Aのように斜めに交差させると目の錯覚もあり、正確な比較はできません。
- 間接くらべ – リボンAとリボンB、どちらが長いかを間接比較で調べます。何を使うとよいですか?最も適切なものを答えましょう。
- 解説: 離れた場所にある物や、柔らかいリボン同士を比べるにはひも(糸)やメジャーのようなものが便利です。ここでは「ひも」を使うのが適切です。リボンAの長さをひもに写し取り、それをリボンBに当てて比べることで間接的に比較できます。※メジャーは1年生未習ですが、原理は同じです。
- ○○何個分 – 花子さんの机のたての長さは、花子さんの手のひら4つ分でした。では横の長さが花子さんの手のひら8つ分の場合、横とたてではどちらが長いですか?
- 解説: 同じ「花子さんの手のひら」を単位にしています。縦は4手分、横は8手分なので、横の方が長いことがわかります。4と8を比べればOKですね。答え:横の長さの方が長いです。
かさくらべ:練習問題
- 見た目にだまされないで – AとB、2つの入れ物に同じオレンジジュースが入っています(見た目はBの方が高さがあります)。どちらが多く入っているか調べるにはどうすればよいですか。正しい方法を選びましょう。
a. AとBのジュースを同じ大きさのコップにうつしてくらべる
b. 見た目で高さがあるBの方が多いと判断する- 解説: a のように、共通の容器に移し替えて比べるのが正しい方法です。bは誤りです。背が高くても容積が小さい場合もあるので、実際に移し替えることで正確に比較できます。これは容量の保存を確かめる基本的な活動ですね。
- ○杯分で比較 – コップAは小さいカップで6杯、コップBは同じカップで4杯の水が入りました。どちらがたくさん入りますか?
- 解説: 同じ小さいカップ(任意単位)で測った結果、コップAは6杯、コップBは4杯でした。6杯 > 4杯なので、コップAの方がたくさん入ると言えます。数字で比べると一目瞭然ですね。
- 水を移そう – ビンに入った水をボウルに全部移したら、水はボウルの半分以下の高さにしかなりませんでした。このことから言えるのは次のどれですか。
① ビンとボウルの水の量は変わらない ② ビンよりボウルの方がたくさん水が入る ③ 移し替えは意味がない- 解説: ビンの水をボウルに移したら半分以下にしかならなかった=ボウルはビンより容量が大きいことを示しています。従って ② 「ボウルの方がたくさん水が入る」が正しい判断です。①は量自体は同じ水ですが、文脈からは容量比較の話なので不適。③は誤りです。実際、移し替えてみたからこそ容量差が判明したのです。
とけい:練習問題
- 何時かな? – 短い針が7と8の間、長い針が12を指しています。今は何時でしょう?(○時と答えます)
- 解説: 長針が12なので「ちょうど○時」です。短針は7と8の間にあるということは、まだ8時にはなっていないことを意味します。従って 「7時」ちょうどとなります。短針が数字の間にあるときは、直前の数字を読む約束でしたね。
- なんじはん? – 長い針が6、短い針が3と4の間にあります。このときの時刻を答えましょう。
- 解説: 長針が6なので「○時半」です。短針は3と4の間にあるので、3時を過ぎて4時になる途中ですね。したがって 「3時半」となります。3と4の間=3時台ということです。
- 長針の場所 – 「○時半」のとき、長い分針は文字盤のどこ(何の数字)を指しますか?
- 解説: 「半」は30分を意味し、アナログ時計では長針が6を指す位置です。これをしっかり覚えておきましょう。答えは 「6」のところです。
文章題:練習問題
- 足し算 or 引き算? – 「ケーキが3つあります。2つ買ってきました。全部で何個になりましたか。」この問題は足し算と引き算のどちらで計算しますか?式も書きましょう。
- 解説: ケーキが増えています(買ってきた)ので、足し算で考えます。元の3個に新たな2個を合わせるので、式は 3 + 2 = 5 となります。答えは5個です。文章中の「買ってきた」は量を追加するキーワードですね。
- 引き算の3パターン – 次の文章題のうち、引き算で解けるものには○、違うものには×をつけましょう。
a. 「りんごが5個ありました。2個食べたら残りはいくつ?」
b. 「赤い風船5個、青い風船7個。青はいくつ多い?」
c. 「みかんが3個残っています。2個食べる前は何個あった?」- 解説:
a. ○ – 典型的な「残りはいくつ」(求残)問題で、5−2 で解けます。
b. ○ – 「どちらがいくつ多い?」(求差)の問題で、7−5=2 の引き算で差を求めます。
c. × – これは隠れた加算(求補)の問題で、実は足し算で解くタイプです。「残り3個は全体の一部で、食べた2個を戻すと元の数になる」ので 3+2=5 となります。引き算で 5−2=3 としてしまうと、ちょうど逆の式で間違いになります。
- 解説:
- 図で考えよう – 「はなこさんはシールを4枚持っていました。ともだちに何枚かもらって、ぜんぶで9枚になりました。ともだちにもらったシールは何枚ですか。」
上の問題は難しいので、図を書いて考えてみましょう。式と答えも書いてください。- 解説: はなこさんが持っていたシール4枚と、もらったシール?枚を合わせて全部で9枚になったと読めます。図としては、□■■■■■■■■(四角4個とあとに?で合計9個になる図)など書き、「4と何かで9」と捉えます。求めるのはもらった枚数なので、9から4を引くと求まります。式は 9 − 4 = 5、答えは 5枚 です。
(考え方):「はじめ4枚、もらって9枚になった」ということは、増えた分がもらった枚数です。増え幅 = 9−4 = 5 です。
- 解説: はなこさんが持っていたシール4枚と、もらったシール?枚を合わせて全部で9枚になったと読めます。図としては、□■■■■■■■■(四角4個とあとに?で合計9個になる図)など書き、「4と何かで9」と捉えます。求めるのはもらった枚数なので、9から4を引くと求まります。式は 9 − 4 = 5、答えは 5枚 です。
答え
数と計算: (1) 2 (2) 1を足して10を作り、答え14 (3) 10と2に分け、答え3
図形: (1) イとウ (2) ③ まる(円) (3) 三角形、円
長さくらべ: (1) B (2) ひも (3) 横の長さ
かさくらべ: (1) a (2) コップA (3) ② ボウルの方がたくさん入る
とけい: (1) 7時 (2) 3時半 (3) 6
文章題: (1) 足し算、3+2=5 (2) ○, ○, × (3) 9−4=5(答:5枚)
つまずき診断表(症状→原因→打ち手)
お子さんの様子から考えられる「つまずき」を早期発見しましょう。症状に応じた原因と、すぐ試せる対処法(打ち手)を一覧にしました。
| 症状(お子さんの様子) | 考えられる原因 | すぐできる打ち手(30秒〜) | 継続練習アイデア |
|---|---|---|---|
| いつまでも指を折って数えている (例: 5+2も指で数) | 数の分解が未定着。数を丸暗記せず、1つ1つ足している段階。 | 指を使わずにできた簡単な計算(+1や+0など)を全力で褒める。「指なしでできたね!」と成功体験を刻む。 | 5の合成・10の補数の徹底反復。 例: カードゲームや百玉そろばんで1と9/2と8…を瞬時に言えるよう練習。 |
| 繰り上がり計算でいつも間違う (例: 7+5=712と書いた) | 位取り(10のまとまり)の誤解。繰り上がりで桁が変わることを理解していない。あるいは補数が曖昧。 | ブロック10個で「10になると束になる」デモを。一の位9+1で束が1つでき、十の位に移る様子を視覚化。 | 繰り上がり特訓: 9+2, 9+3, …9+9 や 8+3,8+4… のカードを集中的に練習。「あといくつで10?」を口グセに。 |
| 繰り下がり引き算でミスが多い (例: 12−9=7と答える) | 減加法の混乱。引くのに足す発想が腑に落ちていない。または10から引くステップ漏れ。 | おはじき12個から9個取り除く実演を一緒に。 結果3個になる体験を再確認し、「12−9=3だね」と事実を認識させる。 | 隠れた数あてゲーム: 10の中に隠した数を当てる遊びで減法の逆=加法を感覚化。 例: 「10のうち見えないのはいくつ?」を繰り返す。 |
| 文章題で足し引きの判断をよく間違える | 文の意味読み取り不足。キーワードに頼りすぎ、状況イメージができていない。 | 一緒に絵を描く。親子で問題文の場面をお絵描き→「この絵ならどう計算する?」と聞く。視覚から式にアプローチ。 | 類題演習: 各パターンの文章題(合併・追加・求残・求差・求補)を数多く経験。絵図・テープ図を描く習慣づけ。 |
| 時計の短針を間違える (例: 4時半を「5時半」と読む) | 短針の読み方のルール未理解。半のとき次の数字に近づく性質を誤解。 | 時計板を使い短針劇場:「短針くんはゆっくり歩いて次の数字に向かってる。でもまだ次の時間じゃない」と物語風に説明。 | 生活と結び付け: 毎日「今何時?」とアナログ時計で聞く癖付け。特に半のときに「◯時半だね」と声掛け習慣。デジタル表示との照合で補強。 |
| 宿題以外の勉強を嫌がる | 習慣化不足 or 達成感不足。勉強が苦痛なものと思っている可能性。 | 時間を5〜10分に短縮してみる。「これだけやったらおしまい!」と見通しを与える。終わったら笑顔で褒める。 | ゲーム性導入: ストップウォッチで「5分チャレンジ計算」「カードめくりで答え合わせ競争」など遊び要素を取り入れる。ごほうびシールも検討。 |
ミニ用語集(算数重要キーワード)
- 繰り上がり / 繰り下がり: 足し算で答えが10以上になる時に位が上がること / 引き算で答えが0未満(マイナス)になりそうな時に一つ上の位から繰り下げること。1年生では「10のまとまりを作って繰り上げる/10から引いて繰り下げる」という考え方で学ぶ。
- 10の補数: 「合わせて10になる組み合わせ」のこと。例: 1と9, 2と8, 3と7, 4と6, 5と5。繰り上がりや繰り下がりの計算で超重要(暗記できると計算が速く正確になる)。
- 減加法: 引き算を考えるテクニックで、減法を加法に置き換えて考える方法。例えば「13−9」は「9にいくつ足せば13?」と考え、答え4と求める。1年生でも繰り下がり引き算の説明として登場。
- 直接比較 / 間接比較: 長さやかさを比べる方法。直接比較は物同士を直接並べて比べること。間接比較はひも・さし棒・同じ容器など媒介物を使って間接的に比べること。1年生では両方経験する。
- 任意単位: 長さ・かさなどを測るときの非標準の単位(メートルやリットルでなく、身近な物)。例: 「この机の長さはえんぴつ7本分」。1年で任意単位による測定感覚を育て、2年でcmやmなど標準単位を導入する。
参考文献・出典
- 【学習指導要領】文部科学省: 小学校学習指導要領解説 算数編(平成29年告示)第1学年の目標・内容mext.go.jpmext.go.jpmext.go.jpmext.go.jp
- 【教科書】東京書籍: 新編 新しい算数 1年 年間指導計画・指導案(令和6年度版)ten.tokyo-shoseki.co.jpten.tokyo-shoseki.co.jpten.tokyo-shoseki.co.jpten.tokyo-shoseki.co.jp
- 【教育資料】鹿沼市立西小学校だより: 算数の苦手な子のために(計算すること)part2(2019) – 指計算からの脱却と具体→半具体→抽象への指導kanuma-school.ed.jpkanuma-school.ed.jp
- 【家庭学習ガイド】りんこ先生: 「算数が苦手」にしない!小学校1年生のつまずきポイントと対策方法(2025)shougakusei-tsushin-kyoiku.comshougakusei-tsushin-kyoiku.comshougakusei-tsushin-kyoiku.com
- 【教育技術】小学館: 小学1年生の勉強の内容は?家庭学習のポイント(2024) – 家庭学習時間と習慣づけshopro.co.jpshopro.co.jp
- 【Google検索品質】Google Search Central: Helpful content: People-first content – 教育分野におけるE-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)の重視shougakusei-tsushin-kyoiku.comcms.oklab.ed.jp
- 【Google検索動向】Google 開発者ブログ: 構造化データの最近の変化(2023年8月) – FAQリッチリザルトの表示制限developers.google.com、How-toリッチ結果の廃止developers.google.com
- 【Core Web Vitals】Screaming Frog (2023): How To Audit Core Web Vitals – 良好なCWV指標: LCP 2.5秒以内・INP 200ms以内・CLS 0.1以下screamingfrog.co.uk。今後INPがFIDを代替web.devweb.dev。
- 【構造化データ】Google Search Central: Practice Problem (Quiz)
(教育Q&A構造化データ) – 英語圏限定の小問リッチリザルトdevelopers.google.com(日本語では非対応)。Math Solver構造化データは公式計算サイトのみ使用可searchengineland.com。
※本記事は、教科書や文科省資料など一次情報を参照して作成しています。お子さんの学習状況に応じて内容を取捨選択し、無理のない範囲でご活用ください。教育現場の最新動向や検索品質にも配慮し、2025年時点の情報でまとめています。(初出: 2025年8月)
