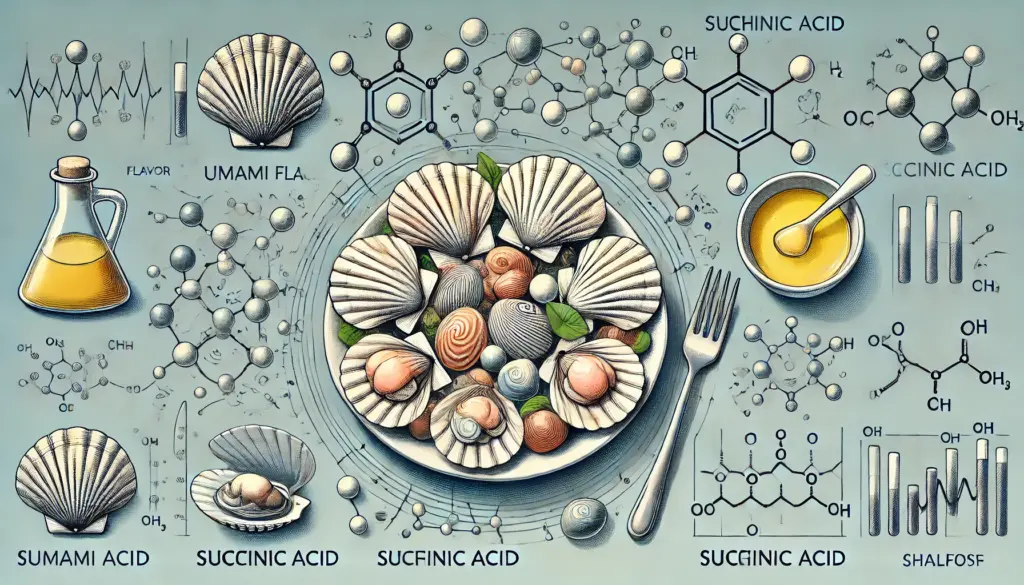
導入
旨味(うま味)はグルタミン酸やイノシン酸などによって生み出される第五の基本味として知られます。しかし近年の研究で、ホタテやアサリなど貝類の旨味の特徴を生み出す有機酸「コハク酸(succinic acid)」も、うま味に寄与する重要な成分であることが明らかになってきました。本記事では、コハク酸がどのようにうま味味覚に影響を与えるのか、味蕾(みらい)における受容体との関係、料理・食品加工への応用例、そして最新の科学的知見に基づく研究動向について詳しく解説します。専門的な内容を盛り込みつつも分かりやすく、日頃の料理に活かせる提案まで紹介します。
コハク酸とは何か?
コハク酸は二価の有機酸で、琥珀(こはく)から初めて抽出されたことにちなみ命名されました。食品中では発酵や熟成の過程で生成し、調味料の添加物としては「コハク酸二ナトリウム」の形で利用されます(食品添加物番号E363)。特にホタテや貝柱、アサリなどの貝類に豊富に含まれることで知られ、これらの食品の独特の風味に深みを与えています。例えば乾燥ホタテ貝柱にはグルタミン酸などのアミノ酸に加えコハク酸が大量に含まれ、貝のだし特有の濃厚な旨味を形成します。また、一部のキノコ類(アミガサタケ等)やチーズなどの熟成食品にもコハク酸が蓄積し、隠し味的な旨味要素となっています。
コハク酸とうま味味覚の関係
コハク酸は「第二の旨味成分」とも言える存在です。グルタミン酸ナトリウム(MSG)のような典型的な旨味物質と比べ、コハク酸の味わいはわずかに酸味・渋みを帯びていますが、それでも明確に旨味様の味覚を引き起こすことが報告されています。実際、Succinate(コハク酸イオン)は貝類の旨味の鍵となる成分で、グルタミン酸による旨味と類似した濃厚で持続性のある旨味を示すものの、後味にわずかな渋みが感じられることが指摘されています。この独特の風味は和食で「貝の旨味」として昔から認識されてきました。
近年の研究によって、コハク酸が旨味としてどの程度寄与するか定量的にも明らかになっています。Maら(2020年)の研究では、ホタテなどに豊富なコハク酸二ナトリウム(WSA)が海産食品の旨味に寄与する主要成分であることが確認されました。この研究では、二点比較試験法によりWSAの旨味強度をグルタミン酸(MSG)と比較し、その濃度と強度の関係を解析しています。結果、中性付近のpH(約7.5)で適度な塩濃度(Na^+ 0.1%)がある条件下でWSAの旨味強度が最大となり、しかも熱に対して安定であることが示されました。これはコハク酸が加熱調理や食品加工の過程でも旨味効果を発揮しやすいことを意味します。また、熟成卵黄(ピータン)に関する研究では、コハク酸が遊離アミノ酸や核酸と並んで旨味寄与度(TAV)の高い物質であることが示され、単独でも旨味を強く誘発する要因になり得ると報告されています。以上のように、コハク酸はグルタミン酸ほど有名ではないものの、科学的に見て確かに「旨味」を感じさせる物質なのです。
味蕾受容体とコハク酸のメカニズム
味を感じるメカニズムは舌の味蕾にある味細胞の受容体によって決定されます。五基本味の中で旨味を感じる受容体として知られているのがT1R1/T1R3受容体(Gタンパク質共役受容体の一種)です。これはアミノ酸系の旨味物質(グルタミン酸など)を検知し、特に5’AMPや5’IMPといった核酸系旨味物質が共存するとシナジー(相乗効果)で強い信号を送ることが知られています。この仕組みにより、昆布のグルタミン酸と鰹節のイノシン酸を合わせ出汁にすると旨味が飛躍的に増す現象(いわゆる「旨味の相乗効果」)が説明できます。しかしコハク酸の場合、その受容体メカニズムは長らく不明でした。グルタミン酸のようなアミノ酸ではないため、T1R1/T1R3が反応しているのかどうか議論があったのです。
GPR91:コハク酸受容の新発見
最新の研究により、コハク酸の味を感じる新たな受容体としてGPR91が浮上しました。GPR91は元々体内でコハク酸をリガンドとするオーファン受容体(SUCNR1)として知られていましたが、2025年にKitajimaらの研究グループが舌の味蕾細胞にもGPR91が発現していることを発見しました。彼らは培養細胞に様々な候補受容体を発現させてコハク酸による応答を調べた結果、GPR91が有力な候補であると突き止めています。さらにGPR91の活性化と人の味覚評価を関連付ける実験を行い、コハク酸の味覚がこの受容体の作用に依存することを示しました。具体的には、GPR91を阻害するとコハク酸の呈味強度が低下し、逆に活性化すると「貝の旨味」に似た味の知覚が生じることが確認されています。この成果は、コハク酸による旨味様の味わい(「貝味」とも称される風味)が、グルタミン酸とは異なる経路で感知されている証拠と言えます。つまり、人の味覚システムには複数の旨味受容メカニズムが存在し、コハク酸は専用の受容体を介して旨味情報を脳に伝えているのです。この発見により、旨味の定義や味覚の分類に新たな知見が加わり、今後「第六の味覚」として議論される可能性も指摘されています(現時点では一般に旨味の一種と捉えられています)。
料理・食品加工への応用例
コハク酸の旨味特性を活かせば、料理のコクや風味を一層高めることができます。実際、食品業界ではコハク酸二ナトリウムを旨味調味料として利用する事例があります。例えばインスタント食品やスナック菓子の成分表示に「コハク酸Na」と書かれていることがありますが、これは旨味と酸味のバランスを調整する添加物です。また、貝由来のエキスはコハク酸を多く含むため、家庭でも活用しやすい調味料として人気があります。市販品では乾燥ホタテ貝柱を濃縮した「ホタテエキス」や、アサリ等のエキスをブレンドした「貝柱だし」の顆粒などが手に入ります。これらをスープやソース、鍋料理に少量加えるだけで、深いうま味とコクが得られます。グルタミン酸系の昆布だしや醤油の旨味にプラスしてコハク酸由来の貝の旨味を加えることで、味に重層的な広がりが生まれます。特に魚介系ラーメンスープやシーフード料理では、コハク酸の旨味が全体の美味しさを底上げしているのです。
食品加工の分野でも、コハク酸の特性は有用です。前述の研究が示すように、コハク酸二ナトリウムは加熱による分解や変質を受けにくいため、缶詰やレトルトなど高温殺菌が必要な製品の風味付けにも適しています。またpHによる影響も比較的少なく、弱アルカリ~中性条件で安定して旨味を維持できることから、加工食品中で他の成分と組み合わせても効果を発揮しやすいのが利点です。例えば発酵食品では乳酸菌が産生する有機酸の一部としてコハク酸が生成され、チーズでは熟成中に増加したコハク酸が旨味を支えるとの報告もあります。このようにコハク酸は自然由来の旨味強化素材として、調味料開発やフードテック分野でも注目されています。
最新の研究動向(2024年まで)
コハク酸と旨味に関する研究はここ数年で飛躍的に進展しました。2020年以降、食品化学の分野で相次いで発表された研究により、その味覚特性の定量評価や呈味メカニズムの解明が進んでいます。特に2020年のMaらの研究は、コハク酸二ナトリウムの旨味強度を科学的に示した点で画期的でした。そして極め付けとして2024年末〜2025年初頭に報告された北島らの研究が、味蕾におけるGPR91受容体の関与という新発見をもたらしました。この発見は各種メディアや学会でも注目を集め、今後の味覚研究のホットトピックとなっています。また、旨味関連の総説論文でもコハク酸の存在感が増しており、旨味化合物の一つとしてチーズやキノコ、肉類での役割が再評価されています。例えば最近のレビューでは、「コハク酸とテアニンはMSGとは異なるプロファイルながら旨味類似の風味を持つ」と紹介され、動植物食品中の風味貢献物質として言及されています。これは従来グルタミン酸や核酸ばかりに注目していた旨味研究が、多様な化合物にも目を向け始めたことを意味します。
こうした動向を受け、食品メーカーもコハク酸を含む旨味素材の開発に乗り出しています。天然素材からの抽出技術や発酵生産技術が進み、より効率的にコハク酸リッチなエキスを得る試みも報告されています。今後は、コハク酸と他の旨味物質との相乗効果の有無や、味覚以外の生理機能への影響(例えば唾液分泌促進や消化吸収への寄与)など、研究の幅がさらに広がっていくでしょう。最新の科学的知見は、我々が日々感じる「美味しさ」の裏側にあるメカニズムを一層鮮明にしてくれるはずです。
結論と読者への提案
コハク酸は、グルタミン酸に次ぐもう一つの旨味の担い手として重要な役割を果たしています。貝類の濃厚な旨味や、発酵食品の奥深い風味の陰には、この有機酸の存在がありました。最新の科学研究により、その味覚メカニズム(専用受容体GPR91の関与)まで明らかになったことで、コハク酸の旨味は裏付けのある事実として認知されています。今後、旨味の定義がアップデートされる可能性すら感じさせる発見と言えるでしょう。
料理愛好家や食品開発に携わる方は、ぜひコハク酸の旨味を積極的に活用してみてください。例えば家庭でホタテやアサリの出汁を使う際には、グルタミン酸系の昆布出汁と合わせてみると、複合的な旨味の厚みを楽しめます。また、肉料理や野菜スープに少量の貝柱エキスを加えてみるのも一案です。コハク酸由来の旨味が加わることで、味にぐっと「深みとキレ」が生まれるでしょう。旨味の世界は奥深く、知れば知るほど料理の引き出しが増えます。是非この機会に、科学が証明したコハク酸の力を日々のキッチンで試してみてはいかがでしょうか。
関連調味料・書籍のご紹介
★コハク酸を手軽に味わえる調味料:「ホタテエキス」「貝柱だし」といった市販の貝類エキス調味料は、コハク酸由来の旨味を家庭で活用するのに最適です。例えばユウキ食品の「貝柱だし」や味の素KK「干し貝柱スープ」などは、お湯に溶かすだけで濃厚な貝の旨味を引き出せる便利なアイテムです。スープや炒め物、ソースの隠し味にぜひ活用してみてください。普段の料理がワンランクアップする心強い味方となるでしょう。
★旨味の知識を深めるおすすめ書籍:「旨味」についてさらに学びたい方には、以下のような書籍がおすすめです。
- 『うま味って何だろう』(栗原堅三 著、岩波ジュニア新書)― グルタミン酸や核酸からコハク酸まで、旨味の基本を平易に解説した入門書。日本人が発見した第五の味について歴史や科学的背景を学べます。
- 『いつもの料理がもっとおいしくなる!「うま味」パワーの活用便利帳』(青春出版社)― 旨味食材の組み合わせや相乗効果をレシピ付きで紹介。実践的なテクニックを通じて、家庭料理で旨味を最大限に引き出すコツが身につきます。
これらの調味料や書籍を活用し、ぜひ日々の食生活で旨味の奥深さとコハク酸の魅力を味わってみてください。知識を味方につければ、料理はさらに楽しく、美味しくなるはずです。
参考文献
- Ma, J. et al. (2020). Quantitative analyses of the umami characteristics of disodium succinate in aqueous solution. Food Chemistry, 316, 126336pubmed.ncbi.nlm.nih.govpubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
- Kitajima, S. et al. (2025). Involvement of GPR91 in the perception of the umami-like shellfish taste of succinate. Food Chemistry, 477, 143549referencecitationanalysis.comreferencecitationanalysis.com.
- Gao, B. et al. (2022). The changes of umami substances and influencing factors in preserved egg yolk: pH, endogenous protease, and proteinaceous substance. Frontiers in Nutrition, 9, 998448frontiersin.org.
- Nur Amaliah, N. et al. (2024). Trends in Natural Flavor Enhancer: A Review on Umami Compounds. BIO Web of Conferences, 96, 01013bio-conferences.orgbio-conferences.org.
- Umami Information Center (2017). Umami - What is Umami? (旨味情報センター「うま味とは何か」パンフレット)umamiinfo.com.




