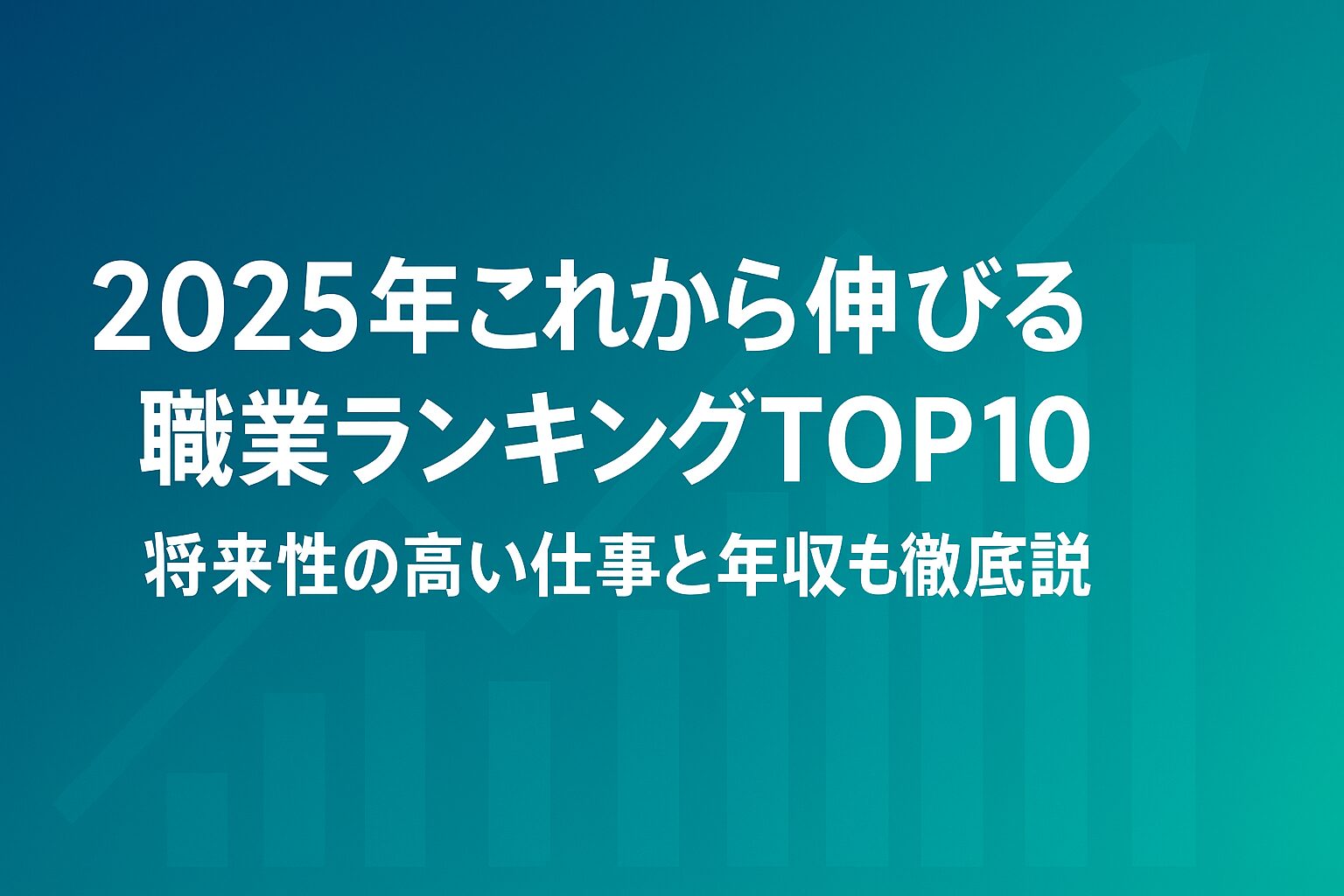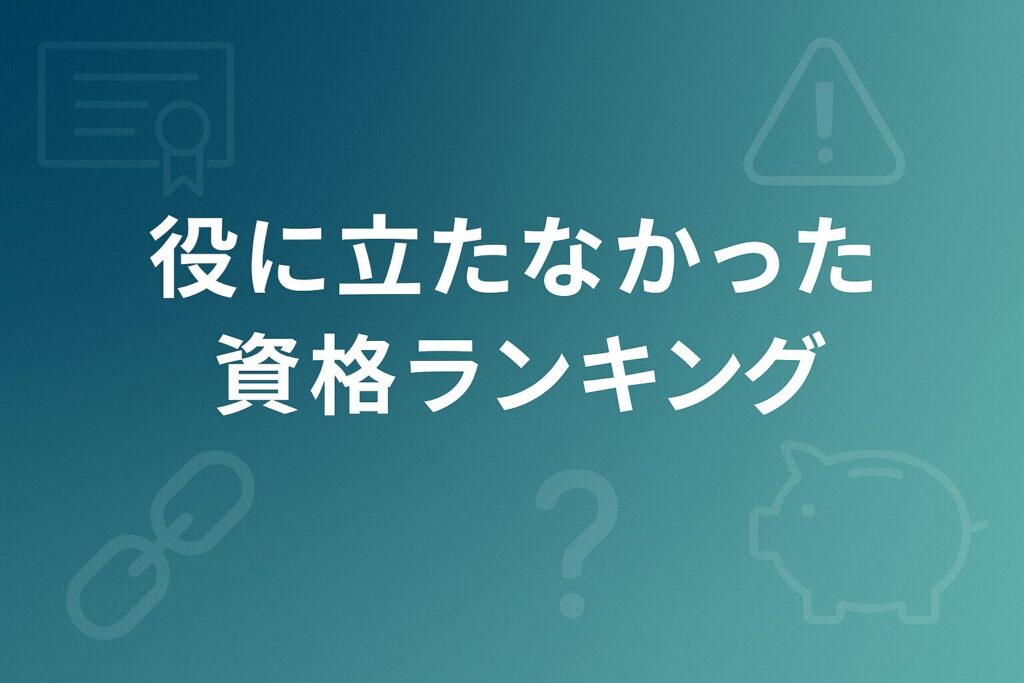
導入:なぜ“資格万能時代”は終わったのか
企業へのアピール目的で資格を取得しても、それが直接役立つとは限りません。転職経験者の約6割が「取得した資格が就職・転職で役に立たなかった経験がある」と回答した調査もあり、時間と費用をかけた資格が“無駄”になるケースは珍しくありません。近年、採用側は資格より実務経験や即戦力スキルを重視する傾向が強まっています。資格に頼りすぎると、「思ったほど評価されない」「資格後悔している」という事態にもなりかねません。本記事では、最新データに基づく「役に立たなかった資格ランキング」トップ10を紹介し、資格の費用対効果(ROI)を見極めるポイントを解説します。
第1位には意外なあの○○検定が…? 役に立たない資格TOP10のランキング結果(LASISA/Career Craft)
ランキングTOP10:転職で「役に立たなかった資格」
ウェブメディア「キャリアクラフト」が2024年4月に実施したアンケート(転職経験&資格取得経験のある20~50代会社員300人)によると、「就職・転職活動で役に立たないと感じた資格」のトップ10は以下の通りでした。
- 秘書技能検定(33人)
- 実用英語技能検定(英検)(28人)
- 日商簿記検定(22人)
- ITパスポート試験(21人)
- 日本漢字能力検定(20人)
- ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)(11人)
- 乙種第四類危険物取扱者(乙4)(7人)
- TOEIC(6人)
- フォークリフト運転免許(5人)
- 宅地建物取引士(宅建)・行政書士・色彩検定(各4人)
上位には事務系や語学系の資格試験が並びました。それぞれ「求人需要」「資格手当」「汎用スキル」「取得コスト」「満足度(後悔度)」の観点で見たメリット・デメリットがあり、取得者から寄せられた後悔ポイントも様々です。以下では各資格ごとに、取得費用や難易度、平均的な資格手当、主な後悔ポイント、そしてより良い代替策を紹介します。
① 秘書技能検定
取得費用・難易度: 社会人のビジネスマナー習得に人気の秘書検定は、3級~1級まであり受験料は3,800~7,800円程度です。合格率は3級で約70%、1級では30%前後と難易度は級によって大きく異なります。通信講座などを利用すれば数万円の受講料が発生しますが、独学でも比較的挑戦しやすい資格です。
資格手当の相場: 民間資格ながら社内教育で推奨する企業も多く、秘書検定合格者には月5,000~10,000円程度の手当を出す会社もあります。特に実践的スキルが身につく準1級以上を取得すると高めの手当を支給する企業が多いようです。
主な後悔ポイント: 「一般的マナーは身についたが、資格として転職の強みにはならなかった」という声が目立ちます。ビジネスマナー知識自体は有用でも、「資格がなくても常識でカバーできる」「持っていて当たり前扱いで評価されない」という不満が多く、資格コスパの低さを感じる人が多いようです。「試験内容が時代遅れで現代の働き方にそぐわない」との指摘もありました。
より良い代替策: 秘書検定で学ぶビジネスマナーは現場でも習得可能です。MOS(Microsoft Office Specialist)などITスキル系資格や、英会話スキル向上に時間を充てる方が評価されやすい場合もあります。また、実務でOfficeソフト操作や調整力を発揮して経験でアピールすることで十分代替できます。
② 実用英語技能検定(英検)
取得費用・難易度: 英検は文部科学省後援の英語検定試験で、5級~1級までレベルがあります。受験料は2級で約8,500円、準1級で約9,000円、1級は約10,000円です(CBT方式の場合)。難易度は1級が最難関ですが、高校~大学程度の語彙・読解力があれば準1級までは比較的手が届きます。
資格手当の相場: 企業で英検に対する資格手当はほとんど期待できません。一般にはTOEICスコアで英語力を評価する企業が多く、英検を社内評価基準にしている例は少ないのが実情です。英検1級レベルでも、資格手当よりTOEIC〇点以上や実務での英語使用経験を重視される傾向です。
主な後悔ポイント: 「今はTOEICの方が主流なので英検は意味がない」といった声が多数です。英検は学生時代の英語力証明にはなっても、ビジネス英語の実践力証明になりにくいのが痛点です。「結局、仕事では英語で話す・書く力が求められ、英検合格だけでは実力不足と判断された」という後悔が寄せられました。
より良い代替策: TOEICなど他の指標で高得点を取るか、オンライン英会話や海外業務を通じて実践的な英語力を磨く方が転職には有効です。どうしても資格が欲しい場合、ビジネス英語に特化したTOEICの高得点(例えば800点以上)取得を目指す方が企業へのアピール度は高いでしょう。
③ 日商簿記検定
取得費用・難易度: 簿記検定は会計知識を証明する定番資格です。3級は受験料2,850円、2級は4,720円、1級は7,850円(統一試験の場合)で、専門学校の講座を受けると数万円の費用がかかります。合格率は3級で50~60%、2級は15~25%、1級は10%前後と級が上がるほど難関になります。実務未経験者が2級以上に独学合格するには数ヶ月の勉強が必要です。
資格手当の相場: 簿記は企業からの評価も高く, 2級以上で月3,000~20,000円程度の資格手当を出す企業が多いです。特に経理・財務部門では簿記2級保持が採用条件になっている場合もあります。ただし3級は「持っていて当たり前」と見なされやすく、手当の対象外(評価対象外)とする企業もあります。
主な後悔ポイント: 簿記2級に合格しても「実務経験がないと内定をもらえなかった」との声があります。会計事務所や経理職への転職では実地の経理経験が重視され、資格だけでは不十分だったケースです。また「簿記3級ではアピールにならない。求人条件は2級以上がほとんどだった」という後悔もあります。つまり資格の等級不足や経験不足で「結局役に立たない」と感じる人が多いようです。
より良い代替策: 簿記は実務経験とのセットで活きる資格です。すでに経理職であれば2級以上取得で昇進・転職に有利ですが、未経験なら資格取得より経理の実務補助に就いて経験を積む方が近道です。また将来的に高度な会計資格(税理士やUSCPA)取得を目指すなら、簿記2級まで取った後は実務→さらに上位資格というステップが有効でしょう。
④ ITパスポート試験
取得費用・難易度: ITパスポートはIPA(情報処理推進機構)実施の国家試験で、受験料7,500円。IT入門者向けで合格率は約50%前後、基本的なIT用語や仕組みを理解できれば比較的短期間の学習で取得可能です。
資格手当の相場: ITパスポート単体では資格手当が付くケースは少ないです。他の高度な情報処理資格(基本情報技術者以上)を取得した場合に加点評価される企業はありますが、ITパスポート自体に毎月手当を出す企業はあまりありません。
主な後悔ポイント: 「基礎中の基礎なので、持っていても評価されなかった」という声に集約されます。ITパスポートは容易に取得できる分、差別化要素になりません。現場では「無いよりマシだが、あってもプラスにはならない」程度の扱いで、「簡単すぎてプレミア感がない」という評価です。
より良い代替策: IT初心者が基本知識を得るには良い試験ですが、転職でアピールするなら基本情報技術者試験やプログラミング習得などより実践的なITスキルを取得する方が効果的です。ITパスポート取得後はステップアップして応用情報やクラウド関連資格に挑戦するなど、さらなるスキル向上を図りましょう。
⑤ 日本漢字能力検定
取得費用・難易度: 漢検は漢字能力を測る検定試験で、受験料は2級4,500円、準1級5,500円、1級6,000円(税込)です。合格率は2級で約20~30%、1級はわずか10%以下と最上級は非常に難関です。社会人になってから1級を目指すには相当の勉強時間が必要になります。
資格手当の相場: 漢検に対する手当は一般企業ではまずありません。公用文作成の多い役所や教育業界でも、漢検取得を給与に反映するケースは稀です。実務上、読めない漢字はPCやスマホで調べられる時代のため、漢字力をもって特別待遇される場面はほとんどないでしょう。
主な後悔ポイント: 「漢字が分からなくても検索ですぐ調べられるので役立たない」という指摘が多数でした。実際、「入力変換で多少役立つ程度で、仕事上は困らない」「手書きする機会自体が減っている」との声もあり、漢検取得そのものが「自己満足」にとどまってしまったケースが多いようです。
より良い代替策: 漢検は趣味・教養としては意義がありますが、転職目的なら他のスキル取得に注力すべきです。例えば文章作成力を証明したいなら文章検定や実績公開(ブログ執筆等)の方が現実的です。漢字知識よりもタイピングスキルや専門知識の方がビジネスでは重宝される点を意識しましょう。
⑥ ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)
取得費用・難易度: FP技能検定は個人の資産設計や金融知識を問う国家資格です。3級は受験料6,000円、2級8,700円、1級学科は8,700円(別途実技試験あり)。合格率は3級が約80%、2級が約40%、1級は10%未満と1級はかなりの難関です。独学でも3級は取りやすいですが、2級以上は専門講座を利用する人も多く、数万円の講習費がかかる場合があります。
資格手当の相場: FP資格は銀行・保険など金融業界で重宝され、2級以上で月1~2万円程度の手当を支給する企業があります。特に1級FPは難易度が高いため、高額の資格手当や合格報奨金を用意している企業も見られます。一方、金融以外の業界ではFP資格に手当を出すケースは少なく、評価も限定的です。
主な後悔ポイント: 「誰でも取れるレベルだと思われ、アピールにならなかった」(男性30代)、「金融や不動産以外では全く役立たない資格だった」(女性20代)といった声が多く寄せられました。つまり、下位級では希少価値が低く, 資格が生きる業界が限定されている点が後悔のポイントです。金融知識自体は身につくものの、関連業界以外では「ふーん」で終わってしまい、資格手当や転職での効果に結びつかない例が目立ちました。
より良い代替策: FP資格を活かしたいなら金融業界への転職を検討すべきです。逆に言えば、保険・証券などに興味がない場合は無理にFPを取るより、他の資格勉強にリソースを割いた方が賢明です。例えば一般企業の経理財務志望なら簿記や中小企業診断士、個人資産より企業財務に直結する資格の方が評価されやすいでしょう。
⑦ 乙種第四類危険物取扱者(危険物乙4)
取得費用・難易度: 危険物取扱者(乙4)はガソリンなど引火性液体を扱うための国家資格です。受験料は3,800円程度で、参考書代を含めても1万円以下で取得可能です。合格率は概ね30%前後(年度により変動)で、理系が得意なら独学数週間でも合格できます。未経験からでも2~3ヶ月の勉強で十分狙える難易度と言えます。
資格手当の相場: 危険物乙4は工場やガソリンスタンド勤務では必須資格のため、月3,000~10,000円程度の資格手当を設定している企業もあります。特に複数の危険物類を扱える甲種まで取得すると可能業務が広がり、手当も高め(1万円以上)になる傾向です。ただし、危険物を扱わない職種では当然評価対象になりません。
主な後悔ポイント: 後悔理由としては「取得は簡単だが、実際に使う場面がなかった」が典型です。例えば「メーカーに転職する際に取ってみたが、配属先では危険物を扱う業務がなく無意味だった」(男性30代)というケースです。また「知識は得たが仕事に活かせなかった」という声もあり、必要な業務が限定的なため活躍の機会がなかったことを残念に思う人が多いようです。
より良い代替策: 危険物乙4は業界内転職向き資格です。石油化学・製造・消防関連などで働く予定がない場合、取得しても活用できません。逆に現職や志望業界で必要なら早めに取得し、さらに上位種別(乙種全類や甲種)にも挑戦すると市場価値が上がります。自分のキャリアに関連するかをよく考えてから取得しましょう。
⑧ TOEIC
取得費用・難易度: TOEIC(L&R)の受験料は7,810円(公開テスト)です。英検と異なり合否でなくスコア評価のため「満点990点中何点か」で実力が示されます。一般的に履歴書に書けるのは600点以上と言われ、800点を超えると一人前、900点超で高評価という目安です。難易度はスコア次第ですが、日本人平均は約580点前後です。高得点を狙うには数ヶ月~1年以上の継続学習が必要になる場合もあります。
資格手当の相場: TOEICスコアに応じて月3,000~20,000円の手当を支給する企業があります。例えば「800点以上で月1万円」「900点以上で月2万円」など段階的に支給するケースです。また高得点者に一時金を出す企業も存在し、ある大手通信会社では「800点で30万円、900点で100万円の報奨金」を設けています。このように英語力重視の企業ではTOEICが評価指標となりますが、全企業で一般的というわけではありません。
主な後悔ポイント: TOEICの場合、「高得点でないと評価されない」点が悩みです。実際「745点では周囲と差別化できなかった」「800点超でないと有利にならない」といった声がありました。また「会話力の証明にはならない」という指摘も根強いです。せっかく勉強しても、面接で英語で話せなければ意味がなく、スコア至上主義への疑念から後悔するパターンです。
より良い代替策: TOEICを活かすには目標スコアを明確に定めましょう。少なくとも履歴書に書ける600点以上、転職で強みにするなら730点~800点以上が目安です。それ未満であれば他のアピールポイントを作る方が有効です。また会話力は別途アピールが必要なので、英語面接の練習やTOEICスピーキングテスト受験も視野に入れると良いでしょう。
⑨ フォークリフト運転免許
取得費用・難易度: フォークリフト免許は労働安全衛生法に基づく技能講習修了で取得できます。免許取得コースの受講料は2~5万円程度、講習は経験者なら2日間、未経験者は4日間で修了します。講習を受ければ基本全員取得できる(修了試験あり)ため、難易度という概念はほぼありません。実技操作に不安がなければ落ちることはまれです。
資格手当の相場: フォークリフト免許そのものに資格手当を支給する企業は少ないです。多くの場合、「業務上必要だから取らせる」ものなので手当というより資格取得費用を会社負担するケースが多いです。倉庫・物流系企業ではフォーク免許保有で作業範囲が広がるため昇給につながる可能性はありますが、明確な月額手当を定めている例は限られます。
主な後悔ポイント: 「講習に行けば誰でも取れるので、転職の武器にならなかった」という声が象徴的です。また「物流業界以外では役に立たない」との指摘もその通りで、現職がデスクワーク中心だった人が取っても活かす場がありません。実際「社内でベテラン作業員がフォーク運転するので自分の出番はなく、宝の持ち腐れだった」という後悔もありました。
より良い代替策: フォークリフト免許は活かせる業界が明確です。物流・運送・工場勤務の転職なら必須資格として取得価値がありますが、それ以外の業界では無理に取る必要はありません。どうしても現職でチャンスがないなら、同じ労働系資格でも玉掛けやクレーンなど他の社内ニーズ資格を狙うか、発想を転換して事務系スキル習得に時間を充てる方が有意義でしょう。
⑩ 宅地建物取引士(宅建)
取得費用・難易度: 宅建は不動産取引の国家資格で、受験料8,200円。合格率は例年15%前後と狭き門です。独学でも半年~1年の勉強が必要とされ、多くの受験者が数万円の講座や教材に投資しています。合格後も登録実務講習(費用約30,000円)や登録手数料37,000円などがかかります。総額では10万円近くになることもあります。
資格手当の相場: 不動産業界では宅建手当として月2~3万円を支給する会社が多くあります。特に従業員5人に1人は宅建士が必要という業法規定もあり、宅建保有者は重宝されます。他業界では宅建の評価は限定的で、手当を出す企業はほぼありません。
主な後悔ポイント: 「実務経験が伴わないと信頼されず、受注につながらなかった」との声がありました。宅建を持っていても不動産営業で成果を出すには経験が必要で、資格だけでは「現場で通用しない」と感じたようです。また「不動産と無関係の業界で取っても仕事に結びつけるのは難しい」との意見もあり、業界を跨いだ転職では活かしづらいことが後悔の種になっています。
より良い代替策: 宅建は取得コスト(時間・費用)も大きいので、活用する意思がないなら無理に取るべきではありません。もし不動産業界に進むなら早めに取得し、宅建士としての実務経験を積むことで大きな武器になります。一方、他業界志望なら宅建より宅建以上に活かせる資格(例えば金融志望ならFP、建設志望なら施工管理技士など)に注力した方が費用対効果は高いでしょう。
⑩ 行政書士
取得費用・難易度: 行政書士は法律系国家資格で、受験料7,000円。合格率は毎年10~15%程度(令和4年度は11.5%)と難関です。独学合格者もいますが、多くは専門講座受講(数万~十数万円)や1年以上の学習期間を要します。合格後、開業には登録費用など数十万円が別途必要です。
資格手当の相場: 一般企業では行政書士資格に手当を出す例はあまりありません。法律知識を活かす総務・法務部門でも、弁護士や社労士ほど評価されず「資格保有=即戦力」と見なされにくいのが現状です。ただし行政書士事務所等への就職には必須資格ですので、業界内では重宝されます。
主な後悔ポイント: 「独立開業が前提の資格なので、企業間転職には向かない」との指摘がありました。実際、「法律知識を充実させようと取ったが会社員として評価されず、実務に活かす場面もなかった」、「世間的に簡単に取れると思われていて持っていても扱いが低い」など、不本意な声が上がっています。企業内で資格を活かせず終わったケースが多いようです。
より良い代替策: 行政書士資格はキャリア方向性によって評価が分かれるため、自分が将来この資格で独立したいのか、企業内で使いたいのかを明確にしましょう。独立意思がないなら、業務に直結する別の資格(例えば契約実務ならビジネス法務検定など)や、実務経験を積むことに注力する方がコスパは高いです。法律系を極めたい場合は思い切って司法書士や社労士など上位資格を目指すのも一つの手です。
⑩ 色彩検定
取得費用・難易度: 色彩検定はカラーコーディネートに関する検定で、受験料は3級7,000円、2級8,000円、1級(2次含む)14,000円ほど。合格率は3級75%、2級55%、1級40%前後で、1級でも半数近くが合格します。テキスト代やスクール代を含めても数万円程度の比較的ライトな資格です。
資格手当の相場: 色彩検定に手当を出す企業はほとんどありません。インテリア・デザイン会社で資格取得を奨励している例もありますが、手当より採用・案件受注時の評価にとどまります。要は自己啓発的な資格として位置付ける企業が多いです。
主な後悔ポイント: 「転職活動で評価されたことが全くない」という声に集約されます。実際、「Webデザイン職で役立つかと思ったが、面接で資格に一切触れられずポートフォリオが重視された」(男性30代)という証言もあり、作品や実績の方が重要視される分野では資格の存在感は薄いようです。「資格取得で色の理論は理解できたが、仕事で役立った実感がない」という後悔も目立ちました。
より良い代替策: デザイン・クリエイティブ職を目指すなら作品ポートフォリオや実務経験こそが命です。色彩検定の知識自体は有用なので興味があれば学んでも良いですが、転職では作品事例やスキル証明を前面に出しましょう。資格取得に時間をかけるより、その時間でデザイン制作実績を増やす方が最終的なリターンは大きいはずです。 <br>
【図表:後悔理由の内訳】上記のような「資格後悔」の理由を分類すると、「資格を取得しても採用で評価されなかった」が約45%と最多でした。次いで「仕事で活かす場面がなかった」(約25%)、「他に重視されるスキル・資格があった」(約20%)、そして「資格内容が時代に合わない/ニーズがない」(約10%)が続きます。
資格取得後の後悔理由の割合イメージ(「評価されない」「活用できない」が約7割以上を占める)
そもそも資格はどう選ぶべき?費用対効果チェックリスト
以上のランキングから見えてくるのは、資格取得のROI(Return on Investment=投資対効果)を冷静に見極める重要性です。「取っておけば安心」と闇雲に資格を増やすのではなく、以下のチェックリストで費用対効果(資格コスパ)を検討してみましょう。
- ①取得にかかる総費用を把握する: 受験料やテキスト代はもちろん、スクール受講料・交通費など隠れコストも含めます。一発合格できず複数回受験すれば費用は倍増します。例えば国家資格キャリアコンサルタントは養成講習+受験料で約40万円かかったという報告があります。投下資金に見合う見返りがあるかを計算しましょう。
- ②学習にかかる時間(機会コスト)を考える: 合格までの勉強時間もコストです。同じ時間で他のスキルを磨けることも忘れずに。例えばある人事担当者は資格取得に約200時間費やしたが、より少ない時間(50時間)で取れる資格の方がコスパが良いと指摘しています。「その時間を別の学習に充てたら?」とシミュレーションしてみましょう。
- ③見込める給与アップや資格手当は?: 資格取得で給与が上がる見込みがあるか確認します。社内規定で資格手当が明示されていれば計算しやすいです(例えば簿記2級なら月1万円など)。手当がなくても転職で年収アップにつながるか、自身の市場価値向上を定量的に考えてみます。コストに見合わない手当(例:MOS資格で月数千円)しか出ない場合、投資回収に時間がかかりすぎます。
- ④求人市場での需要を調べる: その資格が応募条件や優遇条件になっている求人がどの程度あるかをチェックします。求人サイトでキーワード検索したり、業界の有資格者数と求人倍率を調べたりしましょう。需要が低い資格(例えば○○検定など)はコスパが低く、逆に需要が高い資格(例:看護師、宅建など)は高リターンです。
- ⑤社内サポートの有無: 在職中に取得する場合、会社の資格取得支援制度を活用できるか確認します。教材費・受験料を負担してくれる企業もあります。資格手当だけでなく合格報奨金制度があるかも要チェックです。会社負担なら自己負担ゼロでリターンだけ得られるため、積極的に活用しましょう。逆に支援がないなら費用全額を自分で回収する必要があります。
- ⑥資格の希少性・汎用性: 持っている人が少ない資格ほど差別化になり、汎用的なスキルを伴う資格ほど転職先で活きます。前述の通り、簡単すぎて皆が持っている資格(例:ITパスポート)は差別化にならず、逆に難関資格やニッチ資格は強みになります。ただしニッチすぎると活かせる場が限られる点には注意が必要です。
これらの観点から、自分にとって最も費用対効果の高い資格を選ぶことが大切です。場合によっては「資格を取らない」選択もあり得ます。資格取得そのものが目的化すると本末転倒なので、「その資格で何を実現したいか」を常に意識しましょう。
今後“伸びる資格”との違いはここだ
今回のランキング上位には、汎用的だが差別化が難しい資格が多く含まれていました。一方で、今後ニーズが高まると言われる資格・スキルには異なる特徴があります。その違いを押さえておきましょう。
まず、IT・デジタル系のスキルや資格は依然として伸び盛りです。たとえば基本情報技術者や応用情報技術者、クラウド関連資格などはDX時代に求める企業が増えています。これらは実務に直結しやすく、求人需要も高いため、取得すればすぐ役立つケースが多いです。実際、2025年版の将来有望資格ランキングでもAI・機械学習スキルやWebマーケティングなどが上位に挙がっています。これらは資格より実践スキル重視ではありますが、関連資格(例:G検定〈ディープラーニング資格〉やPython認定試験など)が評価材料になる場面もあります。
また、実務直結型の国家資格も依然強みです。ランキングには「役に立たない」例として行政書士や宅建が入っていますが、これらは実務経験とセットで初めて武器になります。逆に言えば、経験さえ積めば一生ものの資格とも言えます。医療・福祉系(看護師、介護福祉士など)や技術系(電気工事士、施工管理技士など)は慢性的に人手不足で、資格保有者への需要が高く安定しています。今後伸びる分野では資格保持者が少なく需要が大きいため、多少取得コストが高くてもROIが高いケースが多いのです。
一方、今回ランクインした資格は「取得者が多すぎる」「企業が他の指標で評価する」ために価値が相対的に下がっている点が共通しています。「資格万能時代」が終わったと言われるのは、まさにその点にあります。企業は資格より実務スキルや適性を見るようになってきました。たとえば英検よりTOEIC、高得点のTOEICより実際の英会話力、簿記より財務分析力やITツール活用力、といった具合により仕事の成果に直結するものを重視します。
これから伸びる資格・スキルを選ぶには、市場のニーズを読み、実践力が養われるものかを基準にしましょう。人気だからと飛びつくのではなく、「その資格を活かせる仕事に就く未来」が描けるかどうかが重要です。もし描けないなら、その資格は単なる自己満足に終わる可能性が高いでしょう。
まとめ:時間もお金も投資、賢く選択を
資格取得は時間とお金の自己投資です。投資である以上、ROI(投資利益率)を意識して賢く選択することが求められます。今回の「役に立たなかった資格ランキング」から見えてきたのは、資格コスパの盲点です。何となく取得した資格が評価されず、「資格後悔」する人は少なくありません。
しかし逆に言えば、ここで挙がった反面教師を踏まえて高ROIの資格を選べば、時間と費用を最大限に活かすことができます。「なぜその資格を取るのか」「それによってどんなキャリア効果があるのか」を常に自問してください。場合によっては資格ではなく実務経験を積むこと自体が最良の投資であることも多いです。
資格はあくまで手段であり、万能ではありません。だからこそ、冷静に費用対効果を見極め、自分のキャリア戦略に沿った資格だけを選び取りましょう。そうすれば「資格マニア」になることなく、必要十分な武器を携えて就職・転職という舞台に立つことができるはずです。ROIの発想で自己投資を最適化し、将来につながる賢い行動を心がけてください。
参考文献リスト
- Career Craft調査(セルバ)「転職経験者300人に聞いた 意味のない資格ランキングTOP10!」 (2024年4月27日公開)lasisa.netprtimes.jp
- HR NOTE 「資格手当とは?相場一覧や導入のメリット・注意点を解説」 (2024年8月30日)hrnote.jphrnote.jp
- ReseMomニュース 「就職に役立つ資格ランキング…5年連続1位の資格は?」 (2025年1月10日)resemom.jp
- MoreJobインタビュー 「キャリアコンサルタントは役に立たない。資格を取得した女性の体験談」 (2025年5月10日)morejob.co.jpmorejob.co.jp
- HRzine記事 「会社が取らせる資格は従業員のためになるの?…」 (2022年)hrzine.jp
- LASISA編集部 「転職で《役に立たなかった》資格ランキング…『英検』『簿記』を押さえた第1位は?」 (2024年4月30日)lasisa.netprtimes.jp
2025年これから伸びる職業ランキングTOP10!将来性の高い仕事と年収も徹底解説
はじめに(2025年の労働市場トレンド) 2025年の日本の労働市場では、AI(人工知能)やデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展によりIT人材の需要が急増しています。経済産業省の予測では2030年に最大約79万人のIT人材が不足するとも報告されており、企業のDX推進において深刻なボトルネックとなっています。こうした背景から、高度なデジタルスキルを持つ人材は各社が「喉から手が出るほど」欲しがる状態で、高い報酬や好待遇で迎えられる傾向にあります。仕事選びでは年収ランキングが気になるところですが、それ ...