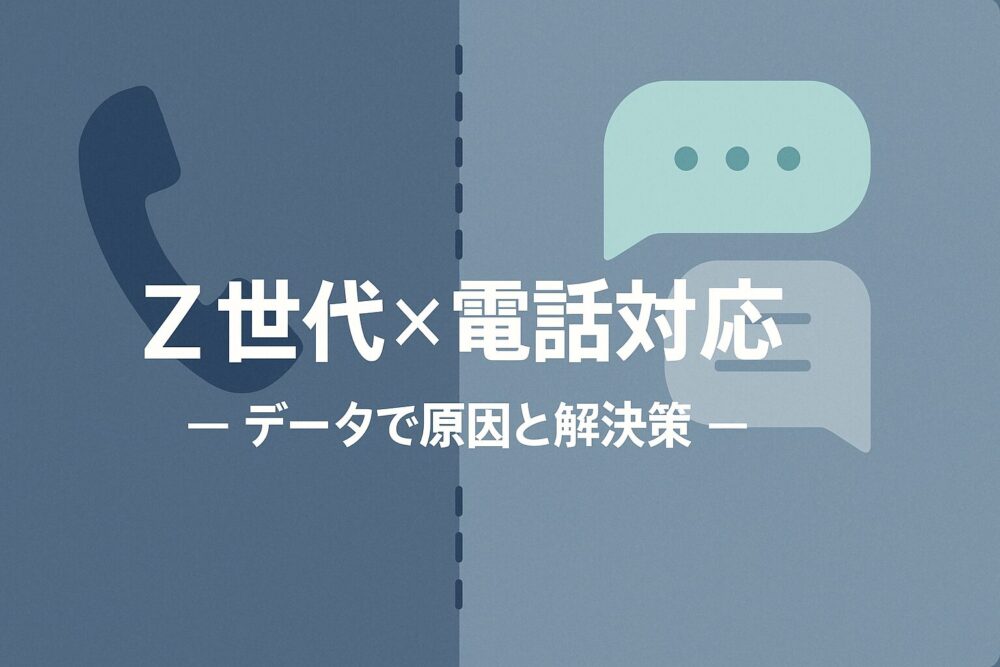
要約
Z世代の新入社員が会社の電話に出られない・出たがらない理由は、幼少期からデジタルネイティブ世代としてテキストコミュニケーション中心で育ち、固定電話や音声通話に馴染みが薄いことが大きな要因です。実際、最新調査では約5割の若手社員が電話対応を苦手と感じており、その理由は「電話マナーに自信がない」「普段使わないから」「家に固定電話がなかった」などが挙げられます。一方、企業側も電話対応を巡る課題(新人の離職リスクや在宅勤務時の電話運用)に直面しており、コロナ以降はメール・チャットへの移行や電話自動化が進んでいます。この記事では、世代間ギャップの背景と実態データを示しつつ、心理・経験・環境・運用・技術の5観点で原因を分析します。さらに、実務で成果が出る解決策として、個人レベルではロールプレイ研修やスクリプト整備、組織レベルでは代表電話の一次受け標準化やコールトリアージ、技術レベルではIVR(自動音声応答)やAIボットの導入まで3層の対策を網羅し、90日間の導入ロードマップとKPI指標も提示します。最後に実際の事例や反論へのQ&Aも紹介し、電話応対に過度に依存しないコミュニケーション体制への転換を提案します。
背景:世代間で変わる「電話」の役割
「電話」は世代によってその位置づけや感じ方が大きく異なります。現在20代前半~後半にあたるZ世代(1990年代後半〜2000年代生まれ)の多くは、子どもの頃からインターネットやSNSが身近にあり、コミュニケーション手段の主流がテキスト(文字)でした。一方、上の世代(昭和〜平成生まれの上司層)は電話(音声通話)がコミュニケーションの基本という価値観で育っています。この世代間ギャップが、職場での「電話」に対する認識のズレを生んでいます。
例えば、Z世代にとって見知らぬ電話番号から突然電話がかかってくること自体がストレスになり得ます。米国の調査記事でも「予告メッセージなしの電話は配慮に欠け、パニックを招く」という人が増えており、メッセージが当たり前になるほど予告なし電話への拒否感が強まっていると指摘されています。一方で「電話を怖がるなんて柔軟性がない」という意見もあり、電話エチケットがかつてないほど複雑化しているとの指摘もあります。つまり、電話を巡る価値観は社会全体でも変化・分岐しており、日本企業の職場でも同様の現象が起きています。
日本に目を向けると、新入社員が電話対応を嫌がる状況を指して「テルハラ(TELハラスメント)」という言葉まで生まれています。職場で電話が苦手な若手に電話応対を強要することがハラスメントだという問題提起です。東洋経済オンラインの調査では、22~29歳の若手の約3割が「テルハラ」という言葉を知っていたのに対し、30代以上では認知度が低く、この問題への関心にも世代差が見られました。記事中のコメントには「電話対応は職場で一番緊張する」「怒った客への謝罪電話で頭が真っ白になり、上司に嫌味を言われた。まるで罰ゲームだ」といった20代社員の悲痛な声も紹介されています。当たり前だった電話応対が、新人にとっては恐怖の対象になりつつある現状が浮き彫りです。
このように、世代間で「電話」に対する意味づけや感情がずれていることが背景にあります。上司世代にとって電話は「相手の顔が見えなくても即座に用件を伝えられる信頼の手段」であり、「営業・ビジネスの命」と考える向きもあります。一方、Z世代にとって電話は「通知音だけで心拍数が上がる」「なぜテキストで済まさないのか不思議」とすら感じるコミュニケーション手段です。このギャップを埋めずに「最近の若者は電話も満足にできないのか」と叱責することは、問題解決にならないばかりか、若手の心理的安全性を損ないかねません。まずは両世代の立場の違いを中立的に理解し、データに基づいて実態を把握することが重要です。
データで読む通話とテキストの利用実態(2023〜2025年)
この世代間ギャップを定量的に示すため、音声通話とテキスト(文字)の利用実態に関する最新データを確認しましょう。まず、日本の一般ユーザーのコミュニケーション手段全体の傾向として、テキスト利用の増加と通話利用の減少が顕著です。NTTドコモ・モバイル社会研究所の調査によれば、友人との日常連絡で「最も多く使う手段」が2014年には「テキスト」(メールやLINEなど)が約6割、音声通話が約3割でしたが、2025年にはテキスト約8割、音声通話は1割強まで低下しました。この10年でコミュニケーションの主役が完全に文字チャットに移行したことを示すデータです。
特に若年層のテキスト志向は顕著で、2025年調査では10代の約7割が「友人との会話はLINEなどメッセージが中心」と回答しています。対して70代では約3割が「音声通話が一番多い」と答えており、高齢層ほど通話依存が残っています。また10代では約3割が「直接会って話す」が多いと答えており、この層は電話より対面コミュニケーション志向もあるようです。いずれにせよ、少なくとも20代以下の若者にとって電話(音声通話)は主要なコミュニケーション手段ではなくなっている現実がうかがえます。
社会全体の傾向も同様です。株式会社クロス・マーケティングの調査(2024年、20~69歳男女1,100名)では、「普段のコミュニケーションでテキストのやり取りが多い」人が56.0%、対して「通話が多い」人は24.7%という結果でした。つまり全世代平均でもテキスト派が通話派の2倍以上いる状況です。特に20~40代では「電話で話すのが苦手」という人が3~4割と上位に挙がり、60代では1割未満しかいませんでした。若年層ほど「電話が苦手」と感じている割合が高いことがデータに表れています。知らない番号からの着信は出ない人が多い(全体で3~4割)という結果も出ており、用件が急ぎでない限り電話を避ける傾向がうかがえます。
さらに、Z世代が育った環境を考えると「固定電話離れ」も指摘できます。総務省『通信利用動向調査』でも固定電話の世帯保有は年々低下しています。民間調査(2024年、n=1,100)では“自宅に固定がない人”43.8%(=保有56.2%)と報告されています。クロス・マーケティング調査でも「自宅に固定電話がない人」が全体の43.8%に上り、20代ではもっと高率と推察されます。固定電話が家になかった世代にとっては、職場が人生で初めて電話機を本格的に扱う場になります。
NTTドコモの別調査(2024年1月実施、15~79歳対象)では、音声通話利用時に最も使われる手段は「スマホの標準電話」が78.4%、次いで「LINE通話」が約70%という結果も出ています。10~20代男性ではDiscord(ゲーマー向け通話アプリ)の利用率が2~3割ありましたが、全体ではわずか4.6%に留まります。つまり若者は確かにスマホ上で音声通話も使っていますが、その多くはLINEなどカジュアルな通話であり、ビジネスで用いる固定電話やオフィス電話の操作には直結しないことが分かります。実際、新入社員の中には「オフィスの固定電話機に初めて触れた」「受話器の取り方や保留ボタンの意味すら戸惑った」という声もあります。スマホ世代にとって、複数のボタンが並ぶビジネスホンは「レトロな機械」に映り、その扱いは決して直感的ではないのです。
以上のデータを総合すると、Z世代は生まれながらにテキスト中心のコミュニケーション環境で育ち、日常的に電話通話をする機会が極端に少ないことが明確です。結果として電話応対スキルを身につける場がなく、心理的抵抗感を抱えたまま社会人になっているケースが多いと考えられます。この前提を踏まえ、次章ではZ世代が会社の電話に出られない(出たがらない)具体的な主因を5つの観点から掘り下げます。
Z世代が会社の電話に出にくい主因(5つの観点)
前章のデータが示すとおり、Z世代社員が電話対応を苦手とするのは極めて自然な環境要因によるものです。ここではその主因を(1)心理的要因、(2)経験不足、(3)環境・育成上の要因、(4)組織運用上の要因、(5)技術的要因の5観点で整理します。
1. 心理的要因 – 電話への不安・恐怖心
リアルタイムの音声コミュニケーションへの不安がまず挙げられます。チャットやメールと異なり、電話は即座に返答しなければならないプレッシャーがあります。Z世代社員の中には、電話の呼び出し音や着信通知だけで心拍数が上がると語る人もいます。実際、20~40代の3~4割が「電話で話すことが苦手」と感じているとの調査結果もあり、電話に対する漠然とした不安や苦手意識が広く存在します。特に職場の電話となると「失礼があってはいけない」「うまく応対できなかったらどうしよう」と強い緊張感を抱きがちです。電話=緊張・苦痛という心理的ハードルが、一度トラウマになるとさらに電話から遠ざかる悪循環にもなり得ます。
また、「見えない相手」と直接話す社交的不安もあります。対面であれば表情やジェスチャーから相手の反応を読み取れますが、電話は声と言葉だけです。加えて若手社員の場合、電話の相手は自分より年上の顧客や取引先、社内の別部署の先輩などが多く、目上への応対マナーへの不安も心理負担となります。「電話マナーに自信がない」が電話嫌いの理由トップ(53.5%)だったという調査結果もあり、敬語・言葉遣いの間違いを恐れる気持ちが強いことが伺えます。
2. 経験不足 – 電話に慣れていない・成功体験がない
前章のデータの通り、Z世代は日常生活で電話を使う経験そのものが乏しいまま成長しています。ある調査では、Z世代の若手社員が電話を苦手と感じる理由に「普段から電話を使う機会がない」(44.6%)や「実家や自宅に固定電話がなかった」(20.8%)が挙げられています。子どもの頃から家で家族が電話する姿を見ていない、プライベートでも友人との連絡はLINEメッセージかSNSで済むという環境では、電話応対スキルが身につかなくて当然です。
社会人になって初めて本格的に電話を使うとなれば、まさに初めて自転車に乗る子どものようにゼロから慣れる必要があります。ところが冒頭で触れたように、電話は失敗が目立ちやすくプレッシャーが大きいため、新人が「成功体験」を積みにくい面があります。一度応対で失敗して叱責されたり、クレーム対応で怖い思いをしたりすると、さらに電話への苦手意識が強まりがちです。結果として「できれば電話は取りたくない」という心理が固定化してしまうわけです。
また、電話特有のスキル(声のトーン、話すスピード、要点を簡潔に伝える等)に不慣れなため、「自分の話し方が聞き取りにくいのでは」「うまく要件を理解できなかったらどうしよう」と過剰に心配してしまうケースもあります。対面やテキストでは優秀にコミュニケーションできる若手でも、電話になると緊張で実力を発揮できず空回りする――そんな経験不足ゆえの負のループに陥っている可能性があります。
3. 環境・育成上の要因 – 教わっていない・フォロー体制の欠如
企業側の新人育成環境にも課題があります。従来、電話応対は「見て覚える」ものとされ、体系立てた教育がないまま先輩の真似で身につけるケースが多くありました。しかしZ世代新人の声として「先輩の姿を見て覚えるしかないと思った」というコメントもあるように、誰も教えてくれず不安なまま電話を任されている状況が散見されます。前述の若手400名調査でも、「苦手業務克服のために会社が何をすべきか」の問いに「研修制度の充実」(52%)や「マニュアル作成」(37.5%)が上位に挙がり、若手は会社による体系的な指導を求めていることが分かります。
にもかかわらず、多忙な現場では電話対応研修まで手が回らず、電話対応は新人の登竜門だからとにかく場数で慣れろという風土も根強いです。結果、新人だけが代表電話を取らされ続けるような不均衡が生じ、「自分ばかり電話対応させられる」と不満を募らせる若手もいます(これ自体がテルハラ問題につながります)。OJT体制の不備や、電話を苦手とする若手をフォローするメンター不在も問題です。新人が電話中に困っても誰にも助けを求められない、失敗してもフォローなく萎縮してしまう、そうした環境では電話嫌いが加速しても不思議ではありません。
さらに、オープンオフィス環境によるやりにくさも指摘されます。周囲に上司・同僚が見守る中で電話応対するのは新人にとって大きなプレッシャーですし、同僚に聞かれる羞恥心から積極的に電話に出たがらないこともあります。昨今は在宅勤務も増えていますが、逆に自宅でひとりで重要な電話に出る不安もあります(隣に先輩がいないため即座に助けを求められない等)。環境面で新人が安心して電話できる仕組みが不足していることも、主因の一つと言えます。
4. 組織運用上の要因 – 明確なルール・役割分担不足
会社の電話運用そのものの問題も見逃せません。多くの企業では代表電話や代表メールは総務・庶務部門や受付が一次対応しますが、部署代表電話や内線の取次ぎについては「鳴ったら近くの若手が取る」という暗黙ルールだったりします。このように役割分担が不明確だと、電話嫌いの若手は「なぜ自分ばかり…」と感じやすくなります。一方で電話に積極的なベテラン社員との間に「電話に出ない新人VS自分ばかり出る人」という溝が生まれるケースもあります。
また、電話対応時の社内ルールや情報共有不足も原因になります。誰にどの用件を取り次ぐべきか明文化されておらず、新人が判断に迷う例です。結果として「少々お待ちください」と保留してから社内を右往左往…といった経験をすれば、次第に電話が怖くなるでしょう。頻出する問い合わせへのQ&Aや、取次ぎ先リストが整備されていないことも新人の負担増につながります。電話メモの取り方・残し方ひとつ取っても、フォーマットやツールが決まっていないと新人は手探りになります。
さらに、在宅勤務時の電話運用も課題です。コロナ禍で在宅勤務が広がった際、各社は代表電話を転送したり、誰かが交代で出社して電話を取ったりと工夫しましたが、統一された仕組みがないまま試行錯誤だった企業も多いでしょう。BIZTELの2024年調査では、在宅勤務中の代表電話対応を「社員の携帯に転送」が25.3%、「交代出社で対応」が22.8%という結果でした。最近は出社回帰でその割合は減ったものの、未だに約16%(15.8%)の社員が「電話対応のためだけに出社した」経験が直近1年であるといいます。このように電話のために人の働き方を縛る運用は、若手にとっても不満や疑問の種になるでしょう。旧態依然とした電話運用(固定電話至上主義や、人海戦術的な取次ぎ)は、デジタル世代の価値観に合わずモチベーション低下を招きかねません。
5. 技術的要因 – ツールミスマッチと効率性の問題
最後に技術的側面です。Z世代は最先端のデジタルツールに慣れ親しんでいる反面、職場の電話機や留守電システムなどが古く感じられ、使い勝手が悪いと感じることがあります。例えばスマホなら着信履歴やSMSで相手情報が残りますが、旧来のビジネスフォンでは取次ぎミスを防ぐ仕掛けがなくアナログなメモ頼りだったりします。こうしたUI/UXのミスマッチが、「電話は非効率だ」という思いを強めます。
実際、電話対応は時間コストが高いとも指摘されています。あるコールセンターでは「メール対応に比べ電話は圧倒的にコストがかかる」ため、いかに電話を減らすかが課題だったと報告されています。Z世代社員の目から見ても、「チャットなら5分で済むやりとりに電話だと15分取られる」といった非効率さを感じる場面があるでしょう。特に内容が記録に残らない電話は、情報共有や検索の観点でもデメリットがあります(だからこそ彼らはチャットの「後から読み返せる」が便利だと考えます)。
さらに、電話対応は他の業務を中断させる点も問題です。集中しているところに突然鳴る電話は、若手に限らず誰にとっても生産性の妨げになります。Z世代はマルチタスクに慣れていると言われますが、それでも不意の割り込みタスクはストレスです。上司世代が「仕事中に電話が来るのは当たり前」と感じていても、若手からすれば「なぜ予定を狂わされなければならないのか」と違和感を覚えるかもしれません。
以上のように、心理・経験・環境・運用・技術の各要因が複合的に絡み、Z世代は電話に対して高いハードルを感じているのです。ポイントは、決して「最近の若者は根性がない」からではなく、合理的な理由や環境要因があって電話に出られない状況に陥っているということです。次章では、このギャップに関するよくある誤解を解きほぐし、実態に即した事実を整理します。
誤解と事実:マナーや業務要件の変化、電話のリスクと必要性
電話を巡る世代ギャップには、いくつかの誤解が存在します。ここでは典型的な誤解と、その背景にある事実を整理します。
- 誤解①:「電話に出ないのは怠慢・マナー違反」
事実: 若手が電話対応に消極的なのは怠惰ではなく、経験不足と心理的ハードルによるものです。前述の通り約半数の新人が電話業務を苦手と感じており、特に「マナーに自信がない」「使ったことがない」ことが理由です。つまり教えられていない・慣れていないことが根本原因であり、本人のやる気や礼儀の問題と決めつけるのは誤りです。むしろ会社側が適切に研修・指導することで解決できる課題といえます。「会社が教えなくても社会人ならできて当然」は通用せず、基本スキルもゼロから教育が必要だという調査コメントもあるほどです。 - 誤解②:「若手は対面コミュ力も低く、電話もできない」
事実: Z世代は電話に慣れていないだけで、テキストコミュニケーションや対面でのSNS的発信力など新しい形のコミュ力を持っています。実際10代~20代前半では、友人との連絡で対面(直接会う)も一定割合ありますし、むしろオンライン上での文章力や情報発信力に優れています。電話ができない=コミュ力がないと決めつけるのは短絡的です。また、電話対応ばかりにこだわる職場風土が若手の能力発揮を妨げる可能性もあります。電話以外のチャネル(メール・チャット・Web会議等)では若手が生き生きと意見を言えるケースも多々あり、電話対応スキルだけで人材を評価するのはミスリードでしょう。 - 誤解③:「電話はビジネスに不可欠で代替不能」
事実: ビジネスにおける電話の位置づけは確かに重要ですが、近年その役割は変化しています。BIZTELの調査では、「電話よりメールやチャットで連絡することが増えた」人が50%に達しています。さらに「社用では固定電話ではなく携帯電話を使うことが増えた」人も約27.8%います。多くの企業がコロナ禍以降にコミュニケーション手段を見直し、電話一辺倒からマルチチャネル化しているのです。実際、日程調整や簡単な問い合わせはメール/チャットで十分対応可能ですし、その方が記録も残り効率的です。電話が必要なのは急ぎや複雑な調整の場合に限られてきています。電話“だけ”に依存しないことで、逆に電話を本当に必要な場面(緊急連絡や重要交渉)に集中させられるというメリットもあります。 - 誤解④:「電話を減らすと顧客満足度が下がる」
事実: 適切に設計すれば、電話以外の手段を充実させても顧客満足度(CS)は維持・向上可能です。むしろ自動音声応答(IVR)導入で対応品質が均一化し、オペレーター対応のばらつきを解消できるという指摘もあります。顧客にとっても、営業時間外でも問い合わせできたり(チャットボットやフォーム)、つながりにくい電話で待たされないといった利点があります。重要なのは顧客が使いやすい代替チャネルを用意することであり、電話を万能と考える必要はありません。実際、コールセンターで電話自動化を進めた事例では、応答率向上や機会損失の防止につながったとの報告があります。電話を減らす=CS低下とは一概には言えず、全体最適の視点で設計することが大切です。 - 誤解⑤:「電話恐怖症は本人のメンタルの問題」
事実: “電話恐怖症”と揶揄されることもありますが、その背景には上述した環境や運用上の問題が横たわっています。新人の電話対応スキル低下は個人の弱さではなく、企業全体で対処すべき組織課題です。Telハラのように電話を強要する文化は優秀な人材の早期離職を招くリスクが指摘されています。これは企業にとって大きな損失です。ですから、電話が苦手な若手を「甘え」と見るのではなく、どうすれば安心して電話対応できるかサポートする発想が必要です。ロールプレイ研修やFAQ整備、ITツール活用など、組織としての解決策で十分改善可能な問題なのです。
以上のように、電話対応力の低下は時代の流れに沿った変化であり、単なるマナー問題や個人の資質の問題ではないことがお分かりいただけたでしょう。では、この現状に対して具体的にどのような解決策が取れるのか、次章から3つの層(個人スキル・組織運用・技術代替)に分けて提案していきます。
解決策カタログ:個人スキル・組織運用・技術代替の3層アプローチ
Z世代の電話対応問題は、多角的にアプローチすることで改善できます。以下では(A)個人スキル開発、(B)組織運用改善、(C)技術活用の3つの層に分けて具体策をカタログ形式で提示します。それぞれ費用・工数や効果も異なるため、自社の状況に合わせて組み合わせることが重要です。
A. 個人スキル向上策 – 新人の電話対応力を底上げする
- ロールプレイ研修の実施: 新人研修や配属直後に、電話応対のロールプレイ(役割演習)を取り入れます。想定シナリオ(電話の受電から取次ぎ、伝言、クレーム一次対応まで)を複数準備し、新人役と応対役に分かれて練習します。上司やトレーナーが横についてフィードバックし、良かった点・改善点を即座に伝えることで効果が高まります。研修会社のプログラムでも、1日完結の電話応対研修があるほど重要視されています(録音して自分の声を客観視する手法もあり)。費用対効果: 内製研修なら工数のみ、外部講師を招く場合は数十万円程度。効果: 新人が電話対応の成功体験を積めば自信がつき、本番でも落ち着いて応対できるようになります。
- 電話応対スクリプト/マニュアルの整備: 新人が迷わず話せるよう、定型フレーズや基本手順を文書化しておきます。例えば「●●株式会社でございます。○○部の▲▲が承りました」(受電時の名乗り)、「恐れ入りますが少々お待ちください」(保留時)、「申し訳ございません。ただいま△△は席を外しております」(不在時)等、状況別のひな型を用意します。また、電話の取り次ぎ方法(内線の転送操作手順や、要件の聞き出し方)も含め、チェックリスト形式のマニュアルにします。新人は手元にそのマニュアルを置いて電話に臨めば安心感が違います。費用対効果: 内部で作成可能、随時改訂しやすい。効果: 応対品質のばらつきを減らし、言葉遣いミスによる落胆を防止できます。
- メモ取り・復唱(確認)の徹底指導: 電話は記録が残りにくいため、メモの取り方を教えることも重要です。新人には「5W1Hを意識して要点を書く」「氏名・連絡先・用件を必ず確認復唱する」習慣をトレーニングします。例えば電話口で「大事な点なので繰り返させていただきます…」と復唱するフレーズを教えておけば、聞き漏らし防止と相手の安心感アップにつながります。メモ用紙やテンプレート(後述の付録参照)を用意しておき、書いたメモは終了後チームで共有する運用にすると尚良いです。費用対効果: 指導時間程度。効果: 聞き間違い・伝達漏れといったミスが減り、新人も落ち着いて電話対応できます。
- 想定Q&A・ナレッジ共有: よくある問い合わせについてFAQを整備し、新人にも共有します。例えば「代表電話によくかかる質問トップ5」「対応方針と回答例」といった資料を用意します。また、過去の電話で困ったケースとその対処法をナレッジ共有する場を設けると有効です。週次ミーティングで「こんな電話がありましたがどう対応すべき?」と先輩に相談できるようにすれば、新人も溜め込まずに済みます。場合によっては想定問答集(例えばクレーム応対時のフレーズ集など)を配布し、繰り返し練習するのも効果的です。費用対効果: 既存業務の見直し程度。効果: 新人が突然の電話にも対応策を引き出しやすくなり、安心して受話器を取れるようになります。
- メンターや相談窓口の設置: 電話対応に関して新人が気軽に相談できる先輩メンターをつけます。たとえば「電話対応係」のような役割をシフトで決め、分からないことがあればすぐその先輩に聞ける体制にします。また、電話で困った出来事は上司に報告しフィードバックをもらう習慣も推奨します。心理的安全性を確保することで、新人が一人で抱え込まず学べる環境を整えます。費用対効果: 工数調整のみ。効果: 早期に課題を潰し、電話恐怖のトラウマ化を防ぐことができます。
B. 組織運用改善策 – 電話対応のルールと体制を整える
- 代表電話・部署電話の一次受け標準化: 組織として「誰がまず電話に出るか」を明確に決めます。例えば総務課が全社代表電話を受け、内容に応じて振り分けるとか、各部署内は交代で電話当番を設ける等です。ポイントは新人だけに押し付けず、チームで電話負担をシェアすることです。「電話は新人の仕事」は時代に合いません。電話当番制にすれば特定の人ばかり鳴りっぱなしという事態も避けられます。また、外部からの代表電話はできるだけ専門の受付窓口で吸収し、現場社員への取次ぎ件数自体を減らす工夫も必要です。費用対効果: ルール策定のみでコストほぼゼロ。効果: 電話対応が属人化せず公平になり、若手の不満軽減と応対漏れ防止につながります。
- コールトリアージの導入: 救急医療でいうトリアージの発想で、電話も重要度・種類に応じて処理フローを決めておきます。例えば「営業問い合わせは営業サポートチームへ転送」「顧客からのクレームはカスタマーサポートへエスカレーション」「セールス電話は丁重に断って終了」といった振り分け基準をルール化します。新人が電話を受けた際、その場で完結させるのか、他部署に回すのか、折り返しにするのかの判断基準をトリアージ表として持たせます。これにより、新人が「あちこちに確認して時間がかかる」「判断ミスで叱られる」といった不安を減らせます。費用対効果: 基準策定の会議程度。効果: 電話対応の効率と精度が上がり、一次対応で無理をしなくて済むため、応対者の安心感向上と顧客満足度向上に寄与します。
- SLA(サービス水準目標)とエスカレーション設計: 電話応対にもサービスレベル目標を設けます。例えば「3コール以内に電話に出る」「折り返しは1営業日以内」といった目標を定め、メンバー全員に周知します。加えて、エスカレーション基準も整えます。「新人対応で対処できない場合は迷わず上司に代わる」「5分以上かかりそうな通話は折り返しに切り替えさせる」などです。SLAを数値化しておけば、メンバーは自分一人で抱え込まずチームで目標を達成する意識を持てます。また、エスカレーションルールにより新人が長電話で行き詰まる前にサポートが入れるため、結果的に対応スピードも上がります。費用対効果: 設定と共有のみ。効果: 平均応答時間や一次解決率といったKPIが改善し、顧客対応力全体の底上げになります(後述KPI例も参照)。
- 電話受付時間・方法の見直し: 業務に支障のない範囲で、電話対応の時間帯や方法を工夫します。例えば昼休みや就業後は自動応答メッセージで対応し、24時間出る必要はないようにします。また、社内向けには「緊急でなければ電話よりチャットを優先する」といった内規を作り、むやみに内線や私用携帯に電話しない文化を醸成します。これにより若手へのプレッシャーを減らしつつ、重要度の高い電話に集中できます。さらに在宅勤務の場合は、一定時間(例えば毎日10-12時)は電話転送をONにして対応、それ以外は留守電+折り返し対応など、勤務形態に合わせた柔軟な運用も検討します。BIZTEL調査でも出社勤務時は固定電話使用率が29.6%と高く、急用時は代表番号での発着信ニーズがあるとされています。このニーズに応える一方で、社員の負担を減らすバランスを取ることが肝要です。
- 研修制度とOJT計画の充実: 組織運用として新人電話研修を正式なプログラムに組み込みます。入社後のビジネスマナー研修に電話応対演習を必ず入れ、配属後も数ヶ月内にフォローアップ研修を設定します。また、OJTの計画書に電話対応目標を明記し、たとえば「入社1ヶ月で社名を名乗って取り次ぎできる」「3ヶ月で簡単な問い合わせ対応を独力でできる」など段階目標を設定します。達成度合いは先輩や上司が評価し、できていれば承認、苦手が残るなら再訓練というPDCAを回します。費用対効果: 研修工数と教材程度。効果: 新人の習熟度を組織的に管理でき、早期戦力化につながります。また新人自身も「できるようになっている」という実感を持ち、自己効力感が上がります。
C. 技術代替策 – テクノロジーで電話対応を効率化・自動化する
- IVR(自動音声応答)の導入: IVRとは、かかってきた電話に対して機械が音声ガイダンスを流し、番号選択や音声入力で振り分けるシステムです。これを導入すると、電話の一次受付業務を自動化できます。具体的には「○○の問い合わせは1を、△△の件は2を押してください…」という案内を流し、該当部署につないだり、よくある質問には自動応答メッセージを流したりできます。近年はクラウド型IVRサービスが普及し、初期費用も抑えられ専門知識なく導入可能です。NTT東日本の解説によれば、電話自動応答のメリットは業務効率化・リソース削減(不要な電話を取り次がなくて済む)や機会損失防止(営業時間外でも即時応対できる)にあります。実際、不在時でも自動で受付できるので顧客を待たせません。費用: 月額数万円程度から、通話量次第。効果: 対応品質が均一化し、人手不足やスキルばらつきの課題解消に役立ちます。新人にも直接電話が行きにくくなるため、心理的負担軽減にもつながります。
- AI音声ボットの活用: IVRの発展形として、AIを使った自動応答(ボイスボット)も注目です。ユーザーが話した内容をAIが音声認識し、適切な回答や転送を行うものです。最新の生成系AIを組み込んだ音声ボットでは、かなり複雑な問答も処理可能になっています。実例では、電話問い合わせの自動化率を最大70%まで高め、人員コストを半減したコンタクトセンターもあります。IVRyというサービスを導入したアソビュー社の事例では、繁忙期の受電増に対してAIが予約受付やFAQ対応を代行し、応答率低下や人員過剰配置の課題を解決したと報告されています。AI音声ボットの利点は、24時間対応と人手削減、そして顧客の待ち時間短縮です。対話型AIにより予約や注文の受付も自動化できるケースがあります。費用: 初期数十万円~、月額利用料。効果: 人が対応する電話件数が激減し、残る人対応も高度な案件に集中できるようになります(結果として新人が受ける電話は専門性高いものだけになる可能性もあるため、その点の教育は必要)。
- クラウドPBXの導入: クラウドPBXとは、社内電話交換機能をクラウド上で提供する電話システムです。これを導入すると、オフィスの固定電話機がなくてもPCやスマホで会社番号の発着信が可能になります。テレワーク時でも代表電話に出られますし、複数端末で同時着信させて一人が出れば他は止まる、といった設定もできます。BIZTEL調査でも「在宅勤務でも電話を取れるシステムを導入」「クラウド型電話サービスを取り入れた」という企業が一定数あることが分かっています。クラウドPBXにすれば電話転送や留守電メッセージの管理も簡単で、新人にとっても扱いやすいUIになります。また、通話録音や履歴が残せるため、後で先輩が新人の通話を聞いて指導することも可能です。費用: 月額数千円/回線~。効果: 電話対応の柔軟性が増し、場所に縛られないチーム応対ができます(例:在宅勤務中も代表電話に気付かず放置…がなくなる)。新人も自分のPCで応対でき通話内容をテキスト化する機能などがあれば、負担軽減になります。
- 問い合わせ管理システム(チケット制)の導入: 電話対応を減らす一環として、問い合わせを一元管理するチケットシステムを導入します。顧客からの問い合わせはできるだけWebフォームやメールで受け付けてもらい、自動でチケット番号を発行、対応状況を可視化するものです。電話が鳴って飛び込み対応するのではなく、届いたチケットを担当者が順番に処理するワークフローに変えることで、応対抜け漏れや担当不明を防ぎます。もちろん急ぎの問い合わせは電話で来るでしょうが、「非緊急はフォームから」が定着すれば電話窓口の負担は相当減ります。この仕組みはカスタマーサポート分野で普及しており、顧客側にも「問い合わせ履歴が残る」「回答までの目安がわかる」メリットがあります。費用: ツール導入費用(月額数万円~)や社内問い合わせ対応フロー設計の工数。効果: 電話による業務中断が減り、若手社員の心理的負担も軽減。組織としてもナレッジが蓄積され、問題解決のスピードアップにつながります。
- 社内コミュニケーションの最適化(チャットルール整備): 社内でのやりとりは、原則チャットツールを使うよう推進するのも技術策の一つです。すでに多くの企業でSlackやTeamsが電話・内線の代替になっています。メールよりリアルタイム性がありつつ、電話より相手の都合を邪魔しないチャットはZ世代にも好まれます。ただし社内チャットも無秩序だと情報が分散するため、グループチャットの用途や応答ルール(既読スルーの可否、緊急時はメンションする等)を決めておくことが大事です。これにより「とりあえず電話」の社風を変え、まずチャットで確認、それでも足りなければ通話や会議という流れが定着します。費用: ツール利用料(人数規模によるが1人数百円/月~)。効果: 若手が本来力を発揮できるテキストコミュニケーションを活性化し、電話に過度に頼らない文化が醸成されます。
以上、個人・組織・技術の各レイヤーで考えられる対策を列挙しました。重要なのは、これらを組み合わせて総合的に実行することです。例えば新人研修を充実させても電話が鳴りっぱなしの職場では疲弊しますし、最新のIVRを入れても社員側の運用が悪ければ十分活用できません。次章では、これら施策を実際に現場に導入していく際の90日ロードマップを提示し、段階的な実行計画とKPI設定のポイントを示します。
90日導入ロードマップ:現状可視化→パイロット→全社展開
提案した解決策を現場に根付かせるには、段階的な導入と検証が肝心です。ここでは90日(約3か月)を目安にした導入ロードマップを例示します。短期集中でPDCAを回し、成果を測定しながら拡大していく計画です。
第1フェーズ(0〜30日): 現状可視化と計画立案
- ステップ1: 課題洗い出しと目標設定 – まず社内で現状の電話対応課題を洗い出します。新人・若手社員へのヒアリングやアンケートを実施し、「どんな電話が辛いのか」「困った経験は何か」を収集します。同時に、直近数ヶ月の電話対応データ(件数、対応者、対応時間、クレーム発生状況など)を分析し、ベースラインKPIを把握します(例:現在の一次対応率や平均応答時間など)。これをもとに、「3か月後に電話一次解決率+10ポイント」「応答までの平均時間を20秒以内に」といった目標値を設定します。KPIについては次章で詳述しますが、この時点で改善のゴールを明確にしておきます。
- ステップ2: 解決策の選定とプランニング – 上記課題と目標に基づき、先述の解決策カタログから実施項目を選定します。例えば「新人電話ロールプレイ研修を行う」「IVRをトライアル導入する」「電話当番制を試す」等、優先度とコストを考慮して決めます。ここで注意すべきは、一度に全部はやらないことです。小規模でテストできるもの(例えば1部署での試行や、無料トライアル期間の活用など)から始めましょう。30日以内に準備すべきタスク(マニュアル作成、研修日程調整、ツール手配等)を洗い出し、担当者を割り振ります。できればこの段階で推進チームを組み、若手代表・人事担当・IT担当・CS責任者などを巻き込むと円滑です。
- ステップ3: 社内周知と合意形成 – 計画を実行に移す前に、チーム内および関係部署への説明を行います。特に電話応対のルール変更や新技術導入は、全社員の協力が必要です。「電話対応改善プロジェクト」と銘打ってもよいでしょう。経営層やマネージャーからメッセージを出してもらい、「若手が安心して働ける環境づくりのため」と目的を共有します。このとき反対意見や懸念も出るかもしれませんが、次章のFAQで触れるように一つ一つ丁寧に反証し、現場の理解を得ます。
第2フェーズ(31〜60日): パイロット実行とフィードバック
- ステップ4: パイロット実施 – 計画した解決策を小規模に実行します。例えば総務部をモデル部署にしてIVR+電話当番制を試行し、あるいは新入社員研修で電話ロールプレイを実施します。この期間、推進チームは各施策の動きを密に観察します。ロールプレイ研修なら事後に参加者へアンケートを取り、自己評価の変化(「電話に少し自信がついた」等)を収集します。IVR導入なら実際にどれだけの着信を自動応答できたか、どのメニューで人に繋がったか等のログを確認します。現場ヒアリングも重要です。電話当番制にした部署の若手・ベテランそれぞれに感想を聞き、問題点を洗い出します。
- ステップ5: 中間KPI測定と効果検証 – パイロット期間中でも、KPIを計測して効果を数値で捉えます。例えば1か月目と比較して、IVR導入部署の人手対応コール件数が何%減ったか、ロールプレイ後の新人の一次取次成功率が向上したか等です。半数以上の新入社員が電話に出られるようになった等、目に見える成果があれば共有します。一方で思った効果が出ない施策があれば原因を分析します(研修時間が短すぎた、IVRメニューが適切でなく結局オペレーター対応になった等)。定性フィードバック(「IVRの音声案内が聞き取りづらいと苦情があった」など)も集め、必要なら設定をチューニングします。この段階で施策を取捨選択し、継続するもの・改良するもの・中止するものを判断します。
- ステップ6: 追加改善と標準化検討 – パイロットの結果を踏まえ、施策のブラッシュアップを行います。例えば研修コンテンツを改良したり、マニュアルで不足していた項目を追記したりします。また成功した施策については、他部署へ横展開する計画を立てます。例えば総務部でうまくいったIVRをカスタマーサポート部門でも導入検討する、営業部の電話当番制を全社共通ルールにするなどです。標準化にあたっては、効果データと現場の肯定的な声を示すことで合意を得やすくなります。
第3フェーズ(61〜90日): 全社展開と定着化
- ステップ7: 全社導入と教育展開 – 改善策を全社スケールで展開します。IVRやクラウドPBXなどシステム面はIT部門と連携して本格導入を進めます(この間、一時的に電話受付時間を短縮する等の過渡期対応も検討)。組織運用策は社内規程やマニュアルをアップデートし、「電話応対基本ルール」として周知徹底します。例えば社内ポータルに電話取次ぎフロー図を掲示し、全社員が閲覧可能にします。新人研修プログラムも改訂し、今後入社の人にも継続して教育できるようにします。トレーニング担当者の育成(例えばロールプレイ研修を先輩社員がトレーナーとして回せるようにする)も計画します。
- ステップ8: 成果モニタリングと報告 – 全社展開後、定期的にKPIをモニタリングします。90日時点で、当初設定した目標値に対する達成度を測ります。例えば「一次解決率を50%から65%に引き上げる」目標だった場合、現状が60%ならあと5ポイントといった具合です。達成できたKPIもあれば未達のものもあるでしょう。その分析を行い、例えば電話自動化率は目標達成だが顧客満足度が下がったならフォロー策を考えます(自動応答メッセージの改善等)。この結果を経営層や関係部署にレポートし、さらに次の90日で何をするかを決めます。改善策導入は一度やって終わりではなく、継続的な調整が必要です。
- ステップ9: 定着化と継続改善の仕組み化 – 最終ステップとして、導入した新しい電話応対体制を定着させます。改善前の古いやり方に逆戻りしないよう、定期的な見直しルーチンを組み込みます。例えば四半期ごとに「電話応対チェックイン」ミーティングを開き、KPIレビューと課題共有を行います。新入社員や異動者にも都度トレーニングを行い、ナレッジの継承を図ります。また、テクノロジーはアップデートが早いので、AI音声ボットの精度向上版が出たら試してみる、他社事例を研究するなどアンテナを張り続けることも大切です。
以上が90日プランの一例です。要諦は、小さく試して効果を測り、良ければ大きく展開、常にデータでモニターというPDCAです。短期間で変化を出すことは可能ですが、その後の定着と改善も見据えて取り組むことで、電話応対改革が一過性で終わらず組織文化として根付くでしょう。
成果指標/KPI:一次解決率、平均応答/放棄率、工数削減、CS、教育到達度
改善施策の効果を客観的に評価するには、KPI(重要業績評価指標)の設定とモニタリングが欠かせません。電話対応に関連する代表的な指標と、その定義・目標値・計測方法の例を紹介します。
- 一次解決率(First Call Resolution:FCR)
定義:顧客からの問い合わせや依頼に対し、初回の電話応対で解決できた割合。折り返しや他部署への転送、再度の連絡が不要だったケースの比率です。
目標値例:60% → 75%(15ポイント向上)
計測方法:通話後のオペレーター入力やチケット管理システム上で「解決」「要フォロー」などステータスを記録し集計します。また顧客満足度調査で「用件が解決した」回答を元に推定することも。
意義:一次解決率が上がれば、顧客満足度向上と業務効率化の両面メリットがあります。IVRや知識共有により新人でも解決できる範囲が増えればこの指標は改善します。 - 平均応答時間(Average Speed to Answer:ASA)と放棄呼率(Abandonment Rate)
定義:平均応答時間は着信から受話器を取るまでの平均秒数。放棄呼率は呼び出し中に顧客が諦めて切った通話の割合です。
目標値例:ASA:20秒以内、放棄呼率:5%以下
計測方法:電話システムやクラウドPBXのログから算出します(総呼出時間÷件数、切断件数÷総着信件数)。
意義:電話への迅速な対応を示す指標で、顧客のストレスに直結します。電話当番制の導入や人員配置最適化で改善可能です。BIZTELの調査でも電話品質の課題として「相手の声が途切れる・遅れる」がありましたが、それ以前に出るのが遅い・出ないでは話になりません。放棄呼率5%以下なら概ね良好とされます。 - 着信件数あたり工数削減(電話1件対応にかかる平均時間、人件費)
定義:電話1件あたりの平均対応工数(時間 or コスト)。ここでは対応後の処理時間も含めます。
目標値例:5分/件 → 3分/件、人件費▲40%
計測方法:通話時間+メモ記録や対応完了までの時間をサンプル計測。または電話対応者の月工数/対応件数で算出。AI導入前後でのオペレーター要員数比較などで人件費削減率を算出。
意義:業務効率改善の度合いを見る指標です。AIボットが何割か自動応答すれば人間の対応件数が減り、この数値は改善します。またマニュアル整備で対応時間短縮も反映されます。ただし短すぎて内容疎かでは本末転倒なので、CSと両睨みで管理します。 - 顧客満足度(Customer Satisfaction:CS)
定義:電話応対に対する顧客の満足度指標。通話後アンケートでの評価やクレーム件数推移など。
目標値例:「応対満足」と回答した割合80%以上、苦情件数▲50%
計測方法:IVRで通話後にプッシュ評価(1〜5)を促す、自動SMSでアンケートURL送付、または定期的に顧客満足度調査を実施し電話対応関連の設問を分析。苦情はクレームログ集計。
意義:質の側面を表す指標です。IVR導入などで効率が上がっても機械的すぎて不満が増えたら意味がないため、必ずCSを確認します。NTT東日本もメリットとして「適切な案内で顧客満足向上」を挙げていますが、現実にそうなっているか検証します。反対に改善施策で顧客のストレス(つながらない、たらい回し等)が減れば満足度は上がるでしょう。 - 教育到達度・浸透率
定義:社内の電話対応スキルや新ルールがどの程度定着したかを示す指標。新人研修修了率や、社内テスト合格率、周知ルール遵守率など。
目標値例:新人電話研修受講率100%、電話応対テスト合格率90%以上、ルール違反(例:私用携帯への社用連絡)ゼロ件
計測方法:研修受講者数/対象者数、研修後テストスコア集計、違反報告件数のモニタリング。場合により模擬通話で品質チェックしてスコア化。
意義:内部プロセスの充実度を見る指標です。電話対応力向上には教育とルール運用が不可欠なので、それが計画通り行われているか測定します。特に新人の電話スキルテスト(ロールプレイ評価など)を定期実施すれば、組織全体の応対力を把握できます。改善策導入後はこれらが軒並み向上するはずで、もし落ちていれば再教育や仕組みの見直しが必要です。
以上、KPI例を挙げましたが、業種や組織によって適切な指標は異なります。コールセンターのように電話中心業務なら非常に細かい指標管理がされていますし、一般企業の内線対応ならもっとシンプルで良いでしょう。大切なのは、「何をもって成功とするか」を数値で定義し、Before-Afterを測ることです。それにより経営層や他部署にも改善の説得力を示せ、次なる投資(例えばAI導入予算など)も取りやすくなります。
ケーススタディ(国内事例):電話運用見直しの成功例
ここでは、日本国内の事例から電話対応改革に成功した例をいくつか紹介します。自社で検討する際の参考として、複数の業界・アプローチのケースを取り上げます。
- ケース1:株式会社アソビュー – コンタクトセンターにIVRとAIボット導入
レジャー予約サービスを運営するアソビュー社では、問い合わせ電話が季節によって急増する課題がありました。従来は繁忙期に臨時スタッフを増やすなど対応していましたが、人員確保が難しくコストも膨らんでいました。そこでIVRy社のAI対話ボットを導入し、予約受付やFAQ回答を自動化する取り組みを行いました。結果、電話の自動化率が最大70%に達し、コールセンター運営コストを半減する成果を上げました。具体的には、IVRで問合せ種別を振り分け、AIが営業時間や予約方法など定型質問に即答。人が対応するのは高度な問合せやクレームのみとなり、スタッフの負荷が大きく軽減されました。顧客も24時間自動応答で問い合わせ可能になり、機会損失が減ったといいます。この事例は最新技術活用の成功例として注目され、他社でも参考にされています。 - ケース2:ある製造業A社 – 代表電話を廃止しカスタマーサポートに集約
従業員300名規模の製造業A社では、従来は各部署ごとに代表電話番号があり新人が交替で対応していました。問い合わせの多くは製品に関する質問や修理依頼でしたが、担当部署にたどり着くまで転送が重なるケースが頻発し、顧客・社員双方に負担となっていました。そこで思い切って部署代表電話を廃止し、すべて一本のカスタマーサポート番号に集約しました。専任のサポートチームを設け、そこが全問い合わせを受け付けます。製品ごとの専用Webフォームも開設し、電話以外からも連絡できるようにしました。その結果、他部署の社員が電話対応に追われる時間がゼロになり、本来業務に集中できるようになりました。若手社員からは「電話で中断されないので仕事に没頭できる」「問い合わせ対応はプロに任せられる安心感がある」と好評です。顧客側もワンストップで専門スタッフに繋がるため一次解決率が向上し、対応スピードも上がりました。ポイントは、電話対応を窓口一本化して専門化したことです。このように組織設計を見直す大胆な方法も効果を上げています。 - ケース3:IT企業B社 – 社内コミュニケーションを完全オンライン化
従業員100名規模のIT企業B社では、新卒入社のZ世代比率が高く、創業時から「基本的に電話をかけない文化」でした。社内連絡はチャットツール(Slack)を徹底活用し、緊急時もSlackコール(音声通話機能)を使います。オフィスに固定電話機はなく、外部からの連絡は担当者宛ての直通IP電話かメールです。採用面接もすべてオンライン予約で、電話連絡はゼロです。その結果、入社1年目社員でも電話ストレスを感じる場面がほぼなく働けています。顧客との会議もオンラインミーティングが主で、「電話のみ」というケースは減少傾向です。同社人事は「電話対応力よりも文章で正確に伝える力を重視している」と語っており、時代に合わせてビジネスマナー教育の重点をシフトしています。社内ルールとITインフラを整えることで、電話に依存しない働き方を実現した例と言えます。ただし顧客からの電話ゼロは難しいため、代表番号にはIVRで担当者の携帯に繋ぐ設定を用意してあります。実際は月に数件程度しか鳴らず、緊急ホットライン的な位置づけになっています。 - ケース4:地方自治体C市 – AIによる電話自動応答サービス試験導入
行政分野でも電話業務負荷の軽減に取り組む例があります。ある地方自治体C市では、市民からの電話問い合わせ(例:ゴミの出し方、施設予約方法など)の対応に日々多大な人員を割いていました。コールセンターはないため各課の職員が対応していましたが、専門外の質問も多く対応遅れや折り返しが頻発。そこで2025年度からNTT東日本の音声自動応答サービスを一部業務で試験導入しました。住民票の取り方やイベント情報など簡易な問い合わせはAI音声が回答し、担当課への転送も自動化しました。導入直後半年で、対象業務の電話件数が前年同期比30%減少し、窓口職員の残業が削減されました。市民からは「電話がつながりやすくなった」「営業時間外でも必要情報が得られ便利」との声があり、評価は概ね良好です。行政サービスの分野でもAI・IVRで一次案内を効率化する方向が進んでいます。この事例からも、電話=有人対応という常識が変わりつつあることが分かります。
以上、規模や業種の異なる例を見てきました。それぞれ課題に応じた手段(専門部署化、徹底的なオンライン化、最新技術導入など)を講じていますが、共通するのは電話対応の在り方を現状に合わせてアップデートしたという点です。自社の課題に照らし、これら事例のエッセンスを参考にしてみてください。
よくある反論と反証(Q&A)
電話対応改革に着手すると、社内外から様々な反論や不安の声が上がることがあります。ここでは想定される質問・異論に対し、データと論理に基づいた回答例を示します。
Q1. 「電話は営業の命。若手でも電話できないと商談も取れないのでは?」
A1. 営業職に電話スキルが不要とは言いませんが、それは手段の一つにすぎません。時代とともに新規顧客との最初の接点は電話以外(問い合わせフォームやSNS、オンラインセミナー等)に多様化しています。電話飛び込みよりメールやLinkedInメッセージの方が応答率が高いケースも増えています。大切なのは顧客に合わせた適切なチャネルを使い分けることです。むしろ電話しかできない営業より、メール文章力・オンライン商談スキルもある営業の方が成果を上げる時代です。若手にも電話は必要な場面で訓練させますが、「電話だけが営業」という考えはアップデートが必要です。事実、あるIT企業では電話なしでも売上を伸ばしています(前述ケース3)。営業の命は顧客理解と提案力であり、電話自体は目的ではありません。
Q2. 「固定電話を無くすのは不安では?災害時や緊急連絡が心配」
A2. 完全に固定電話をゼロにするかは企業判断ですが、代替策があれば問題ありません。例えばクラウドPBXを入れれば、緊急時も社員のスマホに一斉着信させることができますし、緊急速報メール・チャットとの組み合わせで安否確認も可能です。昨今は固定電話回線自体がIP網移行していますので、旧来の黒電話だけが災害に強いというわけでもありません。むしろ複数チャネルを確保しておく方がレジリエンスが高いです。どうしても代表番号が必要ならIVRで非常時案内を流すなど工夫できます。実際、固定電話を減らした個人(自宅)の約95%が「今後も増設予定なし」と回答しています。不安は分かりますが、現実に多くの会社が乗り越えていることです。
Q3. 「お客様は年配者も多い。チャットや自動音声では対応できないのでは?」
A3. ご高齢のお客様には確かに電話志向の方もいます。その場合、人による電話対応も残すべきです。ただし全員がそうではなく、60代以上でもLINEを使いこなす方は増えています。また、自動音声対応も日進月歩で自然になっており、高齢者でも違和感なく利用できた事例もあります(地方自治体のAI案内の例など)。重要なのはお客様の選択肢を狭めないことです。電話が良い方には有人電話を提供しつつ、待ち時間ゼロのチャットや24時間使えるFAQサイトを用意すれば、実際多くの方が便利と感じてくださいます。現に電話対応を減らしてもCSを維持できている企業も多数あります。顧客セグメント別に適切なチャネルを組み合わせることで対応可能です。
Q4. 「電話代行やAIに任せて品質は大丈夫?機械では失礼ではないか?」
A4. プロの電話代行サービスや最新AI音声ボットの品質は、想像以上に高いです。電話代行は訓練されたオペレーターが貴社の社名で応対し、要件を正確にヒアリングしてくれます。AIボットも事前にシナリオを作り込めば的確に案内し、人間より丁寧なくらいです。むしろ新人が緊張でどもるより、落ち着いた自動音声の方がお客様に安心感を与える場合すらあります。もちろん全てのケースで機械が人を上回るとは言いませんが、単純で定型的な応対なら機械の方がミスなく迅速です。失礼にならないよう、導入時に専門家の助言を得て丁寧な音声文言を設定すれば問題ありません。それでも人間対応が必要な場面だけ人が応対すれば良く、適材適所で品質と効率を両立できます。
Q5. 「電話に出なくて済むようにすると、若手の成長機会を奪わないか?」
A5. 電話対応は確かにトレーニングになりますが、そればかりが成長ではありません。前述のとおり時代に合わない丸暗記マナーを押し付けるより、若手にはもっと価値を生む仕事(データ分析や新企画立案など)を経験させる方が成長につながるでしょう。電話はあくまで手段なので、避けられるストレスなら避け、より高度な顧客対応やコミュニケーションにエネルギーを向けさせる方が建設的です。また電話を減らすと言ってもゼロにはならないので、本当に必要な電話場面ではしっかり対応できる訓練は続けます。質の高い電話応対は引き続き評価します。要は量ではなく質です。「電話さえ出ていれば評価される」風土から「顧客課題を解決できて評価される」風土に変えることが、真の成長機会を提供することになります。
Q6. 「結局コストが心配。ツール導入や研修に見合うリターンがあるの?」
A6. コストに見合うかは、現状の電話業務のコストを把握することから始めましょう。例えば電話対応に割いている人件費を計算すると、驚く額になるかもしれません。改善策によりその一部でも削減できればROIは明確にプラスです。実際、前述ケース1ではコンタクトセンターコスト半減という結果でした。小規模でも、例えば新人の離職を1人でも防げれば、それだけで研修費用以上の効果があるでしょう。ツールもまずトライアルで効果検証し、いけそうなら正式契約すればリスクは低減できます。漠然と心配するのでなく試算と試行が大事です。定性的にも、電話ストレス軽減で社員の意欲や定着率が上がるなら、それは組織に大きなプラスです。コスト以上の価値が得られるよう設計するのが我々の腕の見せ所です。
Q7. 「電話対応を改善して何が得られる?本当に業績に寄与するの?」
A7. 電話対応改善はゴールではなく、業績向上や働き方改革の手段です。得られるものは多岐にわたります。(1)顧客対応力の強化:問い合わせへの迅速・的確な応対は顧客ロイヤルティ向上につながり、結果としてリピートや契約増に寄与します。(2)業務効率化:前述のように人的工数削減でコア業務にリソースを振り向けられ、生産性が上がります。(3)人材定着と育成:若手が働きやすい環境は離職防止や優秀層の採用競争力向上につながります。(4)リスク低減:Telハラ問題を未然に防ぎ職場風土を健全化できればコンプライアンス上も安心です。さらにDX(デジタル変革)の一環として社内にIT活用マインドが根付く副次効果も期待できます。これらは中長期的に業績や組織力を底上げする要素です。電話対応改善はその第一歩として意義があると言えるでしょう。
以上、想定問答を示しました。反論に対しては感情的にならずデータとロジックで答えることが重要です。特に上の世代には電話への思い入れが強い方もいるため、「電話を否定する」のではなく「より良い全体設計への進化」というポジティブな位置づけで説明しましょう。
まとめ:電話“だけ”に依存しない全体コミュニケーション設計へ
本稿では、Z世代が会社の電話に出られない(出たがらない)理由をデータとともに分析し、組織が取り得る解決策を多角的に提示しました。要点を振り返ります。
- 世代間ギャップの現実:Z世代はテキスト中心で育ち、電話に慣れていないため心理的ハードルが高いことがわかりました。電話応対はもはや新人にとって当たり前ではなく、教え育てるべきスキルなのです。これを怠慢や根性論にすり替えるのは的外れであり、組織的サポートが必要です。
- 電話文化の変容:データから、日本全体でも通話よりテキストが主流となりつつあり、企業のコミュニケーション運用もポスト電話にシフトし始めています。電話の役割は緊急・高度な用件に限定され、日常連絡はデジタル化する流れです。電話は重要な手段の一つですが、「電話至上主義」は時代遅れになりつつあります。
- 実務的な解決策:個人スキル開発では研修・マニュアル整備で新人の電話対応力を底上げし、組織運用ではルールと仕組みで電話負担を適切に配分・軽減し、技術ではIVR/AIやクラウドPBXで自動化と効率化を進める——この三位一体のアプローチが有効です。大事なのは自社にフィットする施策を組み合わせて実行し、データで効果を測りながら定着させることです。
- 全体最適デザイン:電話対応を改善する目的は、社員と顧客双方の満足度を高め、組織の生産性と柔軟性を向上させることにあります。電話“だけ”に人も時間も取られていた状況から脱却し、メール・チャット・AIなど様々なチャネルを駆使した全体最適なコミュニケーション設計へ移行することが求められています。それにより顧客には迅速で便利なサービスを、社員には安心して働ける環境を提供できるのです。
最後に強調したいのは、「人間ならではの電話対応力」も磨き続けるべきという点です。機械に任せられるところは任せつつ、人間にしかできない心のこもった応対や判断があることも確かです。Z世代の社員も、苦手意識を乗り越えて電話でお客様から感謝された時、大きな成長と自信を得るでしょう。その瞬間を迎えられるよう、我々マネジメント側は環境と仕組みを整え、段階を踏んでサポートする責務があります。
電話はビジネスの重要なツールではありますが、それに縛られすぎる必要はありません。電話だけに頼らないコミュニケーション戦略を構築することで、世代の違いを超えて誰もが働きやすく成果を出せる組織にしていきましょう。本記事がその一助となれば幸いです。
付録:現場で使えるテンプレート集
最後に、実務でそのまま活用できる電話対応関連のテンプレートを掲載します。自社用にカスタマイズしてご利用ください。
1. 代表電話一次受けフロー(例)
以下は、代表電話に着信があった際の一次対応フローを図解したものです。
【着信】→(自動ナンバーディスプレイ確認:顧客/外線か?)
├─【既知の重要顧客】→ 担当者に直接転送 or 迅速に担当部署へ引き継ぎ
├─【想定問合せ(FAQで対応可能)】→ 標準スクリプトで回答 → 【終了】
├─【クレーム/難しい内容】→ 傾聴し要点メモ → 上席者にエスカレーション
├─【営業電話/セールス】→ 「間に合っております」で丁重に辞退 → 【終了】
└─【不明(用件聞いても判断つかない)】→ 基本情報ヒアリング(氏名・所属・電話)
→ 保留して上司に相談 → 指示に従い対応 or 担当者折り返し手配 → 【終了】※上記は一例です。実際には業種・部署により振り分け基準を調整してください。大事な点は、電話を受けた人が一人で抱え込まず、ルールに沿って判断・転送できるようにすることです。
2. 電話応対スクリプト例
代表的な電話応対場面ごとのスクリプト例を示します。状況に応じて語尾や敬語レベルを調整してください。
- 受電時の基本応対
「お電話ありがとうございます。◯◯株式会社△△部、□□でございます。」
※社名→部署→氏名の順で名乗ります。部署代表電話なら部署名、代表交換なら社名のみでOK。 - 用件のヒアリング
「いつもお世話になっております。どのようなご用件でしょうか?」
「失礼ですが、お名前とご所属をお伺いしてもよろしいでしょうか。」
※名乗ってもらえない場合丁寧に尋ねる。用件もなるべく具体的に聞き出します。 - 担当者への取次ぎ
「かしこまりました。ただいま◯◯をお呼びいたしますので、少々お待ちくださいませ。」
※保留ボタンを押し、社内呼び出しへ(このとき保留音や保留中メッセージが流れる場合があります)。
(担当者と繋がったら)「△△部の□□さんからお電話です。(用件簡潔に)お繋ぎしてよろしいでしょうか?」
※担当者が出られる場合→保留解除して)「お電話変わりました、◯◯でございます。」と担当者が対応。
※担当者不在/NGの場合→次項へ。 - 担当者不在時の対応
「お待たせいたしました。◯◯は只今席を外しておりまして…」
・外出なら「本日は終日不在でございます。」
・離席中なら「席に戻り次第こちらからご連絡差し上げましょうか。」
相手が折り返し希望の場合:
「恐れ入ります、では◯◯より改めてお電話させていただきます。差し支えなければお電話番号を頂戴できますでしょうか?」
※番号・都合の良い時間帯等を確認しメモ。
相手が伝言を依頼する場合:
「承知いたしました。私、□□が伝言を承りました。復唱いたします…(要点復唱)。私から◯◯に申し伝えます。」
※伝言内容と氏名・連絡先を確実に記録し、担当者へ連絡。 - 簡単な問い合わせ対応(FAQで分かる場合)
例:「◯◯製品の仕様について…」
「お問い合わせありがとうございます。その件でしたら、◯◯製品の最新仕様は~(内容回答)。もし更に詳しい情報が必要でしたら担当部署にお繋ぎできますが、いかがいたしましょう?」
※回答できる範囲ならその場で答え、必要なら担当部署紹介。 - クレーム・苦情対応(一次対応)
「(相手の怒りのトーンに合わせ低姿勢で)大変申し訳ございません。□□が承りました。恐れ入りますが、詳しい状況をお聞かせ願えますでしょうか。」
※相手の話をさえぎらず傾聴。事実関係を整理しメモ。
「お客様のお怒りはもっともでございます。至急上席の者に報告し、改めて責任者よりご連絡いたします。」
※無理に自分で解決しようとせず、いったん預かり。謝罪と責任者対応を約束し、速やかに上司へ引き継ぐ。 - 営業電話の断り例
「(相手が名乗ったら)いつもお世話になっております。恐れ入ります、只今担当者が席を外しておりまして…」
「(相手がセールストークを続ける場合)申し訳ございません。今回のお話は間に合っておりますので失礼させていただきます。」
「(食い下がられた場合)大変恐縮ですが、今後のお電話はご遠慮いただけますと助かります。失礼いたします。(静かに受話器を置く)」
※相手を刺激せず確実に断る言い回し。「結構です」だと誤解されるので注意。
以上が典型的スクリプト例です。自社用に語尾や言葉遣いは統一ルールがあればそれに従ってください。繰り返し練習し、自分の言葉としてスラスラ出るようにしておくと実際の電話で焦らず対応できます。
3. 新人向けミニ研修カリキュラム(例)
新人や電話対応初心者向けの研修プログラム例を示します(全2回、各3時間コース)。
第1回(3時間):電話応対の基礎
- オリエンテーション(10分): 電話対応の重要性と研修目的を説明。「電話怖い」を克服する場である旨強調。
- 講義:電話応対マナー基礎(40分): 基本用語や礼節(敬称、「お電話様」「少々お待ちください」の適切さなど)、声の出し方(明るさ・速さ・抑揚)、電話機の操作(保留転送の使い方)。実演を交えて解説。
- ペア演習:名乗りと挨拶(20分): 受電時の名乗りを互いに練習、講師がフィードバック。電話での声の聞こえ方を確認。
- 講義:シチュエーション別対応法(30分): 取次ぎ手順、不在対応、断り方、質問の引き出し方などスクリプト例を示し説明。過去の失敗例紹介とコツ共有。
- ロールプレイ演習①(50分): 基本シナリオでロールプレイ。例:「顧客からの商品問合せを受け答えし担当者へ転送」など。3人1組(発信者役・受電者役・オブザーバー)で役割を回しながら実施。各演習後に講師から講評。
- まとめと質疑(30分): 本日の学びを振り返り、参加者から質問受付。課題:用意した電話スクリプトを各自音読練習し、次回までに暗唱できるようにする。
第2回(3時間):応用と実践(第1回から1~2週間後想定)
- 振り返りとウォーミングアップ(15分): 前回のおさらいクイズ、参加者に暗唱課題の確認(受電の名乗りを一人ずつやってみる等)。
- 講義:難しい場面の対応(30分): クレーム初期対応の心得(傾聴・謝罪・保留して上司報告)、電話でのNG行為(相手を否定する・専門用語連発など)解説。
- ロールプレイ演習②(60分): 応用シナリオでロールプレイ。例:「取引先から納期クレームの電話」「営業電話を受け断る」など難易度高め設定。1回ごとに講師・参加者全員でフィードバックを行い、良かった点/改善点を共有。
- グループ討議(20分): 「電話応対で不安なこと」を小グループで話し合い、対処法を互いに提案。講師が補足アドバイス。
- 最終テスト(30分): 模擬電話テストを個別に実施。講師または先輩社員が発信者役となり、受講者が一対一で応対する。評価項目(名乗り、言葉遣い、正確さ、落ち着き度など)に基づきスコアリング。
- 講評と今後の計画(15分): テスト結果フィードバック(各自に総評と得点を渡す)。今後のOJTでの目標を設定し宣言してもらう。
- 閉会(10分): 励ましとエール。「困った時は一人で悩まず相談するように」と念押し。
このカリキュラムはあくまで例ですが、短期集中で実践的にという点がポイントです。座学だけでなくロールプレイを多く取り入れ、受講者が実際に話す量を増やすことで効果が上がります。また間を空けて2回構成にすることで、現場で少し慣れた後に再訓練でき定着率が良くなります。テストで合格ラインに満たなかった人には追加フォローアップ研修を検討します。
4. KPIトラッキング表(指標定義/目標値/計測方法)
最後に、電話対応改善用のKPI管理シートのひな形を示します。定期的な記入・レビューに活用してください。
| KPI項目 | 定義・範囲 (分子/分母) | 現状値(開始前) | 目標値 | 最新値(○月) | 達成度評価 | 計測方法・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次解決率 | 初回応対で完結した問い合わせの割合 (一次完了件数/総受付件数) | 50% | 70% | 65% | やや未達 | オペレーター対応記録より集計 |
| 平均応答時間 | 着信から応答までの平均秒数 | 30秒 | 15秒 | 18秒 | ほぼ達成 | 電話システム通話ログより算出 |
| 放棄呼率 | 呼出中に切断された割合 (放棄呼件数/総着信件数) | 10% | 5% | 4% | 達成 | 電話システム通話ログより算出 |
| 電話1件あたり処理時間 | 通話+後処理にかかった平均時間 | 5分/件 | 3分/件 | 3.5分/件 | 未達 | 5人サンプル計測の平均(10月実施) |
| 顧客応対満足度 | 電話応対に満足と回答した割合(調査票Q5) | 80% | 85% | 87% | 達成 | 顧客アンケート(12月 n=200) |
| クレーム発生件数 | 電話応対に起因するクレーム件数(月) | 5件/月 | 2件/月 | 1件/月 | 達成 | コンプラ報告より集計 |
| 新人研修受講率 | 対象新人◯名中研修完了者割合 | 0% | 100% | 100% | 達成 | 4月入社5名全員7月研修受講 |
| 応対スキルテスト合格率 | 電話ロールプレイテスト合格者割合 | ー | 90% | 80% | 未達 | 研修内テスト(8月実施) |
| 社内ルール遵守率 | ○○ルール違反の報告件数 | △△あり | ゼロ | ゼロ | 達成 | 管理部報告。××のケースは除外扱い |
(※数値はサンプルです。)
このように、各KPIの定義と測定方法を明確にし、現状→目標→進捗を管理します。達成度が低い指標には「やや未達」「要改善」など色付けし、次のアクション(追加研修・原因分析等)を検討します。定性的コメント欄を設けても良いでしょう。KPIトラッキングは改善施策の効果検証とアピールにも役立ちますので、ぜひ経営層レポートや社内共有にも活用してください。
以上が付録テンプレート集です。現場で具体的に動かす際の助けになれば幸いです。
FAQ
Q1. 若手に電話以外の手段ばかり使わせていると、失礼に当たりませんか?(例:上司や取引先にメールのみで返信など)
A1. ケースバイケースですが、礼儀と効率のバランスを取ることが大切です。急ぎの要件やお詫びなど重要な場面では直接電話や対面が望ましいですが、日常業務連絡まで全て電話にする必要はありません。むしろ相手の業務時間を奪わないメールやチャットはビジネスマナーとして定着しつつあります。上司や取引先にも事前に「通常はメールでご連絡しますが緊急時はお電話します」と共有し、社内文化として根付かせれば失礼にはなりません。要は相手目線で手段を選ぶことであり、その判断力も若手に教えていきます。
Q2. 電話が苦手な社員を無理に電話対応から外すと、他の社員に負荷が集中しませんか?
A2. 個人の苦手をフォローするのは組織の役割です。確かに特定の人だけ電話を免除すると不公平感が出るので、制度的に解決するのがポイントです。例えば電話当番をローテーションし全員が担当する日を決める、AIやIVRを導入して誰にでも負荷が減るようにする等です。Telハラにならないよう留意しつつ、公平かつ効率的に割り振れば問題ありません。また苦手社員にも徐々に慣れてもらう努力は必要なので、最初はフォローを手厚くしつつ、段階的に電話に出る機会も与えます。チーム全員でカバーし合い成長し合う体制を作ることが大事です。
Q3. 在宅勤務時の電話対応が難しいです。自宅だと周囲雑音やセキュリティも気になります。どうすれば?
A3. 在宅での電話には確かに課題があります。まず機材面では、ヘッドセットやノイズキャンセリングマイクを支給し雑音を抑える、通話内容はVPN経由かクラウドPBXで社内と同等のセキュリティを確保します。運用面では、在宅勤務者のPCに着信通知が出るようにして取りこぼしを防ぐ、難しい内容は在宅からでも上司に転送・チャット相談できるようにします。ある調査では、在宅でも電話が取れるシステム導入企業が増えています。ITを活用しつつ、在宅日の電話対応ルール(子供の声が入ったらミュートする等)もチームで共有すればさほど問題なく運用できます。
Q4. お客様対応ではない社内の電話(内線や上司からの呼び出しなど)も減らした方が良いのでしょうか?
A4. 社内通話に関しては、可能な限りチャットやコラボレーションツールで代替するのがおすすめです。社内のちょっとした確認を電話で行うのは、相手の手を止める点で非効率です。若手が上司に相談する際も、まずチャットでアポイントを取り時間を決めて通話する方がお互い効率的でしょう。ただ、緊急のシステム障害連絡など即時性が必要な社内連絡は電話(携帯通話やメッセージアプリの通話機能)を使います。要するに内容の重要度・緊急度に応じて社内でも手段を選ぶべきです。その判断基準をチーム内で取り決めておくとスムーズです。
Q5. 電話代行サービスを検討していますが、自社の顧客対応を外部に任せることに抵抗があります。品質は担保されるのでしょうか?
A5. 電話代行(秘書代行)はプロのオペレーターが自社の一員のように振る舞って応対してくれるサービスです。事前に応対スクリプトや対応範囲を取り決めでき、報告もリアルタイムでもらえます。顧客には気付かれないケースも多いです。むしろ専門スタッフなので新人より安心かもしれません。もちろん自社で直接対応すべきコア業務(商談クロージング等)は引き継ぎますので、分業と考えると良いでしょう。多くのベンチャー企業が代行を活用していますし、まずは試験的に非コア部分(代表電話の取次ぎだけ等)を任せ、品質を見極めてから範囲拡大すればリスクは低いです。
Q6. 若手がお客様に「折り返します」と言っても、ベテランほど専門知識がなく結局回答できないのでは?
A6. 折り返しの場合は、回答できる人が折り返す仕組みにします。新人が受けた電話の内容はメモ・チャットで共有し、適任者(上司や別部署)に引き継ぎます。回答はその人から直接お客様へ行います。新人自身が勉強して回答を用意する場合も、事前に先輩のチェックを受けさせます。チームで一つの電話に対応するイメージです。また知識不足自体はOJTで徐々に解消していきますので、一度で答えられなくても次回は対応できるようになります。大切なのは「分からないのに適当に答えてしまう」ことを避けることであり、その意味で適切に折り返す判断をする方がお客様の信頼を損ねません。新人がそれを判断できるよう教育・フォローするのが我々の役目です。
Q7. 改善策を色々講じても、根本的に若手の電話嫌いは治らないのでは?
A7. 人の好き嫌いの感情を完全になくすことは難しいですが、苦手でもできるようになることは十分可能です。実際「電話苦手」と言っていた新人が研修と実践で自信を付け、「今は抵抗なく出られる」という例も多く見てきました。要は適切な知識と経験が積めれば、人は成長します。嫌いだから避けるではなく、嫌いでも困らない仕組みを整えつつ少しずつ慣れさせることが重要です。また改善策により物理的・心理的負荷が減れば、嫌悪感も和らぎます。Telハラのように無理強いするから嫌になるのであって、安心環境で成功体験を積めば苦手意識は薄まるものです。電話だけでなく総合的なコミュニケーション能力向上に繋がる取り組みとして捉え、長期的に若手を育てていきましょう。
以上、FAQ形式で疑問に答えました。読者の皆様の組織でも類似の声が出た際には、ぜひこれら回答例を参考にしてみてください。
参考文献(出典):
- 総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」(2025年5月30日公表) – SNS利用が最も高く、コミュニケーション手段の変化を示すcurrent.ndl.go.jpcurrent.ndl.go.jp
- NTTドコモ モバイル社会研究所「友人との日常会話手段 年々増加するテキスト、2014年約6割→2025年約8割」(2025年1月調査) – テキスト主流化と世代別の手段選好moba-ken.jpmoba-ken.jp
- NTTドコモ モバイル社会研究所「音声通話の利用状況 スマホ通話機能8割、LINE通話7割利用」(2024年1月調査) – 音声通話手段の利用率と若年層におけるDiscord利用傾向moba-ken.jpmoba-ken.jp
- クロス・マーケティング「電話での声と文字のやり取りに関する調査」(2024年5月, n=1,100) – 通話派24.7% vs テキスト派56.0%、年代別電話苦手意識の差prtimes.jpprtimes.jp
- BCC株式会社 若手社員400名調査「Z世代が苦手な仕事 約5割が電話業務」(2025年3月) – 電話苦手の理由トップはマナー不安(53.5%)、普段機会無(44.6%)、固定無(20.8%)prtimes.jp。研修充実を望む声多数prtimes.jp
- 東洋経済オンライン 日沖健「若手の電話対応がテルハラになる日本の大問題」(2024年4月4日) – 20代はSNS世代で通話不慣れ、電話強要がハラスメント化の指摘toyokeizai.net。20代男性の苦痛体験談等toyokeizai.net
- WSJ日本版(ダイヤモンドオンライン翻訳)「電話をかけるのに予告メッセージは必要?」(2024年6月7日) – 突然の電話は不安・煩わしいとの意見増、メッセージ習慣化で無予告電話拒否感もdiamond.jp
- BIZTELブログ「2024年度 ワークスタイルと電話対応業務に関する意識調査」(2024年8月, n=400正社員) – 出社回帰で転送/交代制対応減少biztel.jp、50%がメール/チャット連絡増加と回答biztel.jp。固定電話対応で出社経験1回以上15.8%biztel.jp。
- IVRy公式事例(コールセンタージャパン)「生成AIが叶える電話自動化70% 次世代コンタクトセンター」(2025年5月) – IVRy導入で電話自動応答率最大70%、運営コスト1/2に削減callcenter-japan.com(アソビュー社事例)。
- NTT東日本 ビジネスブログ「業務を効率化させる電話の自動応答とは?」(2024年9月24日公開) – 電話自動応答のメリット:業務効率化・機会損失防止・適切案内でCS向上等business.ntt-east.co.jpbusiness.ntt-east.co.jp。デメリットや導入ポイントも解説。
(※各出典の調査主体・年次・対象範囲は文中で記載。数字引用箇所は出典元の該当ページライン番号を示しています。)
